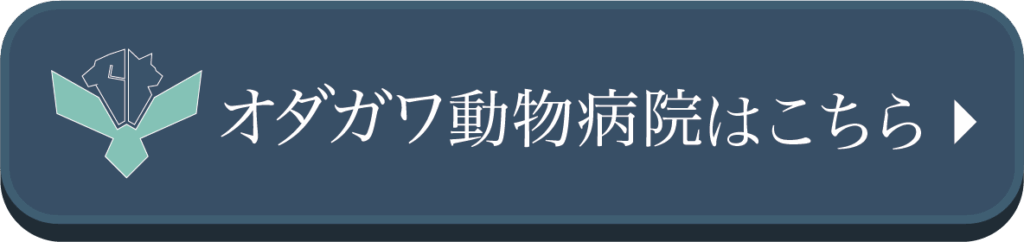「最近、うちの子がおなかを壊してしまって…」
若い犬を飼っている飼い主さんから、こんな相談を受けることがあります。ペットショップで健康チェックを受けてから家に迎え入れたのに、数週間後に下痢や嘔吐が始まることも。実は、消化管寄生虫は身近な存在で、検便1回では見つからないケースもあります。
消化管寄生虫とは
犬のおなかに寄生する虫には、大きく分けて線虫類・原虫類・条虫類(吸虫含む)があります。
最近は都市部での発生は減っていますが、屋外で保護された犬や、ペットショップ・愛護施設から迎えた直後の犬では、まだ珍しくありません。
主な寄生虫と症状
犬回虫・犬鉤虫(線虫類)
小腸に寄生し、下痢や嘔吐、体重減少を引き起こします。犬鉤虫は腸の粘膜に咬みつくため、貧血になることもあります。
※プレパテントピリオド(感染から虫卵が排出されるまでの期間)は2〜4週間あり、この間は検便で見つからないため再検査が必要です。

犬回虫は本院でも時々診ます。成虫は「そうめん」状で雄雌がいて、交尾して写真のような形状の卵(顕微鏡所見)を生みます。

犬鉤虫は体長約1-2cmの寄生虫が小腸の絨毛に咬みついて寄生しています。
犬鞭虫(線虫類)
成犬で感染が見られることが多く、長期的な下痢や体重減少を引き起こします。プレパテントピリオドは2〜3ヶ月。

犬鞭虫は7ヶ月以上の犬で感染が診られます。後天的感染です。
コクシジウム(原虫類)
特に子犬では下痢・脱水が重症化し、命に関わることもあります。

①頻回の下痢で発見されたり、②また偶然検便で診られることもあります。
ジアルジア(原虫類)
全国調査で陽性率は6.7〜59.3%と高く、最も一般的な寄生虫と考えられています。人にも感染する可能性があるため注意が必要です。

検査方法
直接法・遠心法による検便
便を顕微鏡で観察して虫卵や原虫を確認します。
特殊検査
感染初期や低寄生の場合、複数回の検査や特殊な検査が必要なこともあります。
治療
線虫類:駆虫薬を投与し、プレパテントピリオドを考慮して2〜3週間後に再投与
原虫類:原虫に適した薬を1〜2週間投与し、同時に便の処理を徹底
条虫・吸虫類:駆虫薬に加え、中間宿主(ノミや淡水魚など)との接触を防ぐ
予防
・定期的な検便(特に子犬期や新しく犬を迎えた直後)
・屋外での拾い食いや不衛生な環境を避ける
・ノミ・ダニ対策(条虫予防にも有効)
獣医師からのメッセージ
消化管寄生虫は、症状が軽くても放置すると命に関わることがあります。特にジアルジアやコクシジウムは人への感染の可能性もあるため、早期発見・早期治療が大切です。
当院では、寄生虫検査から駆虫治療まで一貫して行っています。子犬・成犬ともに、健康診断時の検便を推奨しています。気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。