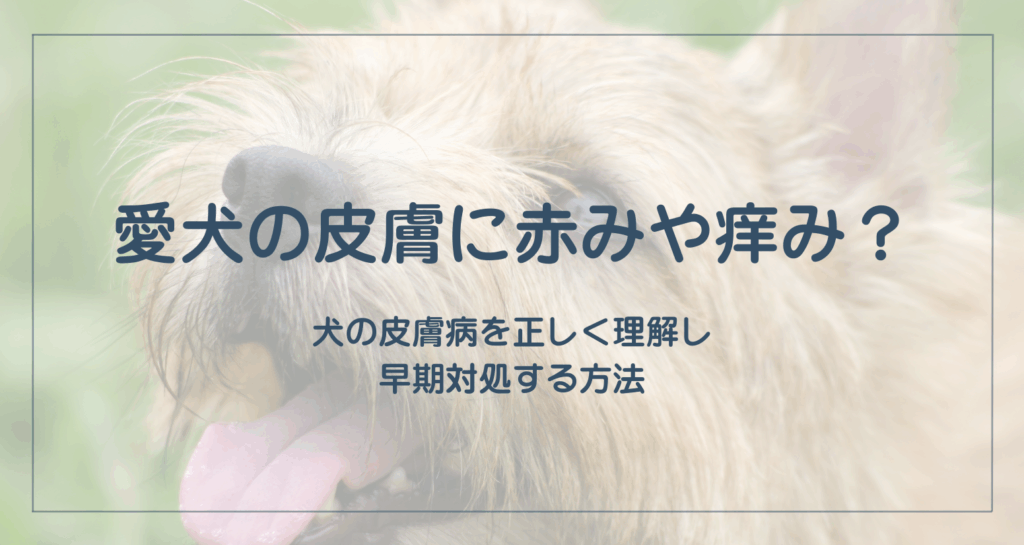
愛犬をなでていて、ふと赤いブツブツやかゆそうな仕草に気づいたことはありませんか?実は、動物病院への来院理由で最も多いのが皮膚のトラブルです。犬の皮膚病は決して珍しいものではなく、どの犬にも起こりうる身近な健康問題といえます。
しかし、「様子を見れば治るだろう」と放置してしまうのは危険です。かゆみや湿疹は適切な治療を受けないまま放置すると慢性化し、愛犬の生活の質を大幅に低下させてしまう可能性があります。また、細菌感染が進行すると、より深刻な皮膚疾患に発展することもあります。
この記事では、犬の皮膚病について以下の内容を詳しく解説します。
・犬の皮膚病の種類と症状
・皮膚病が起こる原因
・動物病院での診断・治療方法
・家庭でできるケアと予防策
・受診すべきタイミングの見極め方
愛犬の皮膚の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
1. 犬の皮膚病とは?
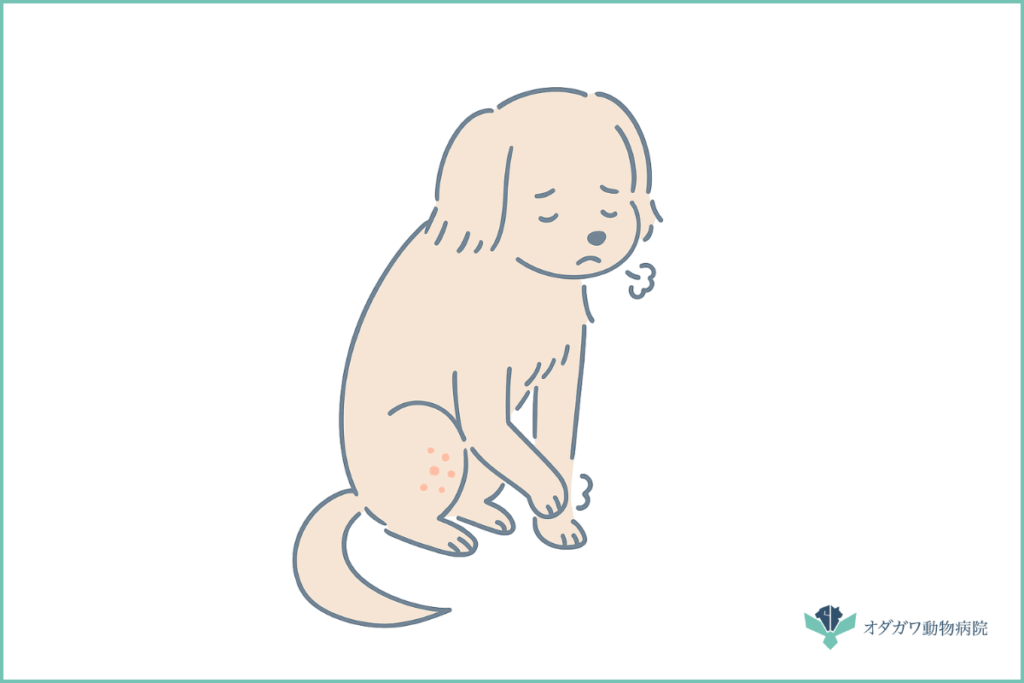
皮膚病の定義
犬の皮膚病とは、皮膚や被毛に炎症、発疹、かゆみなどの異常を引き起こす疾患の総称です。犬の皮膚は人間よりもデリケートで、様々な要因によって容易にトラブルを起こしやすい特徴があります。
主な症状
犬の皮膚病では、以下のような症状が見られます。
視覚的な症状
・皮膚の赤み(発赤)
・ブツブツとした発疹
・フケの増加
・被毛の脱毛
・皮膚の黒ずみ
・膿や分泌物
・皮膚の肥厚(厚くなる)
行動の変化
・頻繁に体を掻く
・特定の部位を舐め続ける
・地面や家具に体を擦りつける
・落ち着きがない
・睡眠の質の低下
飼い主が気づきやすいサイン
日頃の愛犬との触れ合いの中で、以下のようなサインに注意を向けてください。
触感の変化:いつもより皮膚がざらざらしている、べたつきがある
におい:普段と異なる体臭や、酸っぱいにおいがする
被毛の状態:毛艶が悪くなった、抜け毛が増えた
愛犬の様子:かゆそうにしている時間が増えた、元気がない
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が同時に見られることもあります。早期発見が治療成功の鍵となるため、日頃から愛犬の皮膚状態をチェックする習慣をつけることが大切です。
2. 犬の皮膚病でよく見られる種類
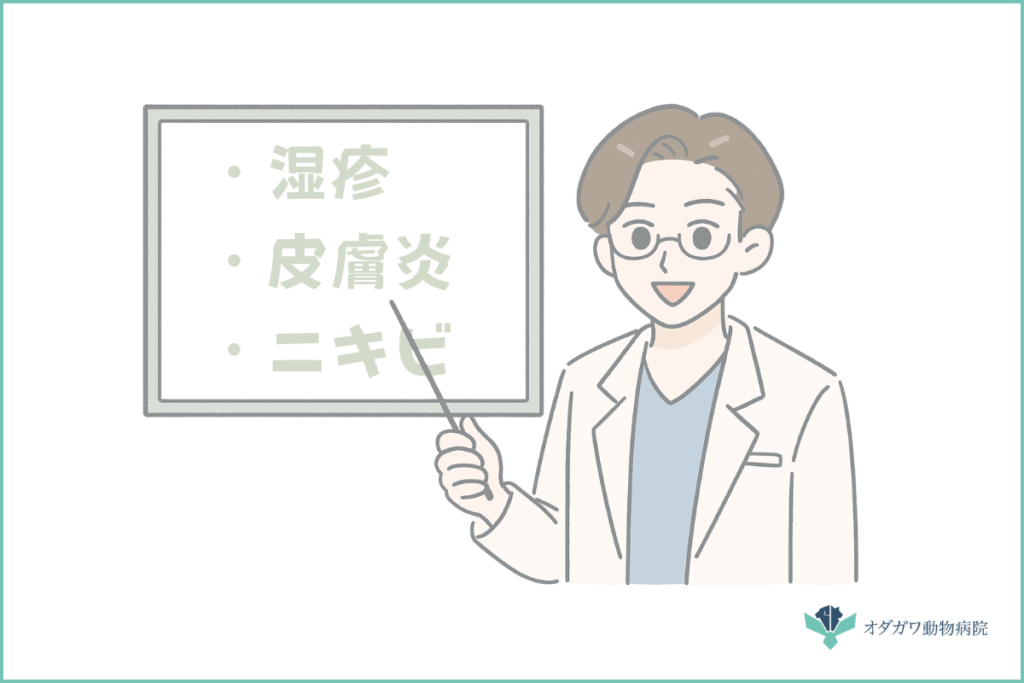
犬の皮膚病には多くの種類がありますが、特によく見られるものをご紹介します。
犬のニキビ
犬のニキビは、主に生後6か月から1歳程度の若い犬に多く見られる皮膚疾患です。人間の思春期ニキビと似た仕組みで発生し、毛穴に皮脂や角質が詰まることで起こります。
特徴
・口周り、あご、唇に小さなブツブツとして現れる
・初期は白っぽい小さな隆起
・進行すると赤く炎症を起こし、膿を持つこともある
・短毛種に多く見られる傾向
原因
・ホルモンの変化(成長期)
・毛穴の詰まり
・細菌の二次感染
・食器の汚れ(不衛生な環境)
犬の湿疹
犬の湿疹は、皮膚に赤みとかゆみを伴う炎症が起こる状態です。急性湿疹と慢性湿疹に分けられ、しばしば細菌や真菌感染も関与します。
急性湿疹の特徴
・突然現れる強い赤みとかゆみ
・ジュクジュクした分泌物
・短時間で症状が悪化する
・熱感を伴うことが多い
慢性湿疹の特徴
・長期間続く軽度から中等度のかゆみ
・皮膚の肥厚や色素沈着
・乾燥してカサカサした皮膚
・治療に時間がかかる
犬の皮膚炎
皮膚炎は犬の皮膚病の中でも特に多く見られ、原因によっていくつかの種類に分類されます。
アトピー性皮膚炎
・遺伝的要因による慢性的なアレルギー性皮膚炎
・目や口の周り、耳、脇、内股、指の間に症状が出やすい
・季節性の悪化を示すことが多い
・生涯にわたる管理が必要
アレルギー性皮膚炎
・特定のアレルゲン(食物、花粉、ダニなど)による反応
・原因物質の除去により改善が期待できる
・食物アレルギーの場合は消化器症状も併発することがある
ノミ・ダニによる皮膚炎
・寄生虫の咬傷や分泌物によるアレルギー反応
・強いかゆみと赤い発疹が特徴
・背中からお尻にかけて症状が現れやすい
・適切な駆虫により予防・治療が可能
その他の皮膚疾患
脂漏症
皮脂の分泌異常により皮膚がべたつく、またはフケが大量に出る疾患。遺伝的要因や内分泌疾患が関与することがあります。
膿皮症
細菌感染による皮膚の化膿性疾患。皮膚のバリア機能低下により細菌が異常増殖することで発症します。
真菌感染症(皮膚糸状菌症)
カビの一種である皮膚糸状菌による感染症。円形の脱毛が特徴的で、人にも感染する可能性があります。
3. 犬の皮膚病の主な原因
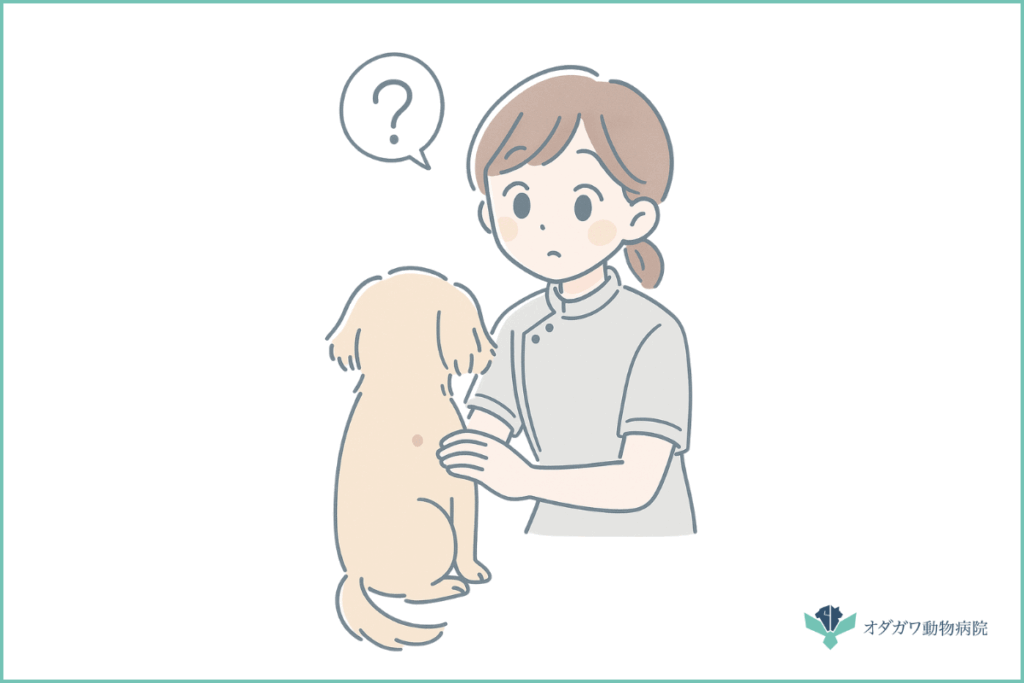
犬の皮膚病の原因は複雑で、しばしば複数の要因が組み合わさって発症します。主な原因を以下に分類して説明します。
外部要因
寄生虫
ノミ
最も一般的な皮膚病の原因。唾液に含まれる物質がアレルギー反応を引き起こす
ダニ
疥癬ダニ、ニキビダニなど様々な種類があり、それぞれ異なる症状を示す
シラミ
まれだが強いかゆみを引き起こす
微生物感染
細菌
黄色ブドウ球菌などが皮膚バリア機能の低下時に異常増殖
真菌
湿度の高い環境や免疫力低下時に感染しやすい
ウイルス
まれだが皮膚病の原因となることがある
内部要因
アレルギー体質
遺伝的にアレルギーを起こしやすい体質の犬は、様々な物質に対して皮膚炎を起こしやすくなります。特に以下の犬種でアトピー性皮膚炎が多く見られます。
・柴犬
・ゴールデンレトリーバー
・ラブラドールレトリーバー
・ウエストハイランドホワイトテリア
・シーズー
免疫異常
免疫システムの異常により、正常な皮膚組織を攻撃してしまう自己免疫疾患も皮膚病の原因となります。
ホルモン疾患
・甲状腺機能低下症
・副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
・性ホルモン異常
これらの内分泌疾患は皮膚の新陳代謝や免疫機能に影響を与え、皮膚病を引き起こしやすくします。
環境要因
シャンプー・グルーミング用品
・刺激の強いシャンプーの使用
・過度なシャンプー(皮膚の保護層を除去)
・シャンプー後の十分でない洗い流し
・不適切なグルーミング用品の使用
食事要因
・食物アレルギーを引き起こす特定のタンパク質
・栄養バランスの偏り
・必須脂肪酸の不足
・人工添加物への反応
環境ストレス
犬も人間と同様にストレスが皮膚の状態に影響を与えます。
・生活環境の変化
・飼い主の留守が長い
・新しいペットの導入
・騒音などの環境要因
物理的環境
・極度の乾燥や多湿
・季節の変わり目
・紫外線の過度な露出
・化学物質(洗剤、殺虫剤など)への接触
これらの原因を理解することで、愛犬の皮膚病の予防や治療方針の決定に役立ちます。多くの場合、複数の要因が関与しているため、包括的なアプローチが必要になります。
4. 動物病院での検査・診断方法
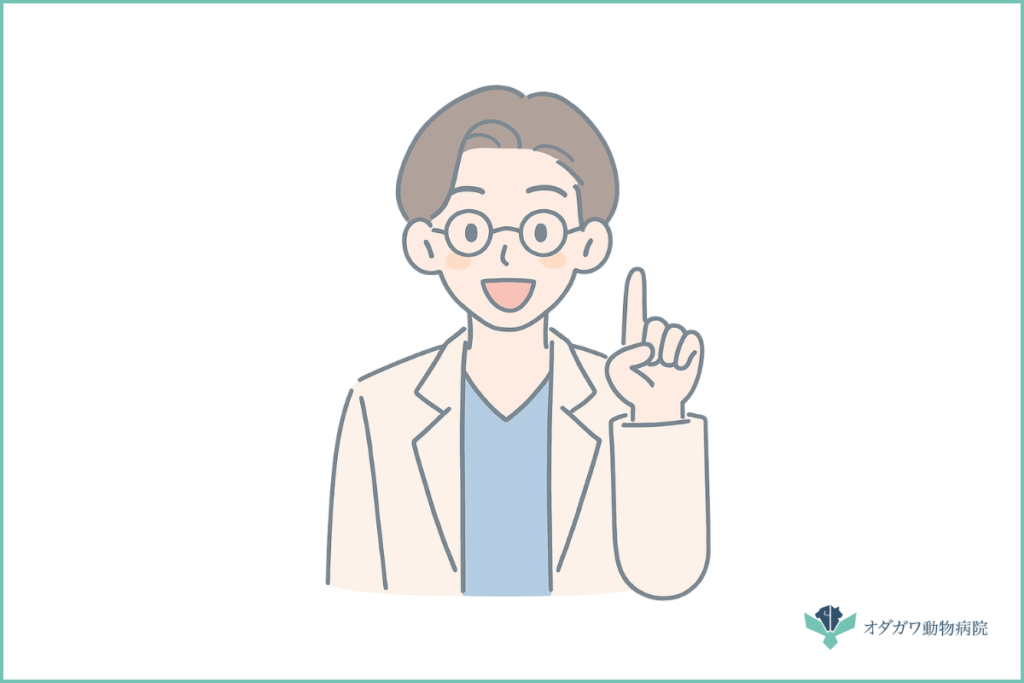
犬の皮膚病の適切な治療のためには、正確な診断が不可欠です。獣医師は以下のような検査を組み合わせて診断を行います。
基本的な診察
問診
・症状の発症時期と経過
・かゆみの程度と時間帯
・食事の内容と変更歴
・使用しているシャンプーやケア用品
・生活環境の変化
・他のペットとの接触歴
・過去の皮膚病の履歴
視診
・皮膚病変の分布パターンの確認
・発疹や脱毛の特徴の観察
・皮膚の色調や質感の評価
・全身状態の確認
触診
・皮膚の厚さや温度の確認
・リンパ節の腫大の有無
・痛みや敏感性の評価
専門的な皮膚検査
スタンプ検査
皮膚表面にスライドガラスを押し当てて採取した検体を顕微鏡で観察し、細菌や真菌、炎症細胞の有無を確認します。簡便で即座に結果が得られる検査です。
皮膚掻爬検査
皮膚の表面を削り取って検体を採取し、ダニなどの寄生虫や真菌を検出します。疥癬ダニやニキビダニの診断に特に有効です。
真菌培養検査
皮膚糸状菌感染が疑われる場合に行います。検体を特殊な培地で培養し、真菌の種類を特定します。結果が出るまで2-4週間要しますが、確定診断に重要な検査です。
細菌培養・感受性検査
重度の細菌感染や治療に反応しない症例で実施します。原因菌を特定し、最も効果的な抗菌薬を選択するための検査です。
高度な検査
アレルギー検査
血清IgE検査
環境アレルゲンに対する特異的IgE抗体を測定
食物除去試験
特定の食物を一定期間除去して反応を見る
皮内反応試験
皮膚にアレルゲンを注射して反応を確認
血液検査
・全身状態の評価
・内分泌疾患のスクリーニング
・炎症マーカーの測定
・免疫状態の確認
皮膚生検
診断が困難な症例や腫瘍性疾患が疑われる場合に実施します。皮膚の一部を採取して病理組織学的検査を行い、確定診断を得ます。
診断を誤らないために
皮膚病は症状が似ていても原因が全く異なることが多く、見た目だけでは正確な診断は困難です。例えば、同じような赤い発疹でも、アレルギー、細菌感染、真菌感染、寄生虫感染など様々な原因が考えられます。
不適切な治療は症状の悪化や慢性化を招く可能性があるため、獣医師による精密な検査と診断が必須です。また、皮膚病の中には人にも感染する可能性があるもの(皮膚糸状菌症など)もあるため、早期の正確な診断が飼い主の健康を守ることにもつながります。
5. 治療方法

犬の皮膚病の治療は、原因や症状の程度に応じて様々な方法を組み合わせて行います。獣医師が適切な診断を行った後、個々の症例に最適な治療計画を立案します。
外用薬による治療
抗菌・抗真菌軟膏
・細菌や真菌感染に対して直接的な効果を発揮
・患部に直接塗布することで高い薬物濃度を維持
・副作用が少なく、長期使用も可能
・代表的な薬剤:ムピロシン、クロトリマゾール、ケトコナゾールなど
ステロイド軟膏
・炎症とかゆみを速やかに抑制
・アレルギー性皮膚炎や湿疹に特に効果的
・使用期間や範囲を適切に管理する必要がある
・長期使用時は皮膚の薄化や色素沈着に注意
保湿剤・皮膚保護剤
・皮膚のバリア機能を回復・維持
・乾燥による症状の悪化を防ぐ
・セラミドやヒアルロン酸含有製剤が効果的
・治療と並行して継続的に使用
内服薬による治療
抗ヒスタミン薬
・アレルギー反応によるかゆみを軽減
・比較的副作用が少なく安全性が高い
・効果に個体差があるため、複数の薬剤を試すことがある
・代表的な薬剤:ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミンなど
抗菌薬
・細菌感染に対する全身治療
・膿皮症や深部感染に必要
・適切な期間(通常2-6週間)の投与が重要
・途中で中断せず、完全に治療することが再発防止の鍵
免疫抑制剤
・重度のアトピー性皮膚炎や自己免疫疾患に使用
・シクロスポリンやステロイド剤が主流
・定期的な血液検査による副作用のモニタリングが必要
・長期管理が必要な症例で重要な選択肢
かゆみ止め(新しい作用機序の薬剤)
・オクラシチニブ(アポキル):JAK阻害薬
・従来の治療で効果不十分な症例にも有効
・速やかなかゆみの改善が期待できる
・適切な使用により副作用のリスクを最小化
シャンプー療法
皮膚病の治療において、適切なシャンプー療法は薬物治療と同じくらい重要な役割を果たします。
低刺激シャンプー
・敏感な皮膚に優しい成分
・皮膚のpHバランスを維持
・日常的なケアに適している
・オートミール、アロエベラ配合製剤が人気
薬用シャンプー
抗菌・抗真菌シャンプー
クロルヘキシジン、ケトコナゾール配合
角質溶解シャンプー
サリチル酸、硫黄配合で余分な角質を除去
保湿シャンプー
セラミド、オメガ脂肪酸配合で皮膚バリア機能をサポート
シャンプーの適切な方法
・ぬるま湯(37-38度)で予洗い
・シャンプーをよく泡立てて優しくマッサージ
・5-10分間放置(薬用シャンプーの場合)
・十分にすすぐ(シャンプー剤が残らないよう注意)
・タオルで優しく水分を拭き取る
・必要に応じてドライヤーで完全に乾燥
食事療法
アレルギー対応食
限定原料食
アレルギーを起こしにくい単一のタンパク源を使用
加水分解食
タンパク質を小さく分解してアレルギー反応を抑制(8-12週間の食事試験により効果を判定)
皮膚サポート食
・オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)を豊富に含有
・抗炎症作用により皮膚の健康を維持
・ビタミンE、亜鉛などの皮膚に重要な栄養素を強化
慢性化した症例への対応
皮膚病が慢性化してしまった場合、以下のような長期管理が必要になります。
定期的な通院
・2-4週間ごとの経過観察
・治療効果の評価と調整
・副作用のモニタリング
・再発の早期発見
生活習慣の改善
・ストレス軽減のための環境整備
・適切な運動と休息のバランス
・室内の湿度・温度管理
・定期的なグルーミングとスキンケア
飼い主教育
・病気に対する正しい理解
・薬物投与方法の指導
・症状悪化の兆候の見分け方
・長期管理の重要性の説明
慢性皮膚病は「治す」より「管理する」という考え方が重要です。適切な治療により症状をコントロールし、愛犬のQOL(生活の質)を維持することが最大の目標となります。
6. 飼い主ができるホームケアと予防策
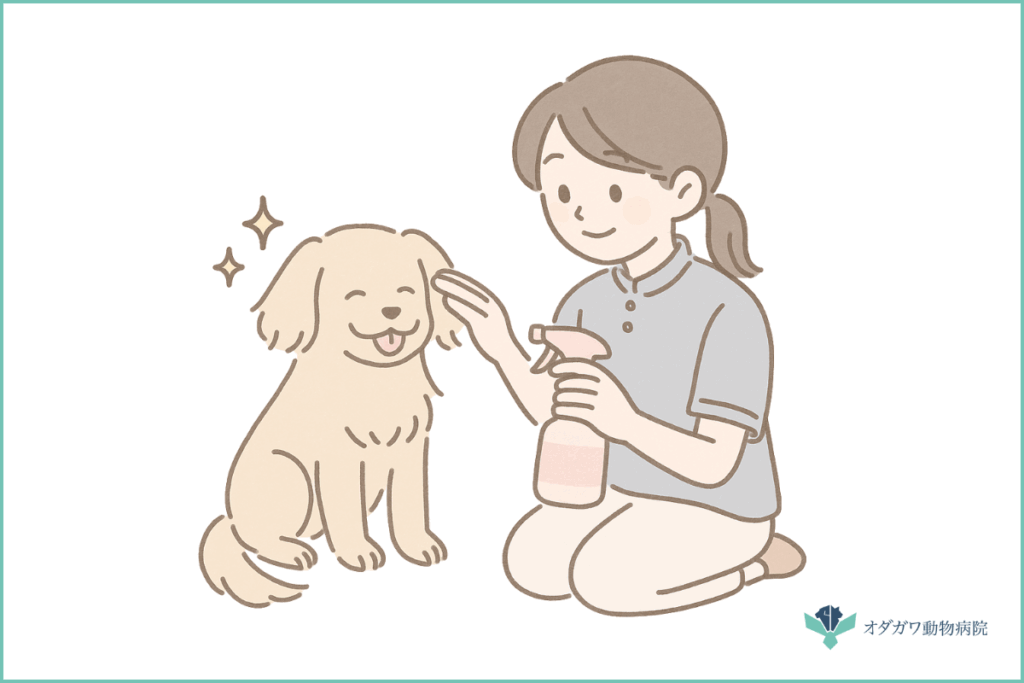
動物病院での治療と並行して、家庭でのケアは皮膚病の改善と予防に大きな役割を果たします。日常的な心がけが愛犬の皮膚の健康を長期的に守ることにつながります。
定期的なシャンプーとブラッシング
適切なシャンプー頻度
・健康な犬:2-4週間に1回
・皮膚病の犬:獣医師の指示に従い、週1-2回の場合もある
・症状や季節に応じた頻度の調整が重要
ブラッシングの重要性
毎日のブラッシングにより以下の効果が得られます。
・死毛や汚れの除去
・皮膚の血行促進
・皮脂の分散による天然保湿効果
・皮膚の異常の早期発見
・愛犬とのコミュニケーション強化
長毛種の特別なケア
・毛玉の予防(毛玉は皮膚の通気性を悪化させる)
・耳の中、脇の下、内股など蒸れやすい部位の重点ケア
・季節の変わり目の集中的なブラッシング
栄養面からのアプローチ
皮膚の健康に重要な栄養素
オメガ3脂肪酸
・EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)
・抗炎症作用により皮膚の炎症を軽減
・魚油、亜麻仁油、チアシードに豊富
・サプリメントでの補給も効果的
オメガ6脂肪酸
・リノール酸、アラキドン酸
・皮膚バリア機能の維持に必要
・鶏脂、大豆油などに含有
・オメガ3とのバランスが重要(理想比率1:5-10)
ビタミンE
・強力な抗酸化作用
・皮膚細胞の老化を防ぐ
・植物油、ナッツ類、緑黄色野菜に豊富
亜鉛
・皮膚の新陳代謝に不可欠
・創傷治癒の促進
・肉類、魚類、穀類に含有
良質なタンパク質
・皮膚と被毛の主成分
・必須アミノ酸をバランスよく含む食品
・消化しやすい動物性タンパク質が理想
室内環境の管理
湿度と温度の管理
・適度な湿度(40-60%)の維持
・急激な温度変化の回避
・加湿器や除湿機の適切な使用
・エアコンの直風を避ける
清潔な環境の維持
寝具の定期洗濯
週1-2回、無香料洗剤使用
掃除機がけ
アレルゲン(ダニ、花粉)の除去
空気清浄機の使用
空中アレルゲンの減少
食器の清潔管理
細菌繁殖の防止
化学物質の除去
・強い洗剤や芳香剤の使用を控える
・天然成分の清掃用品への切り替え
・殺虫剤の使用時は愛犬を別室に移動
・新しいカーペットや家具の十分な換気
ストレス軽減
規則正しい生活リズム
・食事・散歩・睡眠時間の一定化
・予測可能な日課によるストレス軽減
・十分な睡眠時間の確保
適度な運動
・犬種・年齢に応じた運動量
・散歩による外部刺激とストレス解消
・室内でのプレイタイムの確保
・過度な運動による疲労は避ける
安心できる環境
・愛犬専用のリラックススペース
・騒音の少ない静かな場所
・他のペットとの適切な距離感
・飼い主との十分なコミュニケーション時間
皮膚病を繰り返さないための工夫
早期発見のためのセルフチェック
毎日の観察
撫でながら皮膚の状態を確認
週1回の詳細チェック
全身の皮膚を隅々まで観察
記録の習慣
症状や変化をメモやアプリで記録
写真による記録
症状の推移を視覚的に管理
予防的なケアの継続
・症状が改善しても油断せず継続ケア
・獣医師指示のシャンプー療法の継続
・サプリメントの適切な使用
・定期健康診断での皮膚チェック
アレルゲンの回避
・判明しているアレルゲンとの接触を避ける
・新しい食品の導入は慎重に
・季節性アレルギーの場合は該当時期の予防策強化
・散歩コースや時間の調整
これらのホームケアは即効性はありませんが、継続することで愛犬の皮膚の基礎的な健康状態を向上させ、皮膚病の予防と再発防止に大きく貢献します。何より、日々の愛犬との触れ合いを通じて、小さな変化に気づくことができるようになることが最大のメリットといえるでしょう。
7. 動物病院を受診すべきタイミング

愛犬の皮膚に異常を発見した時、「様子を見るべきか」「すぐに病院へ行くべきか」迷うことがあると思います。適切なタイミングでの受診は、治療効果を高め、愛犬の苦痛を最小限に抑えるために極めて重要です。
緊急受診が必要な症状
以下の症状が見られる場合は、できるだけ早急に動物病院を受診してください。
強いかゆみで日常生活に支障をきたしている
・夜中も掻き続けて眠れない状態
・食事中も掻くのをやめられない
・散歩に集中できないほどのかゆみ
・掻きすぎて出血している状態
出血や深い傷がある
・掻きすぎによる出血
・皮膚に深い傷や裂傷
・血が止まらない状態
・傷口が化膿している兆候
急速な脱毛や範囲の拡大
・24-48時間で明らかに脱毛範囲が広がっている
・円形脱毛が複数箇所に出現
・全身に症状が急速に広がっている
・顔面の腫れを伴う脱毛
化膿・強いにおいがある
・膿のような分泌物が出ている
・腐敗臭や強い悪臭がする
・皮膚が熱を持って腫れている
・全身状態の悪化(元気消失、食欲不振)
早めの受診が推奨される症状
持続的な症状
・軽度でも1週間以上続くかゆみ
・フケが急に増加した状態
・皮膚の赤みが改善しない
・毛艶の著しい悪化
行動の変化
・特定の部位を執拗に舐め続ける
・体を家具や地面に擦りつける頻度の増加
・触られることを嫌がるようになった
・普段よりも落ち着きがない
季節性の症状
・毎年同じ時期に皮膚症状が現れる
・季節の変わり目に症状が悪化
・特定の環境で症状が出現
様子を見てもよい軽微な症状
以下の軽微な症状の場合は、2-3日程度様子を見ることも可能です。
・軽度のフケの増加(かゆみを伴わない)
・小さな赤い点が1-2個程度
・軽微な毛艶の変化
・一時的な軽いかゆみ
ただし、これらの症状でも悪化傾向にある場合や、他の症状が併発した場合は早めの受診を検討してください。
早期受診の重要性
皮膚病は初期段階での治療が最も効果的です。症状が軽いうちに適切な治療を開始することで、以下のメリットがあります。
・治療期間の短縮
・使用する薬剤の減量
・副作用のリスク軽減
・治療費の削減
慢性化の防止
放置された皮膚病は慢性化しやすく、一度慢性化すると完治が困難になります。
・皮膚の構造的変化(肥厚、色素沈着)
・細菌の二次感染
・アレルギーの悪化
・生活の質の著しい低下
人への感染リスクの回避
一部の皮膚病(皮膚糸状菌症、疥癬など)は人にも感染する可能性があります。早期診断により適切な予防策を講じることができます。
正確な診断の重要性
似たような症状でも原因が全く異なることがあります。自己判断による市販薬の使用は、時として症状を悪化させる可能性があるため、専門家による診断が不可欠です。
8. まとめ
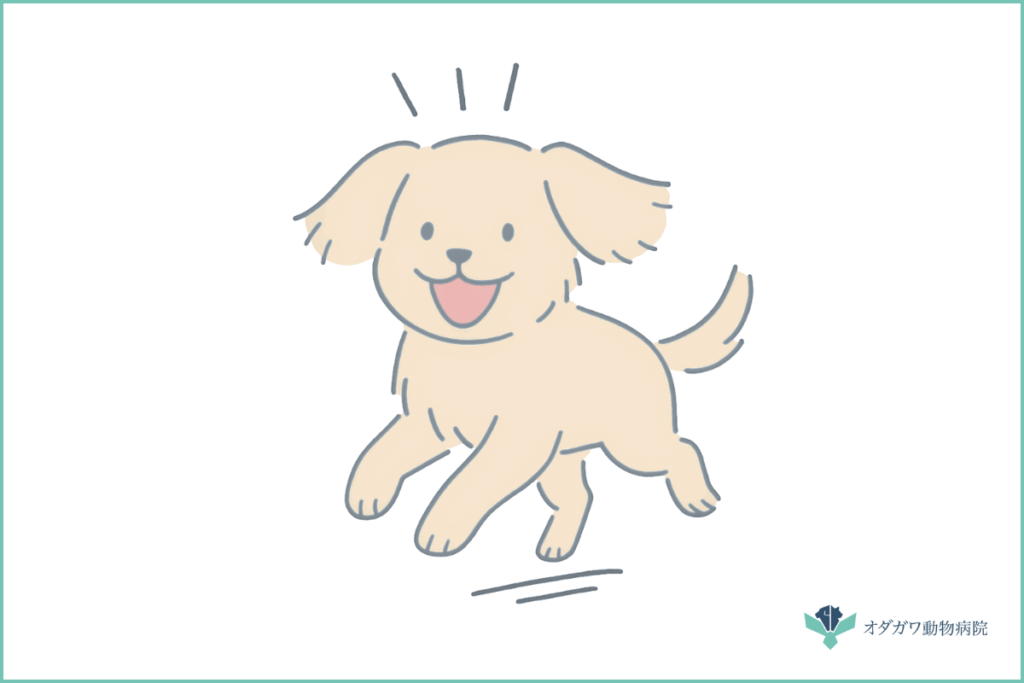
犬の皮膚病は非常に身近で頻度の高い健康問題ですが、適切な知識と対応により、多くの場合で良好な管理が可能です。
犬の皮膚病の特徴
犬の皮膚病は種類が多様で、原因も複雑に絡み合っていることが特徴です。主な皮膚疾患として、若い犬に多い犬のニキビ、かゆみと赤みが特徴的な犬の湿疹、そして最も頻度の高い犬の皮膚炎(アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、寄生虫による皮膚炎)があります。
これらの疾患は、外部要因(寄生虫、細菌、真菌)、内部要因(アレルギー体質、免疫異常、ホルモン疾患)、環境要因(シャンプー、食事、ストレス)が複雑に関与して発症します。
放置は厳禁
皮膚病において最も重要なのは、「放置せずに早期受診すること」です。軽微に見える症状でも、適切な治療を受けないまま放置すると
・症状の慢性化
・二次感染の併発
・治療の複雑化・長期化
・愛犬のQOL(生活の質)の著しい低下
これらのリスクが高まります。強いかゆみ、出血、急速な悪化、化膿、悪臭などの症状が見られる場合は、迷わず緊急受診してください。
日常ケアと獣医師の診断の両立
皮膚の健康維持には普段のケアと獣医師の専門的な診断・治療の両方が欠かせません。
家庭でできること
・定期的で適切なシャンプーとブラッシング
・皮膚に良い栄養素(オメガ3脂肪酸、ビタミンE、亜鉛)を含む食事
・室内環境の清潔維持と湿度管理
・ストレス軽減のための規則正しい生活
・毎日の皮膚チェックと早期発見
獣医師による専門医療
・正確な診断のための各種検査
・原因に応じた適切な治療方法の選択
・薬物療法の安全な管理
・慢性疾患の長期管理計画
長期管理の重要性
多くの皮膚病、特にアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患は、「完治」よりも「適切な管理」が治療の目標となります。定期的な通院により症状をコントロールし、愛犬が快適に生活できる状態を維持することが最も重要です。
飼い主様には、皮膚病を「一時的な病気」ではなく、「愛犬と長く付き合っていく健康管理の一部」として捉えていただき、根気強く治療とケアを続けていただくことをお願いいたします。
当院でのサポート
当院では、皮膚病でお困りの飼い主様と愛犬に対して、以下のようなサポートを提供しております。
・詳細な皮膚検査と正確な診断
・個々の症例に応じたオーダーメイド治療
・ホームケア方法の丁寧な指導
・定期的なフォローアップと治療調整
・慢性疾患の長期管理サポート
皮膚のトラブルでご心配なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。愛犬の皮膚の健康を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

よくある質問(FAQ)
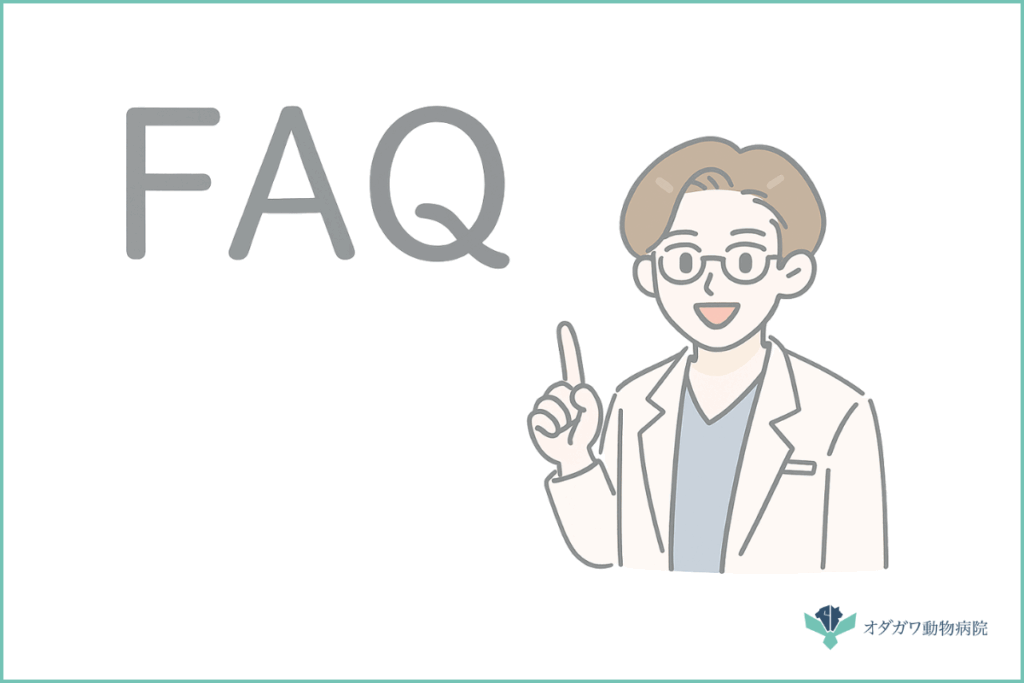
Q1. 犬の皮膚病は自然に治りますか?
A: 軽微な皮膚の赤みやかゆみは、原因が除去されれば自然に改善することもあります。しかし、細菌感染、真菌感染、アレルギー性皮膚炎などの多くの皮膚病は、適切な治療なしには改善せず、むしろ悪化する傾向があります。特に強いかゆみがある場合、愛犬が掻き続けることで症状が悪化し、二次感染を起こすリスクも高まります。早期の獣医師による診断と適切な治療が、愛犬の苦痛を最小限に抑え、早期回復につながります。
Q2. 犬の皮膚病は人にうつりますか?
A: 犬の皮膚病の中で人にも感染する可能性があるのは、主に皮膚糸状菌症(真菌感染)と疥癬です。皮膚糸状菌症は円形脱毛が特徴的で、人では「白癬(はくせん)」として知られています。疥癬は激しいかゆみを引き起こすダニによる感染症です。一方、アレルギー性皮膚炎やアトピー性皮膚炎などは感染性ではないため、人にうつることはありません。愛犬に皮膚病が見つかった場合は、獣医師に感染の可能性について確認し、必要に応じて人への予防策についてもアドバイスを受けることをお勧めします。
Q3. 犬の皮膚病に良い食べ物はありますか?
A: 皮膚の健康に特に重要な栄養素として、オメガ3脂肪酸(魚油、亜麻仁油に豊富)、良質なタンパク質(消化しやすい鶏肉、魚肉)、ビタミンE(植物油、ナッツ類)、亜鉛(肉類、魚類)があります。これらの栄養素は皮膚の炎症を抑制し、バリア機能を向上させます。ただし、食物アレルギーがある場合は、アレルゲンとなる食材を避ける必要があります。市販の皮膚サポート用フードや、獣医師指導のもとでの食事療法も効果的です。サプリメントの使用については、必ず獣医師に相談してから始めることをお勧めします。
獣医師厳選のペットフードはこちら↓















