
毎年相談が増える「フィラリア症」
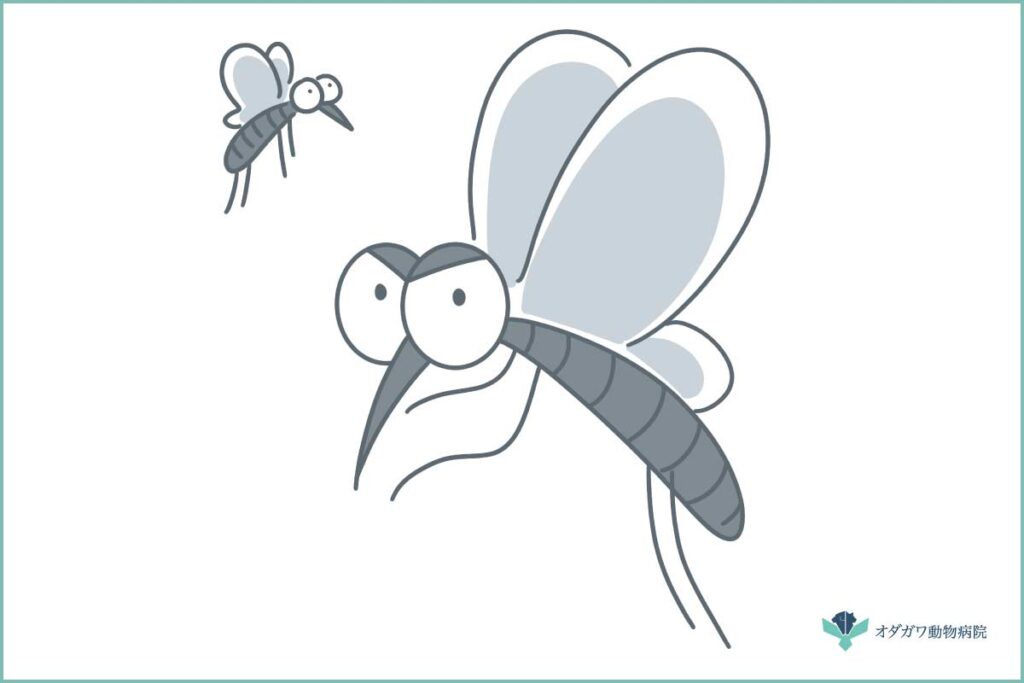
実際の飼い主からの相談事例
春から夏にかけて、当院には多くの飼い主さんからフィラリア症に関する相談が寄せられます。
「最近、愛犬の咳が続いているんです。夜中に苦しそうに咳き込むことが多くて…」
「実は昨年、フィラリアの予防薬を数回飲ませ忘れてしまって。今年検査を受けた方がいいでしょうか?」
「近所の犬がフィラリアで亡くなったと聞いて、うちの子も心配になりました」
これらの相談の多くは、フィラリア症に対する不安や、予防の重要性を実感したときに寄せられるものです。特に印象深いのは、「予防薬を飲ませていたつもりだったのに、実際には不十分だった」というケースです。
フィラリアは「予防できるのに命を落とす」ことがある病気
フィラリア症は、適切な予防さえ行えば100%防げる病気です。しかし、予防を怠ったり、中途半端な予防しか行わなかったりすると、愛犬の命を奪う可能性のある深刻な疾患でもあります。
現代の獣医療では、フィラリア症は「予防が治療に勝る」代表的な疾患として位置づけられています。治療が困難で、犬にとって大きな負担となる一方で、予防は比較的簡単で確実な方法が確立されているからです。
毎年春になると、「去年予防をしていなかったから検査を受けたい」という飼い主さんが来院されます。検査の結果、陽性反応が出たときの飼い主さんの表情は、今でも忘れることができません。「もっと早く、きちんと予防していれば…」という後悔の念が、その表情から伝わってくるのです。
当院では毎年100件以上の予防診療・検査を実施
当院では、毎年春から夏にかけて100件以上のフィラリア予防診療と検査を実施しています。この数字は、地域の飼い主さんがフィラリア予防に対する意識を高く持っていることを示している一方で、まだまだ予防の重要性を十分に理解していない方も多いことを物語っています。
年々、予防に対する関心は高まっているものの、「うちの犬は室内飼いだから大丈夫」「マンションの高層階に住んでいるから蚊はいない」といった誤解から、予防を怠ってしまうケースも少なくありません。
実際に、当院で行った過去5年間の統計では、フィラリア予防を全く行っていなかった犬の約35%が陽性反応を示しました。この数字は、地域の蚊の発生状況や気候条件によって変動しますが、予防の重要性を示す明確な証拠となっています。
犬のフィラリア症とは?
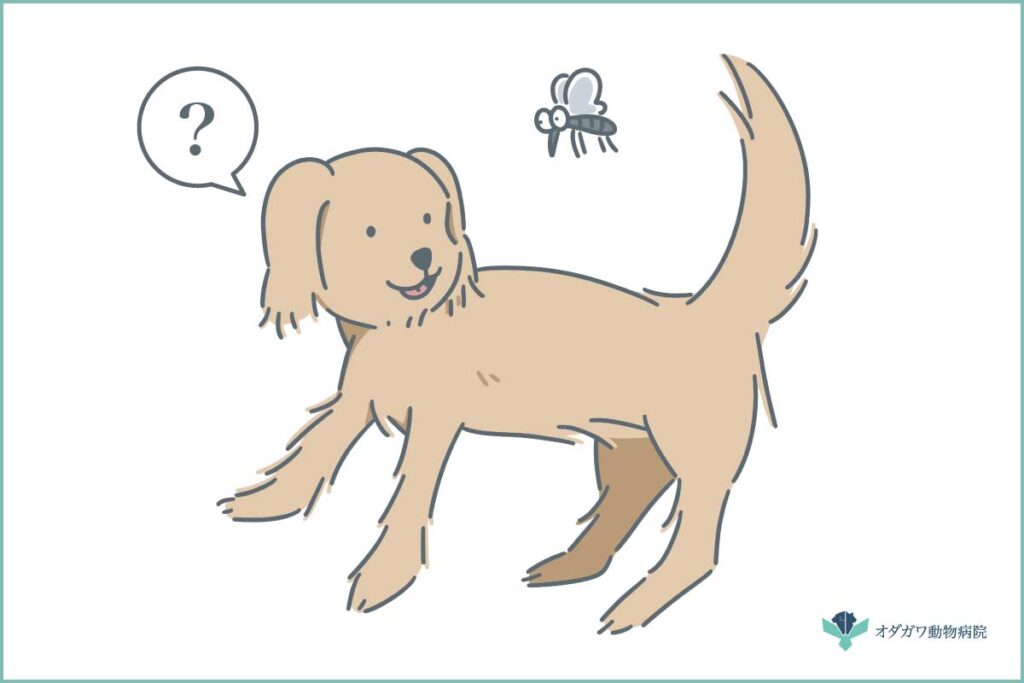
蚊から感染する寄生虫疾患(犬糸状虫)
フィラリア症は、正式には「犬糸状虫症」と呼ばれる寄生虫疾患です。
原因となるのは犬糸状虫(Dirofilaria immitis)という線虫で、成虫は細長い糸状の形をしています。
感染のメカニズムは以下の通りです。
1.蚊が感染犬を吸血
フィラリアに感染した犬の血液中には、ミクロフィラリアという幼虫が循環している
2.蚊の体内で発育
吸血した蚊の体内で、ミクロフィラリアが感染力を持つL3幼虫まで成長
3.健康な犬への感染
感染した蚊が健康な犬を吸血する際、L3幼虫が犬の体内に侵入
4.犬の体内で成長
L3幼虫は犬の体内で約6か月かけて成虫まで成長し、心臓や肺動脈に定着
このプロセスで重要なのは、犬から犬への直接感染はなく、必ず蚊を介して感染するという点です。つまり、蚊がいる環境であれば、どんな犬でも感染のリスクがあるということです。
放置すれば心不全・内臓疾患を引き起こす致命的な病気
フィラリア成虫は、主に犬の心臓の右心房・右心室、および肺動脈に寄生します。成虫の長さは雌で20-30cm、雄で12-20cmに達し、1匹の犬に数十匹から数百匹が寄生することもあります。
実際に見られた症状例
症例1:7歳のゴールデンレトリーバー(雄)
飼い主さんは「最近散歩中に疲れやすくなった」と相談に来られました。詳しく聞くと、以前は1時間の散歩も平気だったのに、最近は30分程度で座り込んでしまうとのこと。検査の結果、フィラリア陽性で、心臓の拡大も認められました。
症例2:5歳の柴犬(雌)
「夜中に咳き込んで眠れない」という主訴で来院。乾いた咳が続き、特に興奮時や運動後に悪化するという症状でした。レントゲン検査で肺動脈の拡大が確認され、フィラリア感染による肺高血圧症と診断されました。
症例3:9歳の雑種犬(雄)
「お腹が膨らんできた」という相談でした。実際に診察すると腹水が貯留しており、フィラリア症による右心不全が原因でした。この段階になると、治療は非常に困難になります。
これらの症例に共通するのは、初期症状が見逃されやすく、飼い主さんが気づいた時には既に進行していることです。そのため、症状が現れる前の予防が何よりも重要になります。
フィラリア症の進行と症状
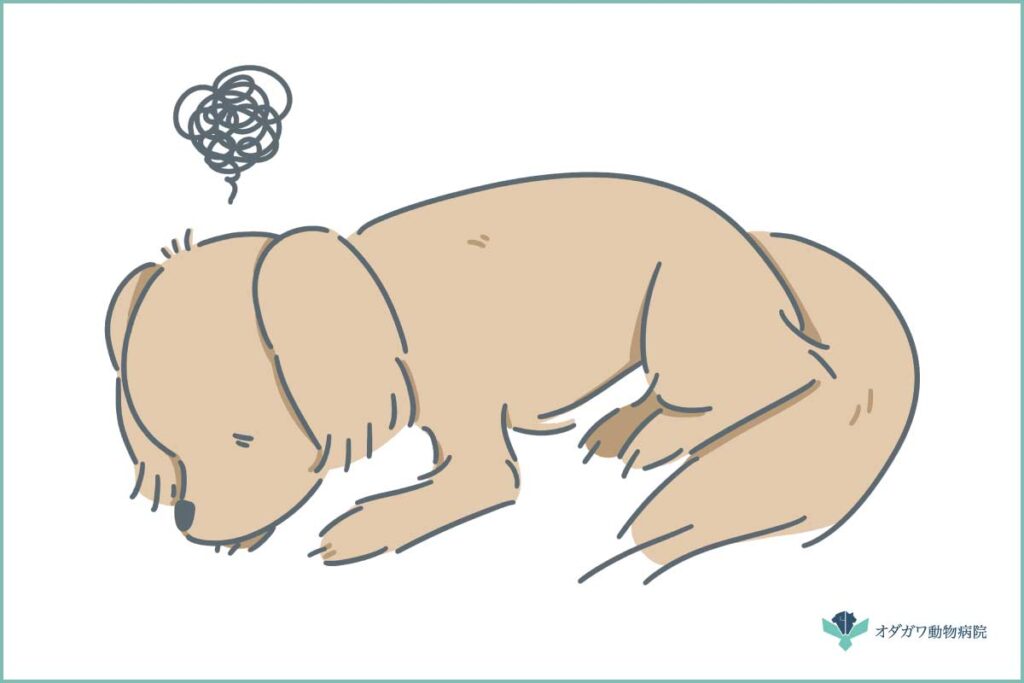
フィラリア症の症状は、感染から時間が経つにつれて段階的に進行します。この進行パターンを理解することで、早期発見の可能性が高まります。
初期症状
・咳が増える
・散歩中に疲れやすい
・運動を嫌がる
・毛艶の低下
この段階では、多くの飼い主さんが「年のせいかな」「少し太ったかな」程度にしか感じないことが多く、見逃されがちです。
中期症状
・呼吸が速くなる
・食欲が減る
・体重の減少
この段階になると、飼い主さんも「何かおかしい」と感じ始めますが、まだ他の心疾患や呼吸器疾患と区別が困難な場合があります。
末期症状
・血尿(赤茶色)
・腹水、むくみ
・失神や突然死
末期になると、治療は極めて困難になり、犬の生命に直接関わる状態となります。特に「大静脈症候群」と呼ばれる状態では、大量の成虫が大静脈に移動し、急激な循環不全を引き起こすことがあります。
「食欲がない」という主訴で受診された犬が、検査によりフィラリア陽性と判明した事例もあります。飼い主様が異変に気づき、早期に相談されたことで大事に至らずに済んだケースです。
当院で実際に見つかった”無症状だけど陽性だったケース”の紹介
フィラリア症の最も恐ろしい点は、症状が現れる前に既に深刻な感染が進行していることです。当院で経験した印象的なケースをご紹介します。
ケース1:4歳のボーダーコリー
年1回の健康診断で来院。飼い主さんは「とても元気で、何の症状もない」と話していました。しかし、フィラリア検査で陽性反応が出たため、詳しい検査を実施。エコー検査では、心臓内に複数のフィラリア成虫が確認されました。症状がないにも関わらず、既に重度の感染状態だったのです。
ケース2:6歳のトイプードル
フィラリア予防を「たまに忘れることがある」程度で行っていた犬です。検査の結果、陽性反応が出ましたが、普段の生活では全く症状を示していませんでした。しかし、心臓の機能検査では、既に軽度の心機能低下が認められました。
ケース3:8歳の柴犬
「室内飼いだから大丈夫」と思い、予防を全く行っていなかった犬です。健康診断で偶然発見されましたが、症状は皆無でした。しかし、血液検査では炎症反応が高く、心臓の負担が相当大きいことが判明しました。
これらのケースが示すように、フィラリア症は「症状がない=感染していない」ではありません。むしろ、症状が現れる前に検査で発見することが、治療成功の鍵となります。
フィラリア予防の考え方
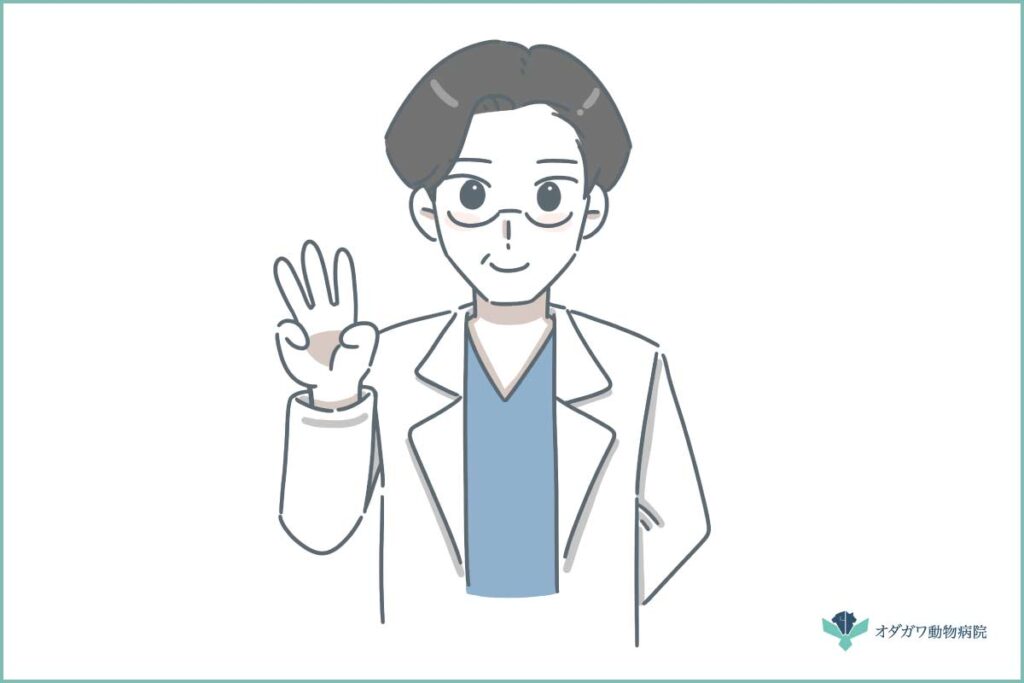
「フィラリア薬を飲ませれば大丈夫」と思われがちですが、実際には個体差や犬種によってリスクが異なります。
当院では、以下の3ステップを基本方針としています。
1.事前検査の徹底
フィラリア予防薬の投与前には、毎年必ずフィラリア感染の有無を検査する必要があります。万が一、すでに感染している状態で予防薬を投与すると、体内の虫が一斉に死滅することでショック症状を起こすリスクがあるためです。
2.ライフスタイルに合わせた薬の選定
犬の年齢や体重、性格、生活環境によって、最適な予防薬は異なります。毎月与えるタイプが向いている子もいれば、年1回の注射が向いている場合もあります。飼い主のライフスタイルや投薬のしやすさも含めて選ぶことが大切です。
特定の犬種(例:コリー系)にはイベルメクチン系の薬で副作用が出るリスクがあるため、必ず体質確認と安全な製剤の選定を行います。
3.継続管理のサポート
予防は一度きりではなく、毎月または年間を通じて継続することが重要です。投与のタイミングや体調変化の確認など、定期的なサポートやフォローアップにより、より確実な予防効果を得ることができます。
定期通院が難しい方には注射型予防も提案していますが、副作用や体調変化についての説明と同意を得ることを大切にしています。おやつ型のチュアブルが好きな犬には、味の好みを考慮して複数メーカーから選べるよう対応しています。
予防薬の種類と選び方

フィラリア予防薬には、投与方法によって大きく4つのタイプがあります。それぞれに特徴があり、犬の性格や飼い主さんの生活スタイルに合わせて選択することが重要です。
チュアブル(おやつ)タイプの特徴と適用
現在最も人気の高い剤形で、犬が喜んで食べるおやつのような形状をしています。ビーフやチキン味など、犬の嗜好に合わせた風味が付けられており、多くの犬が「薬」というよりも「おやつ」として認識するため、投薬のストレスが格段に軽減されます。
この形状の最大の利点は、投薬の確実性です。飼い主さんが直接犬に手渡すことで、確実に摂取したことを確認できます。また、薬を隠したり、無理やり飲ませたりする必要がないため、犬との信頼関係を損なうこともありません。多頭飼いのご家庭でも、各犬に個別に与えることで、投薬の管理が簡単になります。
ただし、食べ物アレルギーのある犬や、普段から食欲不振の犬には適さない場合があります。また、保存方法に注意が必要で、高温多湿な場所に置くと品質が劣化する可能性があります。コスト面では他の剤形と比較してやや高価になる傾向がありますが、投薬の確実性を考慮すると、その価値は十分にあると考えられます。
錠剤タイプの特徴と適用
従来から使用されている最も一般的な剤形で、確実な効果が期待できます。有効成分が安定しており、長期保存が可能で、コストパフォーマンスにも優れています。獣医療の現場では、最も実績のある剤形として位置づけられています。
錠剤タイプの利点は、その確実性と経済性です。有効成分の濃度が正確に管理されており、品質のばらつきが少ないため、予防効果に関して最も信頼性の高い選択肢と言えます。また、保存が容易で、適切な環境で保管すれば長期間品質を保つことができます。
一方で、投薬には一定の技術が必要です。犬の口を開けて舌の奥に錠剤を置き、口を閉じて飲み込むまで待つという一連の動作は、慣れていない飼い主さんには難しく感じられるかもしれません。また、犬によっては錠剤を嫌がり、飲み込まずに吐き出してしまうこともあります。このような場合、飼い主さんは投薬が確実に行われたかどうかを確認する必要があります。
スポット(滴下)タイプの特徴と適用
首筋に薬液を垂らすだけの簡単な投与方法で、経口投与が困難な犬にも使用できる便利な剤形です。投薬のストレスが少なく、胃腸が弱い犬や高齢犬にも安心して使用できます。
この剤形の最大の利点は、投与の簡便性です。犬の首筋の被毛をかき分けて皮膚に直接薬液を垂らすだけで、投薬が完了します。口を開けたり、薬を飲み込ませたりする必要がないため、投薬を嫌がる犬にも比較的容易に使用できます。また、経口投与で胃腸障害を起こしやすい犬にも適しています。
しかし、皮膚トラブルのリスクがあることも事実です。薬液が皮膚に合わない場合、発赤や発疹、かゆみなどの皮膚炎を引き起こす可能性があります。また、被毛の多い犬種では、薬液が皮膚まで届かず、十分な効果が得られない場合もあります。投与後は一定期間入浴を控える必要があり、他のペットや小さな子供との接触にも注意が必要です。
注射タイプの特徴と適用
年1回の注射で1年間の予防効果が得られる、最も確実な予防方法です。投薬忘れの心配がなく、飼い主さんの負担が最小限に抑えられます。多頭飼いでも管理が簡単で、長期間の確実な予防を望む方に適しています。
この方法の最大の利点は、その確実性と持続性です。一度注射を受ければ、1年間は確実に予防効果が持続します。投薬忘れやアクシデントによる投薬失敗のリスクがないため、最も信頼性の高い予防方法と言えるでしょう。また、飼い主さんの日常的な管理負担がなく、多忙な方や多頭飼いの方には特に適しています。
一方で、注射による痛みやストレスは避けられません。特に注射を嫌がる犬には、相当なストレスとなる可能性があります。また、万一副作用が発生した場合、効果が長期間続くため、対応が困難になることもあります。注射部位の腫れや硬結が発生することもあり、これらの症状は数日から数週間続くことがあります。途中で薬を変更したい場合や、副作用が発生した場合に、すぐに中止できないことも大きなデメリットです。
自宅でできる予防とケア方法

フィラリア予防薬の投与と並行して、蚊の侵入を防ぐ環境整備も重要な予防策です。完全に蚊を排除することは困難ですが、侵入を減らすことで感染リスクを大幅に下げることができます
蚊の侵入を防ぐ環境整備
蚊を媒介とするフィラリア感染を防ぐには、蚊が室内に入らないよう工夫することが大切です。網戸の破損は早めに修理し、虫除けグッズや蚊取り線香の活用も効果的です。
犬用の虫除けスプレーなどもあるので、合わせて使うことでより効果的です。

散歩の時間を見直す
蚊の活動が盛んなのは朝方や夕方。これらの時間帯を避け、日中の比較的蚊が少ない時間に散歩を行うことで、フィラリア感染リスクを下げられます。
忘れ防止に「おやつタイプ」「注射タイプ」を検討
月1回の投薬を忘れがちな方には、チュアブルタイプ(おやつ型)や、年1回の注射型も検討しましょう。継続できる方法を選ぶことが予防成功のカギです。
こんな方は動物病院へ

以下のようなお悩みがある場合は、動物病院への相談をおすすめします。
・予防薬を飲ませ忘れてしまうことが多い
・愛犬に合う薬がわからない
・多頭飼育で管理が大変
・過去に副作用が出たことがある
・検査を受けずに市販薬を使ってしまった
初診の方でも安心してご来院いただけるよう、検査結果をもとに投与プランを立て、毎月の管理まで丁寧にサポートしてもらえるクリニックも増えています。
診察時には薬の飲み残しや体調反応を細かくヒアリングし、健康状態の変化を毎月確認しながら進められるのが特徴です。どんな小さなことでも相談してみましょう。
よくある質問Q&A

予防薬はいつから始めればいいですか?
地域にもよりますが、蚊の活動が始まる4月下旬〜5月上旬に投与を開始し、12月ごろまで継続するのが一般的です。
子犬はいつから予防薬を始めれば良いですか?
一般的に、生後6-8週齢から予防を開始できます。ただし、母犬の感染状況や子犬の健康状態を確認してからの開始を推奨しています。
市販薬ではだめですか?
自己判断での市販薬使用はおすすめできません。感染している状態で投与すると、ショック症状が出るリスクがあります。
注射と毎月投薬、どちらがおすすめ?
犬の体質や生活スタイルによって異なります。事前にしっかりカウンセリングを受けることで、納得できる選択ができます。
他の予防薬と併用できますか?
製剤によっては成分が重複する場合があります。必ず獣医師に確認してから併用しましょう。
高齢犬でも予防は必要?
はい。年齢にかかわらず感染リスクはあります。シニア犬の場合は体調管理に注意しつつ予防を続けていくことが重要です。
まとめ|犬の健康を守るフィラリア予防の第一歩
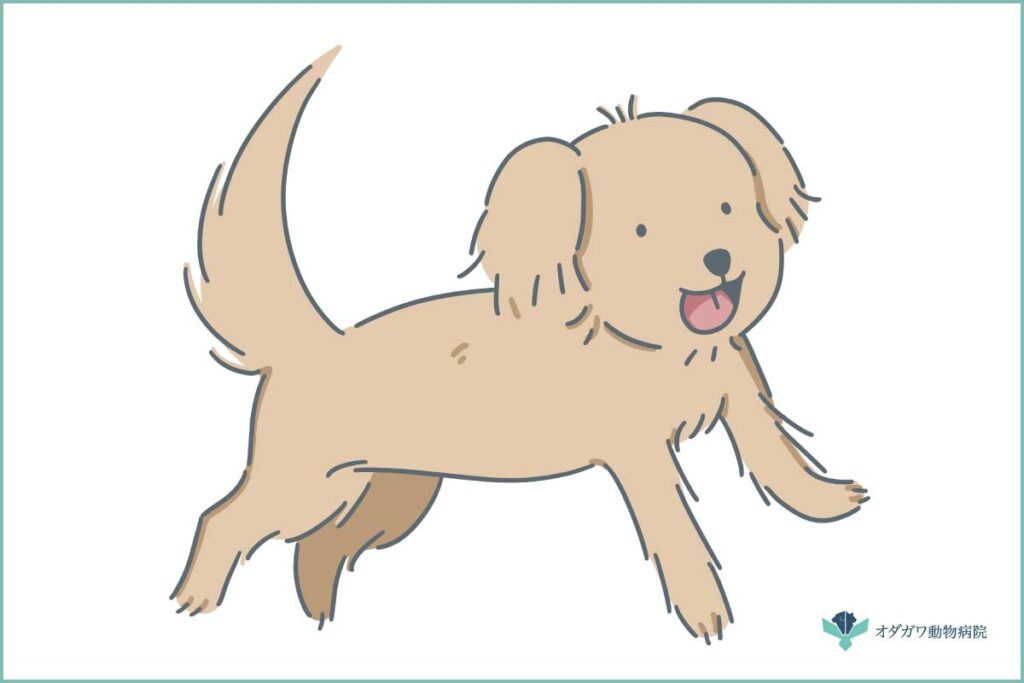
フィラリア症は、現代の獣医療において「完全に予防可能な疾患」として位置づけられています。年に1回の検査と、月に1回の投薬、または年1回の注射という非常にシンプルな方法で、愛犬の命を守ることができるのです。
当院で日々診療に携わる中で、最も心を痛めるのは「もう少し早く予防していれば…」という場面に遭遇することです。フィラリア症による心不全で苦しむ犬を見るたび、予防の重要性を改めて感じます。
数字で見る予防効果
当院のデータでは、適切な予防を行った犬の99.7%が感染を免れています。一方、予防を怠った犬の約35%が感染し、その多くが重篤な症状を示しています。
この数字は、予防が単なる「保険」ではなく、愛犬の生命を守る「必須の医療行為」であることを物語っています。
予防を徹底することで、家族みんなが笑顔に
動物病院では「検査」「薬の選定」「継続的なフォロー」の3つの軸で、飼い主とともに愛犬の健康管理を行っています。
カレンダー管理シートや、服薬記録アプリなどの活用法も紹介してもらえるため、ご家庭での管理もしやすくなります。
愛犬が健康に季節を乗り切るためには、日々の小さな予防や意識の積み重ねがとても重要です。今日からできることを少しずつ取り入れ、家族みんなで安心できる生活を守っていきましょう。
「どの予防薬がいいか分からない」「予防を続けられるか不安」といったお悩みがある方も、まずは一度相談してみてください。















