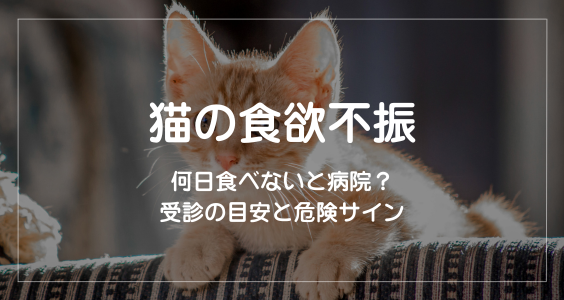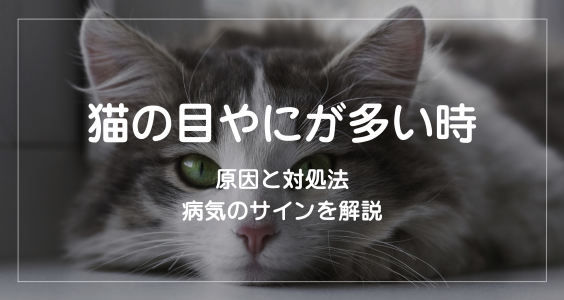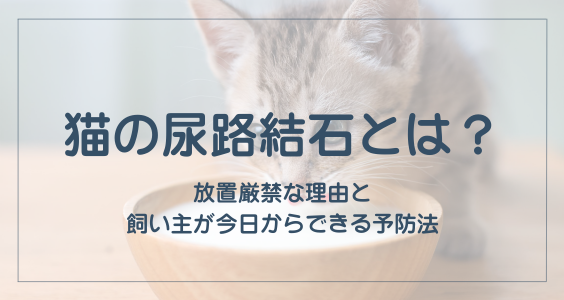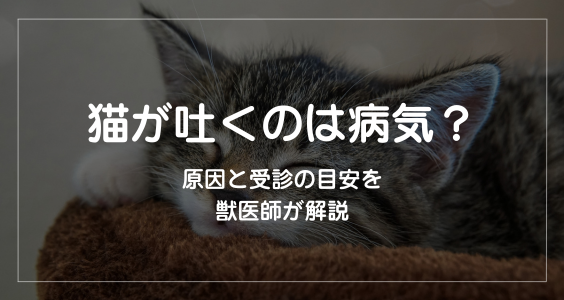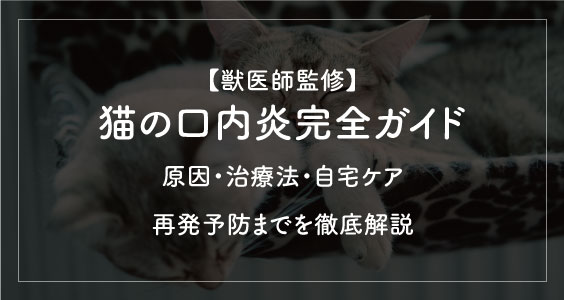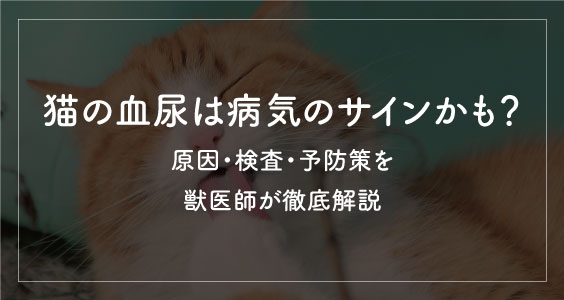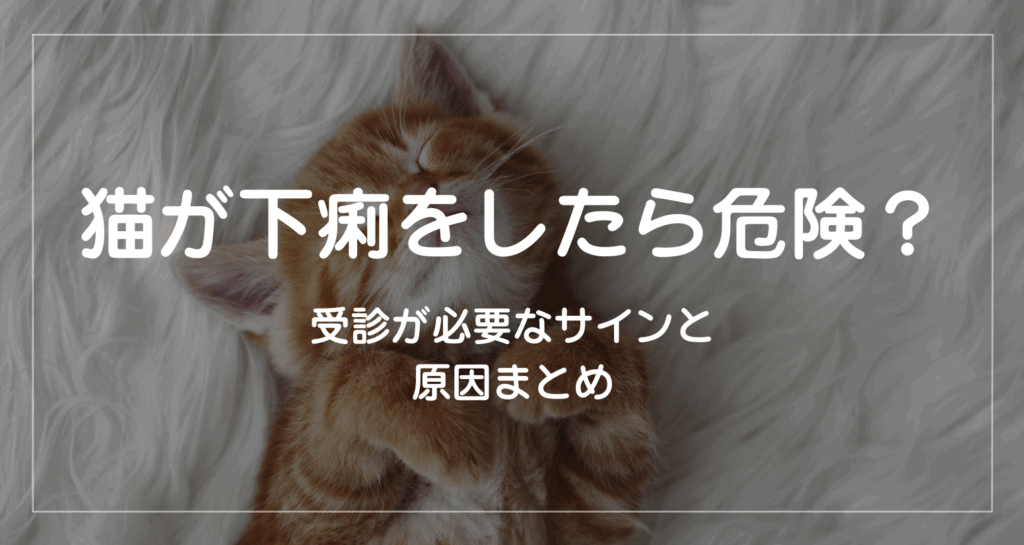
愛猫が突然下痢をしたとき、多くの飼い主様が「病気なのか」「すぐに病院に行くべきか」と不安になられることでしょう。猫の下痢は軽微な食事の変化から重篤な疾患まで、実に様々な原因で起こります。大切なのは、その下痢が緊急性の高いものか、それとも様子を見ても良いレベルなのかを正しく判断することです。
この記事では、獣医師の監修のもと、猫の下痢の色や回数から考えられる原因、受診のタイミング、そして自宅でできるケアまでを詳しく解説いたします。愛猫の健康を守るための実践的な知識として、ぜひお役立てください。
まずは結論|今すぐ受診すべきサイン

猫の下痢で最も重要なのは、緊急性の判断です。以下の症状が一つでも当てはまる場合は、様子を見ずに速やかに動物病院を受診してください。
子猫(~6か月)・高齢猫(7歳~)
年齢による体力や免疫力の問題から、成猫よりも深刻な状況に陥りやすい傾向があります。子猫は脱水や低血糖に陥りやすく、高齢猫は慢性疾患の可能性が高いため、下痢の程度に関わらず早期の受診をお勧めします。
水様便が連続している、または1日3~5回以上の下痢
特にさらさらとした水のような便や、噴水状に勢いよく排泄される下痢は、急性胃腸炎や感染症の可能性が高く、急激な脱水を引き起こす恐れがあります。
血便(鮮血または黒色便)や強い悪臭を伴う下痢
猫がぐったりしている場合は、消化管に重篤な問題が生じている可能性があります。鮮血は大腸の炎症や損傷を、黒色便は上部消化管からの出血を示唆することが多く、いずれも緊急性が高い状態です。
嘔吐や発熱(目安:39.5℃以上)、脱水症状
危険信号です。脱水の簡易チェック方法として、猫の首の後ろの皮膚をつまみ上げて離したとき、皮膚が元に戻るまでに時間がかかる場合は脱水が進行している証拠です。正常であれば瞬時に元に戻ります。
下痢と同時に嘔吐が見られる場合はこちらの記事もご参照ください
異物誤飲を疑う症状
空えづき、腹痛を示すような姿勢(前足を伸ばしてお尻を上げる)、突然の食欲消失などが下痢と同時に見られる場合は、誤飲した異物が腸管に影響を与えている可能性があります。
これらの症状に該当する場合は、迷わず動物病院にご連絡ください。夜間や休日であっても、緊急診療を行っている病院への相談をお勧めします。
気になる症状があればすぐにご相談ください – 判断に迷う場合は、まずはお電話でご相談いただくことも可能です。

猫の下痢とは?基本と観察ポイント
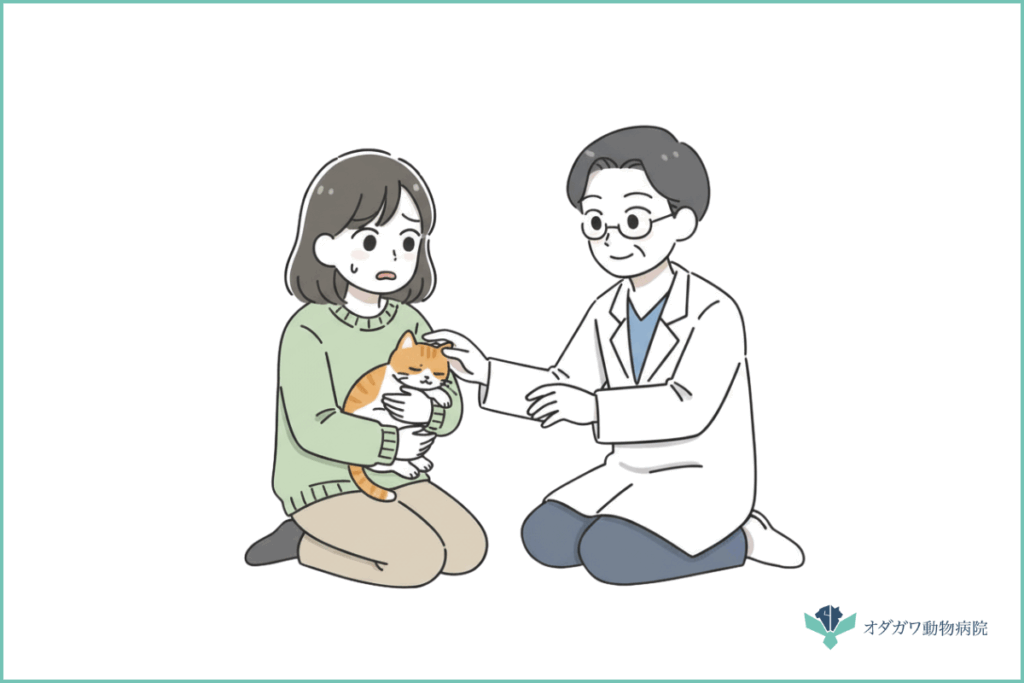
猫の下痢とは、水分が多く形を保てない便のことを指します。正常な猫の便は適度な硬さがあり、形状を保ったまま排泄されます。一方、下痢便は水分含有量が高く、様々な形状を示します。
下痢を正しく評価するためには、回数、量、色、におい、混入物(粘液、血液、未消化物)の観察が重要です。これらの情報は、原因の特定や治療方針の決定に欠かせない手がかりとなります。
便の状態を客観的に評価するため、以下の簡易便スケールを参考にしてください。
便状態評価スケール(1~7段階)
スケール1は「コロコロした硬便」で、便秘傾向を示します。スケール2は「やや硬めの成形便」で、正常範囲の下限です。スケール3は「成形された適度な硬さの便」で、理想的な状態です。スケール4は「やや軟らかい成形便」で、正常範囲の上限です。スケール5は「形はあるが軟らかい便」で、軽度の軟便状態です。スケール6は「形を保てない軟便」で、軽度から中等度の下痢に相当します。スケール7は「水様便」で、受診を強く推奨する下痢の状態です。
日常的に愛猫の便の状態をチェックし、スケール6以上が続く場合や、スケール7の水様便が見られた場合は、獣医師への相談を検討してください。
観察時には、便の色にも注目しましょう。正常な便は茶色から濃い茶色ですが、下痢の際は黄色、緑色、赤色、黒色など様々な色を示すことがあり、それぞれが異なる原因を示唆します。
また、便の臭いも重要な情報です。通常の便臭とは明らかに異なる強い悪臭、酸っぱい臭い、魚のような臭いなどは、特定の疾患や感染症を疑う手がかりになります。
便に混入している物質の確認も欠かせません。粘液(ゼリー状の物質)、血液(鮮血や黒っぽい血)、未消化の食物、寄生虫(虫体や虫卵)などが混じっていないかを確認し、発見した場合はその特徴を記録しておきましょう。
これらの観察は、愛猫の健康状態を把握し、獣医師に正確な情報を伝えるために非常に重要です。普段から愛猫の正常な便の状態を把握しておくことで、異常を早期に発見することができます。
色・性状でわかる”原因のヒント”
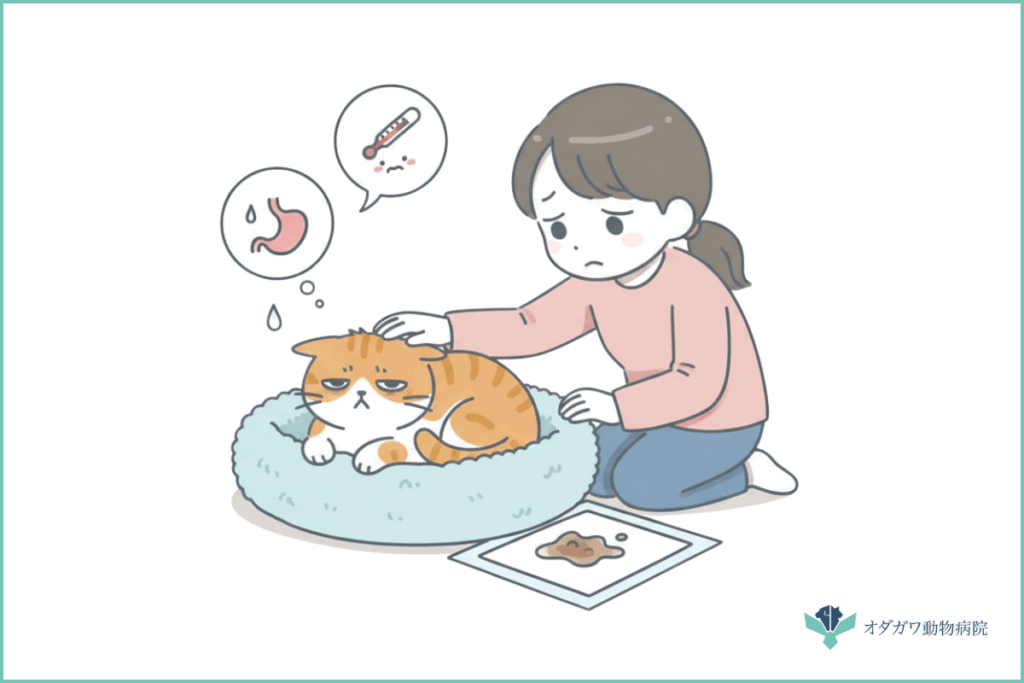
猫の下痢の色や性状は、その原因を推測する重要な手がかりとなります。ここでは、代表的な便の特徴とそれぞれが示唆する可能性のある原因について詳しく解説します。
水様便(さらさら・噴水状)
水のようにさらさらした便や、勢いよく噴水状に排泄される下痢は、急性胃腸炎、寄生虫感染、食餌性の問題などが考えられます。急なフードの切り替えや、普段食べ慣れないものを摂取した場合にもこのような症状が現れることがあります。
特に子猫の場合、水様便は脱水や低血糖のリスクが高いため、原則として獣医師の診察を受けることをお勧めします。子猫は体重に占める水分の割合が成猫よりも高く、短時間での脱水が生命に関わる危険な状態を招く可能性があります。
水様便が続く場合、腸管からの水分と電解質の大量喪失により、短時間で脱水症状が進行する可能性があります。愛猫の活動性や食欲に変化が見られる場合は、迅速な対応が必要です。
血便(鮮血・暗色)
便に血液が混じる血便は、その色によって出血部位をある程度推測することができます。鮮やかな赤色の血液が便の表面に付着している場合は、大腸や直腸などの下部消化管からの出血を示唆します。しばしば粘液を伴い、大腸炎や直腸炎の可能性が高くなります。
一方、黒っぽい血液や、便全体が黒色になっている場合(黒色便)は、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を疑います。これは血液が胃酸と反応して黒く変色するためです。
血便は少量であっても、繰り返し認められる場合は必ず受診してください。出血の原因には炎症性腸疾患、感染症、腫瘍、異物による損傷など、様々な可能性があり、正確な診断と適切な治療が必要です。
特に黒色便は上部消化管の重篤な疾患の可能性があり、緊急性が高い症状です。愛猫に黒色便が見られた場合は、速やかに動物病院を受診してください。
粘液便(ゼリー状)
便に透明から半透明のゼリー状の物質(粘液)が混じる場合は、大腸炎、ストレス性の腸炎、食物アレルギーまたは食物不耐性などが考えられます。粘液は腸壁から分泌される物質で、腸管に何らかの刺激や炎症がある際に増加します。
ストレスによる粘液便は、環境の変化、新しいペットの導入、引っ越し、工事音などの騒音などが原因となることがあります。猫は環境の変化に敏感な動物であり、ストレスが消化器症状として現れることは珍しくありません。
食物アレルギーや食物不耐性による粘液便の場合、特定の食材に対する反応として症状が現れます。新しいフードやおやつを与えた後に粘液便が見られる場合は、その食材が原因である可能性があります。
粘液便が継続する場合は、根本的な原因の特定と治療が必要です。ストレス要因の除去、食事の見直し、場合によっては抗炎症治療などが検討されます。
悪臭・脂っぽいテカリ
通常の便臭とは明らかに異なる強い悪臭や、便の表面に脂っぽいテカリが見られる場合は、消化・吸収不良、膵炎、膵外分泌不全などの可能性があります。
膵外分泌不全は猫では比較的稀な疾患ですが、膵臓から分泌される消化酵素が不足することで、脂肪や蛋白質の消化が不完全になり、特徴的な脂肪便を呈します。この場合の便は量が多く、悪臭が強く、水に浮く傾向があります。
膵炎による下痢の場合、しばしば嘔吐や腹痛を伴います。猫の膵炎は症状が軽微な場合も多く、慢性化しやすい疾患です。継続する消化器症状がある場合は、膵炎の可能性も考慮した精査が必要です。
消化・吸収不良は、腸管の疾患、食物アレルギー、細菌の過剰増殖など、様々な原因で起こります。適切な診断と治療により、多くの場合改善が期待できます。
これらの症状が見られる場合は、便サンプルの持参と詳細な問診により、原因の特定を進めていきます。愛猫に下痢と嘔吐が同時に見られる場合の対応について詳しく知りたい方は、当院の「猫が吐く症状について」の記事もご参照ください。また、血便や腹痛が強い場合の鑑別診断については、「誤飲・異物」に関する記事もお役に立ちます。
年齢別の注意点

猫の年齢は下痢の原因や対応方法を考える上で極めて重要な要素です。それぞれの年齢層で特に注意すべき点と、考えられる原因について詳しく説明します。
子猫の下痢
生後6か月までの子猫の下痢は、成猫以上に注意深い対応が必要です。子猫は免疫系が未発達で、体重に占める水分の割合も高いため、下痢による脱水や体調悪化が急速に進行する可能性があります。
子猫の下痢の主な原因として、寄生虫感染が非常に多く見られます。回虫、鉤虫、コクシジウム、ジアルジアなどの寄生虫は、母猫からの感染や環境からの感染により子猫に高頻度で認められます。これらの寄生虫は便検査により確認でき、適切な駆虫薬による治療で改善します。
ウイルス性の胃腸炎も子猫では重篤になりやすい疾患です。猫パルボウイルス感染症(猫汎白血球減少症)は特に危険で、激しい下痢と嘔吐、発熱、白血球の著明な減少を引き起こします。適切なワクチン接種により予防可能ですが、ワクチン未接種の子猫では注意が必要です。
子猫の下痢対応で最も重要なのは、絶食を避けることです。成猫では一時的な絶食が治療に有効な場合もありますが、子猫では低血糖や脱水の悪化を招く危険があります。下痢が見られても、少量頻回の給餌を継続し、早期に獣医師の診察を受けることが重要です。
また、子猫は体温調節能力も未発達なため、下痢により体調を崩した際は保温にも注意を払う必要があります。室温を適切に保ち、必要に応じて毛布やヒーターなどで体温維持をサポートしてください。
母猫からの初乳により得られる移行抗体は、子猫の免疫を支える重要な要素です。早期に離乳した子猫や、母猫からの授乳期間が短かった子猫では、感染症のリスクが高くなる傾向があります。
成猫
生後6か月から7歳未満の成猫では、下痢の原因として食事関連の要因が多く見られます。急なフードの切り替え、高脂肪のおやつの過剰摂取、乳糖を含む食品の摂取などが一般的な原因です。
食物アレルギーや食物不耐性も成猫でしばしば見られる問題です。特定の蛋白質(牛肉、鶏肉、魚など)や炭水化物に対するアレルギー反応として下痢が生じることがあります。この場合、アレルゲンとなる食材を特定し、除去することで症状の改善が期待できます。
ストレスも成猫の下痢の重要な原因の一つです。引っ越し、新しいペットの導入、家族構成の変化、工事などの騒音、来客の増加など、環境の変化が消化器症状として現れることがあります。猫は非常にデリケートな動物で、飼い主が気づかない小さな変化でもストレスを感じることがあります。
トイレ環境の問題もストレス性の下痢を引き起こす要因です。トイレの清潔度、設置場所、砂の種類の変更などが影響することがあります。理想的には、猫の頭数プラス1個のトイレを用意し、常に清潔に保つことが推奨されます。
成猫では、軽度の下痢であれば12~24時間程度の経過観察が可能な場合もありますが、症状が悪化する場合や他の症状を伴う場合は速やかな受診が必要です。
高齢猫
7歳以上の高齢猫では、下痢の背景に慢性疾患が隠れていることが多く、より慎重な対応が必要です。加齢に伴い免疫機能や臓器機能が低下するため、若い猫では軽症で済む病気も重篤化しやすい傾向があります。
甲状腺機能亢進症は高齢猫で非常に多く見られる内分泌疾患で、下痢、体重減少、多飲多尿、頻脈などの症状を示します。甲状腺ホルモンの過剰分泌により全身の代謝が亢進し、消化管の運動も活発になることで下痢を生じます。血液検査による甲状腺ホルモン(T4)の測定により診断可能です。
炎症性腸疾患(IBD)や慢性腸症も高齢猫で頻度が高い疾患です。慢性的な炎症により腸管の構造や機能に異常が生じ、持続する下痢や軟便を引き起こします。確定診断には病理組織検査が必要ですが、まずは血液検査や画像検査、食事療法への反応などを総合的に評価します。
膵炎も高齢猫でしばしば見られる疾患で、急性と慢性の両方の病型があります。膵炎による下痢は、しばしば嘔吐や腹痛を伴い、重篤な場合は脱水や電解質異常を引き起こします。膵臓特異的リパーゼ(Spec fPL)の測定により診断の補助とします。
腫瘍性疾患も高齢猫では考慮すべき原因の一つです。消化管リンパ腫は猫で最も多い消化管腫瘍で、慢性的な下痢や体重減少を引き起こします。早期診断と適切な治療により、生活の質の改善が期待できる場合もあります。
高齢猫の下痢では、体重減少、多飲多尿、嘔吐などの併発症状に特に注意が必要です。これらの症状は重篤な全身疾患を示唆する可能性があり、速やかな精査が推奨されます。
高齢猫では定期的な健康診断(年1~2回)を受けることで、疾患の早期発見と早期治療につながります。甲状腺機能亢進症、膵炎、慢性腎臓病などの詳細については、当院の専門記事もご参照ください。
原因別の整理
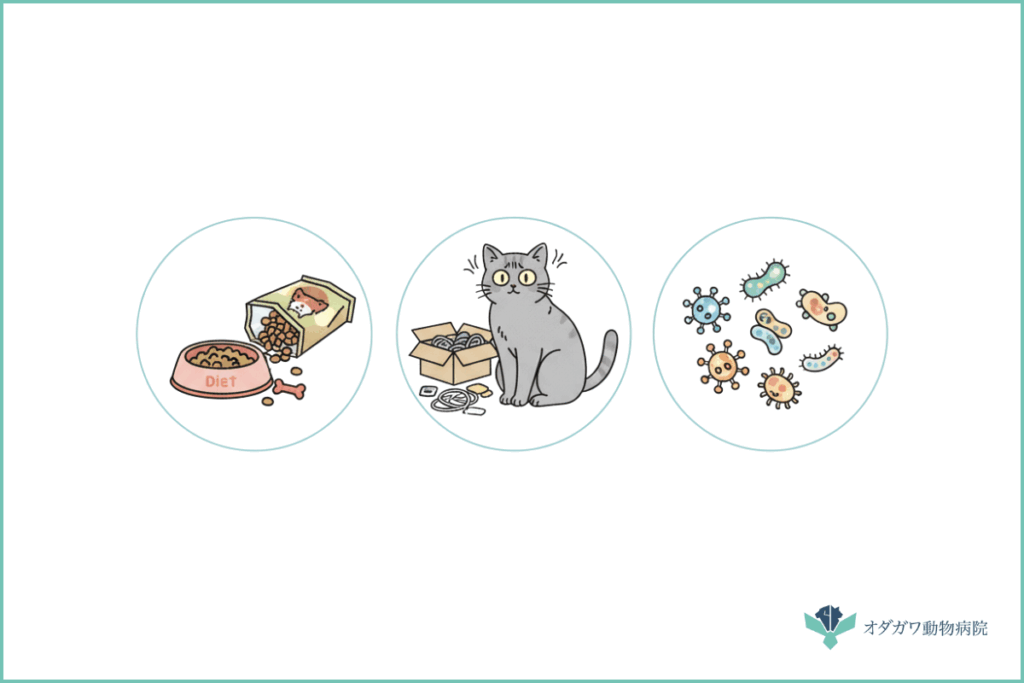
猫の下痢の原因は多岐にわたり、適切な治療のためには原因の特定が重要です。ここでは、主要な原因を系統立てて整理し、それぞれの特徴や診断のポイントについて詳しく解説します。
食事関連の原因
猫の下痢で最も一般的な要因の一つです。急なフードの切り替えは、腸内細菌叢のバランスを崩し、一時的な下痢を引き起こすことがあります。新しいフードへの切り替えは、7~10日かけて段階的に行うことが重要です。最初の2~3日は新しいフードを25%、既存のフードを75%の割合で混合し、その後徐々に新しいフードの割合を増やしていきます。
脂肪過多の食事も下痢の原因となります。高脂肪のおやつやテーブルフードの与えすぎ、脂肪含有量の高いフードへの急な変更などが該当します。猫は犬と比べて脂肪の消化能力が高いとされていますが、急激な脂肪摂取量の増加は消化不良を引き起こす可能性があります。
乳糖不耐性も見逃せない要因です。成猫では乳糖分解酵素(ラクターゼ)の活性が低下するため、牛乳などの乳製品を摂取すると消化不良による下痢を生じることがあります。猫には猫専用のミルクを与えるか、乳糖を除去した製品を選択することが推奨されます。
食物アレルギーや食物不耐性は、特定の食材に対する免疫反応や消化能力の問題により生じます。主要なアレルゲンには牛肉、鶏肉、魚類、乳製品、小麦、大豆などがあります。診断には除去食試験が有効で、疑われるアレルゲンを含まない食事を8~12週間継続し、症状の改善を評価します。
適切なフード選びが難しいと感じる方は、一度獣医師や動物病院に相談してみるのが良いでしょう。
獣医師が厳選したフードはこちら↓

感染症による下痢
寄生虫感染が特に重要です。便検査により虫卵や原虫の検出が可能で、回虫、鉤虫、コクシジウム、ジアルジア、トリコモナスなどが一般的です。寄生虫による下痢は、適切な駆虫薬により比較的短期間で改善することが多く、早期診断と治療が重要です。
細菌感染による下痢では、サルモネラ、カンピロバクター、クロストリジウムなどが原因となることがあります。これらの細菌は人にも感染する可能性があるため、適切な診断と治療、そして衛生管理が重要です。
ウイルス感染では、猫パルボウイルス(猫汎白血球減少症)、猫コロナウイルス、ロタウイルスなどが下痢を引き起こすことがあります。特に猫パルボウイルス感染症は重篤で、適切なワクチン接種による予防が重要です。
炎症性腸疾患(IBD)・慢性腸症
腸管の慢性炎症により持続的な消化器症状を示す疾患群です。原因は完全には解明されていませんが、免疫反応の異常、遺伝的素因、環境要因などが関与すると考えられています。診断は病理組織検査により確定されますが、臨床症状、血液検査、画像検査、治療反応などを総合的に評価します。
ストレス性の下痢
猫の敏感な性格を反映した重要な原因です。環境の変化、新しいペットの導入、家族構成の変更、引っ越し、工事音などの騒音、来客の増加など、様々な要因がストレスとなり得ます。トイレ環境の変化も重要なストレス要因で、清潔度、設置場所、砂の種類の変更などが影響します。
多頭飼育環境では、猫同士の関係性もストレスの要因となります。新しい猫の導入時期、餌場やトイレの競争、テリトリーの問題などが消化器症状として現れることがあります。
薬剤関連の下痢
抗菌薬による腸内細菌叢の変化が最も一般的です。抗菌薬は病原菌だけでなく正常な腸内細菌にも影響を与えるため、腸内環境のバランスが崩れ下痢を生じることがあります。必要に応じて整腸剤の併用や、プロバイオティクスの投与が検討されます。
その他の薬剤では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、免疫抑制薬、化学療法薬などが下痢の原因となることがあります。薬剤の副作用による下痢が疑われる場合は、獣医師との相談により薬剤の変更や中止を検討します。
誤飲・異物による下痢
特に好奇心旺盛な猫や若い猫で注意が必要です。糸状の物質(毛糸、釣り糸、裁縫糸など)、プラスチック片、小さなおもちゃ、植物の一部などの誤飲により、消化管の通過障害や炎症を引き起こすことがあります。
糸状異物は特に危険で、腸管に絡まることで腸重積や腸管の壊死を引き起こす可能性があります。空えづき、腹痛(前足を伸ばしてお尻を上げる姿勢)、食欲消失などの症状を伴う場合は、緊急手術が必要になることもあります。
内分泌・代謝性疾患による下痢
甲状腺機能亢進症が高齢猫で特に重要です。甲状腺ホルモンの過剰分泌により全身の代謝が亢進し、腸管運動の促進による下痢が生じます。体重減少、多飲多尿、頻脈、興奮性の増加などの症状を伴うことが多く、血液検査により診断可能です。
膵外分泌不全は猫では比較的稀ですが、膵臓からの消化酵素分泌不足により脂肪便を特徴とする下痢を引き起こします。血清トリプシン様免疫反応性(TLI)の測定により診断されます。
これらの原因を適切に鑑別し、個々の猫に最適な治療法を選択することが、下痢の根本的な解決につながります。複数の原因が重複していることも多く、総合的な評価と治療が重要です。
受診前にここを記録(持参メモ)

動物病院を受診する前に、愛猫の症状や経過を詳しく記録しておくことは、正確な診断と適切な治療のために非常に重要です。獣医師が限られた診察時間の中で最大限の情報を得るために、以下の項目について事前に整理しておきましょう。
発症時期と経過
いつから下痢が始まったか、症状の変化はあるか、良くなったり悪くなったりしているかなどを記録します。「3日前から」「昨夜から急に」など、具体的な時期を伝えることで、急性か慢性かの判断材料になります。また、症状の程度が一定なのか、徐々に悪化しているのか、波があるのかなども重要な情報です。
回数と量の記録
1日に何回下痢をしているか、普段の排便回数と比べてどうか、1回あたりの量はどの程度かを記録しましょう。「いつもは1日1回だったが、今は1日4~5回」「少量ずつ頻繁に」「大量の水様便」など、具体的な表現で記録してください。
色と性状の観察
先ほど説明した便スケール(1~6段階)を参考に、便の硬さと形状を評価しましょう。色については、茶色、黄色、緑色、赤色(血液)、黒色など、具体的に記録します。また、粘液(ゼリー状の物質)の有無、泡立ち、未消化物の混入なども重要な観察ポイントです。
食欲・飲水・体重変化の記録
こちらも診断に重要な情報を提供します。食欲は「いつも通り」「やや減少」「全く食べない」など、段階的に評価しましょう。飲水量については、「いつもより多く飲む」「水を飲みたがらない」など、普段との比較で記録します。体重変化がある場合は、どの程度の期間でどのくらい変化したかを記録してください。
フード・おやつ・サプリメントの変更歴
食事性の下痢を疑う重要な手がかりです。最近2週間以内に新しいフードに変更したか、新しいおやつを与えたか、サプリメントを開始したかなどを記録します。また、変更の方法(急に切り替えたか、段階的に行ったか)も重要な情報です。
家族や来客が与えた食べ物、テーブルフードの摂取、誤食の可能性なども含めて記録しましょう。「いつものフードしか与えていない」という情報も、食事性要因を除外する上で重要です。
ワクチン・駆虫歴
感染症の可能性を評価するために必要です。最後にワクチンを接種した時期、駆虫薬を投与した時期、これまでの感染症の既往歴などを記録してください。子猫の場合は、母猫のワクチン歴や、兄弟猫の健康状態も参考になります。
多頭飼育の有無と他の動物の健康状態
他の猫や犬に同様の症状が見られるか、新しい動物を迎え入れたか、他の動物との接触歴があるかなどを記録します。感染性の疾患では、同居動物への感染拡大の可能性も考慮する必要があります。
環境の変化
引っ越し、模様替え、工事、新しい家族の加入、来客の増加など、猫がストレスを感じる可能性のある変化があったかを振り返ってみてください。
現在服用中の薬剤
薬剤名、投与量、投与期間を正確に記録します。処方薬だけでなく、市販のサプリメントや健康食品も含めて報告してください。
便サンプルの持参
診断に極めて有用です。新鮮な便(排泄から2時間以内)を清潔な容器や小袋に入れて持参しましょう。便サンプルの採取が困難な場合は、便の写真を撮影しておくことも参考になります。写真は便の色や性状がよくわかるよう、明るい場所で撮影してください。
便サンプル採取の際は、トイレの砂を混入させないよう注意し、使い捨てのスプーンや割り箸などを使用して清潔な容器に採取します。冷蔵保存し、できるだけ早めに病院に持参してください。
症状の記録表を作成し、日時、便の回数と性状、食事内容、その他の症状(嘔吐、発熱、元気の有無など)を時系列で記録することをお勧めします。これにより、症状の変化や治療効果の評価が正確に行えます。
これらの情報を整理しておくことで、獣医師はより正確な診断を行い、愛猫に最適な治療方針を立てることができます。記録は詳しいほど良いですが、観察に夢中になりすぎて愛猫の様子を見落とすことのないよう、バランスを取って行ってください。
動物病院で行う検査
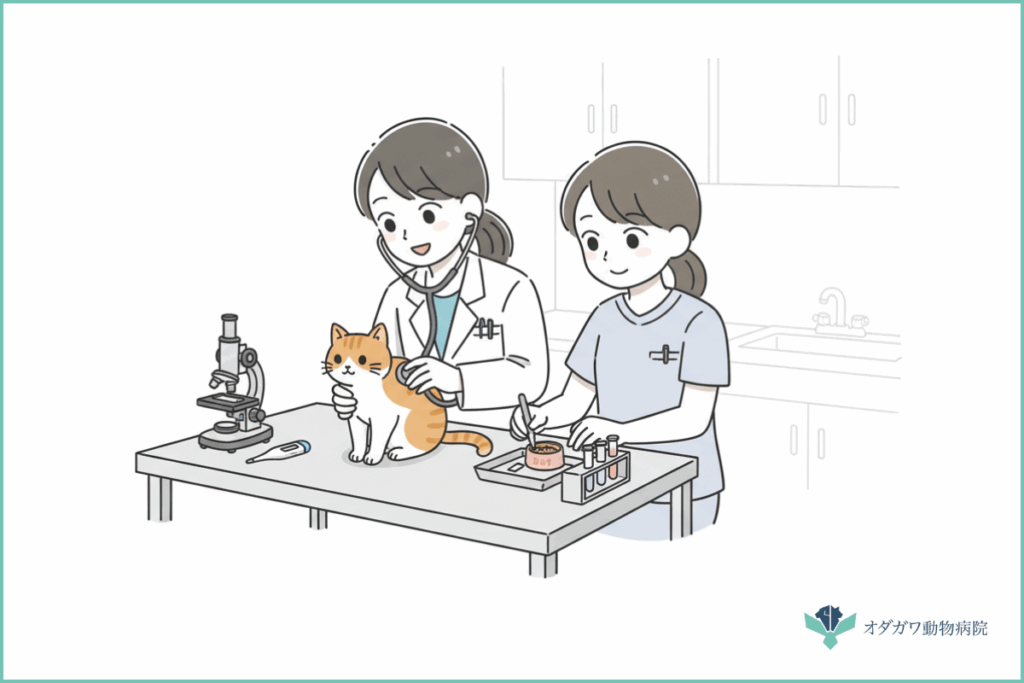
下痢の診断では、問診と身体検査から始まり、必要に応じて各種検査を組み合わせて原因の特定を進めます。ここでは、動物病院で実際に行われる検査の内容と目的について詳しく説明します。
問診と身体検査
診断の基礎となる重要なステップです。獣医師は先ほど説明した記録項目を参考に、症状の詳細な聞き取りを行います。その後、全身の身体検査により、脱水の程度、腹部の触診所見、体温、心拍数、粘膜色などを評価します。
脱水の評価
下痢の患者では特に重要です。皮膚テント試験(首の後ろの皮膚をつまみ上げて戻るまでの時間を測定)、粘膜の乾燥度、眼球陥没の有無などにより脱水の程度を判定します。軽度脱水(5%未満)では明らかな症状はありませんが、中等度脱水(5~10%)では皮膚の戻りが遅くなり、重度脱水(10%以上)では明らかな症状が現れます。
便検査
下痢の原因特定において最も重要な検査の一つです。新鮮な便を用いて、直接塗抹検査、浮遊法、沈殿法などを組み合わせて実施します。
直接塗抹検査では、便を生理食塩水で希釈し、顕微鏡で観察することで、原虫(ジアルジア、トリコモナス、コクシジウムなど)、細菌、白血球、赤血球、未消化物などを確認します。この検査は短時間で結果が得られ、緊急性の判断に有用です。
浮遊法は、便を特殊な液体に浮遊させることで、比重の軽い虫卵を効率的に検出する方法です。回虫、鉤虫、鞭虫などの線虫類の虫卵検出に優れています。
必要に応じて、PCR検査(遺伝子検査)により、特定の病原体(猫パルボウイルス、コロナウイルス、ジアルジア、クリプトスポリジウムなど)の検出を行うこともあります。PCR検査は感度が高く、培養が困難な病原体の検出にも有効です。
血液検査
全血球計数と血液生化学検査を組み合わせて実施します。白血球数の増加は細菌感染や炎症の指標となり、白血球数の減少は重篤なウイルス感染(猫パルボウイルス感染症など)を示唆することがあります。
血液生化学検査では、脱水に伴う血液濃縮、電解質異常(ナトリウム、カリウム、クロールなど)、腎機能や肝機能への影響、蛋白質の低下(吸収不良や喪失)などを評価します。
高齢猫では、甲状腺ホルモン(T4)の測定を検討します。甲状腺機能亢進症は高齢猫で非常に多く、下痢の重要な原因となるためです。T4値の上昇により診断されますが、軽度の場合や他の疾患を併発している場合は、追加の検査(T3抑制試験、遊離T4測定など)が必要になることもあります。
画像検査
レントゲン検査とエコー検査が主に使用されます。レントゲン検査では、腸管の拡張、異物の存在、腹水の有無、他の臓器の異常などを評価します。異物による腸閉塞や腸重積などの緊急事態の診断に有用です。
エコー検査では、腸管壁の厚さや層構造、腸管内容物、リンパ節の腫大、膵臓や肝臓の状態などをより詳細に観察できます。炎症性腸疾患、腫瘍、膵炎などの診断に重要な情報を提供します。
膵炎関連検査として、猫膵臓特異的リパーゼ(Spec fPL)の測定があります。膵炎は猫では診断が困難な疾患の一つですが、Spec fPLは膵炎の診断補助として有用な検査です。正常値は3.5μg/L以下で、12μg/L以上で膵炎を示唆します。
その他の特殊検査として、ビタミンB12とフォレートの測定があります。これらは小腸の吸収機能を評価する指標で、炎症性腸疾患や小腸細菌過剰増殖症候群(SIBO)の診断に有用です。ビタミンB12の低下は回腸の吸収不良を、フォレートの異常は十二指腸・空腸の問題を示唆します。
慢性的な下痢で、これらの検査でも原因が特定できない場合は、内視鏡検査や開腹による腸管生検を検討することもあります。これらの検査により、炎症性腸疾患やリンパ腫などの確定診断が可能になります。
検査の選択と実施順序は、猫の症状、年齢、全身状態などを総合的に評価して決定されます。すべての検査を一度に実施する必要はなく、段階的に進めることで効率的な診断が可能です。
治療の考え方(原因+対症)
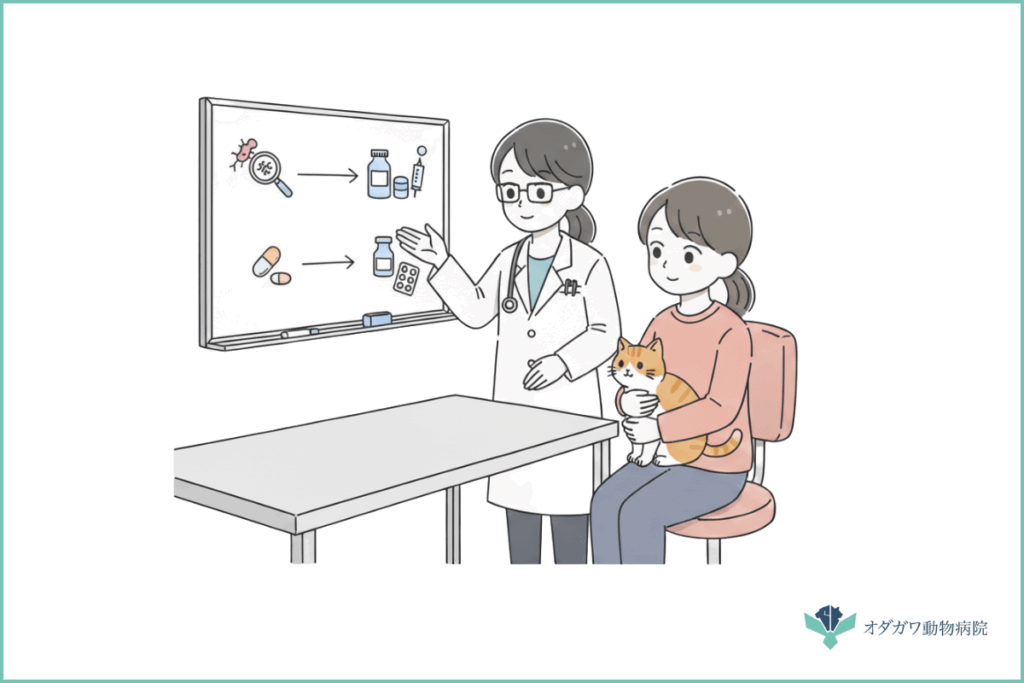
猫の下痢の治療は、根本原因への対処と症状緩和を目的とした対症療法を組み合わせて行います。治療方針は個々の猫の状態、原因、重症度に応じて個別に決定されますが、基本的なアプローチについて詳しく説明します。
補液療法(脱水是正)は下痢治療の基盤となります。下痢により失われた水分と電解質を補給することで、全身状態の改善と臓器機能の維持を図ります。軽度の脱水であれば経口補液や皮下補液で対応可能ですが、中等度以上の脱水では静脈内補液が必要になります。
補液の種類と量は、脱水の程度、電解質の状態、腎機能、心機能などを総合的に評価して決定します。一般的には乳酸リンゲル液や酢酸リンゲル液が使用され、電解質異常がある場合は個別に調整を行います。
整腸剤の使用は、腸内細菌叢のバランス回復を目的として行われます。プロバイオティクス(有用菌)、プレバイオティクス(有用菌の栄養となる物質)、シンバイオティクス(両者の組み合わせ)などが使用されます。これらは獣医師の指示のもと、適切な製品を適切な期間使用することが重要です。
食事療法は下痢治療において極めて重要な位置を占めます。消化器サポート用の療法食は、消化しやすい原材料を使用し、適切な繊維含量に調整されており、下痢の改善に効果的です。可溶性繊維は腸内で短鎖脂肪酸を産生し、大腸の健康維持に寄与します。
食事の与え方も重要で、1日の食事量を3~4回に分けて少量頻回で与えることで、消化管への負担を軽減できます。新しい食事への切り替えは7~10日かけて段階的に行い、急激な変化を避けることが大切です。
原因療法では、特定された原因に対する具体的な治療を行います。寄生虫感染が確認された場合は、適切な駆虫薬を使用します。回虫や鉤虫にはピランテルやミルベマイシン、コクシジウムにはスルファジメトキサジンやトルトラズリル、ジアルジアにはメトロニダゾールやフェンベンダゾールなど、病原体に応じた薬剤を選択します。
細菌感染が疑われる場合は、培養検査と薬剤感受性試験に基づいて適切な抗菌薬を選択します。ただし、抗菌薬の使用は必要最小限に留め、腸内細菌叢への影響を考慮して慎重に判断します。不適切な抗菌薬の使用は、かえって下痢を悪化させる可能性があります。
食物アレルギー・食物不耐性が疑われる場合は、除去食試験を実施します。これまで摂取したことのない新規蛋白質(例:鹿肉、カンガルー肉など)を含む食事、または加水分解蛋白質を含む療法食を8~12週間継続し、症状の改善を評価します。症状が改善した場合は、疑われるアレルゲンを含む食材を再度与えることで診断を確定します。
**炎症性腸疾患(IBD)**の治療では、免疫抑制薬の使用が検討されます。プレドニゾロンなどのステロイド薬が第一選択として使用され、効果が不十分な場合はクロラムブシルなどの免疫抑制薬を併用することもあります。これらの薬剤は副作用もあるため、定期的な血液検査によるモニタリングが必要です。
甲状腺機能亢進症による下痢の場合は、甲状腺ホルモンの産生を抑制する治療を行います。メチマゾールの内服療法、放射性ヨウ素治療、外科的治療(甲状腺摘出術)などの選択肢があり、猫の状態や飼い主の希望に応じて選択されます。
子猫と高齢猫の特別な配慮が重要です。子猫では絶食による低血糖のリスクがあるため、原則として絶食は避けます。また、脱水の進行が早いため、早期の積極的な補液療法が必要です。電解質バランスの変動も大きいため、頻繁なモニタリングが必要です。
高齢猫では、腎機能や心機能の低下を考慮した治療調整が必要です。補液療法では心負荷に注意し、薬剤の選択では腎機能への影響を考慮します。また、複数の基礎疾患を併発していることが多いため、総合的な治療計画が必要です。
重要な注意事項として、人用の下痢止めを猫に与えることは絶対に避けてください。ロペラミドなどの人用下痢止めは、猫に対して重篤な副作用や中毒症状を引き起こす可能性があります。また、市販の整腸剤や胃薬も、獣医師の指示なしに使用すべきではありません。
治療効果の評価は、症状の改善、便の性状の正常化、体重回復、全身状態の改善などを総合的に判断して行います。治療開始から数日で改善が見られることが多いですが、慢性的な疾患では数週間から数か月の継続治療が必要な場合もあります。
定期的な再診により、治療効果の評価と治療方針の調整を行います。症状が改善しない場合や悪化する場合は、原因の再評価や治療方法の変更を検討します。
自宅でできるケアと再発予防
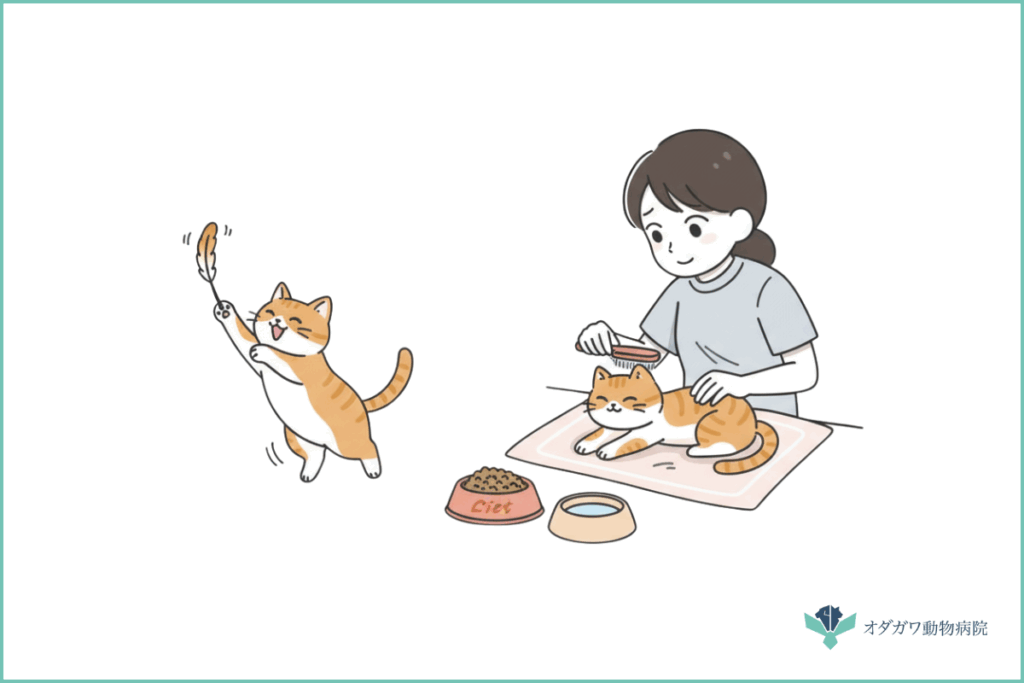
下痢の治療と並行して、自宅でのケアと再発予防対策を適切に実施することで、愛猫の回復を促進し、将来的な再発リスクを軽減することができます。ここでは、飼い主様が日常的に実践できる具体的な方法について詳しく説明します。
水分確保は下痢の猫にとって最も重要なケアの一つです。下痢により大量の水分が失われるため、積極的な水分補給が必要です。新鮮な水を複数の場所に設置し、猫がいつでも飲めるようにしましょう。水は毎日交換し、容器も清潔に保ってください。
水温は常温が理想的です。冷たすぎる水は胃腸に負担をかけ、熱すぎる水は飲みたがらない傾向があります。猫によっては流水を好む場合があるため、自動給水器の使用も検討してみてください。
ウェットフードの活用も水分補給に効果的です。ドライフードと比べて水分含量が高いため、自然な形で水分摂取量を増やすことができます。また、ドライフードにぬるま湯を加えてふやかすことでも水分量を増やせます。
ストレス軽減は、特にストレス性の下痢において重要な対策です。猫が安心して過ごせる環境を整えることで、症状の改善と再発防止につながります。
隠れ家の提供は猫のストレス軽減に効果的です。段ボール箱、猫用ベッド、キャットタワーの個室など、猫が安心して休める静かな場所を用意しましょう。特に多頭飼育の環境では、各猫が独立したスペースを持てるよう配慮が必要です。
トイレ環境の整備も重要です。理想的なトイレ数は「猫の頭数プラス1個」とされています。例えば2匹の猫を飼っている場合は3個のトイレを設置します。トイレは静かで人通りの少ない場所に設置し、常に清潔に保ちましょう。便は排泄後速やかに除去し、砂は定期的に全交換します。
トイレの砂の種類を急に変更することもストレスの原因となるため、変更する場合は段階的に行いましょう。また、トイレの大きさは猫の体長の1.5倍程度が理想的で、縁の高さは猫が楽に出入りできる高さに調整します。
フード管理は下痢の再発防止において極めて重要です。原材料の一貫性を保つため、可能な限り同一のフードを継続使用することをお勧めします。フードを変更する必要がある場合は、7~10日かけて段階的に切り替えを行います。
給餌量と時間の固定も重要です。1日の総給餌量を計量し、3~4回に分けて規則正しい時間に与えます。少量頻回の給餌は消化管への負担を軽減し、消化吸収効率を改善します。
フードの保存方法にも注意が必要です。開封後は密封容器に移し替え、直射日光を避けて涼しい場所で保存します。酸化や湿気による品質低下は、消化器症状の原因となる可能性があります。
おやつの与え方も見直しが必要です。下痢が治まるまでは、おやつを控えるか、消化に良いものを少量に留めます。人の食べ物やテーブルフードは与えないよう、家族全員で徹底しましょう。
多頭飼育での特別な配慮が重要です。感染性の下痢が疑われる場合は、症状のある猫を一時的に隔離し、感染拡大を防ぎます。隔離期間中は専用のトイレを使用し、他の猫との接触を避けます。
隔離が困難な場合でも、トイレは症状のある猫専用のものを用意し、使用後は速やかに清掃・消毒を行います。手洗いの徹底、タオルや食器の共用避けなど、基本的な衛生管理を徹底してください。
餌場の分離も検討しましょう。食事の際の競争や急食いはストレスや消化不良の原因となるため、各猫が落ち着いて食事できる環境を整えます。
環境の安定化を図ることで、ストレス性の下痢を予防できます。猫は環境の変化に敏感な動物であるため、可能な限り生活環境を一定に保ちます。模様替えや新しい家具の導入は段階的に行い、猫が慣れる時間を与えます。
来客や騒音などの一時的なストレス要因に対しては、猫が避難できる静かな部屋を用意します。工事や引っ越しなど、避けられない環境変化がある場合は、事前に獣医師に相談し、必要に応じて一時的な抗不安薬の処方を検討することもあります。
定期健康診断による予防医学的アプローチも重要です。7歳以上の高齢猫では年1~2回、若い猫でも年1回の定期健診を受けることで、疾患の早期発見と早期治療が可能になります。
定期健診では血液検査、便検査、身体検査を組み合わせ、甲状腺機能、腎機能、肝機能、寄生虫感染の有無などを評価します。また、体重の定期的な測定により、慢性疾患の早期発見につながります。
予防接種と駆虫の適切な実施も重要な予防策です。ワクチン接種により感染症による下痢を予防し、定期的な駆虫により寄生虫感染を防ぎます。特に子猫や屋外に出る機会のある猫では、より頻繁な駆虫が推奨されます。
これらの自宅ケアは、獣医師の治療と併用することでより効果を発揮します。症状の変化や新たな問題が生じた場合は、速やかに獣医師に相談してください。
愛猫の下痢と嘔吐が同時に見られる場合の詳細な対応については「猫が吐く症状について」を、口腔痛により食事摂取が困難で二次的な消化不調が起きている場合は「猫の口内炎」の記事をご参照ください。また、異物誤飲のリスク対策については「誤飲・異物」の記事が参考になります。毛玉が原因で便秘と下痢を繰り返す場合については、今後公開予定の「毛球症」に関する記事もご活用ください。
よくある質問(FAQ)
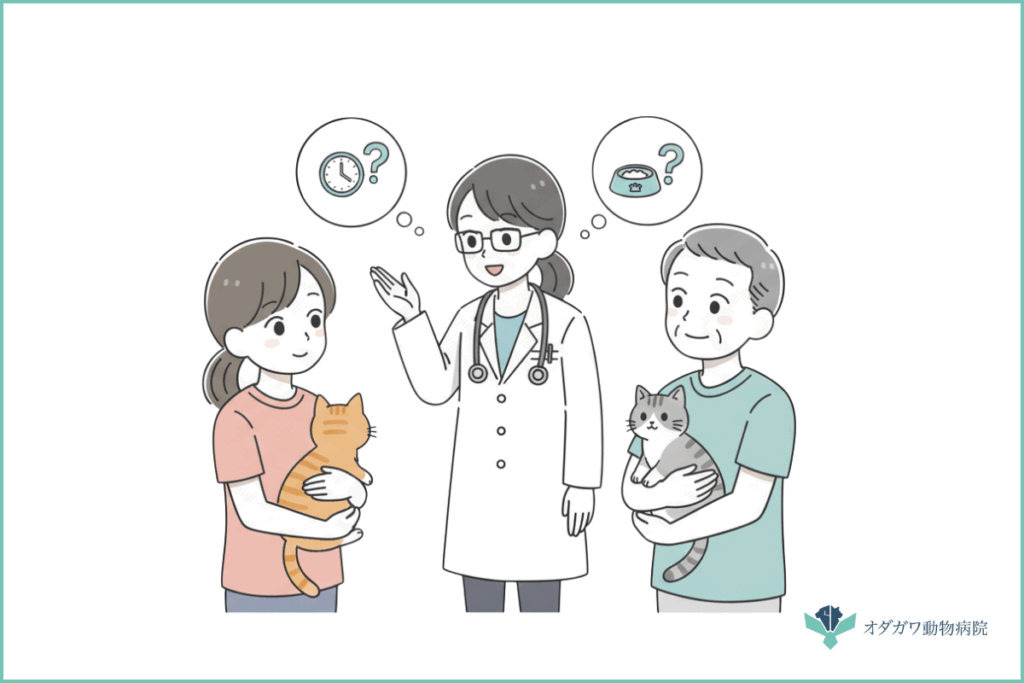
猫の下痢について、飼い主様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報が、適切な判断と対応の助けとなることを願います。
Q1. 1回だけの下痢は様子見でいいですか?
A: 1回だけの軟便や軽度の下痢の場合、成猫で元気や食欲があれば12~24時間程度の様子観察が可能です。ただし、子猫(6か月未満)や高齢猫(7歳以上)の場合は、1回の下痢であっても早期の獣医師への相談をお勧めします。これらの年齢層では、体力や免疫力の問題から症状が急速に悪化する可能性があるためです。
様子観察中も、猫の全身状態(食欲、活動性、体温など)を注意深く観察し、症状が悪化する場合や他の症状(嘔吐、発熱、ぐったりするなど)が現れた場合は速やかに受診してください。また、水様便や血便が見られた場合は、1回であっても受診を検討しましょう。
Q2. 絶食させた方が良いですか?
A: 子猫と高齢猫では絶食は原則として避けるべきです。子猫は低血糖のリスクが高く、数時間の絶食でも危険な状態に陥る可能性があります。高齢猫も体力の低下により、絶食による悪影響を受けやすい傾向があります。
成猫の場合も、長時間の絶食は推奨されません。消化管の休息という観点から短時間(12時間以内)の絶食が検討される場合もありますが、その後は消化の良い食事を少量頻回で与えることが重要です。
下痢の際は、普段のフードよりも消化しやすい食事(消化器サポート用療法食、茹でた鶏胸肉と白米など)を少量ずつ、1日3~4回に分けて与えることをお勧めします。自己判断での絶食は避け、必要に応じて獣医師に相談してください。
Q3. 市販の整腸剤や人の薬は使っても大丈夫ですか?
A: 猫に人用の薬剤を与えることは非常に危険です。人用の下痢止め(ロペラミド、ビスマスサブサリチレートなど)は、猫に対して重篤な副作用や中毒症状を引き起こす可能性があります。特にロペラミドは猫では致命的な中毒を引き起こすことが知られています。
市販の動物用整腸剤についても、獣医師の指示なしに使用することは推奨されません。下痢の原因によっては、整腸剤の使用が症状を悪化させる場合もあります。感染症による下痢の場合、症状を抑えることで病原体の排出が遅れ、治癒が遅れる可能性もあります。
安全で効果的な治療のためには、まず獣医師の診察を受けて原因を特定し、適切な薬剤の処方を受けることが重要です。緊急時であっても、人用の薬剤の使用は避け、獣医師への相談を優先してください。
Q4. 血便が少しだけ出ました。緊急性はありますか?
A: 血便は少量であっても注意が必要な症状です。特に以下の場合は緊急性が高いため、速やかに受診してください:繰り返し血便が見られる場合、猫の元気がなくぐったりしている場合、黒色便(上部消化管出血の可能性)が見られる場合です。
鮮血が便の表面に付着している程度であれば、大腸炎や軽微な直腸の炎症の可能性がありますが、それでも獣医師の診察を受けることをお勧めします。血便の原因には感染症、炎症性腸疾患、腫瘍、異物による損傷など様々な可能性があり、正確な診断が重要です。
血便が一度だけで、その後正常な便に戻り、猫の全身状態に問題がない場合でも、数日以内に獣医師に相談することをお勧めします。便サンプルや写真があると診断の参考になります。
Q5. フードを変えたら下痢になりました。どうすればよいですか?
A: フード変更後の下痢は比較的よく見られる問題です。急激なフードの変更は腸内細菌叢のバランスを崩し、消化不良を引き起こすことがあります。
まず、可能であれば以前のフードに一度戻し、症状の改善を確認してください。症状が改善した場合は、新しいフードへの切り替えを7~10日かけて段階的に行います。
段階的切り替えの方法は以下の通りです:1~2日目は新フード25%、旧フード75%の比率で混合。3~4日目は新フード50%、旧フード50%の比率。5~6日目は新フード75%、旧フード25%の比率。7日目以降は新フード100%に切り替え。
この方法でも下痢が継続する場合は、新しいフードに含まれる特定の成分に対するアレルギーや不耐性の可能性があります。この場合は、フードの変更を中止し、獣医師に相談して適切な食事療法について指導を受けてください。
Q6. 多頭飼育で他の猫にもうつりますか?
A: 下痢の原因が感染性(寄生虫、細菌、ウイルス)の場合、他の猫に感染する可能性があります。特に以下の状況では感染リスクが高くなります:トイレを共用している場合、食器を共用している場合、グルーミングで互いを舐め合う場合、子猫や高齢猫など免疫力の低い猫がいる場合。
感染拡大を防ぐための対策として、可能であれば症状のある猫を一時的に隔離します。専用のトイレを設置し、使用後は速やかに清掃・消毒を行います。食器や水入れは個別に用意し、共用を避けます。症状のある猫を触った後は、必ず手洗いを行ってから他の猫に触れます。
他の猫に同様の症状が現れていないか定期的に観察し、異常が見られた場合は速やかに獣医師に相談してください。多頭飼育の環境では、1匹でも感染症による下痢が確認された場合、他の猫も検査を受けることが推奨される場合があります。
これらの質問と回答は一般的なガイドラインです。個々の猫の状況は異なるため、心配なことがあれば獣医師に直接相談することが最も安全で確実な方法です。特に症状が重篤な場合や、複数の症状が同時に現れている場合は、早期の専門的な診察と治療が重要になります。
まとめ
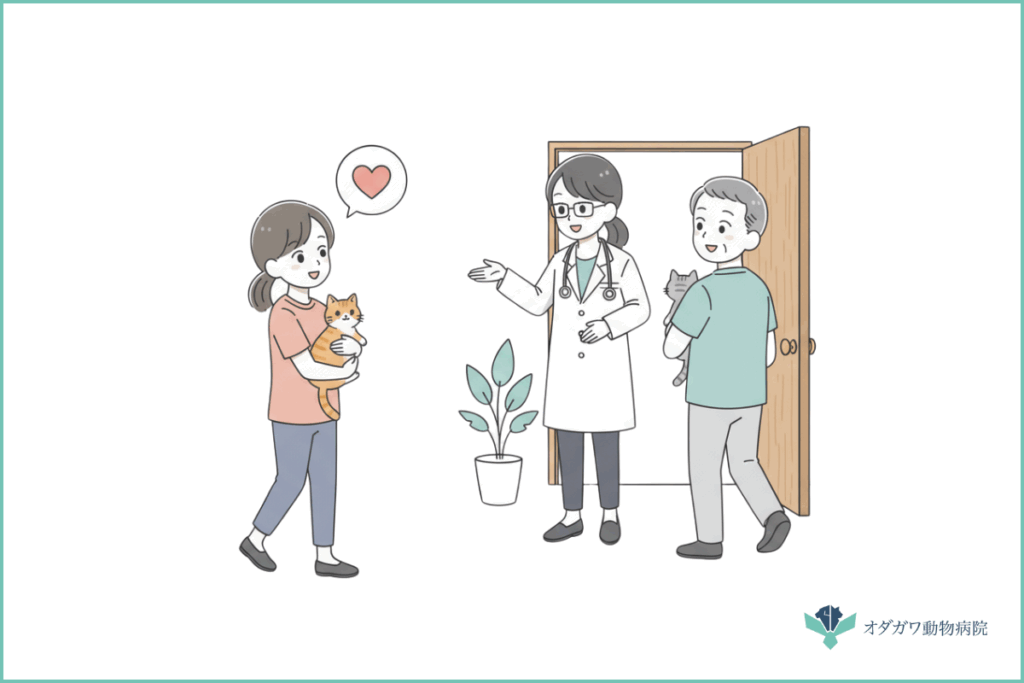
猫の下痢は軽微な食事の変化から重篤な疾患まで、様々な原因で起こる症状です。最も重要なのは、緊急性の高い症状を見極め、適切なタイミングで獣医師の診察を受けることです。
子猫や高齢猫の下痢、水様便、血便、嘔吐や発熱を伴う場合、異物誤飲を疑う症状などは、様子を見ずに速やかな受診が必要です。一方、成猫の軽度な下痢であれば、短期間の様子観察も可能ですが、症状が改善しない場合や悪化する場合は迅速な対応が求められます。
下痢の色や性状は原因を推測する重要な手がかりとなります。水様便は急性胃腸炎や感染症を、血便は消化管の炎症や損傷を、粘液便は大腸炎やストレスを示唆することが多く、これらの観察により適切な初期対応が可能になります。
年齢別の注意点として、子猫では寄生虫感染や脱水・低血糖のリスクに、高齢猫では甲状腺機能亢進症や炎症性腸疾患などの慢性疾患に特に注意が必要です。それぞれの年齢層に適した対応と治療が重要になります。
受診前の記録と便サンプルの持参は、正確な診断のために非常に有用です。発症時期、回数、色と性状、食事の変更歴、他の症状などを詳しく記録し、獣医師に正確な情報を提供することで、効率的な診断と治療につながります。
治療は原因療法と対症療法を組み合わせて行われ、補液、整腸剤、食事療法が基本となります。寄生虫には駆虫薬、細菌感染には抗菌薬、食物アレルギーには除去食療法など、原因に応じた特異的な治療も重要です。
自宅でのケアと再発予防では、適切な水分確保、ストレス軽減、フード管理、多頭飼育環境での感染対策などが重要です。特に環境の安定化と定期的な健康診断により、多くの下痢は予防可能です。
下痢は猫にとって比較的よく見られる症状ですが、その背景には様々な原因が潜んでいる可能性があります。飼い主様が正しい知識を持ち、適切な観察と判断を行うことで、愛猫の健康を守ることができます。
症状の程度に関わらず、心配なことがあれば遠慮なく獣医師にご相談ください。早期の適切な対応により、多くの場合良好な予後が期待できます。愛猫の健康管理において、この記事の情報が少しでもお役に立てれば幸いです。

本記事は獣医師の監修のもと作成されていますが、個々の症例により対応が異なる場合があります。愛猫に気になる症状がある場合は、必ず獣医師の診察を受けてください。