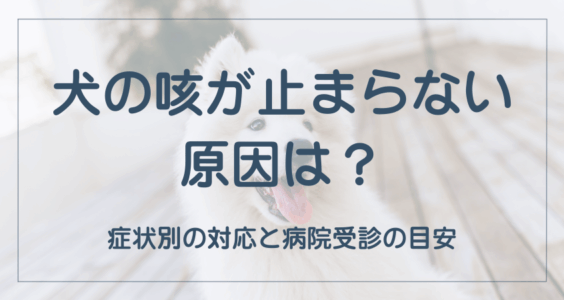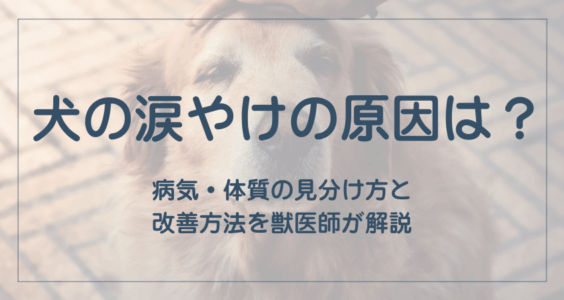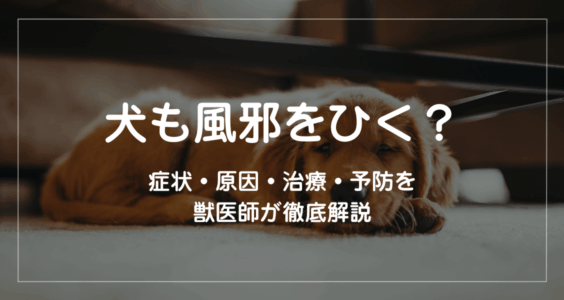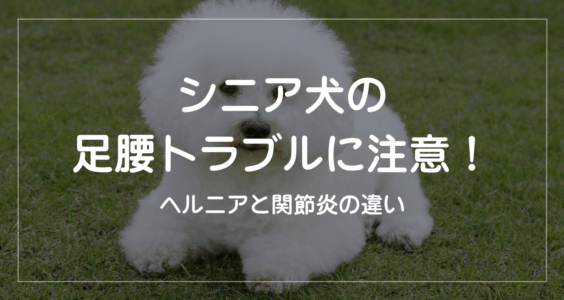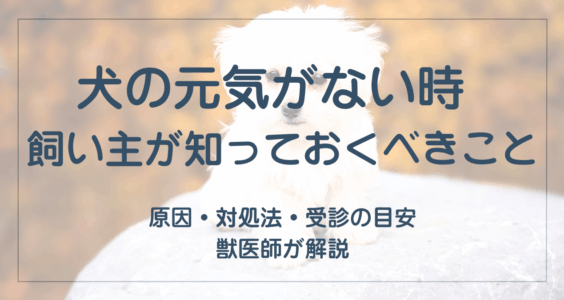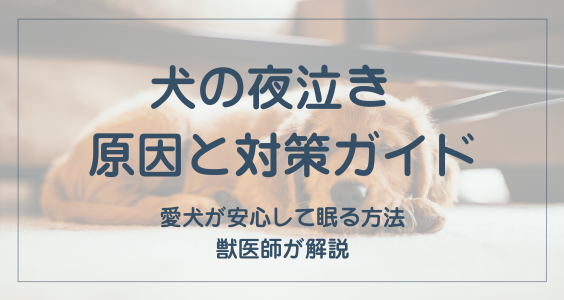愛犬の口臭が気になる、歯茎が赤く腫れている、食べ方がおかしい……。こうした症状に心当たりがあるなら、それは歯周病のサインかもしれません。実は、3歳以上の犬の約80%が歯周病またはその予備軍とも言われており、犬にとって非常に身近な病気です。しかし、放置すると単なる口の病気では済まず、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、犬の歯周病について、その原因から症状、治療法、そして自宅でできる予防・ケア方法まで、獣医師の視点から詳しく解説します。愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
1.犬の歯周病とは?
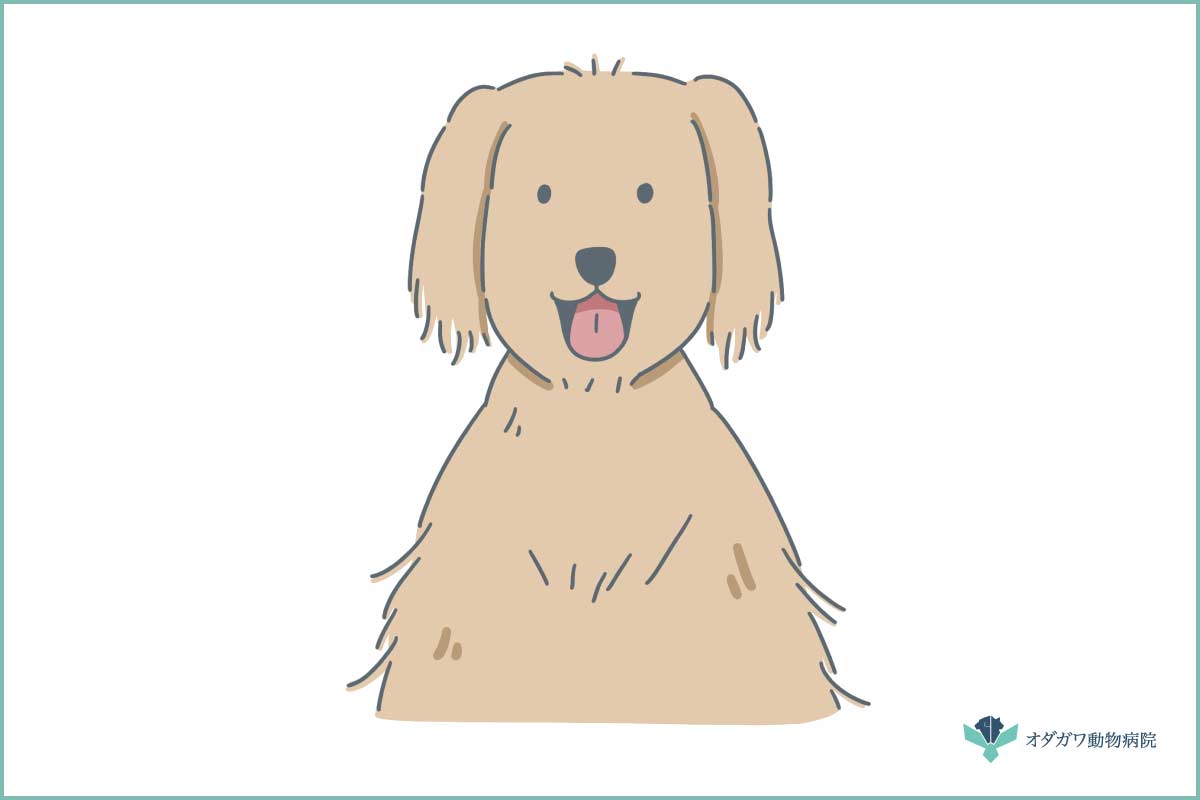
歯周病とは、歯の周囲の組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨など)に炎症が起こる病気の総称です。具体的には「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられます。
歯肉炎は、歯と歯肉の境目に歯垢(プラーク)が蓄積することで起こる、歯肉の炎症です。この段階では、歯肉が赤く腫れたり出血したりしますが、歯を支える骨まではダメージが及んでいません。適切なケアを行えば、元の健康な状態に戻すことができる可逆的な段階です。
一方、歯周炎は歯肉炎が進行した状態で、炎症が歯肉だけでなく、歯を支える歯槽骨や歯根膜にまで達しています。この段階になると、歯周ポケット(歯と歯肉の間の溝)が深くなり、歯がグラグラと動くようになります。歯周炎は不可逆的で、一度失われた骨は自然には戻りません。
歯周病の原因となるのは、歯垢です。歯垢は細菌の塊で、食べ物の残りカスや唾液中の成分と混ざり合って歯の表面に付着します。この歯垢を放置すると、約3〜5日でミネラル成分が沈着して硬い歯石へと変化します。歯石はザラザラとした表面を持つため、さらに歯垢が付きやすくなり、悪循環が生まれます。
歯垢や歯石に含まれる細菌は、毒素を産生して歯肉組織を破壊し、炎症を引き起こします。さらに、この細菌や毒素が血流に乗って全身に広がると、心臓、肝臓、腎臓などの重要な臓器にも影響を及ぼす可能性があるのです。
2.なぜ犬は歯周病になりやすいのか?
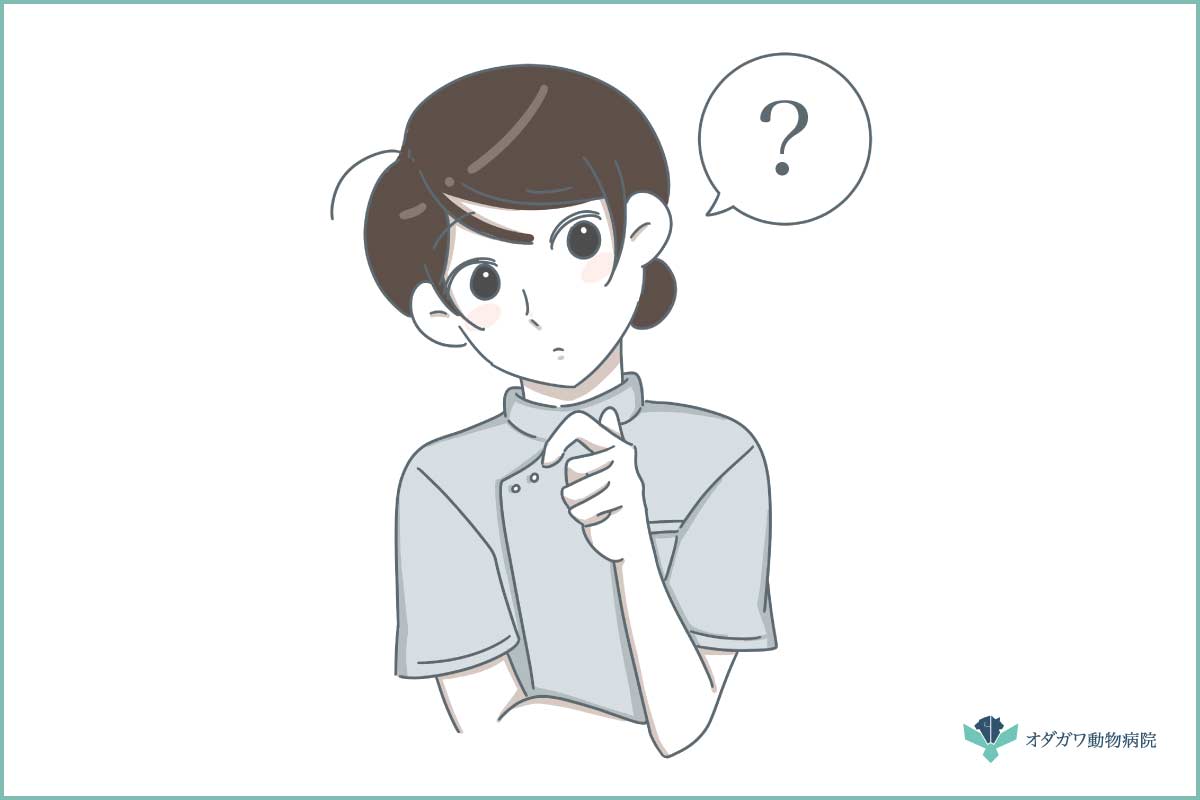
犬は人間以上に歯周病になりやすい動物だと言われています。その理由はいくつかあります。
歯磨き不足と食生活
最も大きな原因は、歯磨き不足です。野生の犬や狼は、獲物の骨や硬い組織を噛むことで、自然と歯の表面が磨かれていました。しかし、現代の家庭犬は柔らかいドッグフードを食べることが多く、歯の自浄作用が働きにくくなっています。
また、人間用の食べ物やおやつを与えすぎると、糖分や炭水化物が歯垢の形成を促進します。特に、粘着性のある食べ物は歯に付着しやすく、細菌の温床となります。
多くの飼い主さんは犬の歯磨きの重要性を理解していても、実際に毎日行うのは難しいのが現実です。犬が歯磨きを嫌がる、時間がない、正しい方法がわからないなど、さまざまな理由で歯のケアが後回しになりがちです。
口腔内の構造や犬種特性による影響
犬の口腔内の構造も、歯周病のリスクに影響します。犬の歯は人間よりも尖っており、歯と歯の間に隙間があるため、食べ物が挟まりやすい構造になっています。
特に小型犬は、顎のサイズに対して歯が密集しているため、歯垢が溜まりやすく、歯周病のリスクが高まります。トイプードル、チワワ、ヨークシャーテリア、マルチーズなどの小型犬種は、特に注意が必要です。
また、短頭種(パグ、ブルドッグ、シーズーなど)は、顎の構造上、歯並びが悪くなりやすく、歯が重なって生えることもあります。こうした部分は歯ブラシが届きにくく、歯垢が蓄積しやすくなります。
さらに、不正咬合(噛み合わせの異常)がある犬も、特定の歯に負担がかかったり、自浄作用が働きにくかったりするため、歯周病のリスクが高まります。
唾液の性質や加齢によるリスクも
犬の唾液は人間と比べてアルカリ性が強く、pH値が高いという特徴があります。このアルカリ性の環境は、歯石の形成を促進します。人間の唾液は弱酸性から中性であるため、歯石ができるまでに約20日かかると言われていますが、犬の場合はわずか3〜5日で歯石が形成されてしまいます。
また、加齢とともに免疫力が低下すると、細菌に対する抵抗力も弱まります。高齢犬では歯周病の進行が早く、重症化しやすい傾向があります。唾液の分泌量が減少することも、自浄作用の低下につながります。
さらに、糖尿病や腎臓病などの全身疾患を持つ犬は、免疫力が低下しているため、歯周病にかかりやすく、また歯周病が持病を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
3.歯周病の症状と進行段階
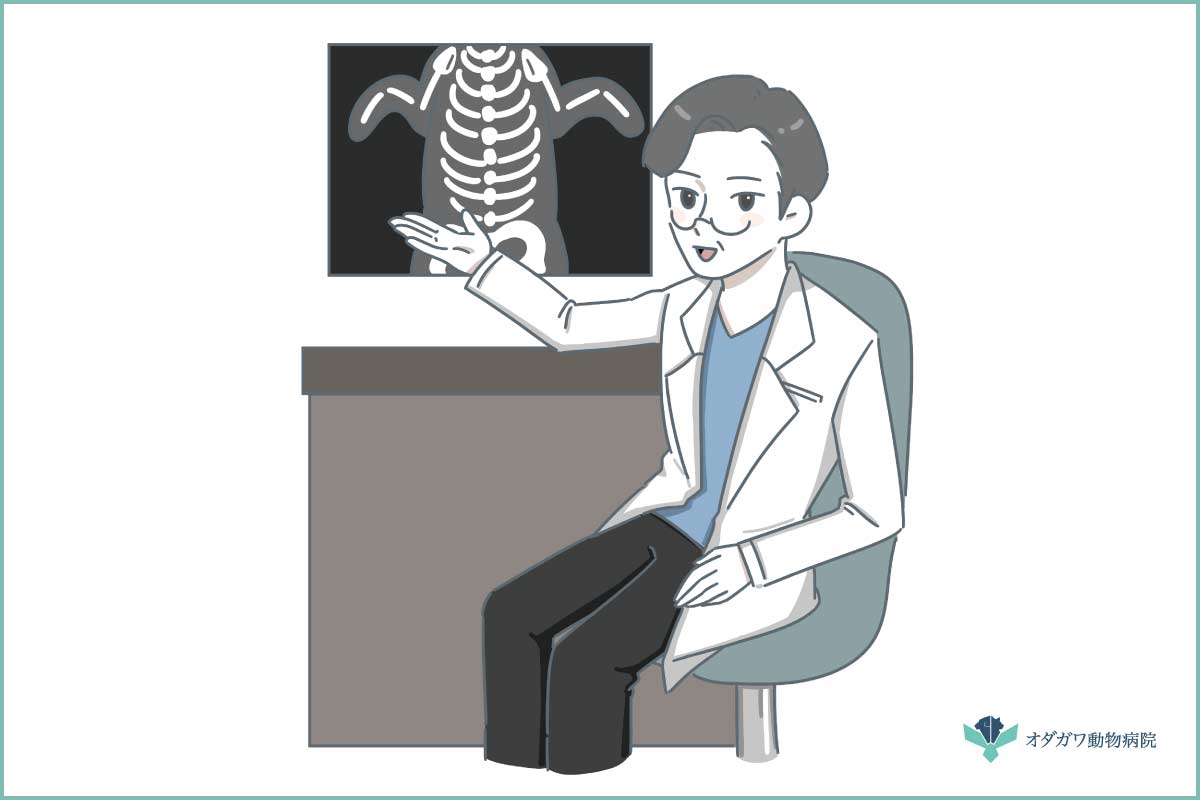
歯周病は段階的に進行します。早期に発見して適切な治療を行えば、進行を食い止めることができます。ここでは、歯周病の進行段階とそれぞれの症状について説明します。
ステージ1:歯肉炎(軽度)
最も初期の段階です。歯と歯肉の境目に歯垢が溜まり、歯肉に軽い炎症が起こります。
・歯肉が赤く腫れる
・歯肉から軽い出血がある(歯磨き時など)
・軽度の口臭
・歯に黄色っぽい歯垢が付着
この段階では、犬はほとんど痛みを感じないため、飼い主さんも気づきにくいことが多いです。しかし、適切なブラッシングと獣医師による歯垢除去を行えば、健康な状態に戻すことができます。
ステージ2:軽度歯周炎
歯肉炎が進行し、炎症が歯を支える組織にまで及び始めます。
・歯肉の腫れが目立つ
・歯肉からの出血が増える
・口臭が強くなる
・歯石が目立ち始める
・歯周ポケットが深くなる(2〜3mm程度)
・歯槽骨の軽度な喪失(レントゲン検査で確認)
この段階では、犬は食事の際に多少の違和感を感じることがありますが、まだ明らかな痛みの症状は見られないことが多いです。
ステージ3:中等度歯周炎
歯周病がさらに進行し、歯を支える骨が25〜50%失われた状態です。
・歯肉の著しい腫れと出血
・強い口臭
・歯がグラグラし始める
・歯周ポケットが深くなる(4〜6mm程度)
・歯肉から膿が出ることがある
・食事の際に痛みを感じる様子が見られる
・よだれが増える
・口を触られるのを嫌がる
この段階になると、犬は明らかに不快感や痛みを感じており、硬いものを噛むのを避けたり、片側だけで噛んだりするようになります。
ステージ4:重度歯周炎
歯を支える骨が50%以上失われ、歯が大きくグラつく、または抜け落ちる段階です。
・歯肉が後退し、歯根が露出
・歯が大きくグラグラする、または自然に抜け落ちる
・歯周ポケットが非常に深い(6mm以上)
・重度の口臭
・顔面の腫れ(特に目の下)
・膿の排出
・食事が困難になる
・明らかな痛みの兆候(鳴く、食欲不振、元気消失)
・よだれに血が混じる
重度の歯周病では、細菌感染が顎の骨や周囲の組織に広がり、さらには血流を通じて全身に影響を及ぼす可能性があります。
歯周病の症状は、初期段階では見逃しやすいものです。定期的に愛犬の口の中をチェックし、少しでも異常を感じたら、早めに動物病院を受診することが大切です。
4.歯周病を放置するとどうなる?
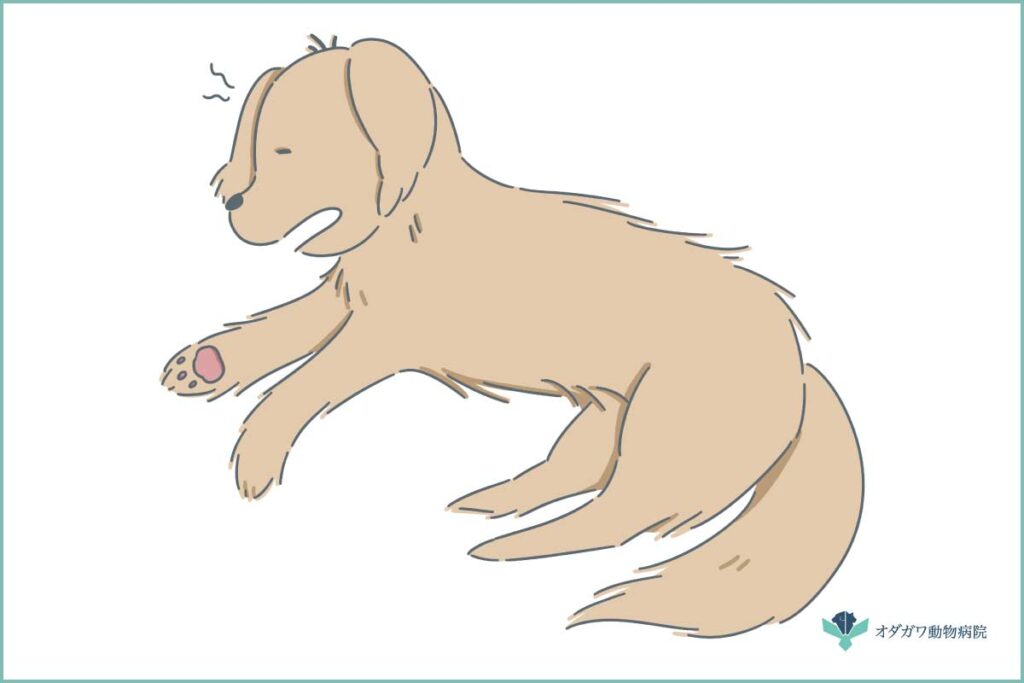
食べたいのに食べられない──歯の痛みで食欲不振に
歯周病が進行すると、歯肉や歯の周囲組織に強い痛みが生じます。犬は本能的に痛みを隠そうとするため、飼い主さんが気づいた時には、すでにかなりの苦痛を感じていることが多いのです。
痛みのために食事を避けるようになると、栄養不足に陥り、体重が減少します。特に高齢犬や小型犬では、わずかな体重減少でも健康に大きな影響を及ぼします。食べたいのに痛くて食べられないという状態は、犬にとって大きなストレスとなり、生活の質を著しく低下させます。
また、痛みから硬いフードを避けて柔らかいものばかり食べるようになると、歯の自浄作用がさらに低下し、歯周病が悪化するという悪循環に陥ります。
頬の腫れや皮膚の損傷につながることも
上顎の奥歯(第4前臼歯や臼歯)の歯周病が進行すると、歯根部に膿瘍(膿の溜まり)が形成されることがあります。この膿瘍が拡大すると、顔面、特に目の下が腫れてきます。
さらに悪化すると、膿瘍が皮膚を突き破って外に開口し、「歯性瘻管」という状態になることがあります。目の下や頬から膿や血が出てくるため、飼い主さんは非常に驚かれますが、これは歯周病が原因であることが多いのです。
下顎の歯周病でも同様に、顎の下に膿瘍ができ、皮膚が破れて膿が排出されることがあります。こうした状態になると、傷口からの二次感染のリスクもあり、治療が複雑になります。
顎の骨が弱くなり、骨折の場合も
歯周病が進行して歯槽骨が大きく失われると、顎の骨全体が弱くなります。特に小型犬では、下顎の骨が非常に薄いため、歯周病による骨の喪失が深刻な問題となります。
骨が弱くなった状態で硬いものを噛んだり、転倒したり、あるいは日常的な動作をしているだけでも、下顎骨が骨折してしまうことがあります。これを「病的骨折」と呼びます。
下顎骨の骨折は、犬にとって非常に痛みを伴い、食事ができなくなるだけでなく、治療も複雑で長期間を要します。場合によっては、外科的に金属プレートで固定する必要があり、犬への負担も大きくなります。
血流を通じて内臓疾患に発展するリスク
歯周病の最も深刻な影響は、口腔内だけでなく全身の臓器に及ぶ可能性があることです。歯周病によって歯肉に炎症が起こると、その部分の血管が損傷し、細菌や毒素が血流に入り込みやすくなります。
血流に乗った細菌や毒素は、全身を巡り、さまざまな臓器に到達します。特に影響を受けやすいのは、以下の臓器です。
心臓:細菌が心臓の弁に付着して増殖すると、心内膜炎を引き起こします。心内膜炎は、心臓の機能を低下させ、不整脈や心不全の原因となります。特に、もともと心臓病を持つ犬では、歯周病が心臓疾患を悪化させるリスクが高まります。
肝臓:血流に乗った細菌や毒素は肝臓で処理されますが、慢性的に大量の細菌や毒素が流れ込むと、肝臓に負担がかかり、肝機能障害を引き起こすことがあります。
腎臓:腎臓も血液をろ過する臓器であるため、細菌や毒素の影響を受けやすいです。歯周病が慢性腎臓病の発症や進行に関与している可能性が指摘されています。
さらに、歯周病による慢性的な炎症は、全身性の炎症反応を引き起こし、免疫系に負担をかけます。これにより、他の病気にかかりやすくなったり、既存の病気が悪化したりする可能性があります。
歯周病は口の中だけの問題ではありません。愛犬の全身の健康を守るためにも、歯周病の予防と早期治療が極めて重要なのです。
5.歯周病の治療法
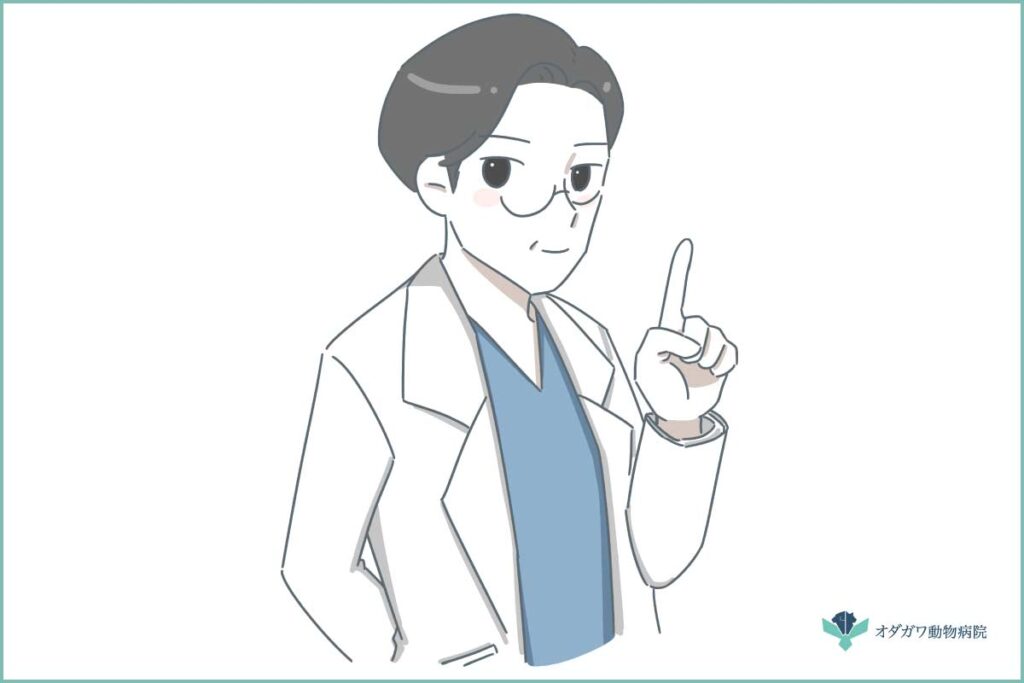
歯周病の治療は、その進行段階や重症度によって異なります。ここでは、主な治療法について詳しく説明します。
基本治療
スケーリング(歯石除去)
歯周病治療の基本は、歯垢や歯石を除去することです。犬の場合、効果的なスケーリングを行うためには、全身麻酔が必要です。全身麻酔下で行う理由は以下の通りです。
・犬が動かないようにして、安全かつ徹底的に処置を行うため
・歯周ポケットの奥深くや歯の裏側など、見えにくい部分まで確実に処置するため
・超音波スケーラーの使用時に飛び散る水や細菌を含んだエアロゾルから気道を保護するため
・処置中の痛みやストレスを軽減するため
スケーリングでは、超音波スケーラーやハンドスケーラーを使って、歯の表面だけでなく、歯周ポケット内の歯石や歯垢も丁寧に除去します。
ルートプレーニング(歯根面の滑沢化)
スケーリングで歯石を除去した後、歯根の表面を滑らかにする処置を行います。これにより、細菌が付着しにくくなり、歯周組織の回復を促進します。
ポリッシング(研磨)
スケーリングやルートプレーニング後、歯の表面には微細な傷がつき、そこに歯垢が付着しやすくなります。研磨用のペーストとラバーカップを使って歯の表面を滑らかに磨き上げることで、歯垢の再付着を防ぎます。
洗浄と消毒
歯周ポケット内を洗浄液で洗い流し、消毒します。これにより、残存する細菌を減少させます。
外科治療
中等度から重度の歯周病では、基本治療だけでは十分でなく、外科的な処置が必要になることがあります。
抜歯
歯周病が進行して歯を支える骨が大きく失われ、歯がグラグラになっている場合や、歯根部に膿瘍がある場合は、抜歯が必要になります。
抜歯と聞くと、多くの飼い主さんは「歯がなくなったら食事ができないのでは」と心配されますが、実際には、痛みの原因となっている歯を抜くことで、むしろ快適に食事ができるようになることが多いのです。犬は歯がなくてもフードを丸飲みしたり、歯茎で噛み砕いたりして食べることができます。
抜歯後は、抜歯窩(歯を抜いた後の穴)を縫合し、感染を防ぐために抗生物質を投与します。
歯周ポケットの外科的処置
深い歯周ポケットがある場合、歯肉を切開して歯根部を露出させ、歯根面に付着した歯石や感染組織を徹底的に除去する「フラップ手術」を行うことがあります。
また、失われた歯槽骨を再生させるために、骨移植や歯周組織再生材料を使用することもありますが、犬の場合は適用が限られています。
ブラッシング
治療後、最も重要なのは、歯周病の再発を防ぐための日常的なケアです。動物病院での治療は、あくまでも現在の歯周病を改善するものであり、その後のケアがなければ、再び歯周病が進行してしまいます。
治療後は、自宅での毎日のブラッシングが不可欠です。獣医師や動物看護師から、正しいブラッシング方法について指導を受け、実践しましょう。
また、定期的(通常3〜6ヶ月ごと)に動物病院で口腔内のチェックを受け、必要に応じて再度スケーリングを行うことが推奨されます。
治療後の抗生物質や鎮痛剤などの投薬も、獣医師の指示通りに必ず行いましょう。
6.歯周病になったらどうすればいい?
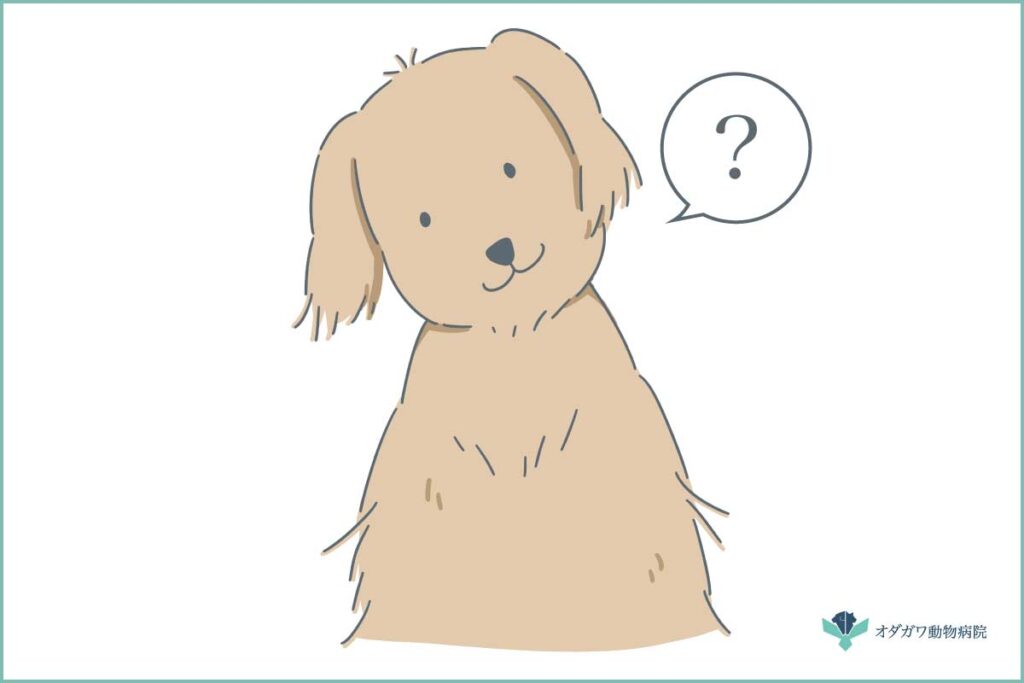
歯周病が疑われる場合はすぐに動物病院へ
口臭の悪化、歯茎の赤みや腫れ、食欲不振などの症状が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。歯周病は進行性の疾患であり、時間が経つほど治療が困難になり、愛犬への負担も大きくなります。
「まだ軽そうだから様子を見よう」と思わず、気になる症状があれば獣医師に相談することが大切です。
動物病院で行う診察と検査の流れ
動物病院では、まず視診により口腔内の状態を確認します。歯石の付着状況、歯茎の炎症の程度、歯の動揺の有無などを詳しく検査します。
必要に応じてレントゲン検査を行い、歯根部や歯槽骨の状態を確認します。これにより、見た目だけではわからない深部の病変も把握できます。
血液検査により全身状態や麻酔のリスクを評価し、治療計画を立てます。特に高齢犬や他に疾患を抱える犬では、詳細な検査が必要です。
治療後に気をつけたい再発防止と日常ケア
治療後は定期的な検診と日常的な口腔ケアが再発防止の鍵となります。獣医師の指導のもと、適切な歯磨きの方法を身につけましょう。
食事内容の見直しも重要です。ドライフードを中心とし、歯に良いとされるデンタルケア用のフードやおやつを活用するのも効果的です。
定期的な専門的クリーニング(3-6ヶ月ごと)も検討し、愛犬の口腔内を常に健康な状態に保つよう心がけましょう。
オダガワ動物病院の公式Youtubeチャンネル「世界一受けたい動物授業」では歯周病ケアにおすすめの商品も紹介しています。
7.自宅でできる予防・ケア方法
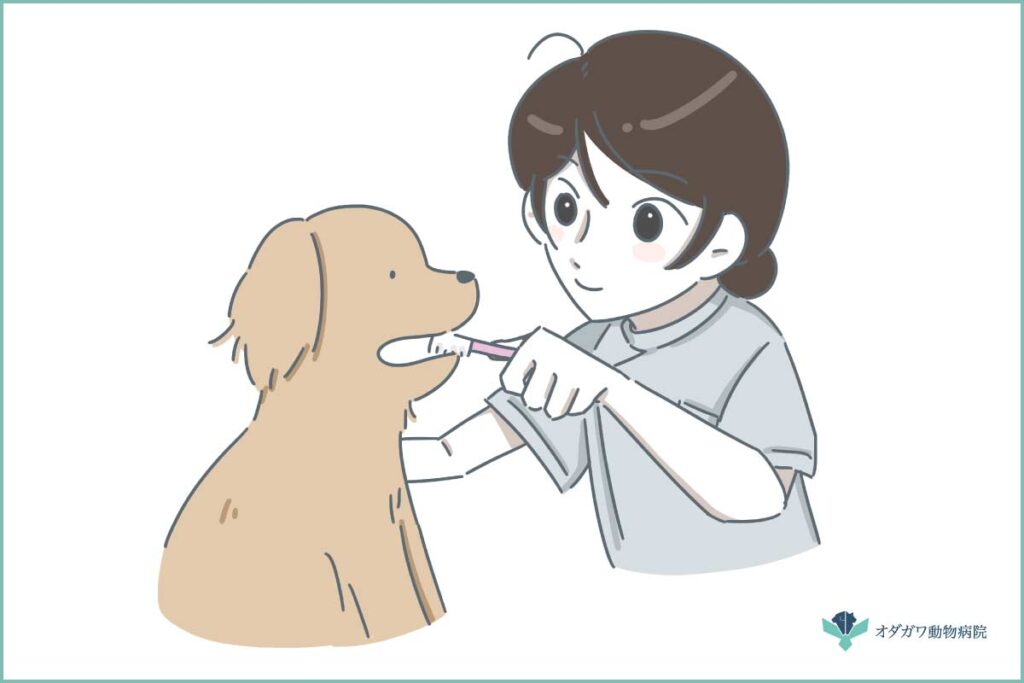
歯周病の最良の治療法は、予防です。毎日の適切なケアにより、歯周病の発症を防ぎ、愛犬の口腔内を健康に保つことができます。
毎日の歯磨きが最も効果的
歯周病予防の基本中の基本は、毎日の歯磨きです。理想的には、1日1回、できれば夜に歯磨きを行いましょう。
歯垢は約3〜5日で歯石に変わってしまうため、歯石になる前に歯垢を除去することが重要です。一度歯石になってしまうと、自宅でのブラッシングでは除去できず、動物病院での処置が必要になります。
歯磨きのステップ
犬の歯磨きに慣れていない場合は、段階的に進めることが大切です。
ステップ1
口周りを触ることに慣れさせる まずは、口の周りを優しく触り、触られることに慣れさせます。嫌がらずに触らせてくれたら、褒めておやつを与えましょう。数日から1週間程度かけて、口周りを触ることに抵抗がなくなるまで続けます。
ステップ2
唇をめくって歯に触れる 次に、唇を優しくめくり、指で歯や歯肉に触れます。最初は前歯から始め、徐々に奥歯にも触れるようにします。この段階でも、上手にできたら褒めておやつを与えます。
ステップ3
歯磨きペーストの味に慣れさせる 犬用の歯磨きペーストを指につけて、舐めさせます。犬用の歯磨きペーストは、チキンやビーフなどの味付けがされており、多くの犬が好む味になっています。人間用の歯磨き粉は、犬が飲み込むと有害な成分が含まれているため、絶対に使用しないでください。
ステップ4
指にガーゼを巻いて歯を磨く 指に濡らしたガーゼを巻き、歯磨きペーストをつけて、歯の表面を優しくこすります。最初は前歯だけ、慣れてきたら奥歯や歯の裏側も磨きます。
ステップ5
歯ブラシを使った歯磨き 犬用の歯ブラシ(柔らかい毛のもの)に歯磨きペーストをつけて、歯を磨きます。歯ブラシを歯と歯肉の境目に45度の角度で当て、小刻みに動かしながら磨きます。特に、歯と歯肉の境目や奥歯は歯垢が溜まりやすいので、重点的に磨きましょう。
最初は数本の歯を磨くだけでも十分です。徐々に磨く歯の数や時間を増やしていき、最終的にはすべての歯を磨けるようにします。
デンタルケア用品の活用
歯磨きが難しい場合や、歯磨きの補助として、以下のようなデンタルケア用品を活用することもできます。
デンタルガム・おやつ
噛むことで歯の表面の歯垢を除去する効果があるデンタルガムやおやつが市販されています。VOHC(米国獣医口腔衛生協議会)の認定を受けた製品を選ぶと良いでしょう。
ただし、デンタルガムだけでは歯周病を完全に予防することはできません。あくまでも補助的な役割として考え、ブラッシングと併用しましょう。また、カロリーにも注意が必要です。
デンタルトイ
歯磨き効果のある凹凸や溝がついた噛むおもちゃです。遊びながら歯のケアができるため、犬も楽しく続けられます。
口腔ケアサプリメント・水に混ぜるタイプ
飲み水に混ぜることで、口腔内の細菌の増殖を抑える製品もあります。こちらもブラッシングの代わりにはなりませんが、補助的に使用することができます。
指サック型歯ブラシ
指にはめて使うタイプの歯ブラシで、歯ブラシよりも扱いやすく、初心者にもおすすめです。
歯磨きシート
指に巻いて歯を拭くシートタイプの製品もあります。歯ブラシが苦手な犬の導入段階として有効です。
食事の工夫
食事内容も口腔ケアに影響します。
ドライフードは、噛むことで歯の表面をこする効果があるため、ウェットフードよりも歯垢が付きにくいとされています。ただし、ドライフードだけでは歯周病は防げないため、ブラッシングは必須です。
人間の食べ物、特に糖分の多いものは与えないようにしましょう。
デンタルケア用に設計された特別なフードもあります。獣医師に相談してみましょう。
定期的な健康診断
年に1〜2回、動物病院で健康診断を受ける際に、口腔内のチェックも依頼しましょう。獣医師による専門的なチェックで、自宅では気づかない初期の歯周病を発見できることがあります。
また、3歳以上の犬や、小型犬、歯周病のリスクが高い犬種の場合は、年に1回の専門的なスケーリング(歯石除去)を定期的に受けることも、歯周病予防に効果的です。
子犬の頃からのケアが重要
歯周病予防は、子犬の頃から始めることが理想的です。乳歯の時期から口を触ることや歯磨きに慣れさせておくことで、成犬になってからのケアがスムーズになります。
また、若い頃から定期的なケアを行うことで、歯周病の発症を遅らせたり、防いだりすることができます。
※当院では歯周病予防としてK-ブラッシュの使用をおすすめしております。
↓ご購入はこちらから↓

8.まとめ・今すぐできること

犬の歯周病は予防可能な疾患です。愛犬の健康を守るために、今日からできることを始めましょう。
今すぐできること
・愛犬の口の中をチェック – 歯茎の色、口臭、歯石の付着状況を確認
・歯磨きの準備 – 犬用歯ブラシと歯磨きペーストを購入
・食事の見直し – ドライフード中心の食事に変更
・かかりつけ医への相談 – 現在の口腔状態について獣医師に相談
歯周病は愛犬の生活の質を大きく左右します。痛みにより食事が困難になったり、全身への悪影響により重篤な疾患を引き起こしたりする可能性もあります。
しかし、適切な知識と日常ケアがあれば、歯周病は十分に予防・管理できる疾患です。愛犬がいつまでも健康で快適に過ごせるよう、今日から口腔ケアを始めてみませんか?
定期的な専門的ケアと日常的な予防ケアを組み合わせることで、愛犬の口腔内を健康に保ち、全身の健康維持にもつながります。気になることがあれば、遠慮なく動物病院に相談し、愛犬にとって最適なケア方法を見つけていきましょう。