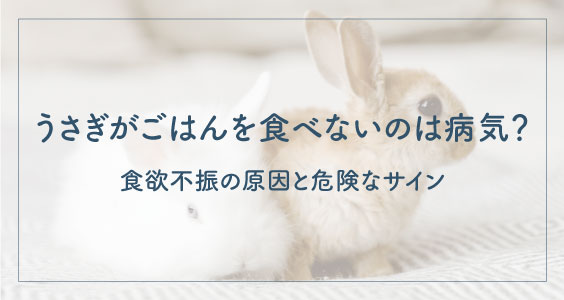「うちの子、なんだか最近うんちがゆるいな…」「お尻が汚れているけど、これって下痢?」
うさぎを飼っている飼い主さんなら、一度は軟便や下痢で悩んだ経験があるかもしれません。見た目は元気そうだし、病院に行くべきか迷う…。そんな気持ち、とてもよくわかります。しかし、うさぎの下痢は、命に関わることもある見過ごせない症状です。特にうさぎは体の小さい動物なので、少しの体調変化が命取りになることも少なくありません。
この記事では、うさぎの軟便と下痢の違いから、その原因、そして「病院に行くべきか?」を見極めるポイント、さらには家庭でできる予防と改善策まで、詳しく解説していきます。あなたの愛するうさぎが健康で快適な毎日を送れるよう、一緒に学んでいきましょう。
うさぎの下痢と軟便の違い|命に関わる症状の見分け方とは?
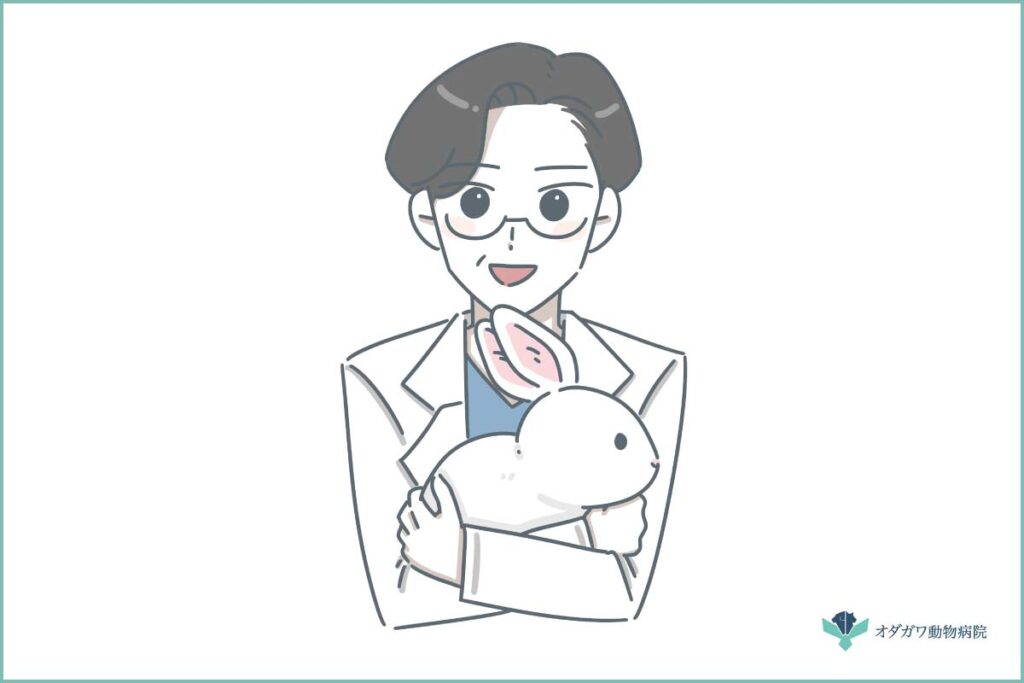
うさぎの便は、健康状態を示すバロメーターです。普段からよく観察することで、異常にいち早く気づくことができます。
盲腸便との見分け方
まず、うさぎの「うんち」には大きく分けて2種類あることをご存知でしょうか?
・硬便(コロコロうんち)
普段よく目にする、丸くてコロコロとした便です。繊維質を多く含む健全な便の証拠です。
・盲腸便(ぶどうの房状うんち、食糞)
夜間から早朝にかけて排出され、うさぎ自身が食べ直す(食糞する)ことで、必要な栄養素を効率よく吸収するための大切な便です。黒っぽく、ブドウの房のように連なっていて、少しやわらかく、表面には粘液のような光沢があるのが特徴です。
では、「軟便」と「下痢」はこれらとどう違うのでしょうか?
・軟便
通常の硬便よりも水分が多く、形が崩れている便を指します。べたつきがあったり、つぶれたような形をしていたりします。盲腸便がうまく形成されず、べちゃっとしている場合も軟便と見なされることがあります。一般的に、硬便の形が保たれていれば軟便と判断されることが多いです。
・下痢
水分が非常に多く、形をなさない液体状の便を指します。水のようにシャバシャバしていたり、ゼリー状の粘液や血液が混じっていたりすることもあります。お尻周りがひどく汚れてしまうのも下痢の特徴です。
盲腸便と軟便・下痢の区別が難しいと感じる飼い主さんもいるかもしれません。盲腸便は粘液で覆われていますが、形はブドウの房状をしています。一方、軟便や下痢は、形が完全に崩れていたり、水っぽかったりします。もし判断に迷うようであれば、すぐに動物病院に相談しましょう。
下痢は危険?|命に関わるケース・緊急サイン
「たかが下痢」と軽く見てはいけません。うさぎの下痢は、命に関わる非常に危険な症状となることがあります。特に、以下のサインが見られた場合は、一刻も早く動物病院を受診する必要があります。
・水っぽい下痢が続いている
脱水症状が急速に進行し、命に関わります。
・お尻周りがひどく汚れている
下痢が長時間続いている証拠です。皮膚炎やハエ蛆症の原因にもなります。
・元気がない、食欲がない、水を飲まない
脱水や病状の悪化を示唆する重篤なサインです。
・ぐったりしている、体を丸めている、動きたがらない
強い痛みやショック状態に陥っている可能性があります。
・発熱している(耳が熱いなど)
感染症の可能性も考えられます。
・便に血液やゼリー状の粘液が混じっている
腸炎や寄生虫感染など、重篤な疾患が疑われます。
・低体温
体が冷たくなっている場合は、非常に危険な状態です。
・歯ぎしりをしている
うさぎは痛みを感じると歯ぎしりをすることがあります。
うさぎは体調不良を隠す習性があるため、「いつもと違う」と感じたら、すでに病状が進行している可能性も考えられます。特に子うさぎは免疫力が未発達なため、下痢が重症化しやすく、あっという間に命を落としてしまうこともあります。
下痢が出たら、「もしかして大丈夫かも?」ではなく、「すぐに病院へ」という意識を持つことが、うさぎの命を守る上で非常に重要です。
オダガワ動物病院で実際に診断した症例カルテはこちら↓
【食欲不振のうさぎに隠れた病気】腎臓病と毛球症の症例|診断カルテ
うさぎが下痢をする7つの原因|ストレス・食事・感染症まで解説

うさぎが下痢になる原因は多岐にわたります。単一の要因だけでなく、複数の要因が絡み合って発生することもあります。ここでは、主な7つの原因について詳しく見ていきましょう。
1. 不正咬合(歯の異常)
うさぎの歯は一生伸び続けるため、正常に摩耗しないと不正咬合と呼ばれる状態になります。不正咬合があると、以下のような問題が起こり、結果的に下痢につながることがあります。
食欲不振・食事量の減少
歯の痛みで食べることが困難になり、食欲が落ちます。特に牧草のような繊維質の摂取量が減ると、腸の動きが悪くなります。
咀嚼不足による消化不良
食べ物を十分に噛み砕けないため、消化不良を起こしやすくなります。
腸運動の低下
食物繊維の摂取不足や痛みによるストレスで、腸のぜん動運動が低下し、消化管うっ滞を引き起こしやすくなります。
不正咬合は見た目ではわかりにくいことも多いため、食欲不振やよだれ、涙目などの症状が見られたら、歯のチェックも視野に入れる必要があります。定期的な健康診断で獣医さんに歯の状態を確認してもらうことが大切です。
2. 毛球症・消化管うっ滞
うさぎは毛づくろいをする動物なので、抜け毛を飲み込んでしまうことがあります。通常は便と一緒に排出されますが、過剰な毛や、腸の動きが悪いとうまく排出されずに胃や腸に溜まって毛球を形成することがあります。
毛球症
飲み込んだ毛が胃や腸で大きな塊となり、消化管を詰まらせてしまう病気です。
消化管うっ滞
毛球症だけでなく、食欲不振やストレス、痛みなど様々な原因で腸の動きが極端に悪くなり、消化物が停滞してしまう状態です。
毛球症や消化管うっ滞が起こると、食欲不振、便秘、そして二次的に下痢を引き起こすことがあります。腸の停滞によって異常発酵が起こり、ガスが溜まったり、腸内細菌のバランスが崩れたりすることで、水っぽい下痢になるケースも少なくありません。
3. 食物繊維不足・高炭水化物食
うさぎの消化器は、豊富な食物繊維を摂取することで正常に機能するようにできています。牧草を主食とするのはこのためです。
食物繊維不足
牧草の摂取量が少なかったり、主食がペレットや野菜に偏っていたりすると、食物繊維が不足します。食物繊維は腸のぜん動運動を促進し、腸内細菌のバランスを整える上で不可欠です。不足すると、腸の動きが鈍くなり、盲腸便の消失や、腸内環境の乱れによる軟便・下痢を引き起こします。
高炭水化物食
ペレットの与えすぎや、穀物、おやつなどを与えすぎると、炭水化物過多になります。炭水化物は盲腸内で異常発酵を起こしやすく、有害な細菌が増殖することで、腸内環境が乱れ、下痢の原因となります。
適切な量の牧草を与え、ペレットやおやつの量を管理することは、うさぎの健康な消化器を維持するために非常に重要です。
4. 感染症(寄生虫・細菌・ウイルス)
下痢の直接的な原因として、様々な感染症が挙げられます。
寄生虫
コクシジウム
子うさぎに多く見られる原虫で、腸の粘膜に寄生して炎症を起こし、重度の水様性下痢を引き起こします。食欲不振、脱水、発育不良を伴うことが多く、子うさぎでは命に関わることもあります。
エンセファリトゾーン
腎臓や脳などに寄生する原虫ですが、下痢や食欲不振の原因となることもあります。
細菌
クロストリジウム属菌
正常な腸内にも存在しますが、ストレスや食事内容の変化などで異常増殖すると、毒素を産生して重度の腸炎や下痢を引き起こします。
パスツレラ菌
鼻炎や肺炎の原因菌として有名ですが、消化器に感染して下痢を引き起こすこともあります。
大腸菌
種類によっては病原性を示し、下痢の原因となることがあります。
サルモネラ菌
食中毒の原因菌として知られていますが、うさぎも感染すると下痢を起こすことがあります。
ウイルス
ロタウイルス
特に子うさぎで重度の下痢を引き起こすことがあります。人間と同様に、経口感染します。
コロナウイルス
うさぎの消化器症状を引き起こすウイルスとして知られています。
これらの感染症は、糞便検査や血液検査で診断されます。特に多頭飼いの場合、感染が広がりやすいので注意が必要です。
5. ストレス・環境変化
うさぎは非常にデリケートな動物で、環境の変化やストレスに敏感に反応します。ストレスは、自律神経のバランスを崩し、腸のぜん動運動に影響を与えることがあります。
・引越しやケージの移動
環境が大きく変わることで、不安を感じ、食欲不振や軟便・下痢につながることがあります。
・新しいペットや家族の増加
縄張り意識が強いため、新しい存在にストレスを感じることがあります。
・騒音や振動
普段と異なる大きな音や振動もストレスの原因となります。
・室温や湿度の急激な変化
快適な環境から逸脱すると、体調を崩しやすくなります。
・不適切な飼育環境
ケージが狭すぎる、清潔でない、隠れる場所がないなどもストレスの原因となります。
ストレスによる下痢の場合、原因を取り除き、うさぎが安心できる環境を整えてあげることで改善が見られることが多いです。
6. 腫瘍などの疾患
稀ではありますが、消化器系の腫瘍などが下痢の原因となることもあります。
直腸腫瘍
便の通り道を塞いだり、炎症を起こしたりすることで、下痢や血便を引き起こすことがあります。
リンパ腫
消化器系に発生すると、吸収不良や下痢を引き起こすことがあります。
その他内臓疾患
肝臓や腎臓などの機能低下が、間接的に消化器症状として下痢を引き起こすこともあります。
高齢のうさぎや、慢性的に下痢が続く場合は、これらの疾患の可能性も視野に入れ、詳しい検査が必要となることがあります。
7. 子うさぎ特有の問題
子うさぎは大人に比べて、下痢を起こしやすく、また重症化しやすいという特徴があります。
免疫機能が未発達
病原体に対する抵抗力が弱いため、感染症にかかりやすく、一度かかると重症化しやすいです。
消化器機能が未発達
消化器系がまだ成熟していないため、食事内容の急な変化や、消化しにくい食べ物によって下痢を起こしやすいです。
ストレスへの感受性
環境の変化や授乳中のストレスなど、様々な要因で体調を崩しやすいです。
コクシジウムなどの寄生虫
子うさぎに特によく見られ、重度の下痢を引き起こします。
子うさぎの下痢は特に注意が必要です。少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院を受診してください。
「病院に行くべき?」見極めと相談のタイミング

うさぎの便に異変を感じたら、「様子を見ようかな…」と迷う気持ちもわかりますが、基本的には下痢が出た時点で速やかに動物病院を受診することを強くお勧めします。
下痢が出た時点で速やかに動物病院へ(脱水リスクあり)
なぜ、すぐに病院に行くべきなのでしょうか?
脱水症状の危険性
うさぎは体が小さいため、下痢によって体から水分が失われると、あっという間に脱水症状に陥ります。脱水は命に関わる非常に危険な状態です。
病状の急速な悪化
うさぎは病気を隠す習性があるため、飼い主さんが気づいた時にはすでに病状が進行しているケースが少なくありません。下痢は重篤な病気のサインである可能性が高く、早期発見・早期治療が重要です。
正確な診断と適切な治療
自己判断で対処しようとすると、かえって症状を悪化させてしまうことがあります。獣医による正確な診断がなければ、適切な治療を行うことはできません。
特に、以下のような状況では、迷わず緊急で動物病院を受診してください。
・水のような便が何回も出ている
・元気がない、ぐったりしている
・食欲がない、水を飲まない
・便に血やゼリー状の粘液が混じっている
・低体温(体が冷たい)になっている
・歯ぎしりをしているなど、痛がっている様子がある
これらのサインは、命に関わる重篤な状態である可能性が高いです。
持参するべき情報
動物病院を受診する際は、できるだけ多くの情報を持参することで、獣医さんがより正確な診断を下す助けになります。
便の状態
・実際に下痢をしている便を持参する
可能であれば、ラップなどに包んで持っていくと良いでしょう。採取後、時間があまり経っていないもの、異物が混じっていないものを選びましょう。
・色、硬さ(水っぽさ)、量、臭い、粘液や血液の有無
具体的にどのような状態の便が出ているかを詳しく伝えましょう。写真や動画を撮っておくのも有効です。
・いつから下痢が始まったか、頻度
発症からの経過を伝えます。
食事内容の変化
・普段与えているフード(牧草、ペレット、野菜、おやつなど)の種類と量
具体的な商品名や与え方を伝えましょう。
・最近、新しいフードやおやつを与えたか
食事内容の急な変更は下痢の原因になることがあります。
・与え方や食事量の変化
食事の時間が不規則になった、量が減った、増えたなど。
環境・ストレス変化
・最近、引越しやケージの移動、新しい家族の増加など、環境に変化があったか
・騒音や温度変化など、うさぎにとってストレスになるような出来事があったか
・飼育環境の清潔さ
ケージの掃除頻度や、床材の種類なども伝えると良いでしょう。
その他の症状
・元気や食欲、飲水量の変化
普段と比べてどうか。
・尿の量や色
正常か、異常があるか。
・呼吸の状態
荒い、速いなど。
・毛並みや皮膚の状態
脱毛や皮膚の炎症など。
・体重の変化
最近体重が減ったなど。
これらの情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。
「盲腸便の下痢」との判別も獣医にお任せが安心
前述の通り、うさぎの便には硬便と盲腸便があり、盲腸便は通常よりもやわらかい性質を持っています。そのため、「これは盲腸便がうまく排出できなかっただけなのか、それとも本格的な下痢なのか?」と、飼い主さんが自分で判断するのは非常に難しい場合があります。
素人判断で「盲腸便の乱れだから大丈夫」と放置してしまうと、実は重篤な疾患が隠れていて、手遅れになってしまう可能性もあります。盲腸便の異常なのか、本当の下痢なのかの判別も含め、獣医師に診てもらうのが最も確実で安全です。
うさぎの下痢予防法|家庭でできる食事と環境の工夫
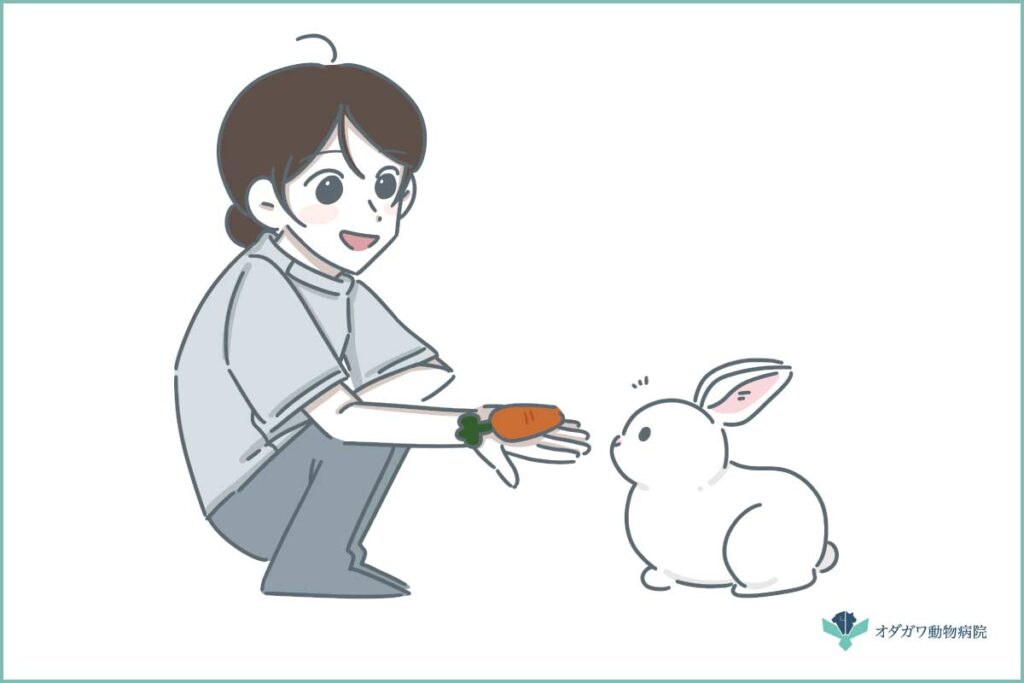
下痢になってしまったらすぐに病院に行くことが大切ですが、普段から下痢を予防し、万が一の際に備えてできることがあります。ここでは、家庭でできる予防と改善の工夫について解説します。
食生活の見直し
うさぎの消化器の健康を保つ上で、食生活は最も重要な要素の一つです。
主食はイネ科牧草(チモシー)をたっぷりと
うさぎにとって最も大切な食べ物はイネ科牧草、特にチモシーです。
・豊富な食物繊維
チモシーにはうさぎが必要とする豊富な食物繊維が含まれています。食物繊維は、腸のぜん動運動を活発にし、消化物のスムーズな通過を助けます。これにより、消化管うっ滞や毛球症の予防につながります。
・歯の摩耗
牧草をよく噛むことで、常に伸び続けるうさぎの歯が自然に摩耗され、不正咬合の予防になります。
・腸内環境の維持
牧草に含まれる食物繊維は、盲腸内の善玉菌の餌となり、健康な腸内フローラを維持する上で不可欠です。
常に新鮮なチモシーをケージに入れて、食べ放題の状態にしておくことが理想です。品質の良い牧草を選ぶことも大切です。
↓獣医師おすすめのフード購入はこちらから↓

ペレットは少量に調整(高タンパク・過多が軟便の原因)
ペレットは、うさぎの必要な栄養素をバランス良く摂取できる便利なフードですが、与えすぎると下痢の原因になることがあります。
・高タンパク・高炭水化物
市販のペレットの中には、高タンパク・高炭水化物のものがあり、これらを過剰に与えると、盲腸内で異常発酵が起こり、腸内細菌のバランスが崩れて下痢を引き起こしやすくなります。
・肥満の原因
ペレットの過剰摂取は肥満にもつながり、運動不足による消化器の不調を引き起こすこともあります。
ペレットの量は、うさぎの体重や年齢、活動量に合わせて適切に調整しましょう。一般的には、体重1kgあたり15g~25g程度が目安とされていますが、個体差が大きいため、獣医さんと相談して決めるのが良いでしょう。特に成長期を過ぎた大人うさぎは、ペレットの量を控えめにし、牧草を主食とすることが重要です。
野菜は新鮮なものを少しずつ、牧草→野菜→ペレットの順で与えると消化促進
野菜はビタミンやミネラルを補給する上で有効ですが、与え方には注意が必要です。
・新鮮なものを少量ずつ
古くなった野菜や、一度に大量に与えると消化不良や下痢の原因になります。洗って水気をよく切った、新鮮なものを少量ずつ与えましょう。
・与える種類
葉物野菜(小松菜、チンゲン菜、ロメインレタスなど)が適しています。キャベツやブロッコリーなど、ガスを発生させやすいものは控えめにしましょう。
・与える順番
牧草をしっかり食べさせた後に、野菜、そして最後にペレットを与えるのが理想的です。この順番で与えることで、まず牧草で満腹になり、他のフードの過剰摂取を防ぎ、消化管の動きを整える効果も期待できます。
新しい野菜を与える際は、ごく少量から始め、便の状態に異常がないか確認しながら徐々に量を増やしていくようにしましょう。
オダガワ動物病院の公式youtubeチャンネル「世界一受けたい動物授業」では、うさぎにおすすめのフードを紹介しています。
環境整備とストレスケア
うさぎの健康は、飼育環境とストレスレベルに大きく左右されます。
清潔な飼育環境を維持する
不衛生な環境は、病原菌の増殖を招き、感染症による下痢のリスクを高めます。
・ケージの定期的な清掃
排泄物が溜まらないよう、毎日トイレの掃除を行い、ケージ全体も週に1回は徹底的に掃除しましょう。
・床材の交換
湿った床材は細菌が繁殖しやすいため、常に乾燥した状態を保ち、定期的に交換しましょう。
・食器や給水ボトルの清潔
毎日洗い、新鮮な水を与えるようにしましょう。
急な環境変化を避け、静かな暮らしを心掛ける
前述の通り、うさぎはストレスに敏感な動物です。
・静かで落ち着ける場所
ケージは家族の出入りが激しくない、静かで落ち着ける場所に設置しましょう。テレビや大きな音の出る家電の近くは避けるのが賢明です。
・隠れ家の設置
うさぎがいつでも身を隠せるようなシェルターやハウスをケージ内に設置してあげましょう。これにより、安心感を与え、ストレスを軽減できます。
・室温・湿度の管理
うさぎが快適に過ごせる室温(18~24℃程度)と湿度(40~60%程度)を保つようにしましょう。急激な温度変化は体調を崩す原因になります。
・生活リズムの安定
毎日決まった時間に食事を与え、遊びの時間を設けるなど、生活リズムを安定させることもストレス軽減につながります。
歯&毛球ケア
日々のケアも、下痢予防に欠かせません。
定期的な歯のチェックと牧草中心の食事で不正咬合予防
不正咬合は下痢だけでなく、様々な健康問題の原因となります。
・牧草中心の食事
これが最も重要です。牧草をしっかり噛むことで、歯が自然に摩耗し、不正咬合の予防になります。
・定期的な歯のチェック
定期的に口元を観察し、よだれが出ていないか、口周りが汚れていないかなどを確認しましょう。また、動物病院での健康診断の際に、獣医さんに歯の状態をチェックしてもらうことも重要です。
換毛期にはブラッシングを頻繁に行い、毛球症予防
うさぎには換毛期があり、この時期は特に抜け毛が増えます。
・こまめなブラッシング
換毛期には、毎日あるいは週に数回、こまめにブラッシングを行い、抜け毛を物理的に除去してあげましょう。これにより、うさぎが飲み込む毛の量を減らし、毛球症のリスクを軽減できます。
・換毛期以外のブラッシング
換毛期以外でも、定期的にブラッシングをしてあげることで、毛並みを清潔に保ち、皮膚の健康も維持できます。
・サプリメントの活用
毛球ケアに特化したサプリメントや、消化を助ける酵素入りのサプリメントなども、獣医さんと相談の上、活用を検討するのも良いでしょう。
うさぎの下痢に効くおすすめフードとサプリメント

獣医師の指導のもと、下痢の改善や予防に役立つフードやサプリメントを検討することもできます。ただし、あくまで補助的な役割であることを忘れず、まずは食事の見直しや環境整備といった基本的なケアを優先しましょう。
乳酸菌/プロバイオティクスサプリ
うさぎの健康な消化器を維持する上で、腸内細菌のバランスは非常に重要です。乳酸菌やプロバイオティクスは、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることで、腸内環境を整える効果が期待できます。
・目的
軟便の予防、腸内環境の改善、消化機能のサポート、免疫力の向上など。
・期待できる効果
腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑制する。
消化吸収を助け、便の状態を改善する。
ストレスなどによる腸の不調を和らげる。
・製品例
「16種乳酸菌エキス・GABA配合サプリ」
多種類の乳酸菌が配合されており、腸内フローラの多様性をサポートします。GABAはストレス軽減効果も期待できるため、ストレス性の軟便にも有効かもしれません。
「サンコー乳酸菌サプリ」
ペレットタイプで与えやすく、フラクトオリゴ糖(善玉菌の餌になるプレバイオティクス)が配合されているものもあります。
与え方
製品によって推奨量が異なりますので、必ずパッケージの指示に従って与えましょう。獣医さんに相談し、うさぎの状態に合ったものを選んでもらうのが最も確実です。
注意点
下痢がひどい場合や、感染症が原因の場合は、サプリメントだけで治すことはできません。必ず獣医さんの診察を受け、指示に従いましょう。
総合サプリ(RNAヌクレオチド、食物繊維、GABAなど)
特定の栄養素や成分を補給することで、うさぎの全体的な健康をサポートし、下痢になりにくい体質を目指すサプリメントもあります。
・RNAヌクレオチド
細胞の再生や免疫機能の維持に重要な役割を果たす成分です。腸の粘膜の修復を助けたり、免疫力を高めたりする効果が期待できます。
・食物繊維
牧草だけでは不足しがちな食物繊維を補給し、消化管の動きをサポートします。
・GABA(ガンマアミノ酪酸)
神経伝達物質の一種で、リラックス効果やストレス軽減効果が期待できます。ストレスによる下痢の予防に役立つ可能性があります。
これらの成分を複合的に配合したサプリメントは、胃腸の健康、免疫力の向上、ストレスケアなど、多角的にうさぎの健康をサポートすることを目的としています。
使い方の注意点
サプリメントはあくまで補助食品であり、万能薬ではありません。
根本原因の特定と改善が最優先
下痢の根本的な原因(食事内容、環境、感染症など)を特定し、それを取り除くことが最も重要です。サプリメントだけで症状が改善することはありません。
獣医師との相談
サプリメントを与える前に、必ず獣医師に相談しましょう。うさぎの状態や、服用中の薬との兼ね合いによっては、与えない方が良い場合もあります。
適切な量の与え方
過剰な摂取はかえって体調を崩す原因となることがあります。製品に記載されている用法・用量を守り、適切に与えましょう。
即効性はない
サプリメントは医薬品とは異なり、即効性は期待できません。継続して与えることで、徐々に効果が期待できるものです。
サプリメントは、適切な飼育環境とバランスの取れた食事、そして獣医による定期的な健康チェックと治療を土台とした上で、プラスアルファとして活用を検討しましょう。
まとめとQ&A

うさぎの軟便や下痢は、飼い主さんにとって心配な症状ですが、正しい知識と迅速な対応で、愛するうさぎの命を守ることができます。
Q1. 下痢が続いたら病院に行った方が良い?
A. はい、すぐに動物病院へ。脱水・重症化のリスクがあります。
うさぎの下痢は、見た目以上に深刻な状態である可能性が高いです。特に水のような下痢が続いている場合、急速に脱水が進み、命に関わる事態に発展することもあります。元気がない、食欲がない、水を飲まないといった他の症状が見られなくても、下痢が出た時点で迷わず動物病院を受診することが、うさぎの命を守る上で最も重要な判断です。早めの受診が、治療の選択肢を広げ、回復を早めることにつながります。
Q2. サプリだけで治りますか?
A. サプリは補助。食事・環境・歯・毛球ケアとのセットが効果的です。
サプリメントは、腸内環境を整えたり、免疫力をサポートしたりする上で有効な補助食品ですが、下痢の根本的な原因を取り除くものではありません。下痢の原因が不正咬合、毛球症、感染症、ストレスなどにある場合、サプリメントだけで症状が改善することはありません。まずは、牧草中心の食事、清潔な飼育環境、ストレスのない生活、そして定期的な歯と毛球のケアといった、基本的な飼育環境の見直しと改善が不可欠です。サプリメントは、これらの基本的なケアと並行して、獣医さんの指導のもとで活用することで、より効果が期待できます。
Q3. 予防で大事なことは?
A. 牧草中心の食事+清潔環境+ストレス軽減+定期ケアです。
うさぎの健康な消化器を維持し、下痢を予防するために最も大切なのは、日々の飼育管理です。
牧草中心の食事
常に新鮮なイネ科牧草(チモシー)をたっぷりと与え、ペレットやおやつは控えめにすることで、豊富な食物繊維を摂取させ、腸の動きを活発に保ちます。
清潔な飼育環境
ケージを清潔に保ち、細菌の繁殖を防ぎ、感染症のリスクを低減します。
ストレス軽減
うさぎが安心して過ごせる静かで落ち着いた環境を整え、急な環境変化や騒音を避けることで、ストレスによる体調不良を防ぎます。
定期的なケア
定期的なブラッシングで毛球症を予防し、歯の健康状態も日頃からチェックすることで、不正咬合などの早期発見・早期対応につながります。
これらの予防策を日常生活に取り入れることで、愛するうさぎが健康で快適な毎日を送れるようになります。もし、あなたのうさぎが下痢で悩んでいるなら、この記事を参考に、まずはかかりつけの獣医さんに相談してみてください。あなたの小さな家族の健康を、一緒に守っていきましょう。