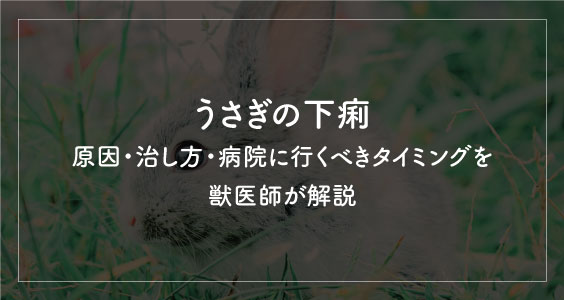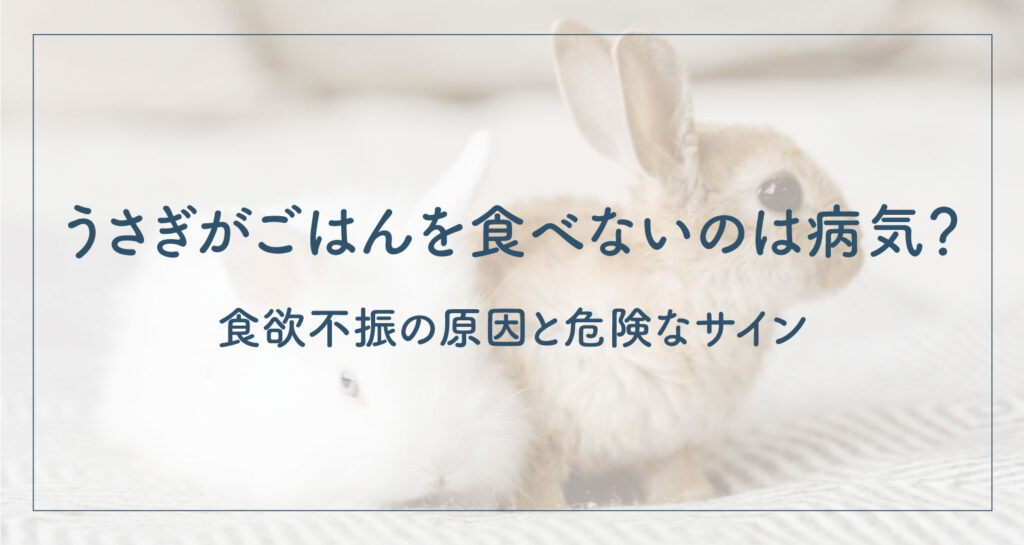
「昨日まで元気にペレットを食べていたのに、今朝になって全く手をつけない」「大好きだった牧草にも見向きもしない」そんな愛うさぎの変化に気づいた時、飼い主として感じる不安は計り知れないものです。うさぎは私たちが思っている以上にデリケートな動物で、体が小さいからこそ数時間から1日食べないだけでも、その後の健康状態に深刻な影響を与える可能性があります。
この記事では、うさぎの食欲不振について詳しく解説し、どのような時に病院に連れて行くべきか、自宅でできる対処法、そして今後の予防方法まで、飼い主として知っておきたい情報を包括的にお伝えします。愛うさぎの健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
うさぎの食欲不振が命に関わる理由
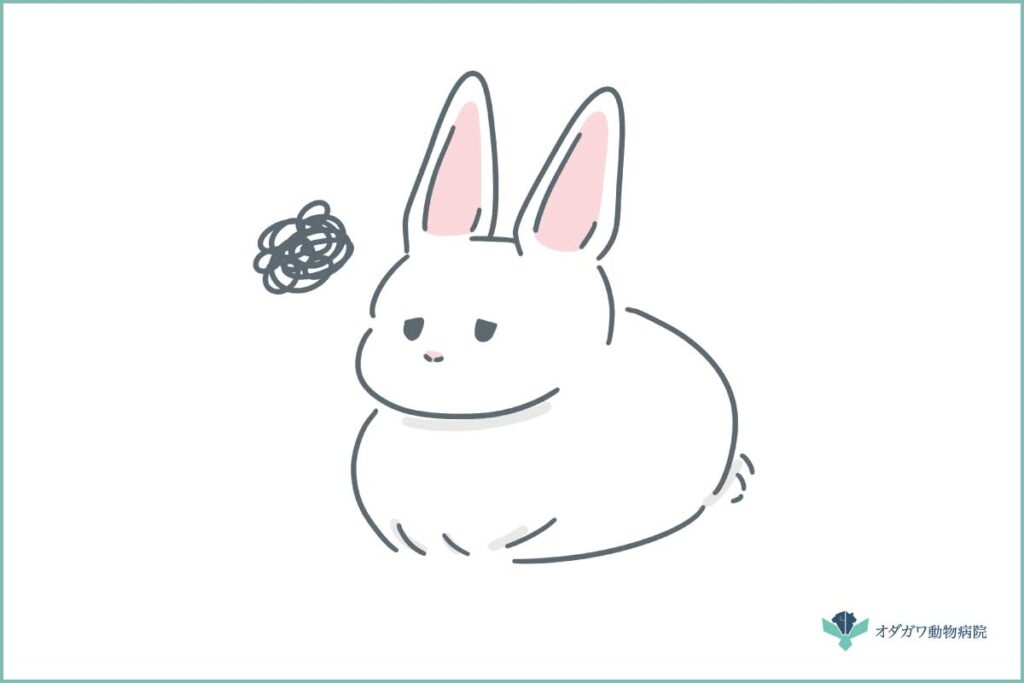
うさぎは「常に胃腸を動かしていないといけない動物」として知られています。これは、うさぎの消化システムが人間や犬猫とは根本的に異なるためです。うさぎの胃腸は食べ物が入ることで動き続けており、この動きが止まると消化管全体の機能が低下してしまいます。
特に注意すべきは、12時間以上食べない状態が続くことです。この状態が継続すると、消化管うっ滞という深刻な病気を引き起こすリスクが高まります。消化管うっ滞は胃や腸の動きが極端に遅くなったり停止したりする状態で、放置すれば命に関わる緊急事態となります。
さらに、うさぎは自分の体調不良を隠す習性があるため、症状が表面化した時にはすでに病気が進行していることが少なくありません。そのため、食欲不振という初期症状を見逃さずに対応することが、愛うさぎの命を守る上で極めて重要なのです。
体重が軽いうさぎにとって、短時間の絶食でも脱水や低血糖を引き起こしやすく、これらの状態は回復を困難にする悪循環を生み出します。だからこそ、「いつものように食べない」という変化に気づいたら、楽観視せずに適切な対応を取ることが求められます。
オダガワ動物病院で実際に診断した症例カルテもご紹介しているので、気になる方はご覧ください↓
【食欲不振のうさぎに隠れた病気】腎臓病と毛球症の症例|診断カルテ
うさぎが食べなくなる主な原因

消化器系のトラブル
うさぎの食欲不振で最も多い原因の一つが消化器系のトラブルです。中でも消化管うっ滞は深刻な状態で、胃や腸の動きが鈍くなることで食べ物の消化・排泄がスムーズに行われなくなります。この病気の一因として毛球症があります。うさぎは毛づくろいの際に飲み込んだ毛を吐き出すことができないため、胃の中で毛玉となって消化を阻害することがあります。
また、腸内環境の乱れも食欲不振を引き起こします。急激なフードの変更や、普段与えていない食べ物を大量に与えた場合、腸内細菌のバランスが崩れて消化不良を起こすことがあります。特に新しいペレットに切り替える際は、段階的に行わず急に変更すると、うさぎの繊細な消化システムに負担をかけてしまいます。
口腔内の問題
うさぎの歯は生涯にわたって伸び続けるという特徴があります。正常であれば牧草やペレットを噛むことで自然に削れていきますが、不正咬合が起こると歯が正しく噛み合わなくなり、過度に伸びた歯が口の中を傷つけたり、物を噛むことが困難になったりします。
口内炎や歯の根っこの異常も食欲不振の原因となります。これらの問題は痛みを伴うため、うさぎは食べることを避けるようになります。特に硬い牧草やペレットを嫌がるようになったら、口腔内に問題がある可能性を疑う必要があります。
歯の問題は見た目だけでは判断が難しく、レントゲン検査によって歯の根っこの状態まで確認する必要があることも多いため、専門的な診断が不可欠です。
感染症や全身疾患
寄生虫感染は意外に多い食欲不振の原因です。特にコクシジウムという寄生虫は、若いうさぎに感染しやすく、下痢や食欲不振を引き起こします。また、回虫やギョウ虫などの腸内寄生虫も消化器症状を伴って食欲を低下させます。
内臓疾患では、腎不全や肝疾患が食欲不振を引き起こすことがあります。これらの病気は初期段階では症状が分かりにくいため、定期的な血液検査による早期発見が重要です。特に高齢のうさぎでは、これらの疾患の発症リスクが高まるため、より注意深い観察が必要となります。
呼吸器感染症や泌尿器感染症なども、全身状態の悪化により食欲不振を引き起こすことがあります。これらの感染症は適切な抗生物質治療により改善することが多いですが、早期の診断と治療開始が回復の鍵となります。
環境・ストレス要因
うさぎは環境の変化に非常に敏感な動物です。引っ越しや模様替え、新しい家族の追加、ペットホテルの利用などは、うさぎにとって大きなストレスとなり、食欲不振を引き起こす可能性があります。
温度管理の不備も深刻な問題です。夏場の高温多湿は熱中症のリスクを高め、冬場の低温は体力を消耗させて食欲を低下させます。うさぎの適温は18-24度程度とされており、この範囲を大きく外れる環境では体調を崩しやすくなります。
騒音や振動、照明の変化なども慢性的なストレスの原因となります。特に工事音や大音量の音楽、頻繁な来客などは、うさぎの神経を過敏にさせて食欲不振を引き起こすことがあります。
その他の要因
老化による食欲低下は避けられない自然現象の一つです。高齢のうさぎでは消化機能が低下し、今まで好んでいた食べ物に対する嗜好性が変化することがあります。また、運動量の減少により基礎代謝が低下し、必要とする食事量が減ることもあります。
フードや牧草の品質や嗜好性の問題も考えられます。いつものペレットが古くなって風味が落ちていたり、牧草が湿気を含んでカビ臭くなっていたりすると、うさぎは食べることを拒否することがあります。特に開封から時間が経ったフードは酸化が進み、うさぎにとって魅力的でなくなることがあります。
薬の副作用や他の疾患の治療中に起こる二次的な食欲不振もあります。これらの場合は獣医師と相談しながら、治療方針を調整していく必要があります。
今すぐ病院へ!緊急受診が必要な症状

愛うさぎに以下のような症状が見られた場合は、様子を見ずにすぐに動物病院を受診することが重要です。
半日以上まったく食べない
半日以上まったく食べない状態は緊急事態と考えてください。うさぎにとって12時間以上の絶食は、消化管うっ滞を引き起こすリスクが急激に高まる危険なサインです。特に普段よく食べるペレットや好物にも全く興味を示さない場合は、深刻な体調不良が疑われます。
水を飲まない
水を飲まない状態も同様に危険です。脱水は短時間で生命に関わる状態となるため、水分摂取量の著しい低下や全く飲まない状態が続く場合は、即座に医療処置が必要です。
便が極端に少ない/出ない
便の状態の異常も重要な指標です。便が極端に少ない、全く出ない、形が異常に小さい、水分が多すぎる下痢便、血便が出るなどの症状は、消化器系の深刻なトラブルを示している可能性があります。
うさぎの下痢についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓
うさぎの下痢|原因・治し方・病院に行くべきタイミングを獣医師が解説
ぐったりして動かない
ぐったりして動かない状態は、うさぎが相当な苦痛を感じているか、重篤な疾患を患っている可能性が高いサインです。普段活発に動き回るうさぎが、隅でじっとしていたり、呼びかけに反応しなかったりする場合は、緊急性が高いと判断してください。
呼吸が浅い、荒い、口呼吸をしている場合も、呼吸器系の問題や痛み、ショック状態を示している可能性があります。また、体温の異常(触った時に異常に熱い、または冷たい)も危険なサインの一つです。
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。どのような症状であっても、普段の愛うさぎと明らかに異なる状態が続く場合は、「もう少し様子を見よう」と考えずに、専門医の診察を受けることをお勧めします。
動物病院での診断の流れ
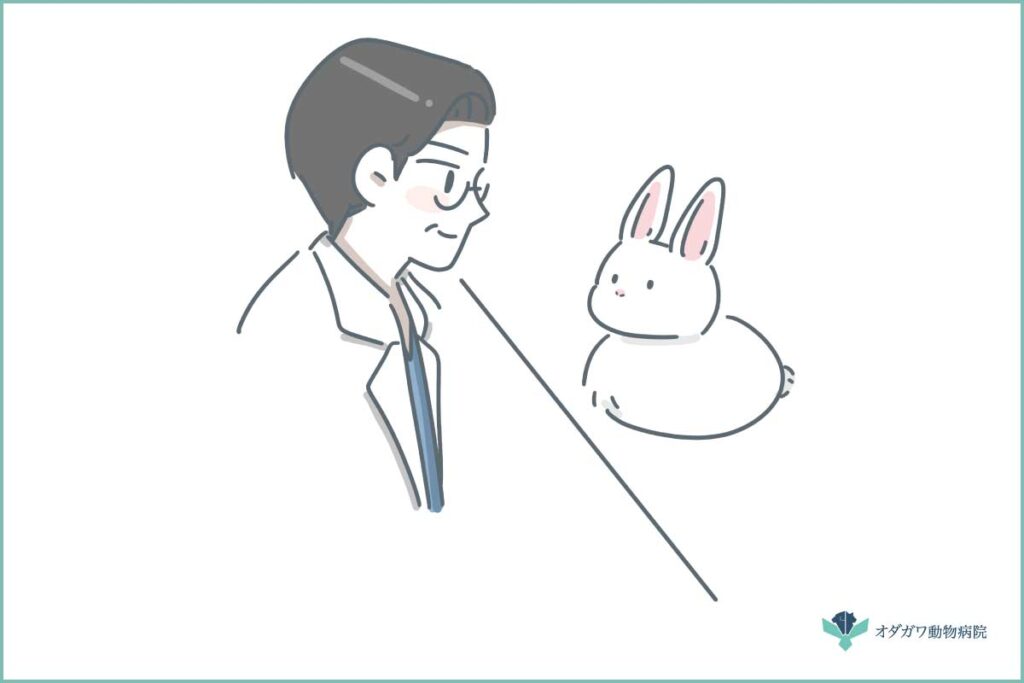
問診
動物病院を受診した際、獣医師はまず詳細な問診を行います。いつから食べなくなったのか、普段何を食べているか、排便の状況、水分摂取量、環境の変化の有無、他に気になる症状はないかなど、愛うさぎの状況を総合的に把握するための質問がされます。この情報は診断の重要な手がかりとなるため、できるだけ詳しく答えることが大切です。
身体検査
次に身体検査が行われます。体重測定により脱水や栄養状態を確認し、体温、心拍数、呼吸数などのバイタルサインをチェックします。口の中の検査では歯の状態や不正咬合の有無、口内炎などの炎症がないかを確認します。腹部の触診では消化管の状態や異常な腫れ、痛みの有無を調べます。
レントゲン
レントゲン検査は多くの場合で実施される重要な検査です。消化管内の食べ物の停滞状況、ガスの蓄積、異物の有無、歯の根っこの状態などを詳しく観察できます。特に消化管うっ滞の診断には欠かせない検査であり、治療方針を決定する上でも重要な情報を提供します。
糞便検査
糞便検査では寄生虫の卵や成虫の確認、腸内細菌のバランス、血液の混入などをチェックします。新鮮な便が採取できれば理想的ですが、採取できない場合は直腸からサンプルを採取することもあります。
血液検査
血液検査は全身疾患の有無を調べるために行われます。肝機能、腎機能、血糖値、電解質バランス、炎症反応などを数値で確認することで、内臓の異常や感染症の有無を判断できます。特に高齢のうさぎや慢性的な症状がある場合は、より詳細な血液検査が必要となることがあります。
これらの検査結果を総合的に評価し、食欲不振の原因を特定して適切な治療方針を決定します。場合によっては追加の検査や専門的な検査が必要となることもありますが、多くの場合は初回の検査で診断に必要な情報を得ることができます。
病院での治療方法と回復への道のり
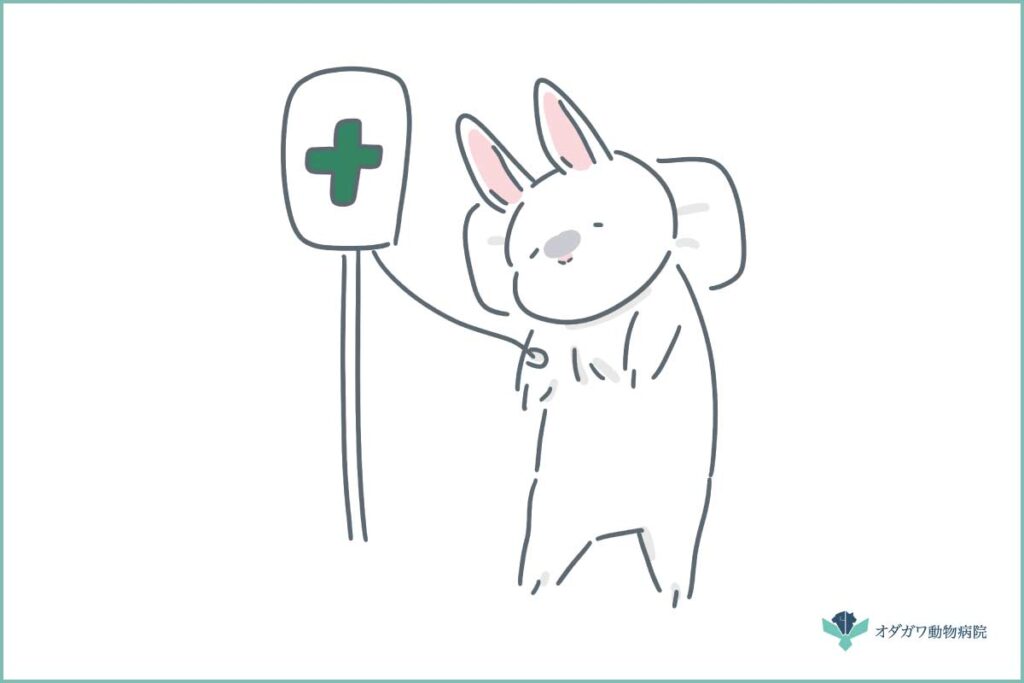
診断結果に基づいて、獣医師は最適な治療方針を決定します。治療の基本は原因に対する根本的な治療と、症状を改善するための対症療法を組み合わせることです。
点滴治療
脱水が認められる場合は、まず点滴による水分・電解質の補正を行います。皮下点滴や静脈点滴により、失われた体液を補充し、循環血液量を正常に戻します。これにより腎機能の改善や毒素の排出促進も期待できます。
薬剤治療
薬剤による治療では、原因に応じて様々な薬が使用されます。消化管うっ滞に対しては消化管運動促進剤が用いられ、胃腸の動きを活発化させます。感染症が疑われる場合は適切な抗生物質が選択され、寄生虫感染では駆虫薬が投与されます。痛みを伴う場合は鎮痛剤により苦痛を和らげ、食欲の回復を促進します。
強制給餌
強制給餌は重篤な食欲不振の場合に必要となる治療法です。Critical Careなどの専用の流動食を使用し、シリンジで直接口の中に与えます。この方法により必要な栄養と水分を確保し、消化管の動きを維持します。強制給餌は技術と注意が必要なため、獣医師や動物看護師による指導のもとで行われます。
外科的治療
外科的治療が必要な場合もあります。不正咬合による歯の問題では歯の削合や抜歯が行われることがあります。消化管内の異物や重篤な消化管うっ滞では、開腹手術により直接的な治療が必要となることもあります。これらの手術は麻酔リスクを伴うため、うさぎの全身状態を十分に評価した上で実施されます。
治療期間は原因や重症度により大きく異なります。軽症の場合は数日から1週間程度で改善することが多いですが、慢性的な疾患や重篤な状態では数週間から数ヶ月の治療が必要となることもあります。定期的な再診により治療効果を評価し、必要に応じて治療方針の調整が行われます。
自宅での応急処置とサポートケア
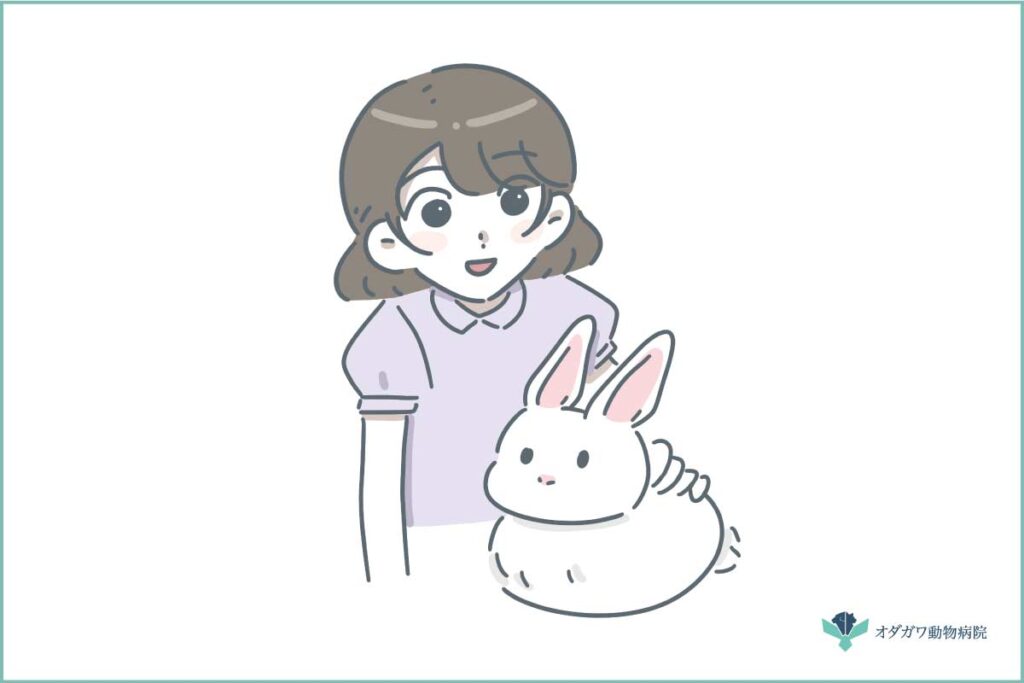
動物病院での治療と並行して、自宅でのケアも愛うさぎの回復には重要な役割を果たします。ただし、これらの対応は病院での治療の代替ではなく、あくまで補助的な役割として理解してください。
牧草を常に新鮮に用意する
牧草の管理は特に重要です。新鮮で質の良いチモシーを常に用意し、古くなったものは速やかに交換します。牧草は消化管の動きを促進し、歯の健康維持にも不可欠です。複数の種類の牧草を用意し、うさぎが好むものを見つけることも効果的です。
水分補給
水分補給は脱水予防の観点から極めて重要です。新鮮な水を常に利用できるようにし、水を飲まない場合はシリンジを使って少量ずつ与えることも可能です。ただし、誤嚥のリスクがあるため、獣医師の指導のもとで行うことが安全です。
部屋の温度管理
環境の温度管理も回復を促進する重要な要素です。室温を18-24度程度に保ち、夏場はエアコンや扇風機で涼しく、冬場はヒーターで暖かく保ちます。急激な温度変化は避け、安定した環境を提供することが大切です。
消化を助けるマッサージ(※獣医師の指導が必要)
消化を助けるマッサージは、獣医師の指導のもとで適切に行えば効果的です。腹部を優しく円を描くようにマッサージすることで、消化管の動きを促進できます。ただし、強く押したり長時間行ったりすると逆効果となる可能性があるため、正しい方法を学ぶことが重要です。
フードの嗜好性を工夫
フードの嗜好性を工夫することも食欲回復に役立ちます。ペレットをぬるま湯でふやかして香りを立たせる、好物の野菜を少量混ぜる、新鮮なハーブを加えるなどの方法があります。ただし、消化に負担をかける食べ物は避け、獣医師と相談しながら行うことが大切です。
静かで安心できる環境作りも重要です。騒音を避け、照明を適度に調整し、他のペットや小さな子供から離れた場所で休めるようにします。ストレスの軽減は免疫力向上と食欲回復に大きく貢献します。
これらのケアを行う際は、うさぎの反応を注意深く観察し、症状の変化があれば速やかに獣医師に報告することが重要です。自宅でのケアは愛情を込めて行うものですが、専門的な判断と治療に勝るものはないことを忘れないでください。
食欲不振の再発を防ぐ予防策

食欲不振の再発を防ぐためには、日常的な健康管理と環境整備が重要です。予防は治療よりもはるかに効果的であり、愛うさぎの生活の質を向上させる最良の方法です。
毎日の糞チェック(量・形・大きさ)
毎日の糞のチェックは最も重要な健康管理の一つです。正常なうさぎの糞は丸くて硬く、濃い茶色をしています。量、形、大きさ、色、においの変化は健康状態の指標となるため、毎日観察する習慣をつけましょう。糞の量が急激に減った、形が小さくなった、柔らかくなった、色が薄くなったなどの変化に気づいたら、早めに対応することができます。
定期的な歯のチェック(不正咬合の早期発見)
定期的な歯のチェックも不可欠です。うさぎの歯は生涯伸び続けるため、不正咬合の兆候を早期に発見することが重要です。食べ方に変化がないか、よだれが増えていないか、顔の形に左右差がないかなどを定期的に確認します。また、年に1-2回は獣医師による専門的な歯科検診を受けることをお勧めします。
高繊維質の牧草を主食に
食事管理では高繊維質の牧草を主食とし、チモシーを中心とした食生活を維持することが基本です。ペレットは体重に応じた適量を与え、おやつは週に数回程度に留めます。新しいフードに変更する際は、1-2週間かけて段階的に切り替え、急激な変化を避けます。
Youtubeではうさぎにおすすめのフードについて解説していますので気になる方はご覧ください。
おすすめフードのご購入はこちら↓

住環境の整備
住環境の整備も予防の重要な要素です。ケージ内を清潔に保ち、適切な広さを確保し、隠れ場所やリラックスできるスペースを用意します。温度と湿度を適正に管理し、直射日光や騒音から守ります。また、誤飲につながる危険物を除去し、安全な環境を維持します。
定期健診
定期健診は少なくとも年1回、高齢のうさぎでは年2回受けることを推奨します。健康な時の数値を把握しておくことで、異常が生じた際の比較ができ、早期発見につながります。血液検査、レントゲン検査、糞便検査などを組み合わせた総合的な健康チェックが理想的です。
ストレス管理も長期的な健康維持には欠かせません。規則正しい生活リズムを保ち、適度な運動機会を提供し、飼い主との良好な関係を築くことで、精神的な安定を図ります。環境の変化がある際は、段階的に慣らしていくことが大切です。
日常の観察ポイントとチェックリスト

愛うさぎの健康状態を把握するためには、系統的な観察が重要です。以下の項目を日常的にチェックすることで、健康状態の変化を早期に発見できます。
1日の食べる量
食事に関する観察では、1日の食べる量を把握することが基本です。ペレットは何グラム程度食べているか、牧草はどの程度消費しているか、好みの変化はないかを記録します。食べ方にも注目し、いつもより時間がかかる、片側だけで噛んでいる、食べこぼしが多いなどの変化があれば、口腔内の問題を疑う必要があります。
飲水量
飲水量の観察も重要です。水のボトルやお皿の水の減り具合から、1日の飲水量を推定します。急激に増加した場合は腎臓病や糖尿病、急激に減少した場合は食欲不振や口腔内の問題の可能性があります。
排便の状態
排便の観察では、1日の糞の数、大きさ、形、硬さ、色を確認します。正常なうさぎは1日に150-300個程度の糞をします。また、盲腸糞という柔らかい糞を食べる行動も正常な生理現象なので、これが見られなくなった場合は注意が必要です。
元気・行動の様子
元気や行動の様子も重要な指標です。普段の活動レベル、遊びに対する反応、飼い主に対する反応、休息時の姿勢などを観察します。いつもより動きが鈍い、隠れて出てこない、呼びかけに反応しないなどの変化は、体調不良のサインかもしれません。
体重変化
体重変化の把握には定期的な計測が必要です。週に1回程度、同じ時間帯に体重を測定し、記録をつけます。1週間で体重の5%以上の変化があった場合は、何らかの健康問題の可能性があります。
また、外見的な変化の観察では、毛づやの状態、目ヤニや鼻水の有無、姿勢の変化、呼吸の様子などをチェックします。毛がボサボサになった、目が濁ってきた、背中を丸めてじっとしているなどの変化は、健康状態の悪化を示している可能性があります。
これらの観察項目を記録することで、獣医師への相談時により具体的で有用な情報を提供できます。日記形式で記録するか、スマートフォンのアプリを活用するなど、継続しやすい方法を選択することが大切です。
まとめ:愛うさぎの健康を守るために
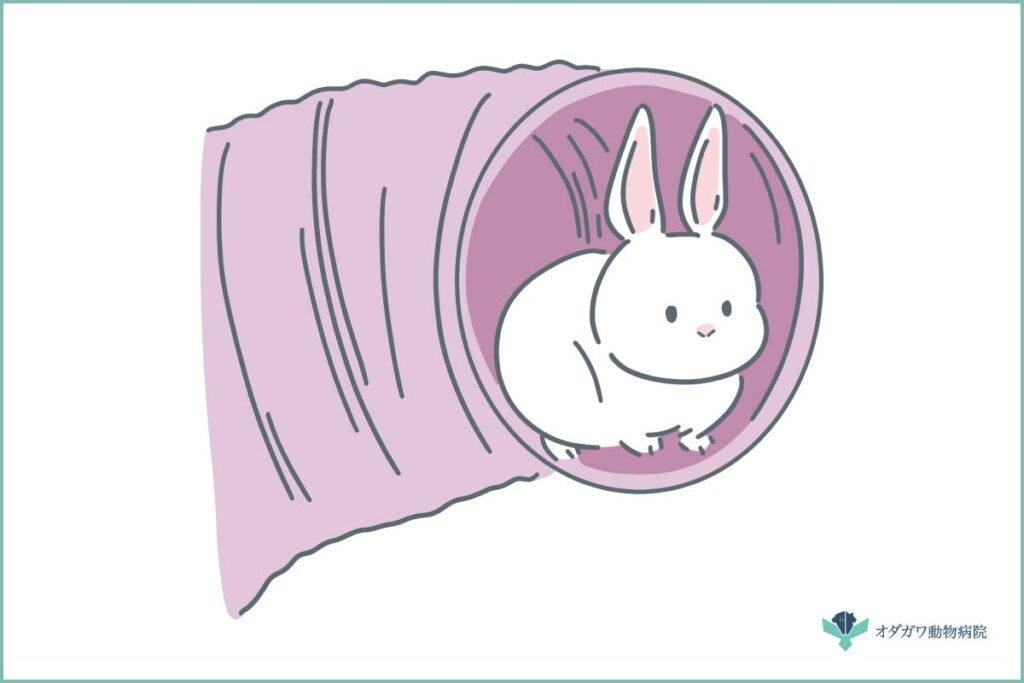
うさぎの食欲不振は決して軽視できない症状です。「食欲不振はよくあること」と油断せず、愛うさぎからの健康に関するSOSサインとして真剣に受け止めることが重要です。12時間以上食べない状態が続く場合や、他の症状を伴う場合は、迷わず早めに動物病院を受診してください。
早期発見・早期治療が愛うさぎの健康を守る最も確実な方法です。日頃から愛うさぎの様子を注意深く観察し、わずかな変化も見逃さないようにしましょう。食事量、排便状況、行動の変化などを記録し、異常を感じたら獣医師に相談することで、深刻な病気を未然に防ぐことができます。
自宅での適切なケアと予防管理も同様に重要です。質の良い牧草の提供、適切な環境管理、ストレスの軽減、定期健診の受診などを通じて、病気になりにくい環境を整えることができます。これらの取り組みは、愛うさぎの生活の質を向上させ、長く健康な生活をサポートします。
最も大切なことは、愛うさぎとの日々のコミュニケーションを大切にし、その子特有の性格や習慣を理解することです。普段の様子を知っているからこそ、わずかな変化に気づくことができ、適切なタイミングで対応することが可能になります。
愛うさぎは家族の大切な一員です。その小さな命を守るために、知識を身につけ、日々の観察を怠らず、必要な時には迷わず専門医の助けを求めることで、共により良い生活を築いていくことができるでしょう。