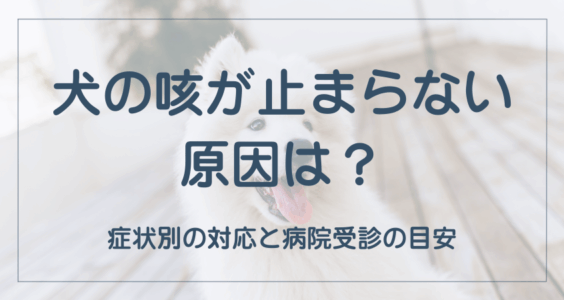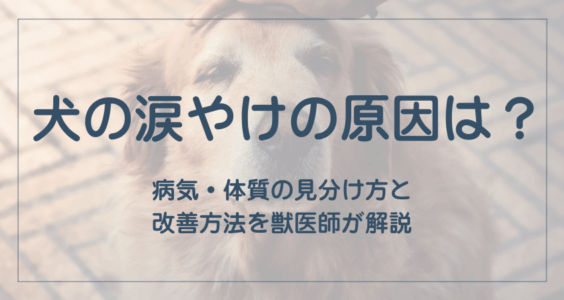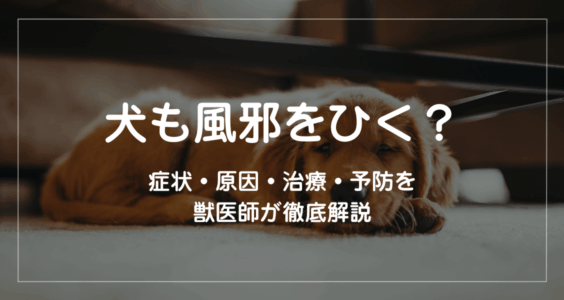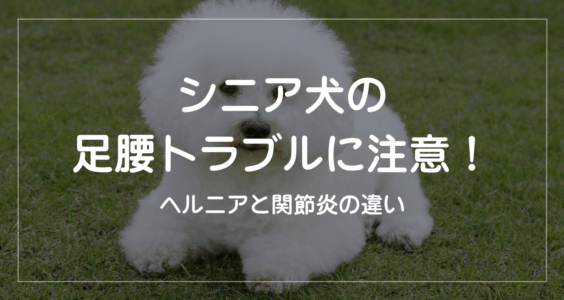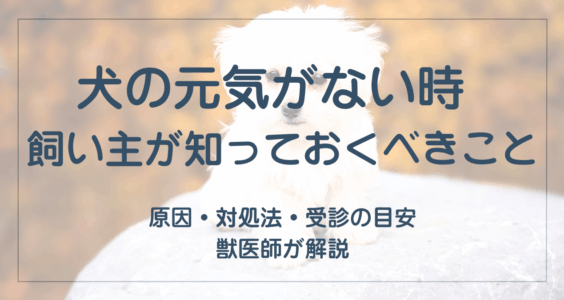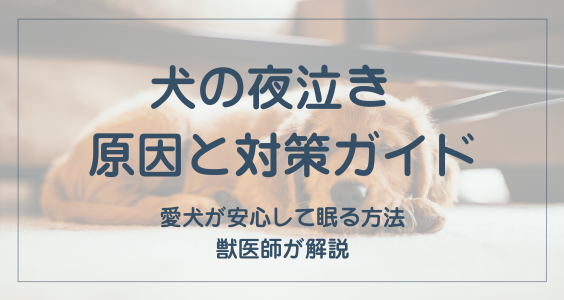愛犬が突然吐いてしまったとき、飼い主さんは慌ててしまうものです。「すぐに病院に連れて行くべき?」「様子を見ても大丈夫?」といった不安を抱える方も多いでしょう。
犬の嘔吐は、軽い胃の不調から重篤な疾患まで、さまざまな原因で起こります。適切な判断と対処を行うためには、犬の嘔吐について正しい知識を持つことが大切です。
この記事では、犬が吐く原因から受診の目安、家庭での観察ポイント、動物病院での検査・治療まで、飼い主さんが知っておくべき情報を詳しく解説します。愛犬の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
犬はなぜ吐きやすい?(嘔吐と吐出の違い)
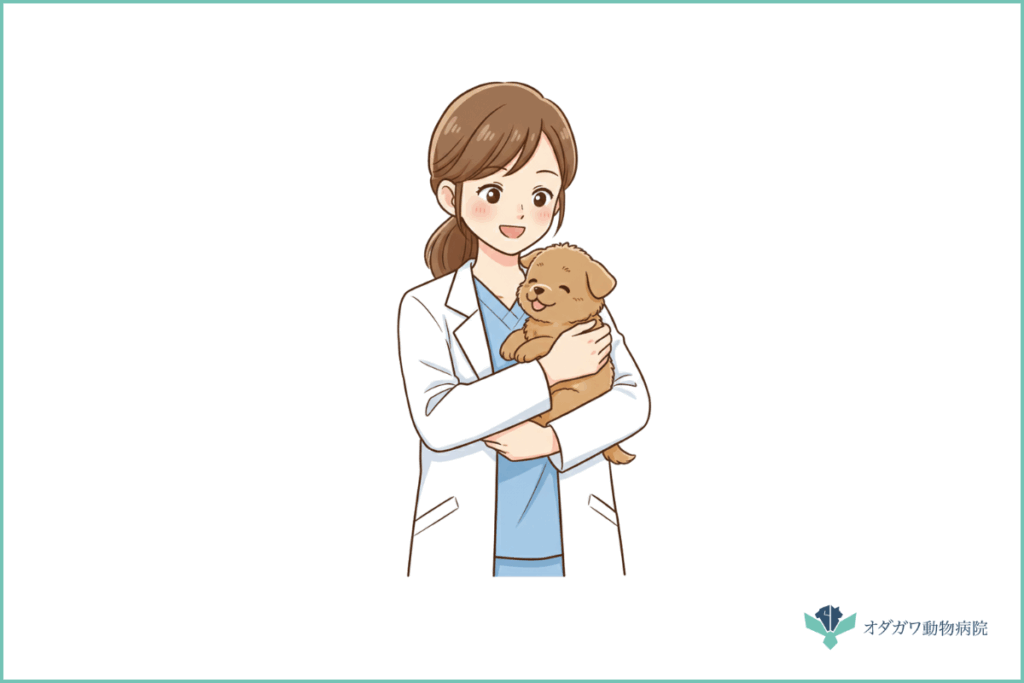
犬は人間より吐きやすい動物
実は、犬は人間と比べて嘔吐しやすい動物です。これは犬の生理的な特徴によるもので、以下のような理由があります。
犬の胃は人間よりも敏感で、ちょっとした刺激でも嘔吐反射が起こりやすくなっています。野生時代の犬の祖先は、危険なものを食べてしまった際に素早く体外に排出する必要があったため、この機能が発達したと考えられています。
また、犬は早食いをする習性があり、十分に咀嚼せずに飲み込んでしまうことが多いため、消化不良を起こしやすいのも特徴です。さらに、犬は好奇心旺盛で、散歩中に草や石、ゴミなど、本来食べるべきでないものを口にしてしまうことがあります。
このような理由から、健康な犬でも時々嘔吐することがあるのは自然なことです。しかし、だからといって全ての嘔吐を軽視してはいけません。中には重篤な疾患のサインである場合もあるため、適切な判断が重要になります。
嘔吐と吐出の違いを理解しよう
犬が食べたものを戻す現象には、「嘔吐」と「吐出」の2つがあります。この違いを理解することは、原因を探る上で非常に重要です。
嘔吐(おうと)は、胃の内容物が食道を通って口から出されることです。嘔吐の前には、犬は不快そうな表情を見せ、よだれを垂らしたり、舌なめずりをしたりします。そして、お腹を上下に動かしながら「えづく」ような動作を繰り返した後に、胃液と混じった内容物を吐き出します。
一方、吐出(としゅつ)は、食べたものが胃に達する前に、食道から戻ってくることです。食事直後に起こることが多く、嘔吐のような前兆はほとんどありません。吐出されたものは、胃液と混じっていない、食べたままの形をしていることが特徴です。
吐出は主に食道の問題(食道拡張症、食道炎など)や、食べ方の問題(早食い、一度に大量摂取)で起こります。嘔吐は胃や腸、その他の臓器の問題で起こることが多いため、この区別ができると獣医師への説明がより正確になります。
症状別の原因(白い泡/黄色/血/食後すぐ 等)
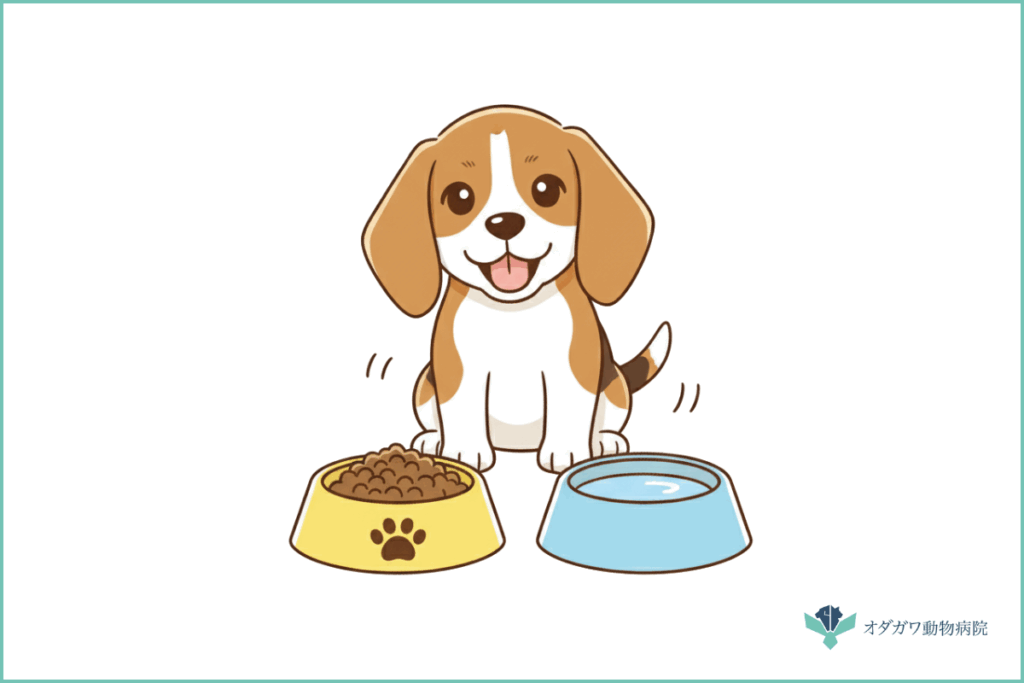
犬の嘔吐には、急性のものと慢性のものがあります。原因を正しく理解することで、適切な対処と受診のタイミングを判断できるようになります。
急性の原因(食べ過ぎ・異物誤飲・食事の急変)
急性の嘔吐は、短期間で突然起こる嘔吐のことです。多くの場合、明確なきっかけがあります。
食べ過ぎによる嘔吐
犬は満腹感を感じにくい動物で、与えられた分だけ食べてしまう傾向があります。普段より多く食べた後や、おやつを大量に与えた後に嘔吐することがあります。この場合、吐いた後はケロッとしていることが多く、食欲や元気も普段通りであることがほとんどです。
異物誤飲による嘔吐
散歩中に拾い食いをしたり、家の中でおもちゃの破片やボタンなどを飲み込んでしまったりした場合の嘔吐です。異物が胃を刺激することで嘔吐が起こります。小さな異物であれば嘔吐と一緒に出てくることもありますが、大きな異物の場合は腸閉塞を起こす危険性があります。
食事の急変による嘔吐
フードを急に変更したり、普段と違う食べ物を与えたりした場合に起こる嘔吐です。犬の消化器は急激な食事の変化に対応しにくいため、新しい食べ物に慣れるまでの間に嘔吐することがあります。
ストレスによる嘔吐
環境の変化、長時間の留守番、来客など、犬にとってのストレス要因があった後に嘔吐することがあります。特に神経質な性格の犬に多く見られます。
車酔いによる嘔吐
車での移動中や移動後に起こる嘔吐です。犬も人間と同様に車酔いをすることがあり、よだれを垂らしたり、ぐったりしたりした後に嘔吐します。
慢性的な原因(消化器疾患、腎不全、肝疾患、膵炎)
慢性的な嘔吐は、数週間から数ヶ月にわたって断続的に続く嘔吐のことです。多くの場合、内臓の疾患が原因となります。
消化器疾患による嘔吐
胃炎、胃潰瘍、腸炎、炎症性腸疾患などの消化器系の病気では、慢性的な嘔吐が見られます。これらの疾患では、嘔吐以外にも下痢、食欲不振、体重減少などの症状が併発することが多いです。
胃捻転は大型犬に多い緊急疾患で、胃がねじれることで血流が遮断され、急激に悪化します。この場合は、お腹が膨らみ、よだれを垂らし、嘔吐しようとしても何も出ないという特徴的な症状が見られます。
腎不全による嘔吐
腎臓の機能が低下すると、体内に老廃物が蓄積し、これが嘔吐の原因となります。腎不全では、嘔吐の他に多飲多尿(水をたくさん飲み、おしっこもたくさんする)、食欲不振、体重減少、口臭などの症状も見られます。特に高齢犬では注意が必要な疾患です。
肝疾患による嘔吐
肝炎、肝硬変、肝腫瘍などの肝臓の病気では、肝機能の低下により毒素が体内に蓄積し、嘔吐を引き起こします。肝疾患では、黄疸(白目や歯茎が黄色くなる)、腹水(お腹に水が溜まる)、元気消失などの症状も併発することがあります。
膵炎による嘔吐
膵臓の炎症である膵炎は、激しい腹痛と嘔吐を引き起こします。急性膵炎では、前足を伸ばしてお尻を上げる「祈りのポーズ」を取ることがあります。慢性膵炎では、断続的な嘔吐と下痢が続きます。高脂肪の食事が引き金になることが多い疾患です。
内分泌疾患による嘔吐
糖尿病、副腎皮質機能低下症(アジソン病)、甲状腺機能低下症などのホルモンの病気でも嘔吐が起こることがあります。これらの疾患では、嘔吐以外にも様々な全身症状が現れます。
吐く内容物でわかるサイン
吐いた物の色や性状を観察することで、原因や重症度をある程度判断することができます。ただし、これらはあくまで参考程度に留め、心配な場合は必ず獣医師に相談してください。
白い泡を吐く場合
白い泡状の嘔吐物は、主に胃液や胃酸です。空腹時に胃酸が分泌されすぎて嘔吐することがあります。朝の散歩前や食事前に白い泡を吐く場合は、空腹による胃酸過多が原因の可能性があります。
この場合、食事の回数を増やしたり、就寝前に少量の食事を与えたりすることで改善することがあります。ただし、頻繁に続く場合は胃炎などの可能性もあるため、獣医師に相談しましょう。
黄色の液体を吐く場合
黄色い液体は胆汁です。胆汁は肝臓で作られ、胆嚢に貯蔵された後、十二指腸に分泌されて脂肪の消化を助けます。空腹が長時間続いた時や、逆流性の消化器疾患がある場合に胆汁を吐くことがあります。
朝一番や食事前に黄色い液体を吐く場合は、空腹による胆汁の逆流が考えられます。しかし、頻繁に続く場合や、他の症状(食欲不振、元気消失など)がある場合は、消化器疾患や肝疾患の可能性があるため注意が必要です。
血が混じる場合
嘔吐物に血が混じっている場合は、消化管のどこかで出血していることを示す重要なサインです。血の色によって出血部位をある程度推測できます。
鮮やかな赤い血の場合は、口腔、食道、胃の上部からの出血が考えられます。一方、コーヒーかすのような黒っぽい血(吐血)の場合は、胃や十二指腸からの出血で、胃酸により血液が変色したものです。
いずれの場合も、消化管出血は緊急性の高い症状です。胃潰瘍、胃がん、異物による消化管の損傷、血液凝固異常などが原因として考えられます。血が混じった嘔吐を確認した場合は、速やかに動物病院を受診してください。
食べ物がそのまま出てくる場合
食べたものが消化されずにそのまま出てくる場合は、前述の「吐出」の可能性があります。食道の問題や早食いが原因として考えられます。また、胃の動きが悪くなる疾患でも同様の症状が見られることがあります。
緑色の嘔吐物
緑色の嘔吐物は、胆汁が濃縮された状態や、腸液が逆流した場合に見られます。腸閉塞などの深刻な消化器疾患の可能性があるため、注意が必要です。
受診の目安(何度も吐く・血・ぐったり・腹部膨満 ほか)

犬が嘔吐した場合、受診が必要かどうかの判断は飼い主さんにとって難しいものです。以下のガイドラインを参考に、適切な判断を行いましょう。
経過観察でも良い場合
一度だけの嘔吐で、以下の条件が揃っている場合は、しばらく様子を見ても良いでしょう。
・嘔吐は1回だけで、その後は吐いていない
・食欲がある、または普段通りの食欲がある
・元気があり、普段と変わらない行動をしている
・排便・排尿に異常がない
・発熱していない(耳の内側や鼻が冷たく湿っている)
・嘔吐物に血が混じっていない
このような場合は、12〜24時間程度様子を見ても構いません。ただし、その間も愛犬の様子をよく観察し、症状が悪化した場合はすぐに受診してください。
すぐに受診が必要な場合
以下の症状が見られる場合は、緊急性が高いため、速やかに動物病院を受診してください。
何度も嘔吐を繰り返す
短時間で複数回嘔吐する場合や、1日に何度も嘔吐する場合は、深刻な疾患の可能性があります。脱水症状を起こすリスクも高いため、早急な対応が必要です。
嘔吐物に血が混じっている
鮮血でも黒い血でも、血液が混じっている場合は消化管出血の可能性があり、緊急性の高い症状です。
ぐったりして元気がない
嘔吐と同時に元気がなくなり、普段の活発さが見られない場合は、全身状態の悪化を示している可能性があります。
下痢も併発している
嘔吐と下痢が同時に起こると、脱水症状が急激に進行する危険性があります。特に子犬や高齢犬では要注意です。
お腹を痛がっている
腹痛のサインには、お腹を丸めて寝る、触られることを嫌がる、前述の「祈りのポーズ」を取るなどがあります。
呼吸が荒い、発熱している
呼吸困難や発熱は、感染症や重篤な疾患を示す可能性があります。
何も飲食できない
水も飲めない状態は脱水症状のリスクが高く、緊急性があります。
小型犬・子犬・高齢犬は要注意
小型犬、子犬、高齢犬は、成犬と比べて嘔吐による影響を受けやすいため、より注意深い観察が必要です。
小型犬の場合
体重が軽い小型犬は、少量の水分や栄養の損失でも体への影響が大きくなります。また、低血糖症を起こしやすいため、食事を摂取できない状態が続くと危険です。
子犬の場合
生後6ヶ月未満の子犬は、免疫システムが未発達で、脱水症状や低血糖症を起こしやすいです。また、誤飲・誤食をしやすい年齢でもあるため、嘔吐の原因として異物誤飲を疑う必要があります。
高齢犬の場合
7歳以上の高齢犬は、腎不全、肝疾患、腫瘍などの慢性疾患を患っている可能性が高くなります。また、体力や回復力が若い犬より劣るため、嘔吐による体調悪化が深刻になりやすいです。
これらの犬種・年齢の犬が嘔吐した場合は、軽症に見えても早めに獣医師に相談することをお勧めします。
家庭でできる応急対応と記録の付け方
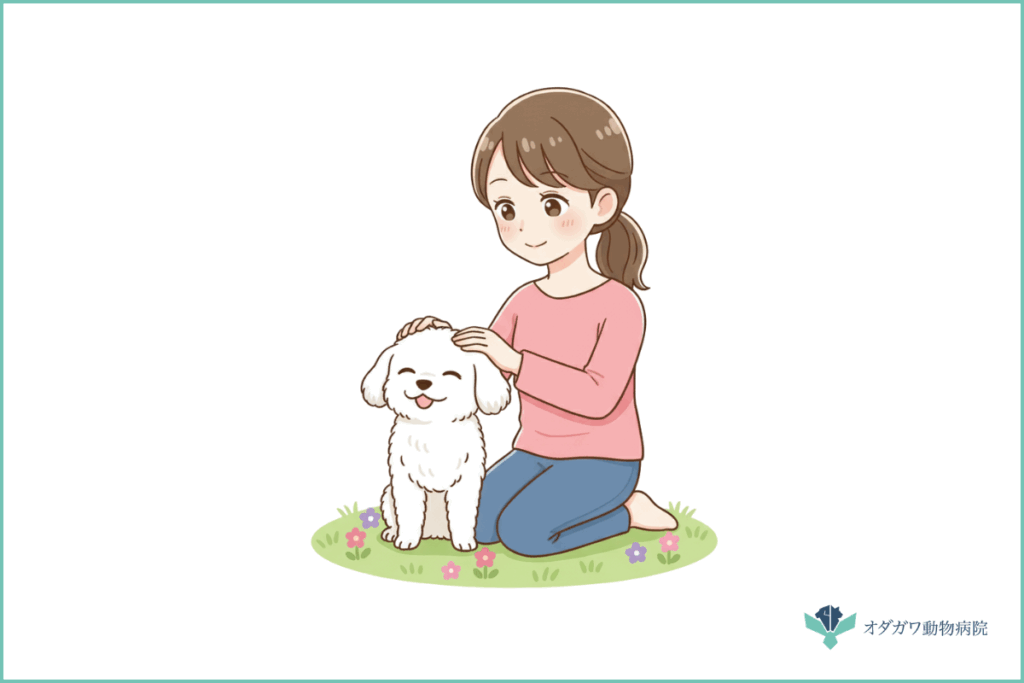
愛犬が嘔吐した際、飼い主さんが家庭でできることがいくつかあります。適切な観察と記録は、獣医師の診断に大いに役立ちます。
吐いた物は捨てずに保管を
嘔吐物の観察は、診断において非常に重要な情報となります。可能な限り、吐いた物は捨てずに保管し、動物病院へ持参しましょう。
保管方法
・密閉できる容器やビニール袋に入れる
・写真を撮って記録しておく
・冷蔵庫で保管し、なるべく早く病院へ持参する
観察ポイント
・色(白い泡、黄色い液体、血液の有無など)
・性状(液体、固形物、泡状など)
・量(大さじ1杯程度、コップ1杯程度など)
・臭い(酸っぱい、腐敗臭など)
・未消化の食べ物や異物の有無
これらの情報は、獣医師が原因を特定する上で貴重な手がかりとなります。恥ずかしがらずに、詳しく伝えるようにしましょう。
詳細な記録をつけよう
嘔吐の状況を詳しく記録することで、獣医師はより正確な診断を行うことができます。以下の項目を記録しておきましょう。
嘔吐の記録
・日時(何月何日の何時頃)
・回数(1日に何回吐いたか)
・食事との関係(食前、食後何時間後など)
・嘔吐前の様子(前兆はあったか、どんな行動をしていたか)
食事の記録
・最後に食べた時間と内容
・普段と違うものを食べたか
・食欲の変化(いつもの何割程度食べるか)
・水分摂取の状況
その他の症状
・排便の状況(下痢、便秘、血便の有無)
・排尿の状況(色、回数、量の変化)
・元気度(普段の何割程度の活発さか)
・発熱の有無 その他気になる症状
環境や状況の変化
・フードの変更
・散歩コースの変化
・来客や引っ越しなどのストレス要因
・誤飲・誤食の可能性
絶食・絶水の注意点
犬が嘔吐した際、「胃を休ませるため」として絶食・絶水を行う飼い主さんがいますが、これには注意が必要です。
短時間の絶食は有効な場合もある
軽い胃腸炎や食べ過ぎによる嘔吐の場合、12〜24時間程度の絶食が胃腸の回復に役立つことがあります。しかし、これは獣医師の指導のもとで行うべきです。
絶水は避けるべき
水分補給は生命維持に不可欠です。嘔吐により体内の水分が失われているため、完全な絶水は脱水症状を悪化させる危険があります。少量ずつでも水分摂取を促しましょう。
独断での長時間絶食は危険
特に小型犬、子犬、高齢犬では、長時間の絶食により低血糖症を起こす危険があります。また、糖尿病の犬では、食事を抜くことでインスリンのバランスが崩れる可能性があります。
適切な対応方法
嘔吐後は以下のような対応を心がけましょう
・水は少量ずつ頻繁に与える
・一度に大量の水を飲ませない(再び嘔吐する可能性があるため)
・食事は2〜3時間様子を見てから、消化の良いものを少量ずつ与える
・24時間以上食事を摂取できない場合は必ず受診する
応急処置として行えること
家庭でできる応急処置には限界がありますが、以下の点に注意することで愛犬の状態悪化を防ぐことができます。
安静にする
嘔吐後は無理に運動させず、静かな場所で休ませましょう。興奮や運動は嘔吐を誘発する可能性があります。
温度管理
体温調節ができるよう、適切な室温を保ちます。特に子犬や高齢犬では体温管理が重要です。
経口補水液の活用
犬用の経口補水液がある場合は、少量ずつ与えることで脱水予防に役立ちます。人間用のスポーツドリンクは糖分や塩分が多すぎるため避けましょう。
口の中のチェック
異物誤飲が疑われる場合は、口の中を確認します。ただし、無理に取り出そうとすると、より深く押し込んでしまう危険があるため、見えている部分のみにとどめましょう。
動物病院で行う検査・治療の流れ
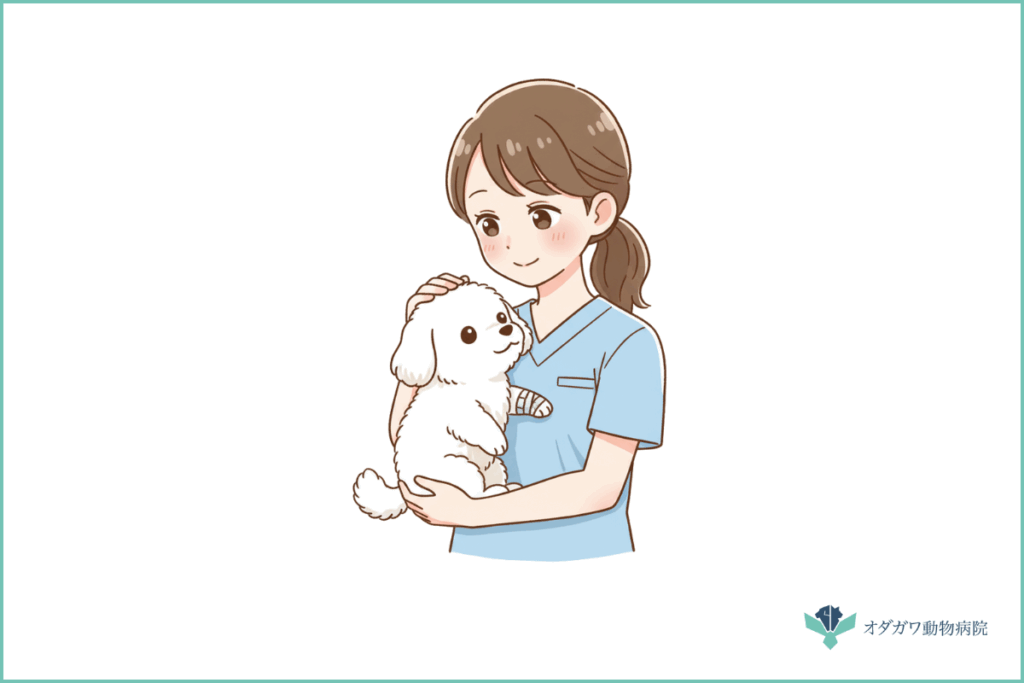
動物病院では、嘔吐の原因を特定し、適切な治療を行うために様々な検査が実施されます。
診断のための検査
問診
獣医師は飼い主さんからの詳しい情報収集を行います。前述した記録があると、より正確な診断につながります。
身体検査
体温、心拍数、呼吸数の測定、腹部の触診、口腔内の確認、リンパ節の触診などを行い、全身状態を評価します。
血液検査
血液検査では、以下の項目を調べます
・一般血液検査:貧血、炎症、感染症の有無
・生化学検査:肝機能、腎機能、電解質バランス、血糖値など
・特殊検査:膵炎マーカー、甲状腺ホルモンなど
X線検査(レントゲン)
腹部X線検査により、異物誤飲、腸閉塞、胃捻転、腹水の有無などを確認できます。バリウム造影検査を行う場合もあります。
超音波検査
腹部臓器の詳細な構造や動き、腫瘍の有無、胆嚢や膵臓の状態などをリアルタイムで観察できます。
便検査
寄生虫、細菌、炎症細胞の有無を調べます。感染性胃腸炎の診断に有用です。
尿検査
腎機能の評価や、全身状態の把握に役立ちます。
内視鏡検査
必要に応じて、胃カメラによる直接観察を行います。胃炎、潰瘍、腫瘍の診断や、異物の除去にも使用されます。
治療方法
嘔吐の治療は、原因に応じて様々な方法が選択されます。
対症療法
・制吐剤:嘔吐を抑える薬物治療
・輸液療法:脱水症状の改善と電解質バランスの調整
・胃粘膜保護剤:胃の粘膜を保護し、炎症を抑制
・消化管運動改善剤:胃腸の動きを正常化
原因に対する治療
・異物除去:内視鏡的除去または外科手術
・感染症治療:抗生物質、抗ウイルス薬
・食事療法:消化器疾患用療法食への変更
・手術:腫瘍摘出、胃捻転整復など
栄養管理
長期間食事摂取ができない場合は、静脈栄養や経鼻カテーテルによる栄養補給を行います。
慢性疾患の管理
腎不全、肝疾患、内分泌疾患などが原因の場合は、基礎疾患の治療と長期管理が必要になります。
獣医師による総合判断の重要性
犬の嘔吐は、同じ症状でも原因や重症度が大きく異なります。インターネットや書籍の情報だけでは、正確な診断と適切な治療を行うことはできません。
獣医師は、問診、身体検査、各種検査結果を総合的に評価し、個々の犬に最適な治療方針を決定します。また、犬の年齢、犬種、既往歴、現在の健康状態なども考慮した包括的な判断を行います。
特に以下のような場合は、専門的な判断が不可欠です
・症状が複雑で、複数の原因が疑われる場合
・慢性的な嘔吐で、根本的な治療が必要な場合
・内科的治療で改善しない場合
・手術適応の判断が必要な場合
・長期的な管理方針の策定が必要な場合
飼い主さんは、愛犬の日常の様子を最もよく知る存在として、獣医師に正確な情報を提供し、治療方針について十分に相談することが大切です。
予防と再発予防(食事管理・誤飲対策)
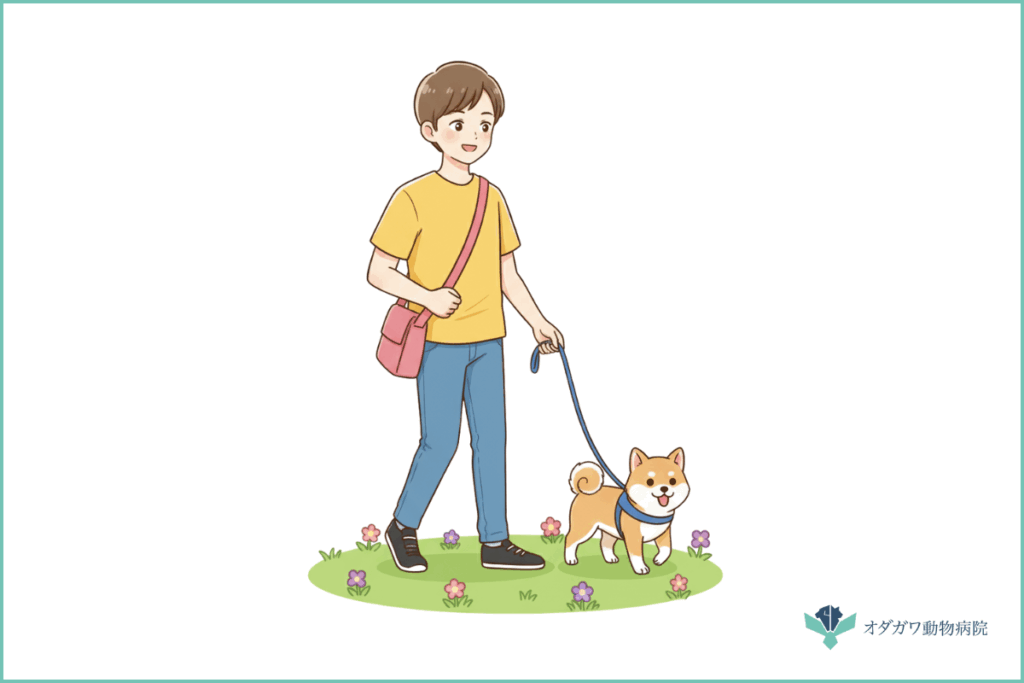
愛犬が嘔吐した際の対応について、重要なポイントをまとめます。
嘔吐は軽い場合もあるが、危険なサインのこともある
犬の嘔吐は、軽い胃の不調から生命に関わる重篤な疾患まで、実に様々な原因で起こります。食べ過ぎや車酔いのような一時的なものであれば大きな心配はありませんが、内臓疾患や異物誤飲による嘔吐では迅速な対応が必要になります。
大切なのは、嘔吐を「よくあること」として軽視せず、愛犬の全体的な状態をしっかりと観察することです。同じ嘔吐でも、その前後の様子、嘔吐物の性状、他の症状の有無によって緊急度は大きく変わります。
「何度も吐く・血が混じる・元気がない」→ すぐ受診が基本
以下の症状が見られた場合は、迷わずに動物病院を受診してください
・何度も嘔吐を繰り返す:短時間で複数回、または1日に何度も嘔吐する場合は、深刻な疾患や脱水症状のリスクが高まります
・嘔吐物に血が混じる:鮮血でも黒い血でも、血液が混じっている場合は消化管出血を示す緊急症状です
・元気がなくぐったりしている:普段の活発さが見られず、反応が鈍い場合は全身状態の悪化を示しています
・下痢も併発している:嘔吐と下痢が同時に起こると脱水が急激に進行します
・何も飲食できない:水も飲めない状態は緊急性が高い症状です
これらの症状は、放置すると生命に危険が及ぶ可能性があるため、夜間や休日でも緊急対応してくれる動物病院を受診することをお勧めします。
飼い主が冷静に観察し、早めに動物病院に相談することが最も大切
愛犬の健康を守るために、飼い主さんには以下の点を心がけていただきたいと思います。
日頃からの観察が重要:普段の愛犬の様子をよく把握しておくことで、いざという時の変化に気づきやすくなります。食事量、元気度、排便・排尿の状況など、日常的な健康チェックを習慣化しましょう。
冷静な判断と対応:嘔吐を発見しても慌てず、まずは愛犬の全体的な状態を確認しましょう。呼吸、意識状態、体温などをチェックし、緊急性の有無を判断します。
詳細な記録の重要性:嘔吐の時間、回数、性状、前後の様子などを詳しく記録することで、獣医師の診断に大きく貢献できます。スマートフォンのメモ機能や写真撮影も活用しましょう。
迷ったら相談する:「受診すべきかわからない」という場合は、遠慮せずに動物病院に電話で相談してみてください。多くの動物病院では、電話での相談に応じてくれます。症状を説明することで、緊急性の判断や適切なアドバイスを受けることができます。
信頼できるかかりつけ医を持つ:普段から愛犬の健康管理をお願いできる、信頼できる動物病院を見つけておくことが大切です。定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見にもつながります。
夜間・救急対応の確認:夜間や休日に緊急事態が発生した場合に備えて、24時間対応の動物病院や救急動物病院の場所と連絡先を事前に調べておきましょう。
予防できることもある
嘔吐の完全な予防は困難ですが、以下の点に注意することで、嘔吐のリスクを減らすことができます。
食事管理
・適切な量の食事を規則正しく与える
・早食い防止用の食器を使用する
・フードの急激な変更は避け、徐々に切り替える
・人間の食べ物や高脂肪食は与えない
環境管理
・誤飲・誤食の原因となる小さな物は犬の手の届かない場所に保管する
・散歩中の拾い食い防止のため、基本的なしつけを身につける
・ストレス要因を可能な限り減らす
定期的な健康管理
・年1〜2回の定期健康診断を受ける
・予防接種、寄生虫予防を適切に行う
・高齢犬では血液検査の頻度を増やす
最後に
犬の嘔吐は、軽いものから重篤なものまで幅広い原因があります。しかし、飼い主さんが適切な知識を持ち、冷静に対応することで、多くの場合適切な処置を受けることができます。
何より大切なのは、愛犬の日頃の様子をよく観察し、変化に敏感に気づくことです。そして、迷った時は遠慮せずに専門家である獣医師に相談することです。
愛犬が健康で長生きできるよう、飼い主さんと獣医師が協力して、最適な健康管理を行っていきましょう。嘔吐という症状を正しく理解し、適切に対応することで、大切な家族である愛犬を守ることができるのです。
この記事が、愛犬の健康管理の一助となれば幸いです。何か心配なことがありましたら、お気軽にかかりつけの動物病院にご相談ください。愛犬との幸せな生活のために、正しい知識を持って日々のケアを行っていきましょう。