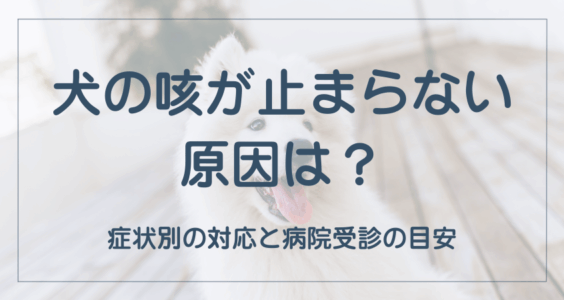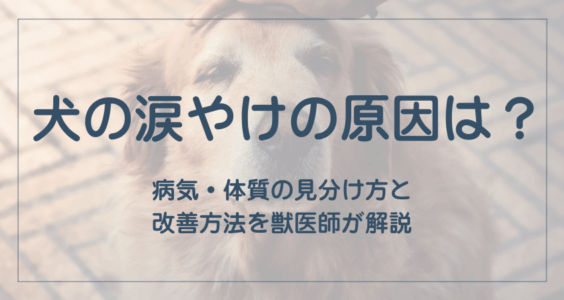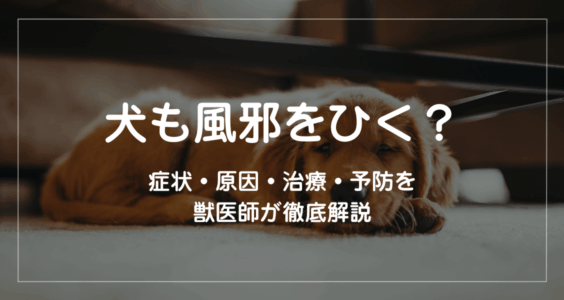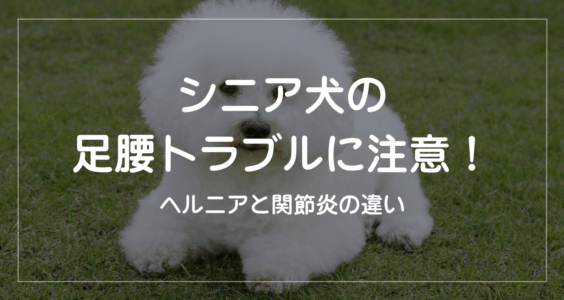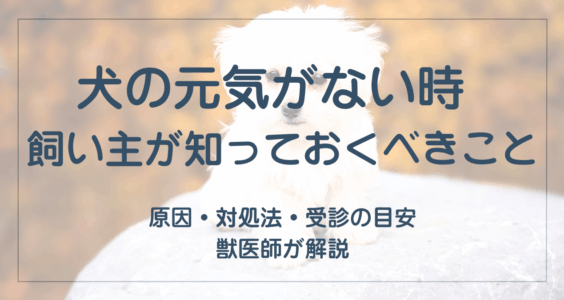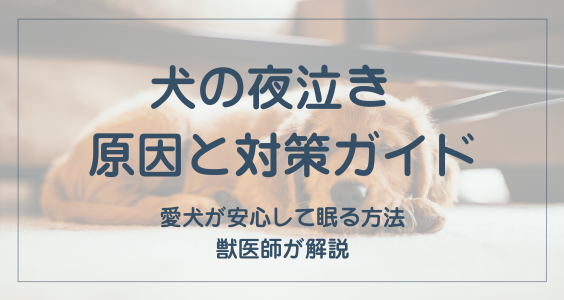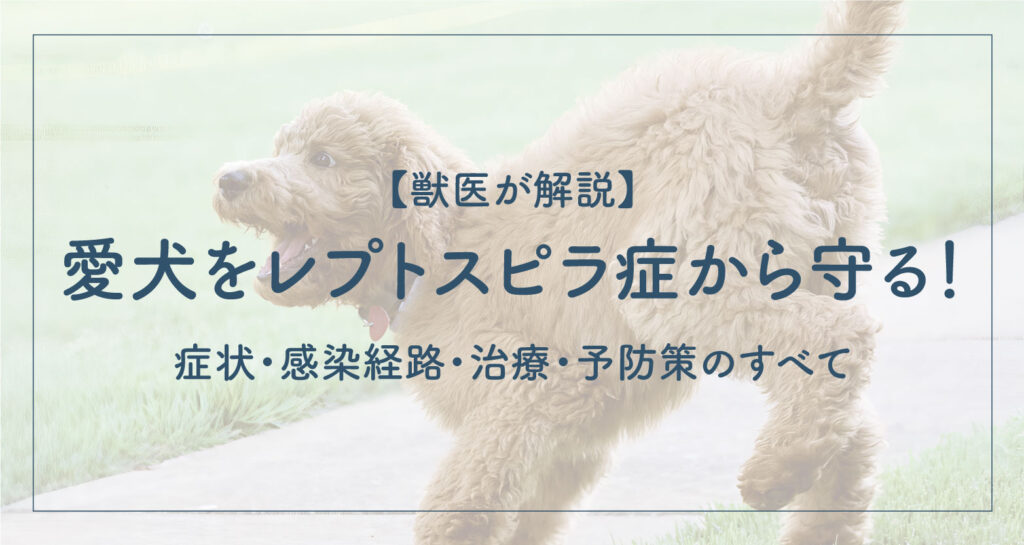
愛犬との散歩や川遊びが楽しい季節ですが、同時に注意すべき感染症があることをご存知でしょうか。それが「レプトスピラ症」という病気です。この感染症は犬だけでなく人にも感染する人獣共通感染症で、適切な知識と対策を持っていないと、愛犬の命に関わる重篤な状態に陥る可能性があります。
今回は、レプトスピラ症について詳しく解説し、飼い主の皆様が適切な予防と対策を取れるよう、専門的な情報をわかりやすくお伝えします。
1.夏から秋にかけて特に注意したい「犬のレプトスピラ症」
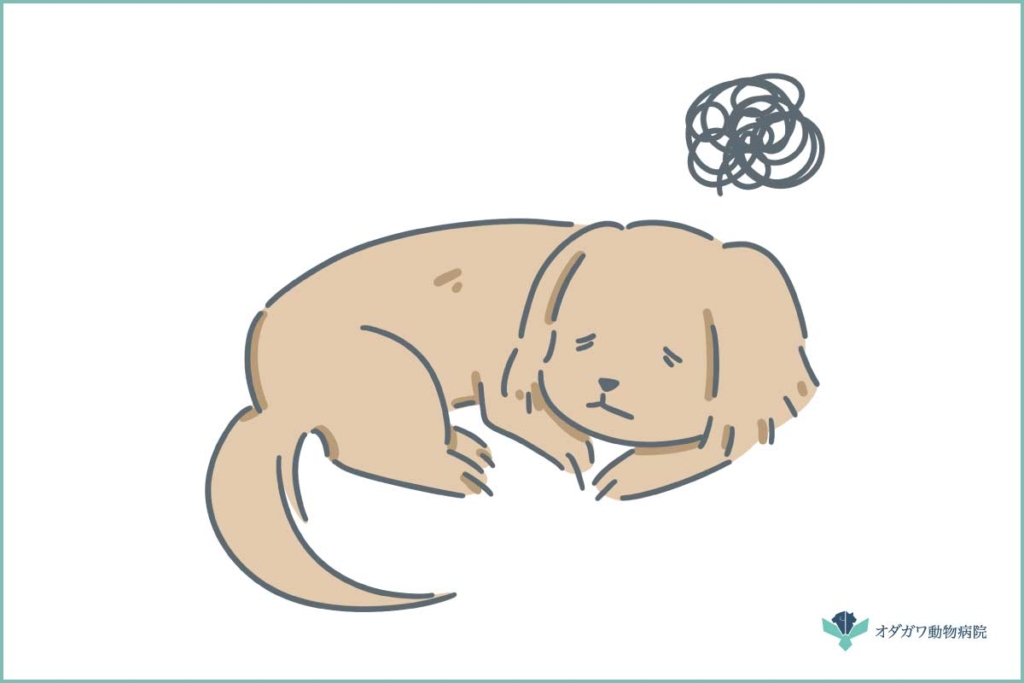
レプトスピラ症とは?人獣共通感染症の背景
レプトスピラ症は、”レプトスピラ”というらせん状の細菌に感染することで発症します。この細菌は、世界中の温帯から熱帯地域にかけて広く分布しており、特に水や湿った土壌を好む特性があります。
なぜ「人獣共通感染症」として重要なのでしょうか?それは、犬が感染源となり、人間にも感染するリスクがあるからです。犬がレプトスピラ菌に感染すると、尿と一緒に菌を排出し続けることがあります。この菌が付着した水や土壌に人間が触れることで、皮膚の傷口や粘膜から感染する可能性があるのです。
人間がレプトスピラ症に感染すると、発熱や頭痛、筋肉痛などのインフルエンザに似た症状から始まり、重症化すると腎臓や肝臓に障害が起きることもあります。特に、免疫力が低下している人や高齢者、小さなお子さんがいるご家庭では、愛犬がレプトスピラ症に感染していると知らずに過ごしてしまうと、思わぬ感染リスクにさらされる可能性もあります。そのため、愛犬の健康を守ることは、ご家族の健康を守ることにもつながるのです。
日本国内の発生状況や季節・地域の傾向(例:夏〜秋、降雨後にリスク増加)
日本におけるレプトスピラ症の発生は、特定の地域や季節に集中する傾向が見られます。一般的に、夏から秋にかけて発生が増加することが知られています。これは、レプトスピラ菌が湿潤な環境を好むため、気温が高く雨量が多い時期に活動が活発になることが影響しています。
特に、降雨後は地面に水たまりができたり、土壌が湿ったりすることで、菌が広がりやすくなります。河川の増水や洪水などが発生した際には、菌が普段いない場所にも拡散されるリスクが高まります。
地域的には、レプトスピラ菌を保菌している野生動物が多い地域や、水田、河川、湖沼、湿地帯など、水が豊富な場所の周辺で発生が多い傾向にあります。都市部でも、公園の池や水たまり、下水などが感染源となる可能性は十分にあります。愛犬が散歩するコースに、そうした水辺や湿った場所がないか、日頃から確認しておくことが大切です。
獣医療の現場では、毎年この時期になるとレプトスピラ症の相談や検査が増える傾向にあります。特に、アウトドア活動を頻繁に行う犬や、散歩コースに草むらや水辺が多い犬の飼い主様は、この時期の予防と症状への注意を怠らないようにしましょう。
2.感染経路とリスクの高い行動

レプトスピラ菌は、主に野生動物の尿によって環境中に排出されます。そのため、愛犬がそうした汚染された環境に触れることが、感染の主な経路となります。
ネズミや野生動物の尿に汚染された水・土との接触が主な感染経路
レプトスピラ菌の主要な保菌動物としては、ネズミ(ドブネズミ、クマネズミなど)が挙げられます。彼らは自身が発症することなく、尿中に大量のレプトスピラ菌を排出し、環境中にばらまく「キャリアー」となることがあります。その他にも、アライグマ、キツネ、イノシシなどの野生動物、さらには牛や豚といった家畜も保菌している可能性があります。
これらの動物の尿によって汚染された水(水たまり、小川、池、沼、下水など)や土壌(湿った草むら、田畑など)に、犬が直接触れることが感染の主な経路となります。
川や池、散歩時に汚水に触れることの注意点
レプトスピラ症は「水」と非常に密接な関係があります。特に、夏から秋にかけては水辺でのレジャーが増える時期でもあり、注意が必要です。
愛犬がこれらのリスクの高い環境に触れてしまった場合は、帰宅後すぐに足を洗う、体を拭くといった対策が有効です。また、散歩中は犬の行動をよく観察し、不必要に水たまりや草むらに近づかせないようにリードでコントロールすることも重要です。
3.潜伏期間と初期症状

レプトスピラ菌に感染してから症状が現れるまでの期間、つまり潜伏期間は、個体差がありますが、一般的に数日から2週間程度とされています。この潜伏期間の長さが、飼い主様が「いつ、どこで感染したのか」を特定することを難しくする要因の一つです。
潜伏期間は数日〜2週間程度
レプトスピラ菌が体内に侵入すると、血液中を循環し、さまざまな臓器に感染を広げていきます。特に、腎臓や肝臓に親和性が高いとされています。この間、菌が体内で増殖し、免疫反応が起こり、ある程度の菌量に達したり、臓器に影響が出始めたりすると症状が現れます。
潜伏期間が比較的長いため、「数日前に水遊びをした」「2週間前にキャンプに行った」といった出来事が、現在の体調不良につながっている可能性を考慮することが重要です。特に、レジャーシーズンや雨の多い時期にアウトドア活動を行った場合は、その後2週間程度は愛犬の体調変化に注意を払うようにしましょう。
初期症状として「発熱」「食欲不振」「元気消失」「嘔吐」「脱水」などが現れる
レプトスピラ症の初期症状は、他の病気と区別がつきにくく、比較的軽度な場合が多いです。しかし、これらのサインを見逃さないことが、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぐ鍵となります。
具体的には、以下のような症状が見られます。
発熱
犬の平熱は人間よりも高く、約38.5℃前後です。レプトスピラ症に感染すると、体温が40℃近くまで上昇することもあります。犬の鼻が乾いていたり、耳が熱いと感じたりする場合は、体温計で正確な体温を測ってみましょう。
食欲不振
いつもはごはんをねだる愛犬が、急にごはんを食べたがらなくなったり、食べ残すようになったりします。おやつにも興味を示さない場合も注意が必要です。
元気消失(元気がない)
散歩に行きたがらない、遊びに誘っても反応が鈍い、一日中寝ている時間が増えた、といった様子が見られます。なんとなく「いつもと違う」「だるそう」といった印象を受けることが多いでしょう。
嘔吐
胃腸の調子が悪くなることで、食べたものを吐いたり、胃液を吐いたりすることがあります。頻繁な嘔吐は脱水症状を招くため、特に注意が必要です。
脱水
嘔吐や食欲不振が続くと、体内の水分が失われ脱水症状になります。歯茎が乾燥している、皮膚をつまんで離してもすぐに戻らない(皮膚の弾力がない)、目のくぼみが見られるなどのサインがあります。
下痢
嘔吐と合わせて下痢が見られることもあります。
筋肉痛・関節痛
全身の倦怠感や筋肉痛、関節痛から、触られるのを嫌がったり、歩き方がおかしくなったりすることもあります。
これらの初期症状は、胃腸炎や風邪など、他の一般的な病気でも見られる症状です。そのため、「少し様子を見よう」と判断してしまいがちですが、特に夏から秋にかけて、水辺での活動や雨上がりの散歩後にこれらの症状が見られた場合は、レプトスピラ症の可能性を疑い、早めに動物病院を受診することが重要です。
4.進行と重症化の症状・合併症
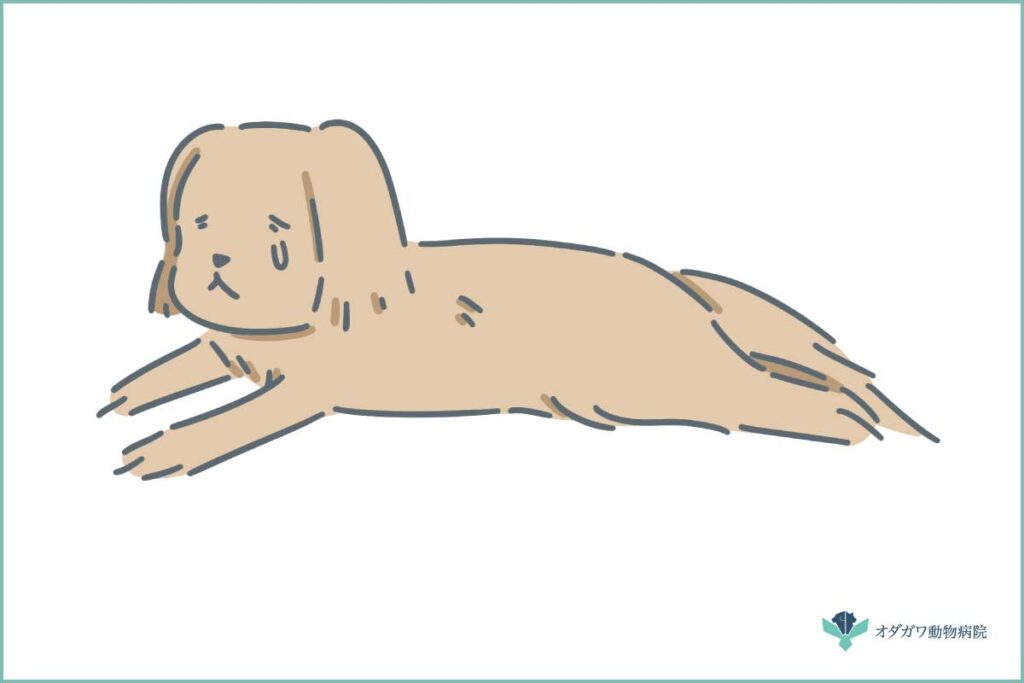
レプトスピラ症は初期症状が軽度であっても、進行すると非常に深刻な状態に陥ることがあります。特に、肝臓や腎臓といった重要な臓器にダメージを与えるため、命にかかわるケースも少なくありません。
黄疸・粘膜出血・タール状便・ぶどう膜炎など重篤な症状の説明
病気が進行すると、以下のような重篤な症状や合併症が現れることがあります。これらの症状が見られた場合は、一刻を争う事態であると認識し、速やかに動物病院で治療を受ける必要があります。
黄疸(おうだん)
レプトスピラ菌が肝臓にダメージを与えると、ビリルビンという色素が体に蓄積し、皮膚や粘膜が黄色く変色します。特に、目の白い部分(結膜)や歯茎、耳の内側などが黄色っぽく見える場合は、黄疸のサインです。黄疸は肝機能の深刻な低下を示唆しており、非常に危険な状態です。
粘膜出血(点状出血、斑状出血)
レプトスピラ菌は血液凝固系にも影響を与えることがあります。そのため、歯茎や舌、目の白い部分などに小さな点状の出血(点状出血)や、皮膚に青あざのような斑状出血が見られることがあります。これは、血小板の減少や凝固因子の異常を示しており、内出血のリスクが高い状態です。
タール状便(黒色便)
上部消化管からの出血がある場合に、血液が消化酵素によって黒く変色し、コールタールのように真っ黒で粘り気のある便が出ることがあります。これは、胃や十二指腸からの出血を示唆しており、重篤な状態です。
ぶどう膜炎
目の内部にあるぶどう膜という組織に炎症が起こることもあります。目の充血、痛み、まぶしそうにする、涙が増える、目が白っぽく濁るなどの症状が見られます。放置すると視力障害につながる可能性もあります。
多飲多尿
腎臓が障害を受けると、尿を濃縮する能力が低下し、頻繁に水を飲むようになり(多飲)、それに伴って排尿量も増える(多尿)ことがあります。 *注意点:初期の多飲多尿は気づきにくいこともあります。
乏尿・無尿
さらに腎臓の機能が悪化すると、尿の量が極端に減ったり、全く出なくなったりすることがあります。これは腎不全が末期に進行している状態であり、非常に危険です。
呼吸器症状
稀に、肺炎を起こして咳や呼吸困難が見られることもあります。
多臓器不全(肝不全・腎不全)のリスクと致死率の高さ
レプトスピラ症が最も恐ろしいのは、全身の臓器に影響を及ぼし、最終的に多臓器不全を引き起こすリスクが高いことです。特に、肝臓と腎臓へのダメージが顕著で、これらの臓器が機能不全に陥ると、体内の毒素を排泄できなくなり、生命維持が困難になります。
レプトスピラ症は、進行が早く、治療が遅れると致死率が高い病気として知られています。特に、重症化した場合は集中的な治療が必要となり、それでも救命できないケースも少なくありません。そのため、少しでも初期症状を疑うサインが見られたら、すぐに動物病院を受診し、早期診断・早期治療を開始することが、愛犬の命を救う上で最も重要なことなのです。
5.診断の流れと検査
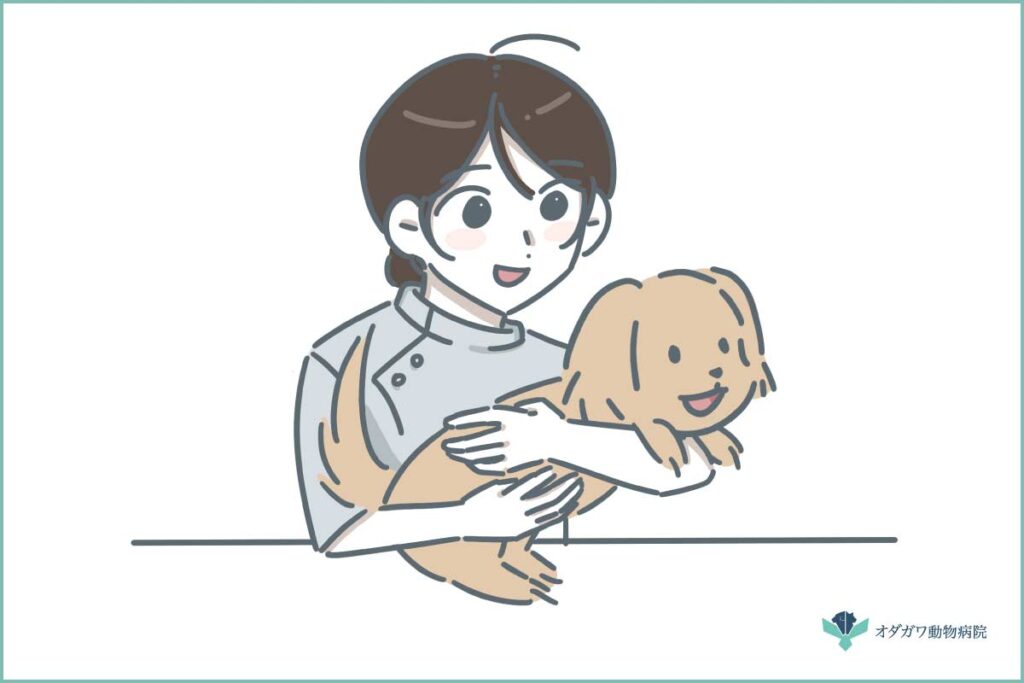
レプトスピラ症の診断は、初期症状が他の病気と似ているため、非常に難しい場合があります。そのため、飼い主様からの詳細な情報(いつ、どこで、どんな行動をしたかなど)と、獣医師による様々な検査を組み合わせることが不可欠です。
血液・尿のMAT抗体検査、ELISA、PCRなどの検査方法
レプトスピラ症の診断には、主に以下のような検査が用いられます。
血球計算と血液生化学検査
血球計算
感染や炎症の有無、貧血の有無などを確認します。レプトスピラ症では、白血球の増加や血小板の減少が見られることがあります。
血液生化学検査
肝臓や腎臓の機能を示す数値(AST, ALT, ALP, BUN, クレアチニンなど)を測定します。レプトスピラ症では、これらの数値が上昇し、肝臓や腎臓にダメージがあることを示唆します。また、黄疸がある場合はビリルビン値の上昇が見られます。
尿検査
尿中のタンパク質や糖、潜血などを調べ、腎臓の機能や感染の有無を確認します。レプトスピラ症では、尿中にレプトスピラ菌が排出されているかを顕微鏡で確認することもありますが、検出が難しい場合が多いです。
レプトスピラ抗体検査
MAT(Microscopic Agglutination Test:顕微鏡凝集試験)
最も信頼性の高い診断法の一つとされています。犬の血液中にレプトスピラ菌に対する抗体があるかを調べます。複数の血清型(レプトスピラ菌の種類)に対応する抗体を同時に検査できるのが特徴です。発症初期には抗体が十分に作られていないことがあるため、診断を確定するためには2~4週間後に再検査(ペア血清検査)を行い、抗体価の上昇を確認することが重要です。抗体価が上昇していれば、現在感染している、または最近感染した可能性が高いと判断されます。
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay:酵素結合免疫吸着測定法)
こちらも抗体を検出する方法ですが、MATよりも迅速に結果が得られる場合があります。ただし、検出できる血清型が限られている場合や、偽陽性・偽陰性の可能性があるため、確定診断には他の検査と組み合わせることが多いです。
PCR検査(Polymerase Chain Reaction:ポリメラーゼ連鎖反応法)
血液、尿、または臓器組織の検体中に、レプトスピラ菌のDNAが存在するかどうかを直接検出する方法です。発症初期でまだ抗体が十分にできていない時期や、菌の排出が始まる時期に有用ですし、ワクチン接種後の抗体がある場合でも菌の存在を直接確認できます。尿のPCR検査は、犬が菌を排出しているかどうかの確認にも使われます。
これらの検査は、単独で行われるだけでなく、組み合わせて実施することで、より正確な診断につながります。
5種や7種ワクチンと抗体検査の区別の難しさ、PCRでの確定
ここで注意が必要なのが、ワクチン接種歴がある場合の抗体検査の解釈です。
多くの混合ワクチンには、レプトスピラの一部血清型に対する免疫を付与する成分が含まれています。そのため、ワクチンを接種している犬の場合、体内にレプトスピラに対する抗体が存在することがあります。これは、病気による感染ではなく、ワクチンによる免疫反応で抗体が作られたためです。
このため、レプトスピラ抗体検査で陽性が出たとしても、それがワクチンによるものなのか、あるいは実際の感染によるものなのかを区別するのが難しい場合があります。
特に、診断の確定にはMAT抗体価の有意な上昇(ペア血清での確認)や、PCR検査による菌のDNAの直接検出が重要になります。
飼い主様は、愛犬のワクチン接種歴を正確に獣医師に伝えることが重要です。これにより、獣医師は検査結果をより適切に解釈し、正確な診断を下すことができます。
6.治療法と費用の目安
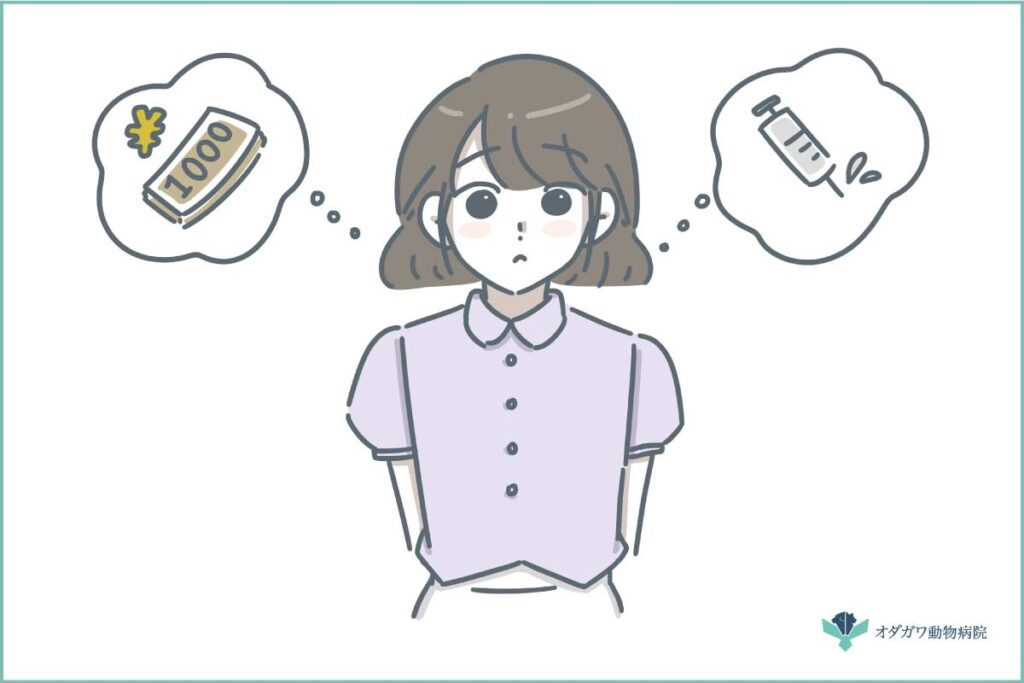
レプトスピラ症と診断された場合、速やかに治療を開始することが非常に重要です。早期の治療開始が、病気の進行を止め、予後を大きく左右します。
抗生物質療法
レプトスピラ症の治療の中心は、抗生物質療法です。レプトスピラ菌は細菌であるため、適切な抗生物質を投与することで菌の増殖を抑え、排除を目指します。
小型犬の治療費の目安(通院注射+内服薬/入院治療など)
レプトスピラ症の治療費は、病気の重症度、治療期間、入院の有無、必要となる検査や薬剤の種類によって大きく変動します。ここでは、あくまで一般的な目安をご紹介します。
軽症・中等症の通院治療(抗生物質注射+内服薬)
診察料、注射料、内服薬(数週間分)などを含めて、数万円〜10万円程度が目安となることがあります。これには、初診時の検査費用(血液検査、尿検査、抗体検査、PCR検査など)も含まれる場合があります。
重症の入院治療
1日あたりの費用
入院費、点滴、抗生物質、その他の薬剤、検査費用(毎日または数日おきに実施)、看護料などを含め、1日あたり3万円〜10万円以上かかることもあります。
総治療費
入院期間が数日〜数週間に及ぶと、総額で数十万円〜100万円以上になるケースも珍しくありません。特に、集中治療室(ICU)での治療や、透析などの高度な治療が必要になった場合は、さらに費用がかさむ可能性があります。
これらの費用はあくまで目安であり、動物病院や地域、個々の症状によって大きく異なります。また、これらの費用には、退院後の経過観察のための通院費用や、長期的に肝臓・腎臓のケアが必要になった場合の療法食代などは含まれていないことが多いです。
ペット保険に加入している場合は、治療費の一部が補償される可能性がありますので、保険会社に問い合わせてみましょう。レプトスピラ症は重症化すると治療費が高額になりがちな病気なので、日頃からの予防が何よりも大切であることを改めて認識しておきましょう。
7.予後と感染後の注意点

レプトスピラ症の予後は、病気の重症度や治療開始のタイミングに大きく左右されます。早期に適切な治療を開始できれば回復が期待できますが、重症化すると残念ながら命を落としてしまうケースも少なくありません。
回復後も数か月~数年にわたり菌を排出するケースあり
レプトスピラ症から回復した犬でも、一つ重要な注意点があります。それは、症状が改善して元気になった後も、数か月、場合によっては数年にわたり、尿中にレプトスピラ菌を排出し続ける「キャリアー」となる可能性があるということです。
これは、抗生物質による治療で症状は改善しても、菌が腎臓の尿細管などに潜伏し、完全に排除されないことがあるためです。キャリアー状態の犬は、見た目には健康そうに見えても、その尿が感染源となり、他の犬や人間にレプトスピラ菌を広げるリスクを抱えています。
そのため、レプトスピラ症に感染した経験のある犬は、回復後も定期的に尿のPCR検査などを行い、菌の排出が続いているかを確認することが推奨されます。もし菌の排出が確認された場合は、獣医師と相談し、さらなる抗生物質投与や、周囲への感染拡大を防ぐための対策を講じる必要があります。
家族や他のペットへの感染リスク、排泄物処理時の注意
愛犬がレプトスピラ症に感染した場合、ご家族や同居の他のペットへの感染リスクも考慮する必要があります。
レプトスピラ症は、愛犬の健康だけでなく、ご家族全員の健康に関わる病気です。感染が確認された場合は、獣医師の指示に従い、適切な治療と感染対策を徹底することが非常に重要です。
8.予防策:日常でできる対策とワクチン接種

レプトスピラ症は、一度発症すると重篤化するリスクが高い病気ですが、適切な予防策を講じることで感染のリスクを大幅に減らすことができます。予防の柱は、日常的な環境管理とワクチン接種の二つです。
汚染された場所(川・池・田畑など)を避け、接触機会を減らす
レプトスピラ菌の主な感染源は、野生動物の尿で汚染された水や土壌です。そのため、日々の生活の中で、愛犬をこれらのリスクの高い場所から遠ざけることが重要です。
・水辺への立ち入りを避ける
散歩中やアウトドアに出かける際は、犬を水たまり、ぬかるみ、小川、池、沼、側溝、下水、河川、湖沼などの水辺に近づけないように注意しましょう。特に雨上がりの後や、長期間水が溜まっている場所では、感染リスクが高まります。また、見た目がきれいな場所でも、野生動物の尿によって汚染されている可能性があるため、キャンプやハイキング時に犬を水遊びさせるのは避けましょう。さらに、田んぼや畑の周辺にはネズミなどの小動物が多く、湿った土壌が細菌の温床となりやすいため、これらの場所での散歩は控えるか、犬が直接土に触れたり水を飲んだりしないよう、リードでしっかりとコントロールすることが重要です。
・草むらや茂みに注意する
湿った草むらや、手入れされていない茂みの中も、野生動物が隠れていたり、排泄したりする場所であり、菌が存在する可能性があります。犬が顔を突っ込んだり、体をこすりつけたりしないように注意しましょう。
・自宅の庭の管理
庭に水たまりができないように水はけを良くする、不要なものを放置してネズミの住処にならないようにするなど、清潔に保つよう心がけましょう。
・帰宅後のケア
散歩から帰宅したら、必ず犬の足回りや体全体を拭き、特に泥や水に触れた場合はシャワーで洗い流すのが理想的です。皮膚に小さな傷があると、そこから菌が侵入するリスクが高まるため、より入念な洗浄が必要です。また、足先や口周りなど、犬が舐める可能性のある部分は、特に丁寧に拭き取るか洗い流すようにしましょう。
・飲用水の管理
散歩中に愛犬が水を欲しがった場合でも、地面に溜まった水や不特定多数の犬が利用する共有の水飲み場ではなく、必ず清潔な飲用水(持参した水)を与えるようにしましょう。
これらの日常的な注意を払うことで、レプトスピラ菌との接触機会を減らし、感染リスクを下げることができます。
ワクチン種類(5種/7種混合)と対応血清型の違い
日常的な予防策に加えて、最も効果的な予防法の一つがワクチン接種です。レプトスピラワクチンは、様々な種類の混合ワクチンに含まれています。
レプトスピラ菌には多くの血清型(種類)が存在します。
レプトスピラワクチンを選ぶ上で重要なのは、愛犬が生活する地域や、よく出かける場所で流行している可能性のある血清型をカバーできるワクチンを選ぶことです。地域によって流行している血清型が異なる場合があるため、獣医師とよく相談し、適切なワクチンを選択することが大切です。
7種混合ワクチンの推奨理由と接種のタイミング(年1回+追加接種)
当院では、レプトスピラ症への対策として、特に7種混合ワクチンを強く推奨しています。6種や8種に含まれる「犬コロナウイルス」については、現時点でのワクチンガイドラインにおいて推奨されていないことから取り扱っておりません。また、レプトスピラの中でも「ポモナ」や「グリッポチフォーサ」といった血清型は、主に海外での報告が多く、日本国内ではヒトを含めて発生例が限られているため、慎重な対応を心がけています。今後も、最新の疫学データに基づいて対応方針を見直してまいります。
なお、すべてのワクチンには副反応の可能性があることを念頭に置く必要があります。特に、ワクチンの種類が増えるほどアレルギー反応のリスクが高まる傾向があるため、生活スタイルや感染リスクを考慮したうえで、必要なワクチンを選択することが大切です。
接種のタイミング
レプトスピラワクチンは、子犬の場合、通常は生後数か月の間に初回の接種を行い、その後2〜4週間間隔で1〜2回の追加接種が必要です。これは、子犬が母犬から受け継いだ移行抗体の影響を避けるためと、確実な免疫を確立するためです。
成犬になってからは、年1回のブースター接種(追加接種)が推奨されます。レプトスピラに対する免疫は、時間の経過とともに低下するため、毎年定期的に接種することで高い防御力を維持できます。
特に、以下のような犬には、年に一度の定期的な接種に加え、秋口の追加接種もご提案することがあります。
・水辺でのレジャーが多い犬
川遊び、湖でのキャンプ、ドッグランの池などで頻繁に遊ぶ犬。
・アウトドア活動が盛んな犬
山林、田畑、草むらなど、野生動物が生息する場所に出かける機会が多い犬。
・雨の多い地域に住んでいる犬
年間を通じて雨量が多く、地面が湿っている期間が長い地域に住む犬。
・ネズミなどの野生動物が多い地域に住んでいる犬
自宅周辺や散歩コースに野生動物の生息が確認されている犬。
夏の終わりから秋にかけては、気温が下がり始める一方で、台風などによる降雨が増え、レプトスピラ菌が活動しやすい環境になります。この時期に再度ワクチンを接種することで、免疫力を高め、最もリスクの高い時期に備えることができます。獣医師と相談し、愛犬の生活環境や活動レベルに合わせた接種計画を立てましょう。
ワクチンでカバーできる血清型の限界と補足的対策
レプトスピラワクチンは非常に有効な予防策ですが、ワクチンでカバーできる血清型には限界があることを理解しておく必要があります。レプトスピラ菌には250以上の血清型が存在すると言われており、現在のワクチンで全ての血清型をカバーすることはできません。
これは、「ワクチンを接種していれば絶対に感染しない」というわけではないことを意味します。ワクチンを接種していても、ワクチンが対応していない血清型に感染する可能性はゼロではありません。
そのため、ワクチン接種と合わせて、日常的な環境管理や注意を怠らないことが非常に重要です。
・リスクの高い場所を避ける
前述の通り、水たまり、汚れた水辺、草むら、野生動物の生息地など、感染リスクの高い場所への立ち入りはできる限り避けましょう。
・帰宅後のケアを徹底する
散歩から帰ったら、足や体を丁寧に拭き、必要であればシャワーで洗い流しましょう。
・健康状態のチェック
日頃から愛犬の様子をよく観察し、食欲不振、元気消失、発熱などの異常が見られたら、ワクチン接種の有無にかかわらず、すぐに動物病院を受診しましょう。
・適切な衛生管理
食器や水入れを清潔に保ち、ネズミなどの侵入を防ぐために自宅の環境管理も行いましょう。
ワクチン接種は強力な盾となりますが、それだけで全てを防げるわけではありません。日常的な注意と組み合わせることで、愛犬をレプトスピラ症から最大限に守ることができます。
9.「こんな時にはすぐ来院を」
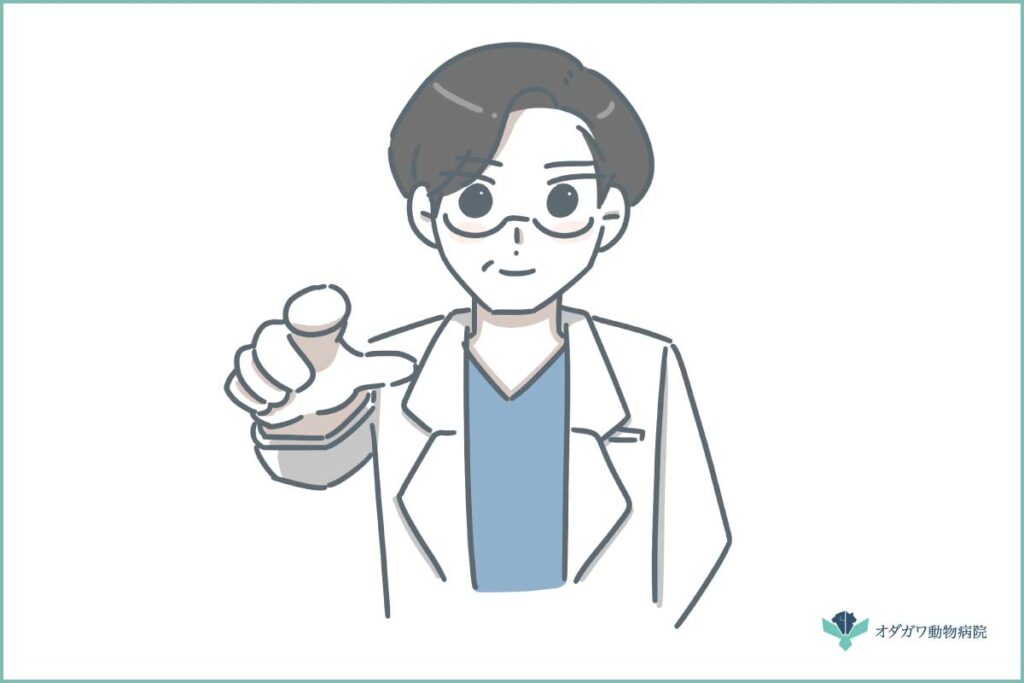
レプトスピラ症は、早期発見・早期治療が非常に重要な病気です。初期症状は他の病気と区別がつきにくいことがありますが、以下のサインが見られた場合は、迷わずすぐに動物病院を受診してください。
食欲が明らかに落ちている・元気がなく散歩を嫌がる・発熱や嘔吐がある場合の早期受診の重要性
「うちの子、なんか変だな?」と感じたら、それは愛犬からの大切なSOSかもしれません。特に、以下の症状が一つでも見られた場合は、すぐに動物病院にご連絡ください。
食欲が明らかに落ちている
・いつもは食いしん坊な子が、急にごはんを食べなくなった。
・おやつにも興味を示さない。
・普段はガツガツ食べるのに、残すようになった。
・食欲不振が24時間以上続いている。
元気がなく散歩を嫌がる
・散歩に行こうとしても、しっぽを振らずに伏せたまま。
・散歩中に立ち止まることが増えた、歩くのが遅くなった。
・普段は活発なのに、一日中寝ている時間が増えた、だるそうにしている。
・遊びに誘っても反応が鈍い、全く遊ぼうとしない。
発熱がある
・鼻が乾いて熱っぽい、耳や体全体がいつもより熱いと感じる。
・体温計で測ったら、平熱(38.5℃前後)より明らかに高い(例:39.5℃以上)。
・震えが見られる場合も、発熱のサインの可能性があります。
嘔吐がある
・何度も吐いている。
・吐物の中に未消化の食べ物や胃液だけでなく、血液が混じっている。
・吐いた後もぐったりしている。
その他の重い症状
・下痢が続いている(特に黒っぽいタール状の便)。
・おしっこの量が少ない、または全く出ていない。
・黄疸(目の白い部分や歯茎が黄色い)が見られる。
・歯茎や皮膚に小さな出血点やあざが見られる。
これらの症状は、レプトスピラ症だけでなく、他の重篤な病気のサインである可能性もあります。自己判断で様子を見たり、市販薬を与えたりすることは非常に危険です。特に、レプトスピラ症は進行が早く、治療が遅れると命にかかわることが多いため、「いつもと違う」と感じたら、その日のうちに、または翌朝一番で動物病院を受診することが、愛犬の命を救う最善の策です。
10.ワクチン接種と食欲減退時のおすすめフード紹介

当院では、愛犬のレプトスピラ症予防と、万が一の際の体調サポートに力を入れています。
ワクチン接種のご案内
当院では、レプトスピラ症の予防に効果的な7種混合ワクチンを常備しております。
レプトスピラ症は、特定の血清型に感染することで発症しますが、当院でご用意している7種混合ワクチンは、日本国内で犬のレプトスピラ症を引き起こす主な血清型の一部をカバーしており、予防効果が期待できます。
愛犬をレプトスピラ症から守るため、毎年のブースター接種を推奨しています。
ワクチンによる免疫は永続的なものではなく、時間の経過とともに低下します。そのため、年に一度の追加接種(ブースター接種)を行うことで、愛犬の高い免疫力を維持し、病気から身を守ることができます。
特に、水辺レジャーが多い犬や、降雨後にアウトドアに出かける機会が多い犬には、秋の追加接種もご提案しています。
夏の終わりから秋にかけては、レプトスピラ菌が活発になりやすい時期です。この時期に水辺での活動や山林への散歩など、感染リスクの高い行動が多い愛犬には年一回の定期接種に加え、このリスクの高い時期に合わせた追加接種を検討することで、より強力な免疫を維持し、感染リスクをさらに低減できます。
ワクチン接種のスケジュールや、愛犬に最適なワクチンの種類については、診察時に獣医師にご相談ください。愛犬の年齢、健康状態、生活環境、活動レベルなどを考慮し、最適な予防プランをご提案させていただきます。

食欲減退時のフォロー
もし愛犬の食欲がなくなったときでも、ご安心ください。当院では、体調不良時でも安心して与えられる消化に優しい療法食やシニア向け・体調不良時対応フードをご用意しております。
レプトスピラ症の初期症状や、その他の体調不良で食欲が落ちてしまうことはよくあります。このような時、無理に普段のフードを与え続けることは、愛犬の負担になったり、さらに食欲を低下させたりする原因になりかねません。
当院では、以下のような特徴を持つフードをご提案し、愛犬の回復をサポートします。
「低脂肪×高消化性フード」:胃腸への負担を最小限に抑え、消化吸収を助けることで、体力の回復を促します。下痢や嘔吐がある場合にも適しています。
「お湯で溶かすスープタイプ」:香りが立ち、食欲を刺激します。水分補給も兼ねられるため、脱水傾向がある場合にもおすすめです。固形物を食べにくい時に、流動食としても与えられます。
「嗜好性の高い缶詰タイプ」:独特の風味や柔らかな食感で、食欲が落ちている犬でも食べやすいように工夫されています。ウェットフードは、ドライフードよりも水分含有量が高く、嗜好性が高いものが多いです。
愛犬の好みや体質、現在の症状に合わせた最適なフードをご提案するため、実際にサンプルをお試しいただくことも可能です。また、フードの与え方や、食欲不刺激のための工夫についても、具体的なアドバイスをさせていただきます。
食欲の低下は、様々な病気のサインであると同時に、体力の低下を招き、回復を遅らせる原因にもなります。愛犬が「食べない」というサインを出したら、無理強いせず、まずは動物病院にご相談ください。適切なフードとケアで、愛犬の早期回復をサポート致します。
↓獣医師おすすめのドッグフードはこちら↓

まとめ|愛犬の健康を守るために
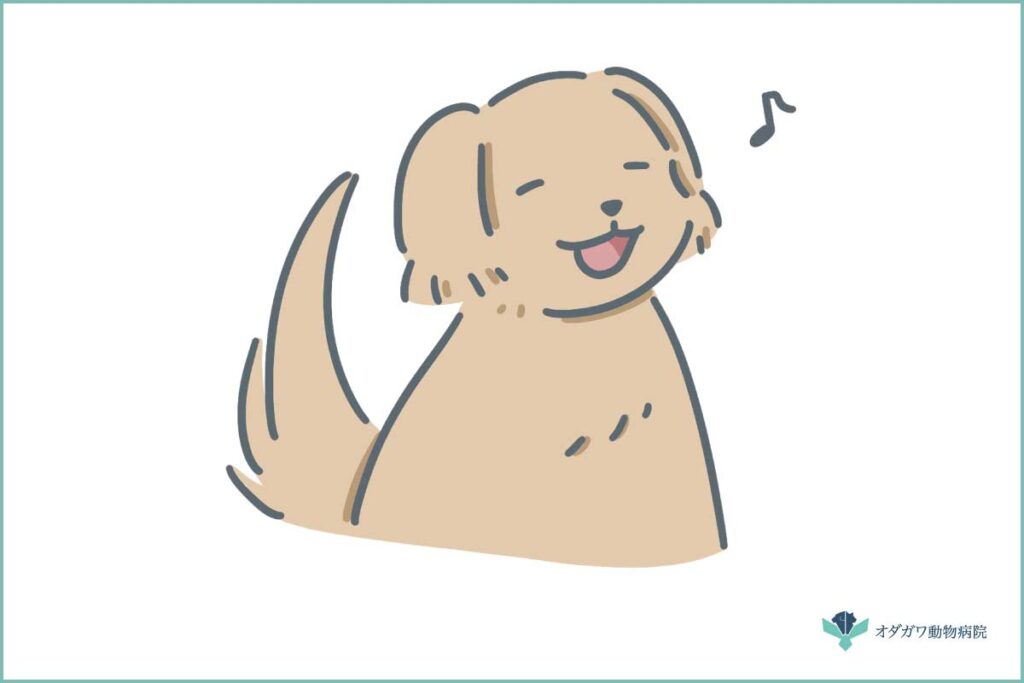
レプトスピラ症は、初期には発熱、食欲不振、元気消失といった軽い症状で始まることが多いですが、放置すると肝不全や腎不全といった多臓器不全に至り、命に関わる重篤な病気です。人獣共通感染症であるため、愛犬だけでなくご家族の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
しかし、この病気は日常的な環境管理と毎年のワクチン接種によって、大きく予防できます。リスクの高い水辺や湿った場所を避け、散歩後の足の洗浄を徹底し、そして何よりも適切なワクチン接種を怠らないことが重要です。
万が一、愛犬に食欲不振や元気がない、発熱や嘔吐があるといった症状が現れた場合は、レプトスピラ症の可能性を視野に入れ、速やかに動物病院で診察・検査・治療を行うことが重要です。早期発見・早期治療が、愛犬の命を救う鍵となります。
また、食欲が落ちたと感じたときにも、当院では愛犬の体調維持をサポートするためのフード相談を行い、消化に優しい療法食など最適なフードのご提案をしています。
愛犬の健康とご家族の安心のために、レプトスピラ症に対する正しい知識と予防意識を持って、この季節を乗り切りましょう。何かご心配なことがあれば、いつでも当院にご相談ください。