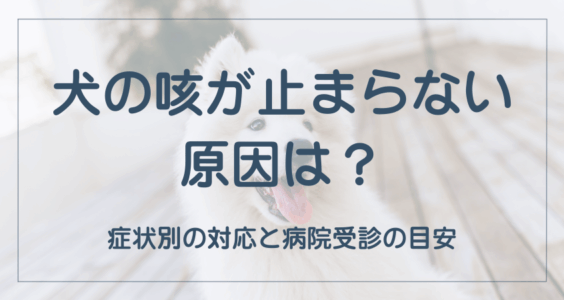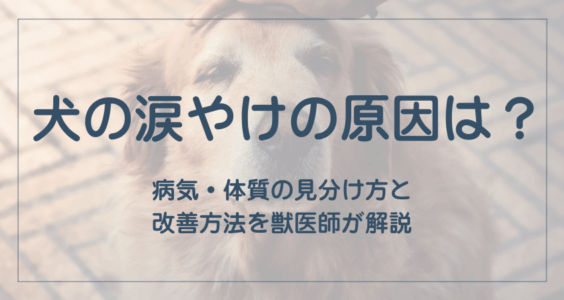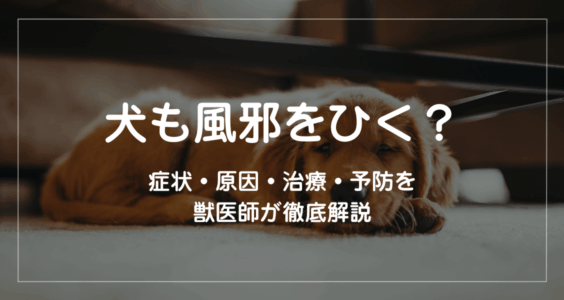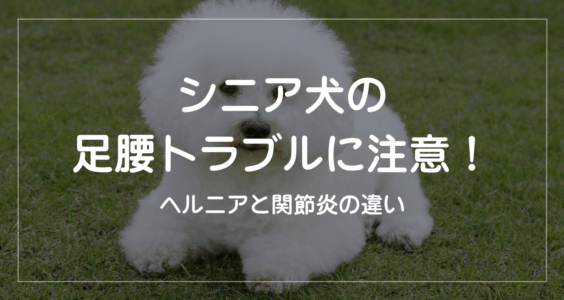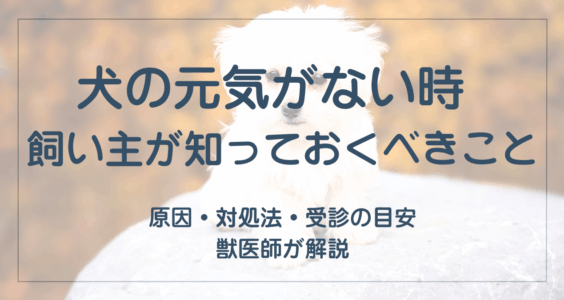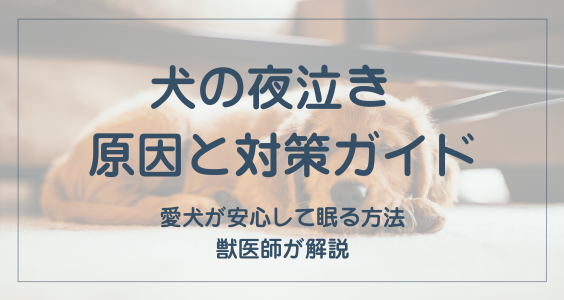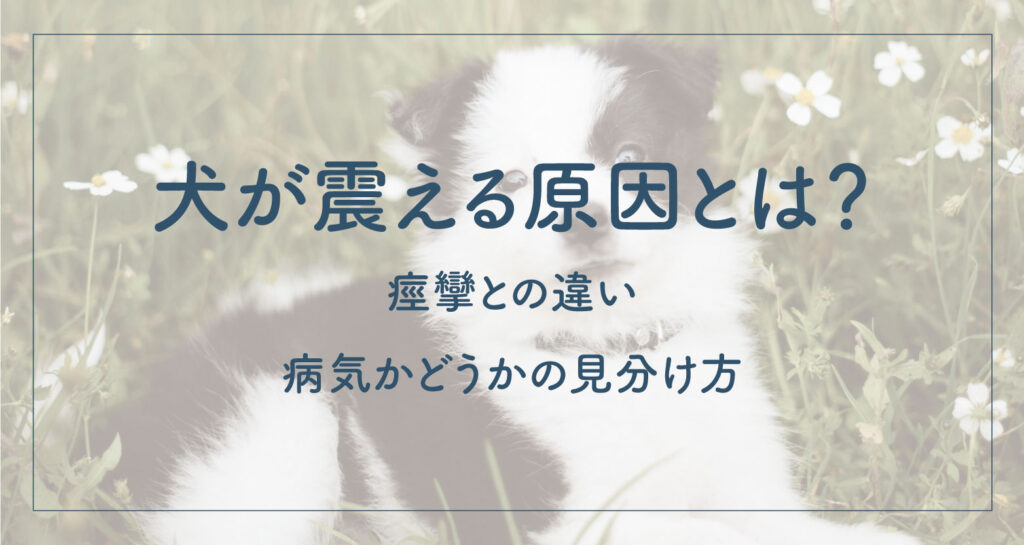
愛犬が震えている姿を見ると、飼い主として心配になるのは当然のことです。「何か重篤な病気なのではないか」「すぐに病院に連れて行くべきなのか」と不安な気持ちが込み上げてきます。
しかし、犬の震えがすべて病気のサインというわけではありません。寒さや興奮、ストレスなど、生理的な原因で震えることも多くあります。とはいえ、中には深刻な疾患が隠れているケースもあるため、適切な対応判断が求められるのが現実です。
この記事では、「なぜ犬は震えるのか?」「痙攣との違いはどこにあるのか?」「いつ獣医に診てもらうべきなのか?」といった疑問を、体系的に整理してご説明します。愛犬の健康を守るため、震えのメカニズムや適切な対処法について一緒に学んでいきましょう。
1. 犬の震え(振戦)とは何か?

医学的定義と特徴
犬の震えは、医学用語では「振戦(しんせん)」と呼ばれることがあります。これは、筋肉が小刻みに収縮と弛緩を繰り返すことで起こる現象です。振戦は、意識がはっきりしている状態で発生することが特徴で、犬は周囲の状況を認識し、飼い主の声かけにも反応できます。
振戦には大きく分けて2つのタイプがあります。安静時振戦は、犬がリラックスしているときに現れる震えで、動き始めると軽減することが多いです。一方、動作時振戦は、歩いたり立ち上がったりする際に現れる震えで、動作を止めると改善されることがあります。
痙攣(痙攣発作)との重要な違い
震えと混同されやすいのが痙攣(けいれん)です。しかし、これらには明確な違いがあります。
振戦(震え)の特徴
・意識がはっきりしている
・飼い主の呼びかけに反応する
・小刻みな筋肉の動き
・体の一部または全身に現れる
・比較的軽微な症状
痙攣発作の特徴
・意識を失うことが多い
・呼びかけに反応しない
・大きな筋肉の収縮と硬直
・全身性の激しい動き
・よだれ、失禁を伴うことがある
この違いを理解することは、適切な対応を取るために非常に重要です。痙攣発作の場合は緊急性が高く、すぐに獣医師の診察を受ける必要があります。
2. 犬が震える主な原因と種類

犬の震えは、大きく「生理的・環境による震え」と「病気や異常が原因の震え」に分類できます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
生理的・環境による震え(心配なし)
寒さによる防御反応
最も一般的な震えの原因が寒さです。犬は体温を維持するため、筋肉を小刻みに動かして熱を産生します。これは正常な生理反応で、暖かい場所に移動すると自然に治まります。
特に小型犬や被毛の薄い犬種、高齢犬は寒さに敏感で、室温が低いと震えやすくなります。冬場の散歩や、エアコンの効いた部屋での震えは、多くの場合この生理的反応です。
興奮・嬉しさによる震え
飼い主の帰宅時や、散歩に行く前、おやつをもらう前など、犬が興奮したり喜んだりする場面で震えることがあります。これは感情の高ぶりによる自然な反応で、健康上の問題はありません。
この種の震えは、犬の尻尾が振れて目が輝いているなど、明らかにポジティブな感情表現と一緒に現れることが特徴です。
恐怖・不安・ストレスによる震え
雷や花火の音、来客、動物病院での診察など、犬が恐怖や不安を感じる状況で震えることがあります。これは交感神経の活性化によるもので、一時的なものです。
ストレス性の震えは、同時に次のような行動が見られることが多いです
・息が荒くなる
・よだれが出る
・隠れようとする
・固まって動かなくなる
高齢犬の筋力低下による震え
高齢になると筋力が低下し、立ち上がる際や歩行時に脚が震えることがあります。これは加齢に伴う自然な変化で、特に後脚に現れやすい症状です。
筋力低下による震えは、安静にしているときは現れず、動作を始めるときに顕著になるのが特徴です。
飼い主の注意を引くための”意図的”な震え
賢い犬の中には、震えることで飼い主の関心を引こうとする場合があります。過去に震えたときに飼い主がやさしく声をかけてくれた経験から、学習によって震える行動を示すことがあります。
この場合、震えている割には元気で食欲もあり、飼い主が注目すると震えが止まることが多いです。
病気や異常が原因の震え(要注意)
神経系疾患による震え
神経系の疾患は、犬の震えの深刻な原因の一つです。
てんかん: 脳の異常な電気活動によって起こる疾患で、震えから始まって痙攣発作に進行することがあります。てんかんは完治が困難ですが、抗てんかん薬によってコントロール可能なケースが多いです。
脳炎・脳腫瘍: 脳の炎症や腫瘍によって神経機能が障害され、震えが現れることがあります。初期症状として震えが現れ、進行すると意識障害や運動失調なども見られるようになります。
水頭症: 特に小型犬に多い疾患で、脳脊髄液の循環障害により脳圧が上昇し、震えや旋回行動などの神経症状が現れます。
神経症状が気になる場合は、早めの健康診断・詳しい診療が重要です。まずは当院の『犬の診療』ページをご覧ください。
中毒・低血糖による震え
中毒症状: チョコレートやキシリトール、ブドウ、ネギ類など、犬にとって有毒な物質を摂取した際に震えが現れることがあります。中毒による震えは、摂取後数時間以内に現れることが多く、緊急対応が必要です。
低血糖: 特に小型犬や糖尿病の治療中の犬で起こりやすく、血糖値の急激な低下により震えや意識障害が現れます。重篤な場合は昏睡状態に陥ることもあります。
内臓疾患による震え
肝機能不全: 肝臓の機能が低下すると、体内の毒素が蓄積され、神経症状として震えが現れることがあります。同時に食欲不振や黄疸などの症状も見られます。
腎不全: 腎臓の機能低下により体内の電解質バランスが崩れ、震えが起こることがあります。多飲多尿や食欲不振なども併発します。
電解質異常: ナトリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質のバランスが崩れると、筋肉や神経の機能に影響し、震えが現れることがあります。
痛みによる震え
椎間板ヘルニア: 背骨の間にある椎間板が突出し、神経を圧迫することで激しい痛みと震えが現れます。特にダックスフンドやビーグルなどの犬種で多く見られます。
関節炎: 加齢や外傷により関節に炎症が起こり、痛みによって震えることがあります。特に寒い日や湿度の高い日に症状が悪化しやすいです。
感染症・寄生虫による震え
ウイルスや細菌、寄生虫による感染症でも、発熱や炎症、痛みにより震えが起こることがあります。特に夏〜秋にかけては、フィラリア症のリスクが高まります。咳や元気消失などの症状とともに震えが見られる場合は、早めの診察が必要です。
オダガワ動物病院の公式youtubeチャンネル「世界一受けたい動物授業」でも解説しています。
3. 「痙攣(けいれん)」との違いを見抜くチェックポイント

震えと痙攣の違いを正確に判断することは、適切な対応を取るために極めて重要です。以下のチェックポイントを参考に、愛犬の症状を観察してください。
意識状態の確認
震え(振戦)の場合
・飼い主の呼びかけに反応する
・目線が合う
・普段通りの表情を見せる
・指示に従うことができる
痙攣発作の場合
・呼びかけに全く反応しない
・目が虚ろになる、または白目をむく
・表情が硬直している
・指示を理解できない状態
体の動きの特徴
震え(振戦)の場合
・小刻みで規則的な筋肉の動き
・体の一部分に限定されることが多い
・飼い主が触ると一時的に止まることがある
・比較的軽微な動き
痙攣発作の場合
・大きく激しい筋肉の収縮
・全身に及ぶことが多い
・手足をばたつかせる、体をよじらせる
・触っても止まらない
随伴症状の確認
震え(振戦)の場合
・呼吸は比較的正常
・よだれは出ても少量
・失禁はまれ
・発作後の意識混濁はない
痙攣発作の場合
・呼吸が荒くなる、または一時的に止まる
・大量のよだれが出る
・失禁することが多い
・発作後にぼんやりとした状態が続く
てんかん発作における段階的変化
てんかん発作は段階的に進行することが多く、初期の震えから重篤な痙攣に発展する可能性があります。
1前駆期: 不安そうにする、隠れる、食欲不振などの前兆症状
2前兆期: 軽い震えや筋肉の緊張が始まる
3発作期: 意識を失い、激しい痙攣が起こる
4回復期: 徐々に意識が戻るが、しばらくぼんやりとしている
この進行を動画で記録することは、獣医師の診断において非常に有効です。スマートフォンなどで症状の様子を撮影し、診察時に見せることで、より正確な診断につながります。
4. 病院へ行くべきタイミングと症状の見分け方
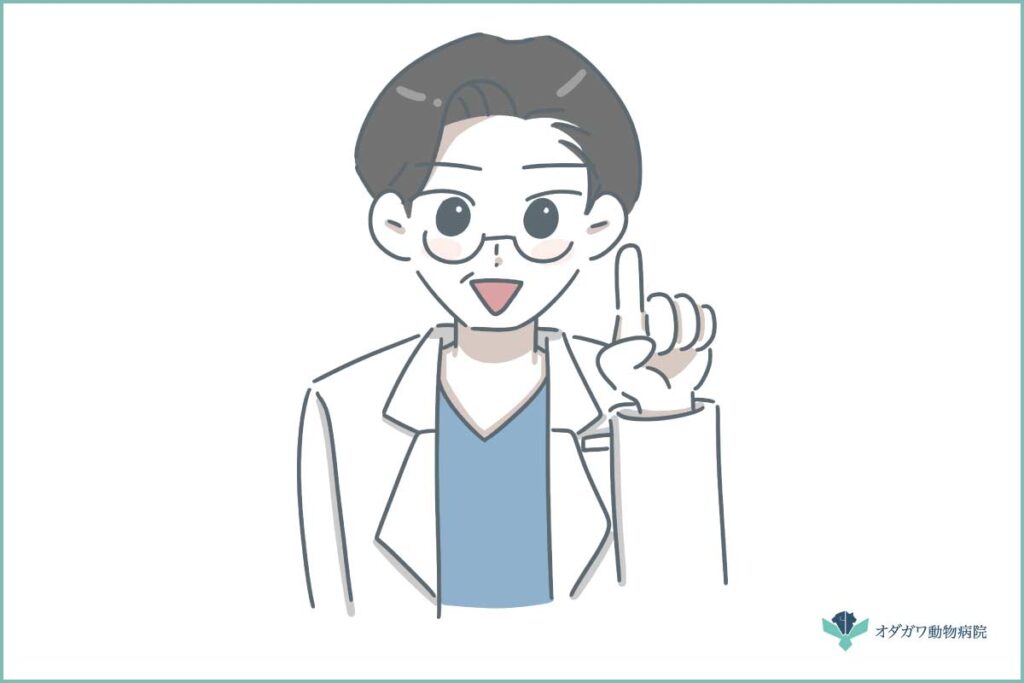
愛犬の震えが病的なものかどうかを判断し、適切なタイミングで獣医師の診察を受けることが大切です。以下の症状や状況に該当する場合は、迷わず動物病院を受診しましょう。
緊急受診が必要な症状
以下の症状が一つでも当てはまる場合は緊急性が高いため、すぐに動物病院に連絡し指示を仰いでください。
意識に関わる症状
・意識がない、または朦朧としている
・呼びかけに全く反応しない
・目の焦点が合わない
・ふらついて立っていられない
呼吸器症状
・呼吸が非常に荒い、または浅くて速い
・口を開けてハアハア息をしている(パンティング)が、暑くもないのに止まらない
・呼吸困難の様子が見られる
消化器症状
・激しい嘔吐や下痢を繰り返す
・血液の混じった嘔吐物や便
・腹部を痛がって丸くなる
神経症状
・痙攣発作が起きている
・体の一部または全身が麻痺している
・旋回行動が止まらない
早期受診が推奨される症状
緊急性は高くないものの、放置すると症状が悪化する可能性がある場合は数日以内に受診することをお勧めします。
震えの持続性
・震えが2時間以上続いている
・1日に何度も震える症状が現れる
・日を増すごとにに震えが強くなっている
全身状態の変化
・食欲が明らかに低下している
・元気がなく、普段より動きたがらない
・水を飲む量が急激に増えた、または減った
・排尿・排便のパターンが変わった
行動の変化
・いつもより鳴くことが多い、または逆に静かすぎる
・飼い主から離れたがらない
・普段好きな活動に興味を示さない
・夜中に起きて震えている
様子を見てもよい場合の判断基準
以下の条件をすべて満たす場合はしばらく様子を見ても大丈夫でしょう。ただし、症状が変化した場合は迷わず受診してください。
震えの特徴
・明確な原因がある(寒い、興奮している、など)
・短時間で自然に止まる
・原因を取り除くと改善する
全身状態
・食欲や元気は普段通り
・意識はしっかりしている
・他の症状を伴わない
過去の経験
・同様の震えを経験したことがあり、問題なかった
・定期的な健康診断で異常を指摘されていない
受診時に準備すべき情報
獣医師の診察をより効果的にするため、以下の情報を整理して持参しましょう。
症状の記録
・震えが始まった日時
・持続時間と頻度
・きっかけや状況
・他の症状の有無
日常生活の変化
・食欲、飲水量、排泄の変化
・運動や散歩の様子
・睡眠パターンの変化
・行動の変化
動画記録
・スマートフォンで撮影した震えの様子
・できれば発作の始まりから終わりまで
医療履歴
・過去の病歴
・現在服用中の薬
・最近受けた治療やワクチン
5. 自宅でできる応急ケアと記録の取り方
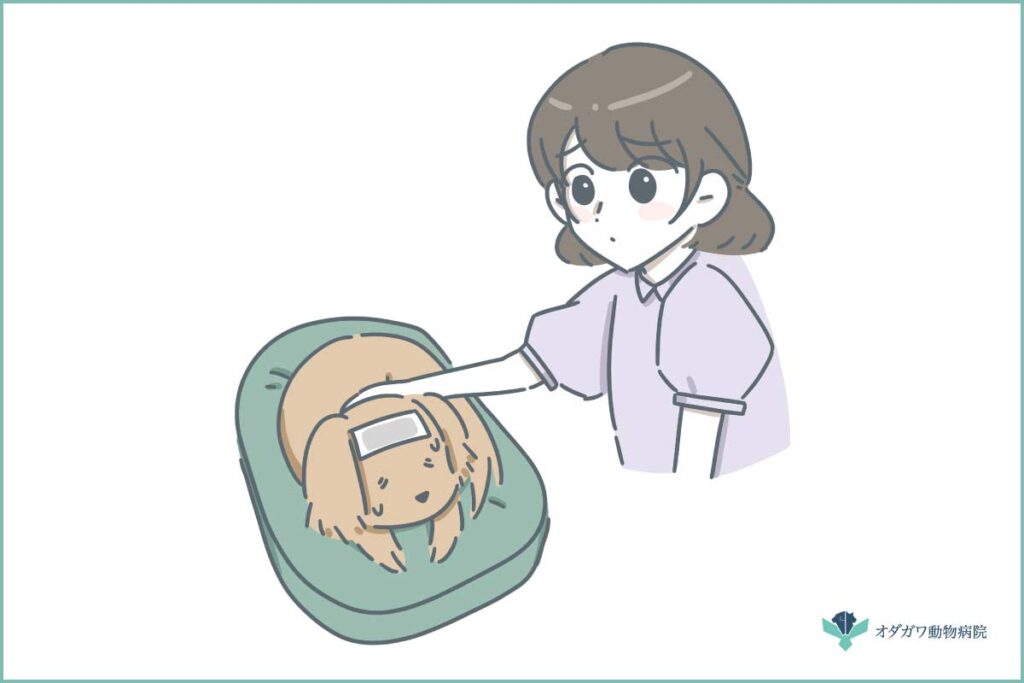
愛犬が震えている時、飼い主として適切な応急ケアを行うことで症状の悪化を防ぎ、愛犬の不安を軽減することができます。
安心できる環境づくり
温度管理: 寒さが原因と思われる場合は、暖かく静かな部屋に移動させます。ただし、急激な温度変化は避け、毛布やタオルで包んで徐々に体を温めます。暖房器具を使用する場合は、直接当てるのではなく、部屋全体を暖めるようにしましょう。
騒音の除去: 雷や花火、工事音などが原因の場合は、できるだけ静かな場所に移動します。カーテンを閉めて外の様子が見えないようにし、テレビや音楽を小さな音量でかけて騒音をマスキングすることも効果的です。
安心できる場所の提供: 愛犬がいつも使っているベッドやクレート、普段隠れる場所など、安心できる環境を整えます。飼い主が側にいることで安心する犬も多いので、優しく声をかけながら見守りましょう。
ケガ防止のための安全対策
痙攣発作に進行する可能性もあるため、周囲の安全を確保することが重要です。
危険物の除去: テーブルの角、階段、硬い床面など、転倒時にケガをする可能性がある場所や物を片付けます。特に高い場所にいる場合は、安全な平らな場所に移動させます。
クッション等の配置: 周囲を毛布やクッションで囲み、激しい動きになった場合でもケガをしないよう配慮します。ただし、呼吸を妨げないよう顔周りは空けておきましょう。
触る際の注意: 震えている犬は興奮状態にあることが多く、普段はしない咬傷事故が起こる可能性があります。声をかけながらゆっくりと触るようにし、犬が嫌がる様子を見せたら無理に触らないようにしましょう。
してはいけない応急処置
良かれと思って行う処置が、かえって症状を悪化させることもあります。以下の点に注意してください。
口の中に物を入れない: 昔は痙攣時に舌を噛まないよう口に物を挟むとされていましたが、現在では推奨されていません。かえって口の中を傷つけたり、誤飲の原因となったりする危険があります。
無理に体を押さえつけない: 激しい震えや痙攣を止めようと体を強く押さえることは避けましょう。筋肉や関節を傷める可能性があります。
水や食べ物を与えない: 意識が朦朧としている時に水や食べ物を与えると、誤嚥の危険があります。完全に意識が回復してから与えるようにしましょう。
6. 高齢犬ならではの震えの背景(加齢・認知症など)
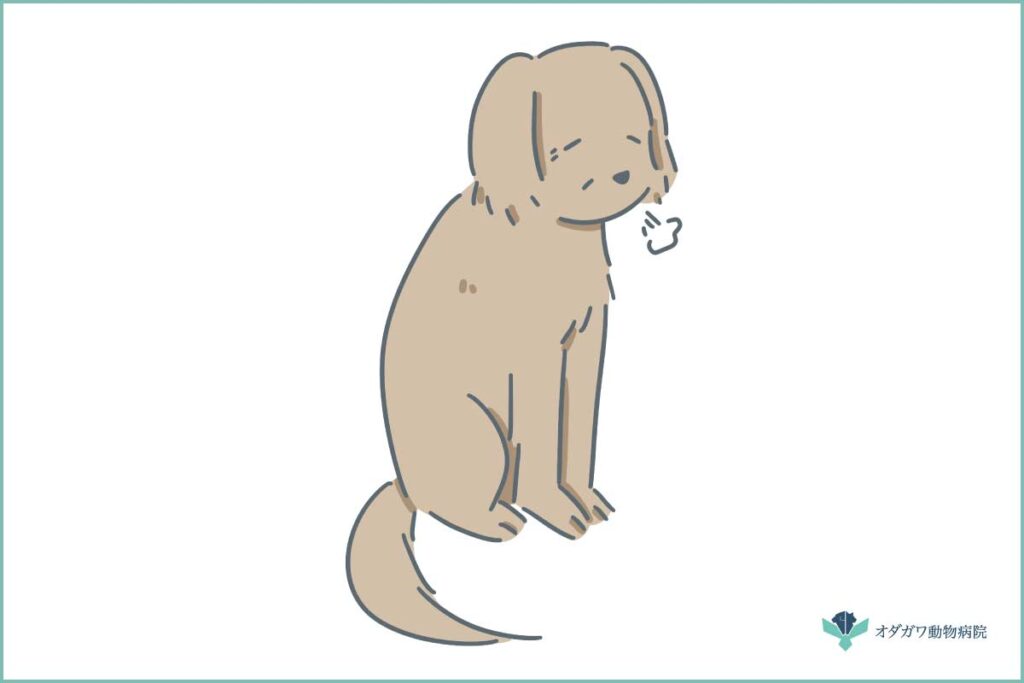
高齢犬の震えには、加齢特有の原因があることが多く、その背景を理解することで適切なケアができます。
筋力低下と関節疾患
加齢による筋力低下: 高齢になると筋肉量が減少し、筋力が低下します。これにより、立ち上がる際や歩行時に脚が震えることがあります。特に後脚の筋力低下は顕著で、階段の昇降や車への乗り降りが困難になることもあります。
関節炎の影響: 多くの高齢犬が関節炎を患っており、関節の痛みや可動域の制限により、体を支える際に震えが生じることがあります。特に寒い日や湿度の高い日、長時間の運動後に症状が悪化しやすいです。
背骨の変形: 椎間板の変性や骨棘の形成により、背骨が変形し神経が圧迫されることで震えや歩行困難が現れることがあります。
認知症(犬の認知機能障害症候群)
犬も人間と同様に認知症になることがあり、その症状の一つとして震えが現れることがあります。
認知症の主な症状
・夜間の徘徊や鳴き声
・名前を呼んでも反応が鈍い
・普段の習慣を忘れる(トイレの場所など)
・食欲の変化
・不安や恐怖の増加
・震えや体の硬直
認知症による震えの特徴: 認知症による震えは、不安や混乱に伴って現れることが多く、特に夜間や環境の変化があった時に顕著になります。昼夜逆転により夜中に起きて震えることもあります。
高齢犬の震えへの対処法
環境改善策
1.温度管理の徹底
・部屋の温度を一定に保つ
・暖房設備の充実
・暖かいベッドやマットの提供
・ドラフト(隙間風)の防止
2.床材の工夫
・滑りにくいマットの設置
・クッション性のある敷物
・段差の解消
・滑り止めの靴下の使用
3.運動環境の整備
・短時間で負担の少ない散歩
・平坦なルートの選択
・関節に優しい運動(水中歩行など)
・無理のない範囲での活動維持
栄養サポート
1.関節サポート成分
・グルコサミン・コンドロイチン
・オメガ3脂肪酸
・抗炎症作用のある成分
2.認知機能サポート
・DHA・EPA
・抗酸化成分
・脳機能をサポートするサプリメント
医療的アプローチ: 高齢犬の震えが日常生活に支障をきたす場合は、獣医師と相談して以下の治療選択肢を検討します。
・関節炎に対する抗炎症薬
・疼痛管理薬
・認知症に対する薬物療法
・理学療法やマッサージ
・鍼治療などの代替医療
高齢犬の生活の質向上
震えに悩む高齢犬の生活の質を向上させるためには、総合的なアプローチが必要です。
日常ケアの充実
・定期的なブラッシングとスキンケア
・爪切りや耳掃除などのグルーミング
・口腔ケアによる健康維持
・適度な刺激と精神的な充足
歯周病や口腔のトラブルが痛みやストレスとなり震えの原因になることもあります。
犬の歯周病とは?症状・原因・治療法と予防ケアを獣医師が解説
飼い主との絆の維持
・穏やかな時間の共有
・優しい声かけとタッチング
・犬のペースに合わせた関わり
・安心できる環境の提供
オダガワ動物病院おすすめのフード・サプリメント
高齢犬の震えには、栄養面からのサポートも重要です。当院では、関節の健康維持や認知機能のサポートに配慮したフードやサプリメントをご提案しております。愛犬の状態やライフステージに合わせてご案内可能ですので、お気軽にご相談ください。
獣医師おすすめのフード・サプリメントはこちら↓

7. よくある質問(FAQ)
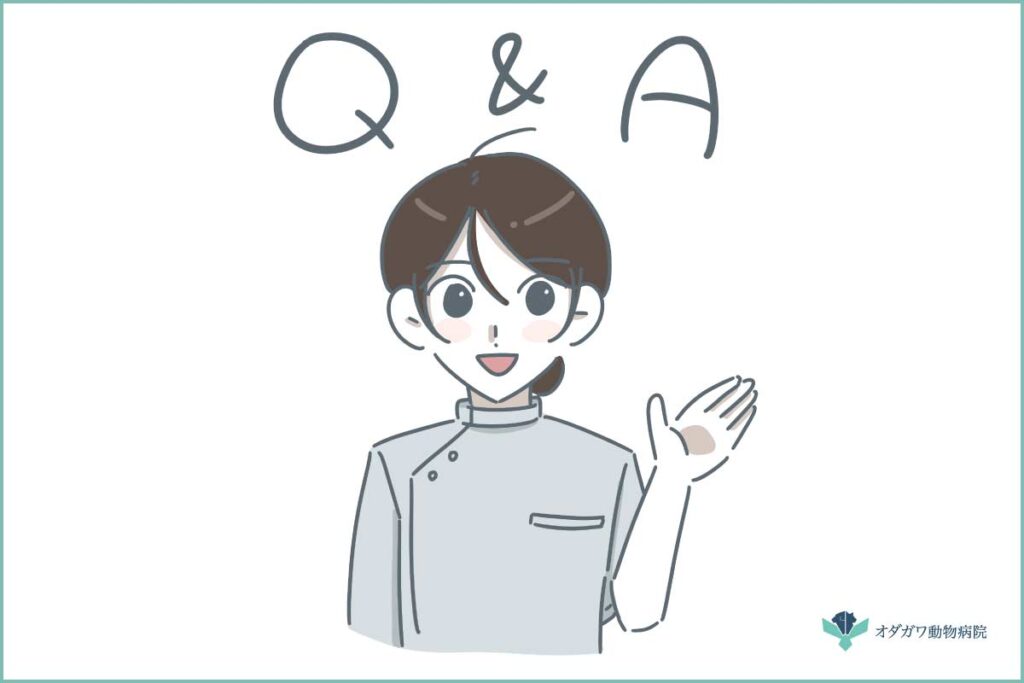
Q1:「震えているけれど元気で食欲もあります。様子を見ていても大丈夫でしょうか?」
A1: 元気で食欲があることは良い兆候ですが、震えが長時間続く場合(2時間以上)や頻発する場合は、念のため動物病院を受診することをお勧めします。
震えの原因が明確で(寒い、興奮しているなど)、原因を取り除くことで改善する場合は、しばらく様子を見ても構いません。ただし、以下の症状が現れた場合は迷わず受診してください
・震えの強さや頻度が増している
・他の症状(嘔吐、下痢、よだれなど)が現れた
・意識状態に変化が見られる
・普段とは明らかに異なる震え方をしている
日頃から愛犬の様子をよく観察し、「いつもと違う」と感じた時は、早めに専門家に相談することが大切です。
Q2:「老犬が最近よく震えるようになりました。これは病気なのでしょうか?」
A2: 高齢犬の震えには、加齢に伴う自然な変化と病気によるものがあります。以下の可能性を考慮して判断しましょう。
加齢による自然な変化
・筋力低下による立ち上がり時の震え
・関節炎による痛みに関連した震え
・寒さに対する敏感性の増加
・軽度の認知機能の低下による不安からの震え
病気の可能性
・神経系疾患の進行
・内臓疾患(肝臓、腎臓など)
・認知症の進行
・疼痛性疾患の悪化
受診の目安: 高齢犬の場合、定期的な健康チェックの一環として獣医師に相談することをお勧めします。特に以下の症状がある場合は早めの受診が必要です:
・食欲や元気の明らかな低下
・歩行困難や立ち上がれない
・夜鳴きや徘徊行動
・排泄の失敗が頻発
・意識状態の変化
高齢犬には個体差があるため、その犬にとって「いつもと違う」状態かどうかが重要な判断基準となります。
Q3:「てんかんと診断されました。完治することはできるのでしょうか?」
A3: てんかんの完治は残念ながら困難ですが、適切な治療により症状をコントロールし、愛犬が快適な生活を送ることは十分に可能です。
てんかんの治療について
薬物治療: 抗てんかん薬により発作の頻度と強度を減らすことができます
継続的な管理: 定期的な血液検査で薬の効果と副作用をモニタリングします
生活環境の調整: ストレス軽減、規則正しい生活リズムの維持が重要です
治療の効果: 多くの犬で抗てんかん薬により発作が大幅に減少し、中には発作がほぼ起こらなくなるケースもあります。ただし、薬は生涯にわたって継続する必要があります。
飼い主ができること
・発作の記録を続ける
・薬の投与を確実に行う
・ストレスの原因を取り除く
・定期的な獣医師のフォローを受ける
てんかんは適切な管理により、犬も飼い主も快適に過ごせる疾患です。獣医師と連携しながら、長期的な視点で治療に取り組んでいきましょう。
Q4:「震えと同時によだれが出ています。緊急性はありますか?」
A4: 震えとよだれが同時に現れる場合は、緊急性が高い状況の可能性があります。以下の点を確認し、該当する場合は直ちに動物病院に連絡してください。
緊急性が高い症状
・大量のよだれが止まらない
・意識が朦朧としている
・呼吸が荒い、または苦しそう
・体温が異常に高い、または低い
・痙攣を起こしている
考えられる原因
・中毒(チョコレート、キシリトールなど)
・熱中症
・てんかん発作の前兆や最中
・口の中の異常(異物、腫瘍など)
・重篤な内臓疾患
応急処置
・涼しく静かな場所に移動
・気道を確保する
・異物が見える場合は取り除く(無理は禁物)
・症状の様子を動画で記録
よだれを伴う震えは、単純な興奮や恐怖以上の原因があることが多いため、迷わず専門家に相談することが重要です。
Q5:「小型犬ですが、よく震えます。犬種による特徴なのでしょうか?」
A5: 確かに小型犬は大型犬に比べて震えやすい傾向があります。これには犬種特有の特徴と体格的要因が関係しています。
小型犬が震えやすい理由
体温調節の特徴
・体表面積が体重に比べて大きく、熱を失いやすい
・皮下脂肪が少なく、寒さに敏感
・筋肉量が少なく、震えによる熱産生に頼りがち
神経系の特徴
・興奮しやすい性格の犬種が多い
・ストレスや不安に敏感
・環境の変化に反応しやすい
遺伝的要因
・特定の犬種では遺伝的に震えが起こりやすい
・チワワ、ポメラニアン、ヨークシャーテリアなどで多く見られる
正常範囲内の震えの特徴
・寒い時や興奮時に一時的に現れる
・原因を取り除くと改善する
・元気や食欲に影響しない
・短時間で自然に治まる
注意が必要な場合: 小型犬だからといって、すべての震えが正常とは限りません。以下の場合は受診を検討してください
・震えが長時間続く(2時間以上)
・他の症状を伴う
・日に日に頻度や強度が増している
・低血糖の症状(ぐったり、意識朦朧)が見られる
小型犬は低血糖を起こしやすいため、震えが見られた時は血糖値の低下も疑い、必要に応じて早めに受診することが大切です。
8. まとめ:愛犬の震えは”サイン”として観察しよう
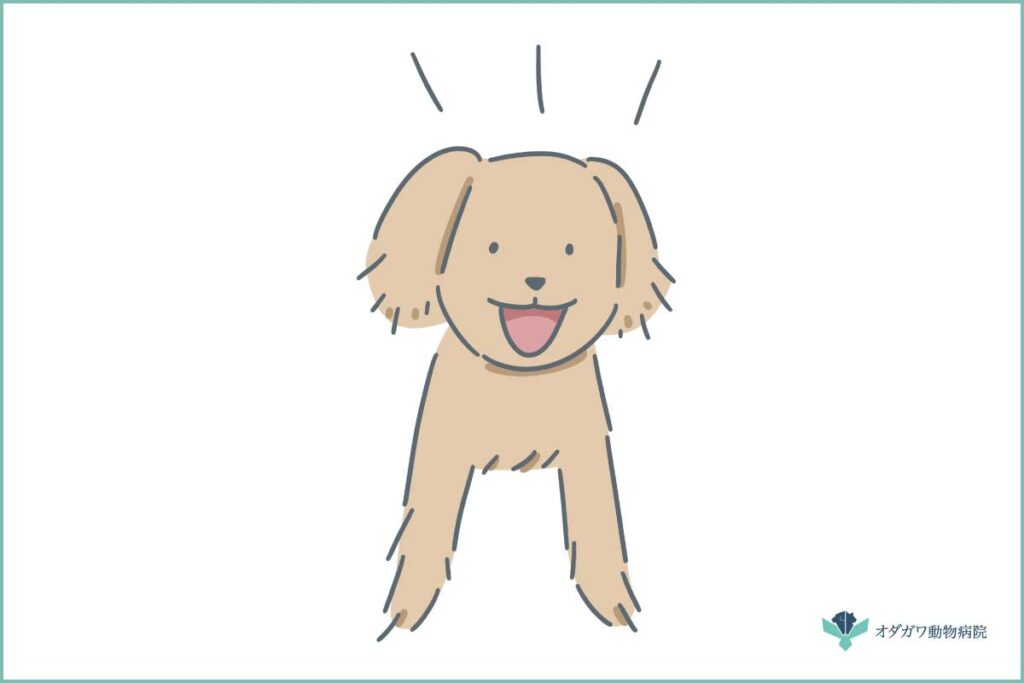
犬の震えは、私たち飼い主に対する大切なメッセージです。単なる寒さや興奮による生理的な反応から、深刻な疾患のサインまで、その原因は多岐にわたります。重要なのは、震えという症状だけで判断するのではなく、愛犬の全体的な状態を総合的に観察することです。
観察のポイントを再確認
日常的な観察項目
・震えの頻度、強度、持続時間
・意識状態と反応性
・食欲、飲水量、排泄の変化
・行動や性格の変化
・体温、呼吸状態
記録の重要性: 症状の記録は、獣医師による正確な診断に欠かせません。スマートフォンでの動画撮影や、症状日記の作成により、客観的な情報を提供できます。特に間欠的に現れる症状の場合、記録があることで診断の精度が大幅に向上します。
早期対応の重要性
震えが病的なものであった場合、早期の発見と治療開始が愛犬の予後を大きく左右します。「様子を見る」ことも時には必要ですが、以下のような変化があった場合は迷わず専門家に相談しましょう。
・症状の悪化や持続
・新たな症状の出現
・日常生活への影響
・飼い主の直感的な不安
愛犬との絆を深める機会として
震えという症状を通じて、愛犬の体調変化により敏感になることは、飼い主としての責任を果たすだけでなく、愛犬との絆を深める機会にもなります。日頃からのスキンシップや観察により、「いつもと違う」変化に気づく力を養いましょう。
専門家との連携
獣医師は愛犬の健康を守るパートナーです。定期的な健康診断を受けることで、震えの背景にある疾患を早期に発見できる可能性が高まります。また、普段から信頼できる動物病院を見つけておくことで、緊急時にも適切な対応を受けることができます。
日常の変化を見落とさない
愛犬の震えは、必ずしも深刻な病気のサインではありません。しかし、軽視してよいものでもありません。大切なのは愛犬の普段の様子をよく知り、変化に敏感になることです。そして、心配な時は迷わず獣医師に相談することです。
適切な観察と記録、そして必要な時の迅速な対応により、愛犬の健康と安心を守ることができます。震えという小さなサインから、愛犬の健康と幸せを守っていきましょう。
参考文献・監修について: この記事の内容は、獣医学的知見に基づいて作成されていますが、個々の症例については必ず獣医師の診察を受けてください。愛犬の健康に関する判断は、信頼できる獣医師との相談の上で行うことをお勧めします。
緊急時連絡先の確保: 愛犬に異常を感じた時のために、かかりつけの動物病院の連絡先を携帯電話に登録し、夜間や休日の緊急診療体制についても事前に確認しておきましょう。