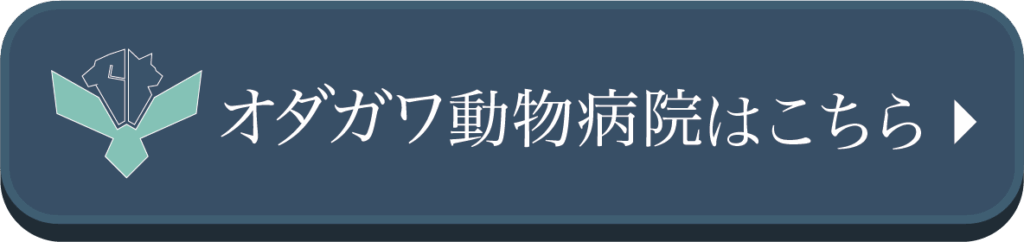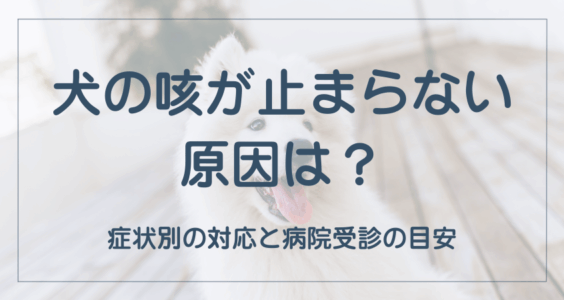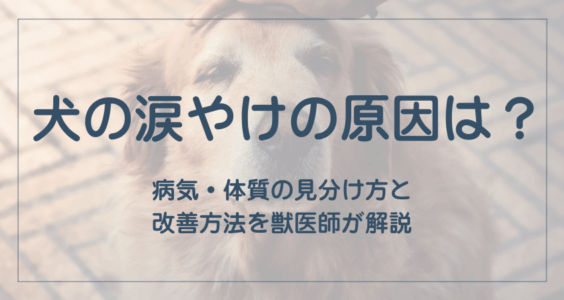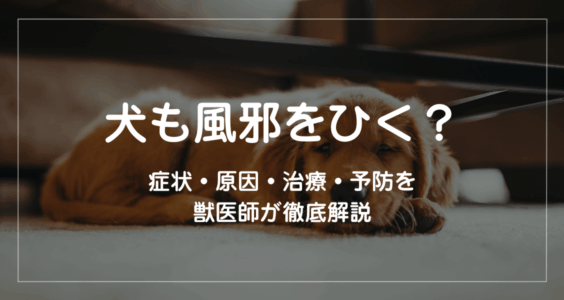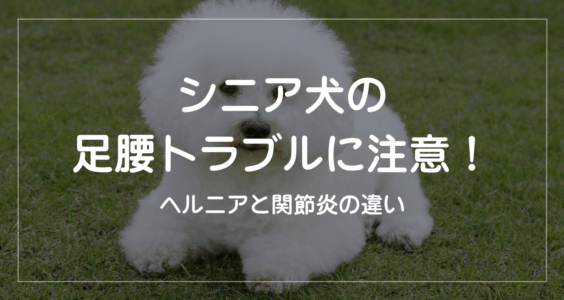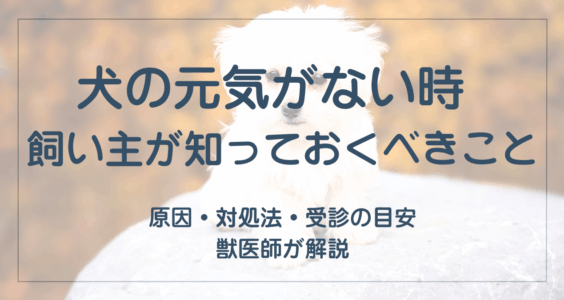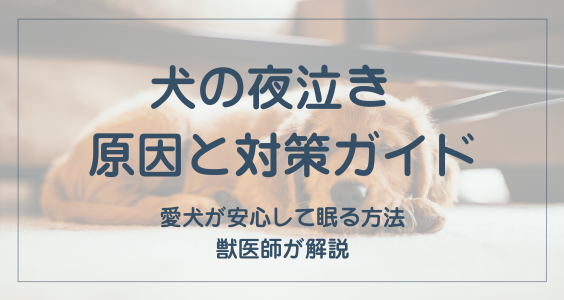痙攣の背景と初期対応
犬の痙攣発作は、「てんかん」だけでなく、低カルシウム血症(低Ca症)、低血糖症、中毒、不整脈など、さまざまな原因によって引き起こされることがあります。
当院では、痙攣が確認された場合、まず飼い主からの稟告(症状の経過や状況)と血液生化学検査を通じて、てんかん以外の病気を鑑別・除外することを優先しています。
その上で、てんかんの可能性が高いと判断された場合には、抗痙攣薬(ジアゼパムなど)の投与を検討します。ただし、これらの薬は「てんかんの維持治療薬」ではなく、緊急時の発作止めとして一時的に使用する薬剤です。
なお、いずれの薬剤も医療用医薬品であるため、処方には必ず診察が必要です。飼い主様ご自身での判断ではなく、必ず動物病院を受診したうえでご相談ください。
緊急受診が必要な痙攣の目安
多くの痙攣は短時間で自然におさまる傾向がありますが、次のような場合には命に関わる可能性があるため、速やかに動物病院を受診してください。
・発作が5分以上続く、または繰り返し起きる(群発発作)
・発作後も意識が回復しない
・1日に複数回痙攣が見られる
・発作中に呼吸困難や失禁を伴う
・発作の頻度が急激に増えている
特に夜間や休日など、通常の診療時間外であっても、緊急対応可能な動物病院を事前に調べておくことをおすすめします。
使用される抗痙攣薬とその特徴
ジアゼパム坐薬

ジアゼパムは、犬において速効性のある短時間作用型の抗痙攣薬として広く使用されています。ヒトでは長時間効果が持続しますが、犬では持続時間が短いため、てんかんの維持管理には適していません。
投与形態
主に動物病院では注射薬として使用されますが、在宅用には坐薬タイプ(写真参照)も処方可能です。
自宅での使用
急な痙攣発作時に、飼い主が肛門から挿入することで発作の進行を抑える目的で使われます。
耐性
連続使用により薬効が低下することが報告されているため、長期使用は推奨されません。
レベチラセタム(イーケプラ®)

ジアゼパムで痙攣が止まらない場合は、次の段階としてレベチラセタム(イーケプラ®)を使用することがあります。
使用方法
緊急時には注射薬を静脈注射します。錠剤は抗てんかん薬の切り替え時や補助的に短期間使用されます。
注意点
長期使用により耐性が生じる可能性があるため、獣医師の指導のもとで管理が必要です。
その他の治療
すべての抗痙攣薬に反応しない場合、麻酔薬による鎮静を行うこともあります。発作の重篤度に応じて、最も適切な薬剤を判断し投与します。
坐薬の基礎知識
坐薬は、薬剤と坐薬基材を均等に混合し、肛門や膣から挿入できるよう成型された外用剤です。体温や分泌物により徐々に溶解・吸収されることで、即効性のある効果を発揮します。
まとめ
犬の痙攣はてんかんに限らず多くの病気のサインであり、誤った対応や遅れた処置が症状の悪化を招くこともあります。発作が起きた際は、まずは冷静に観察し、記録し、早めに動物病院へ相談することが大切です。
また、在宅ケアとしての坐薬処方は、獣医師の診断と処方が必要不可欠です。正しい診断のもと、愛犬に合った治療法を選びましょう。
オダガワ動物病院では、てんかんや痙攣の診療に対応しています。
発作時の不安を減らすため、事前カウンセリングや緊急対応の体制も整えております。気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。