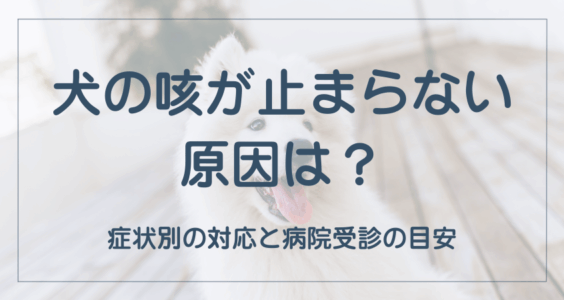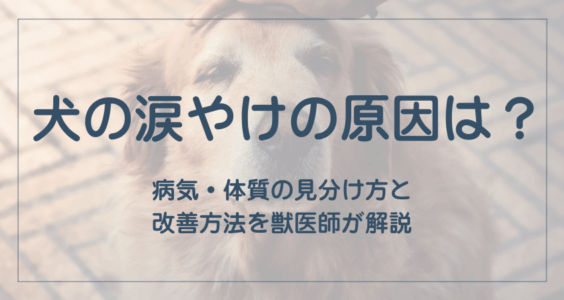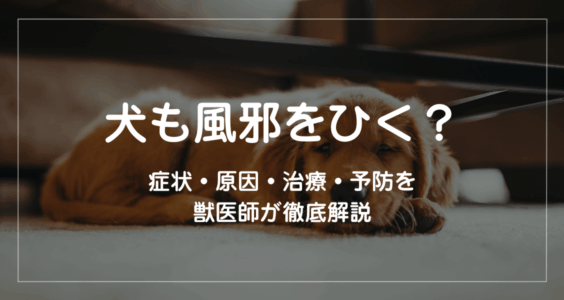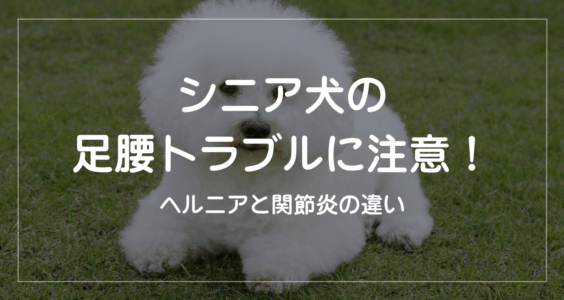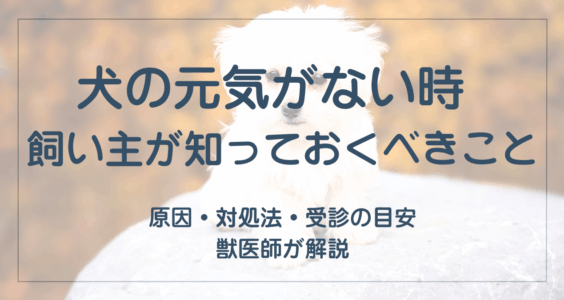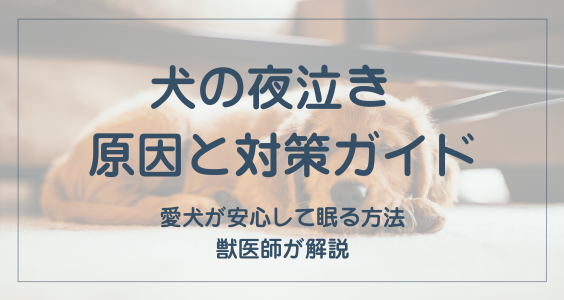愛犬の下痢は、多くの飼い主にとって最も不安を感じる症状の一つです。「なぜ下痢になったの?」「病院に連れて行くべき?」「どのくらい様子を見ていいの?」といった疑問を抱いたことのある飼い主は少なくありません。
犬の下痢は、軽度なものから緊急を要するものまで幅広く、適切な判断と対処が愛犬の健康を守る重要な鍵となります。このガイドでは、犬の下痢の原因から症状の見極め方、自宅でできる対処法、そして受診が必要なタイミングまで、飼い主が安心して判断できる情報を詳しく解説します。
正しい知識を身につけることで、慌てずに適切な対応ができるようになり、愛犬の健康をしっかりと守ることができるでしょう。
犬の下痢、原因はどんなものがある?
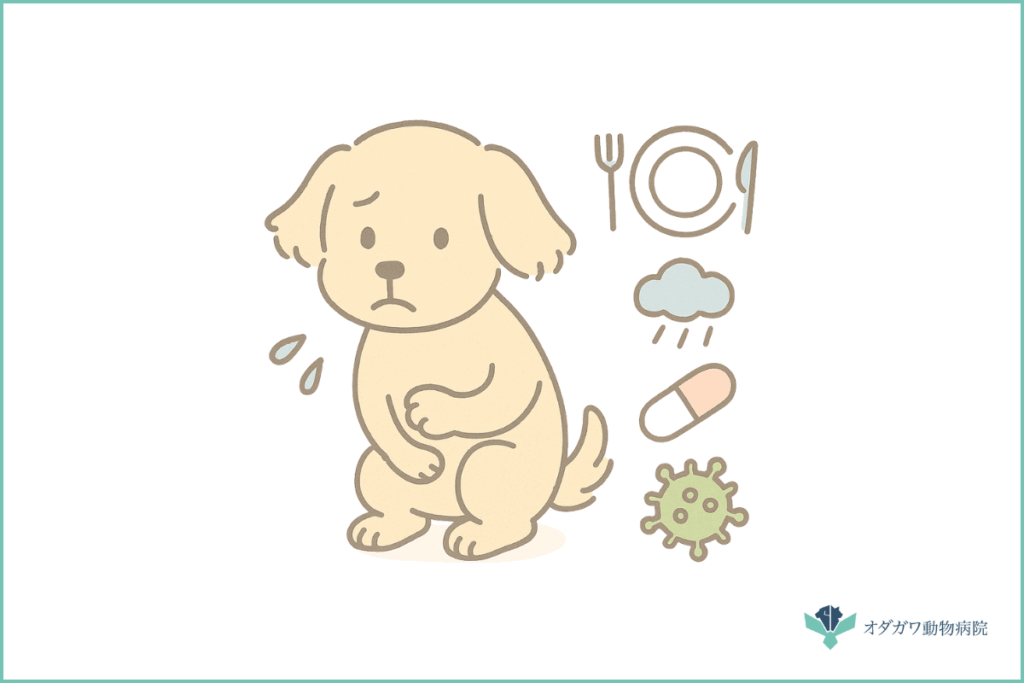
犬の下痢の原因は非常に多岐にわたります。軽度の一過性のものから、治療が必要な重篤なものまで様々です。主な原因を詳しく見ていきましょう。
食事関連の原因
犬の下痢で最も多い原因の一つが食事に関連するものです。
フードの急な変更による下痢
犬の消化器官は敏感で、急激なフードの変更は胃腸に大きな負担をかけます。新しいフードに切り替える際は、1週間程度かけて徐々に混合比率を変えながら慣らしていくことが重要です。現在のフードと新しいフードを7対3の割合から始めて、数日ごとに比率を変えていき、最終的に新しいフードのみにする段階的な切り替えを行うことで、胃腸への負担を軽減できます。
食べ過ぎによる消化不良
犬は本能的に食べ物を見つけると一気に食べてしまう習性があります。食べ過ぎは消化器官に負担をかけ、未消化の食物が腸を刺激して下痢を引き起こします。特に子犬や高齢犬では消化機能が弱いため、適量を守ることが大切です。
脂っこい人間の食べ物の摂取
人間の食事、特に油分の多い食べ物は犬にとって消化が困難です。焼肉、唐揚げ、バター、チーズなど脂肪分の高い食品は膵炎のリスクも高めるため、犬には与えないよう注意が必要です。
食物アレルギー・不耐性
特定の食材に対するアレルギー反応や不耐性により、慢性的な下痢が続く場合があります。よくあるアレルゲンには、牛肉、鶏肉、小麦、大豆、乳製品などがあります。アレルギーが疑われる場合は、除去食試験によって原因を特定することが重要です。
ストレスや環境変化による下痢
犬は環境の変化に敏感で、ストレスが胃腸症状として現れることがあります。
環境の急変によるストレス
引越し、新しい家族の増加、ペットホテルへの預け入れ、長時間の留守番など、犬にとって慣れない環境や状況は大きなストレスとなります。このストレスが自律神経に影響し、腸の動きが活発になって下痢を引き起こすことがあります。
季節の変わり目や気温変化
急激な気温変化や季節の変わり目も、犬の体調に影響を与えます。特に梅雨時期の湿度や気圧の変化、夏から秋への気温変化などは、消化器官の調子を崩しやすい時期です。
感染症・寄生虫・細菌による下痢
感染性の下痢は、特に多頭飼いや子犬で注意が必要です。
ウイルス感染
パルボウイルスは特に子犬に多く、激しい下痢と嘔吐を引き起こす重篤な感染症です。コロナウイルスは比較的軽症ですが、他のウイルスとの混合感染で重症化することもあります。ジステンパーウイルスは下痢以外にも発熱、鼻汁、咳などの症状を伴います。
細菌感染
サルモネラ菌、カンピロバクター、クロストリジウムなどの細菌が原因となる場合があります。特に免疫力の低下している犬や、生肉を摂取した場合にリスクが高まります。
寄生虫感染
回虫は子犬に多く見られ、母犬からの感染や環境からの感染が原因となります。鞭虫は慢性的な下痢を引き起こし、血便を伴うことも特徴的です。ジアルジアは顕微鏡でないと発見が困難な原虫で、慢性下痢の原因となります。コクシジウムは特に子犬に多く、激しい下痢を引き起こす寄生虫です。
異物誤飲・中毒による下痢
好奇心旺盛な犬は、様々なものを口に入れてしまう傾向があります。
異物誤飲
おもちゃの破片、靴下、タオル、石、木の枝など、消化できない物を飲み込むことで腸が刺激され、下痢を引き起こします。場合によっては腸閉塞を起こす危険性もあります。
食べ物による中毒
チョコレート、玉ねぎ、ぶどう、キシリトールなど、犬にとって有毒な食べ物の摂取により下痢が起こります。これらは下痢以外にも重篤な症状を引き起こす可能性があるため、緊急の対応が必要です。
うちの犬がチョコを食べちゃった!焦って駆け込んだダックスフンドのケース
薬物・化学物質の誤飲
人間用の薬、殺虫剤、洗剤、除草剤などの化学物質の誤飲も下痢の原因となります。これらは生命に関わる危険があるため、即座に獣医師の診察を受ける必要があります。
オダガワ動物病院の公式youtubeチャンネル「世界一受けたい動物授業」では、犬に絶対NGな食べ物について説明しています。
内臓疾患・腫瘍など重大な病気
慢性的または重篤な下痢の背景には、深刻な疾患が隠れている場合があります。
膵炎
膵臓の炎症により消化酵素が不足し、消化不良から下痢を引き起こします。脂肪分の多い食事が引き金となることが多く、嘔吐や腹痛を伴うことが特徴です。
炎症性腸疾患(IBD)
腸の慢性炎症により、持続的な下痢が続きます。原因は完全に解明されていませんが、免疫系の異常が関与していると考えられています。
腫瘍
腸管内の腫瘍や、腹腔内の他の臓器の腫瘍が腸を圧迫することで下痢が起こることがあります。特に高齢犬では注意が必要です。
腸重積
腸の一部が隣接する腸管内に入り込んでしまう状態で、激しい下痢と強い腹痛を引き起こします。緊急手術が必要な場合が多い重篤な疾患です。
免疫・内分泌疾患
甲状腺機能低下症、副腎機能不全(アジソン病)、糖尿病などの内分泌疾患も下痢の原因となることがあります。これらは全身症状を伴うことが多く、専門的な治療が必要です。
下痢の種類と危険度の目安
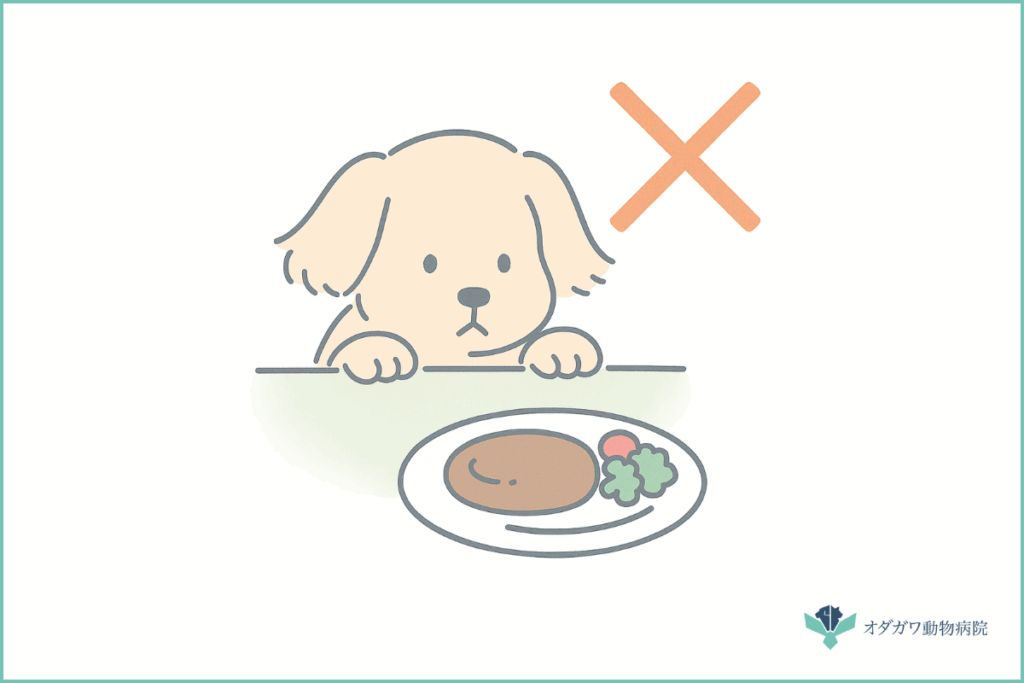
下痢といっても、その程度や性状によって危険度は大きく異なります。適切な対応をするためには、便の状態を正しく観察することが重要です。
軽度軟便(形はあるが柔らかい状態)
特徴と危険度
便に形はあるものの、通常より柔らかく、地面に落とした時に若干つぶれる程度の状態です。色は普段と大きく変わらず、血液や粘液の混入もありません。
危険度:低〜中程度
この程度の軟便であれば、犬の元気や食欲に問題がなく、他の症状を伴わない場合は、1〜2日程度の経過観察が可能です。ただし、高齢犬や子犬、持病のある犬では注意深く観察する必要があります。
考えられる原因
・フードの変更
・軽度の食べ過ぎ
・軽微なストレス
・季節の変わり目
重度軟便(泥状の便)
特徴と危険度
便の形がほとんどなく、泥のような状態で排出されます。量も多くなることがあり、排便時に肛門周囲が汚れやすくなります。
危険度:中〜高程度
腸の機能が相当低下している状態を示しており、放置すると脱水症状を引き起こす可能性があります。24時間以内に改善傾向が見られない場合は、獣医師の診察を受けることをお勧めします。
考えられる原因
・食事性の胃腸炎
・ストレス性の腸炎
・軽度の感染症
・食物アレルギーの初期症状
水様性下痢(液状の便)
特徴と危険度
便が完全に液体状になり、水のように流れ出る状態です。コントロールが困難で、頻回に排便することが多くなります。
危険度:高
大量の水分と電解質が失われるため、急速に脱水症状が進行する危険があります。特に子犬や高齢犬、小型犬では生命に関わることもあるため、できる限り早期の受診が必要です。
考えられる原因
・重度の感染症(パルボウイルスなど)
・食中毒
・重篤な内臓疾患
・毒物の摂取
血便・黒色便
血便(鮮血便)の特徴
明らかに血液が混じった便や、鮮やかな赤色の血液が便に付着している状態です。血液の量や色によって出血部位をある程度推測できます。
黒色便(タール便)の特徴
黒色便(タール便)の特徴:便が真っ黒でタール状になります。これは上部消化管(胃や小腸上部)からの出血が原因ですが、鉄剤や活性炭の投与後でも黒くなることがあるため、受診時には服薬状況も伝えましょう。
危険度:非常に高い
どちらも消化管内での出血を示しており、緊急に獣医師の診察が必要です。出血量が多い場合は、ショック状態に陥る可能性もあります。
考えられる原因
鮮血便の場合
・大腸炎
・肛門周囲の裂傷
・腫瘍
・寄生虫感染
黒色便の場合
・胃潰瘍
・胃腫瘍
・異物による胃腸の損傷
・血液凝固障害
自宅でできる対処と様子見ポイント
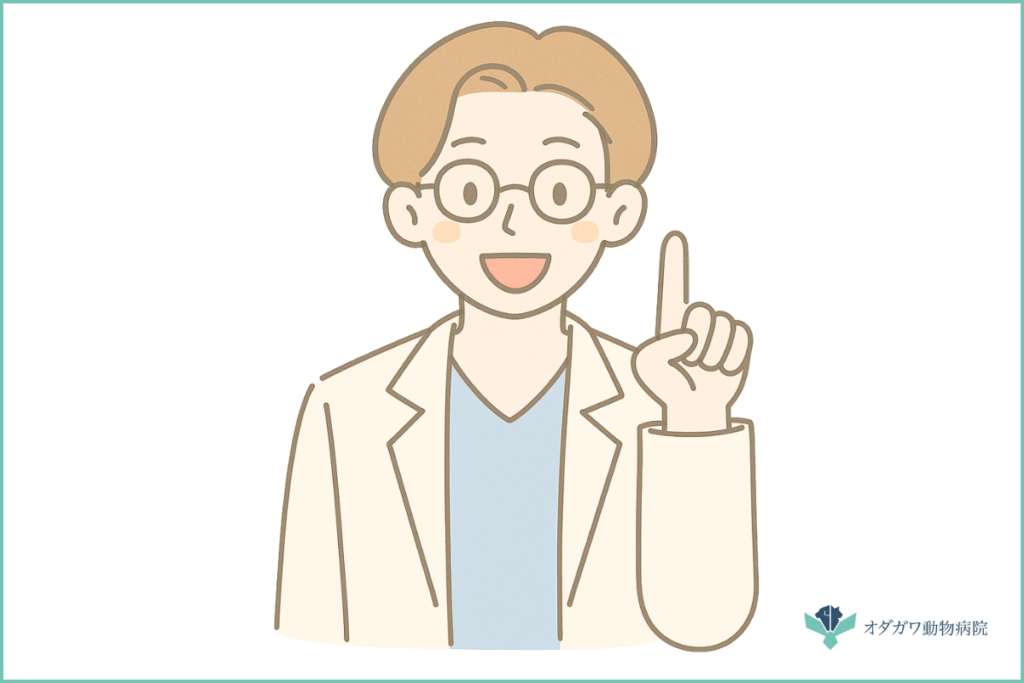
軽度の下痢の場合、適切な自宅ケアにより改善することがあります。ただし、様子見をする場合の条件と限界を理解することが重要です。
経過観察できる場合の条件
基本的な条件
自宅での経過観察を行う場合は、いくつかの重要な条件をすべて満たしている必要があります。まず、犬が元気があり普段と変わらない活動レベルを保っていること、食欲があり水も正常に飲んでいることが前提となります。また、嘔吐を伴わず、血便や黒色便でもないこと、発熱がないこと(鼻が湿っており、耳が熱くない)、1日の排便回数が3回以下であることも重要です。排便以外の時間は普段通りに過ごしているかどうかも観察のポイントです。
観察期間の目安
上記の条件を満たしている場合でも、経過観察の期間は最大24〜48時間程度に留めるべきです。改善の兆しが見られない場合や、少しでも悪化する傾向があれば、速やかに獣医師の診察を受けましょう。
自宅ケアの具体例
食事管理の方法
絶食について 軽度の下痢の場合、12〜24時間の絶食により胃腸を休めることが効果的です。ただし、子犬(6ヶ月未満)や糖尿病の犬、極度に小さい犬種では絶食は危険な場合があるため、必ず獣医師に相談してください。
消化に優しい食事への切り替え 絶食後の食事再開時は、消化に優しい食材を少量ずつ与えます。白米のお粥(塩分なし)、茹でた鶏胸肉(皮と脂肪を除去)、蒸したかぼちゃやさつまいもなどが適しています。普段の1/3程度の量を1日3〜4回に分けて与え、一度に大量に食べさせないよう注意が必要です。
適切な水分補給
下痢により水分が失われるため、十分な水分補給が必要です。ただし、一度に大量に飲ませると嘔吐を誘発する可能性があるため、少量ずつ頻繁に与えることが大切です。新鮮な水を常に用意し、水温は常温が望ましく、氷水や熱い水は避けるべきです。経口補水液の使用については獣医師と相談することをお勧めします。
排便後の清潔ケア
下痢の際は肛門周囲が汚れやすく、皮膚炎や感染症の原因となることがあります。清拭の際はぬるま湯で湿らせたタオルで優しく拭き取り、アルコール系のウェットティッシュは刺激が強いため避けましょう。清拭後は完全に乾燥させ、必要に応じてワセリンなどで保護することも有効です。
環境整備
トイレ環境
・トイレシーツを多めに敷き、汚れたらすぐに交換
・滑りにくい床材を使用
・トイレまでの動線を確保
休息環境
・静かで落ち着ける場所を確保
・適温を維持(暑すぎず寒すぎず)
・他のペットとの接触を制限
様子見の限界と判断基準
以下のような症状が現れた場合は、すぐに経過観察を中止し、獣医師の診察を受けてください。元気や食欲の明らかな低下、嘔吐の開始、血便や黒色便の出現、下痢の頻度や量の増加、体温の変化(発熱や低体温)、ぐったりした様子などが該当します。適切な自宅ケアにより、24時間以内に便の回数の減少、便の形状の改善(水様→泥状→軟便)、元気や食欲の回復、普段の行動パターンへの復帰といった改善が見られることが理想的です。
病院に行くべきサインとタイミング
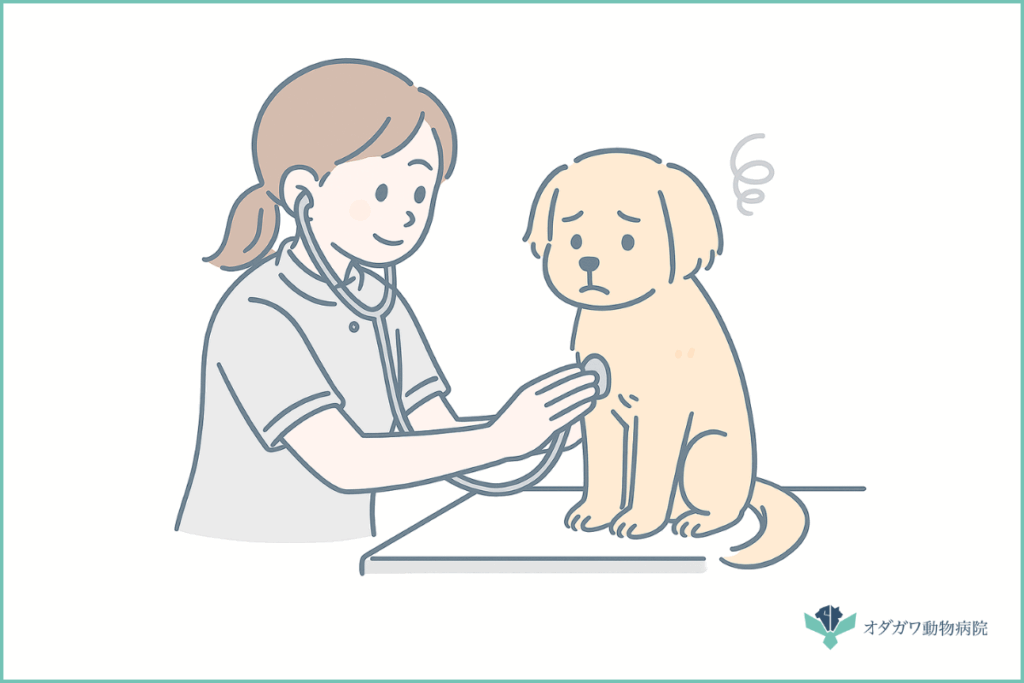
下痢の症状において、獣医師の診察が必要な状況を正しく判断することは、愛犬の生命を守る上で非常に重要です。
すぐに受診が必要な症状
血便・黒色便が見られる場合
血便や黒色便は消化管内での出血を示す重要なサインです。
鮮血便の特徴と緊急度
・便に鮮やかな赤い血が混じっている
・血液の量が多い場合は特に危険
・大腸や直腸からの出血が疑われる
・即座の受診が必要
黒色便(タール便)の特徴と緊急度
・便が真っ黒でタールのような光沢がある
・胃や小腸上部からの出血を示す
・より深刻な状態を表すことが多い
・緊急受診が必要
嘔吐を伴う頻回の下痢
下痢と嘔吐が同時に起こる場合、急速な脱水進行のリスクが高まります。
危険な症状の組み合わせ
・1時間に複数回の嘔吐
・水様性の下痢が続く
・水を飲んでもすぐに嘔吐してしまう
・明らかな腹痛の症状(背中を丸める、うめき声など)
ぐったりしている・食欲が全くない
犬の全身状態の悪化を示すサインです。
注意すべき全身症状
・普段より明らかに元気がない
・好物にも全く興味を示さない
・水も飲みたがらない
・歩き方がふらつく
・反応が鈍い
脱水症状の兆候
下痢による水分喪失が進行すると、脱水症状が現れます。
脱水症状のチェック方法
・首の後ろの皮膚をつまんで離し、戻りが遅い(2秒以上)
・口の中が乾燥している
・目が落ちくぼんでいる
・尿量の減少または無尿
特別な注意が必要な犬種・年齢
子犬(生後6ヶ月未満)
子犬は成犬と比較して免疫力が低く、脱水に対する耐性も低いため、特に注意が必要です。
子犬の下痢で注意すべき点
・症状の進行が早い
・脱水症状が急速に進む
・低血糖のリスクが高い
・感染症の可能性が高い
・軽度の症状でも早期受診を推奨
高齢犬(7歳以上)
高齢犬は基礎体力や免疫力の低下により、下痢による体調悪化が起こりやすくなります。
高齢犬の下痢で注意すべき点
・回復力の低下
・他の慢性疾患との合併症リスク
・薬物代謝能力の低下
・腫瘍性疾患の可能性
・早めの診察と検査が推奨
持病を持つ犬
既存の疾患がある犬では、下痢により基礎疾患が悪化するリスクがあります。
特に注意が必要な基礎疾患
・糖尿病(血糖値の管理が困難になる)
・腎臓病(脱水により腎機能が悪化)
・心疾患(体液バランスの崩れが心臓に負担)
・肝疾患(栄養吸収不良により肝機能が低下)
・免疫抑制状態(ステロイド治療中など)
症状の持続期間による判断
軟便が3日以上続く場合
軽度の軟便であっても、3日以上改善が見られない場合は、何らかの基礎疾患が存在する可能性があります。
考えられる原因
・慢性的な食物アレルギー
・炎症性腸疾患の初期
・寄生虫感染
・ストレス性の胃腸炎
再発を繰り返す場合
一度改善した下痢が短期間で再発する場合も、専門的な検査が必要です。
繰り返す下痢の特徴
・2週間以内に同様の症状が2回以上発生
・治療により一時的に改善するが再燃
・特定の食事やストレスが引き金となっている
・慢性疾患の可能性が高い
緊急受診のタイミング
以下の症状が見られた場合は、時間に関係なく緊急受診を検討してください。
夜間・休日でも緊急受診すべき症状
・大量の血便
・激しい嘔吐と下痢の同時発生
・ぐったりして立ち上がれない
・痙攣や意識障害
・明らかな腹部の痛み(触ると嫌がる、背中を丸める)
・呼吸困難
・体温の著しい変化(39.5度以上の発熱、または36度以下の低体温)
病院での診察と検査で何ができる?
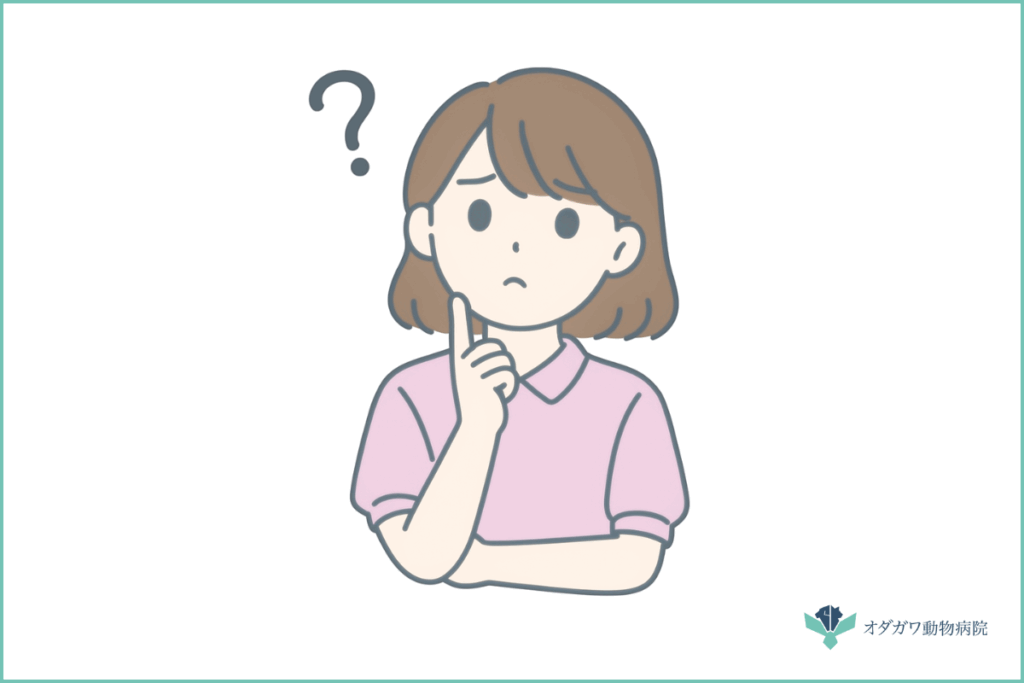
獣医師による専門的な診察では、下痢の原因を特定し、適切な治療を行うための様々な検査が実施されます。
問診と便の観察
詳細な問診の内容
獣医師は下痢の原因を特定するため、以下のような詳細な問診を行います。
症状に関する質問
・いつから下痢が始まったか
・下痢の頻度と量
・便の色、におい、性状の変化
・血液や粘液の有無
・嘔吐の有無とタイミング
・食欲や元気の変化
生活環境に関する質問
・最近の食事の変更
・散歩コースや環境の変化
・他の動物との接触
・誤食の可能性
・ストレスの原因
既往歴に関する質問
・過去の下痢の経験
・現在の投薬状況
・ワクチン接種歴
・最近の健康診断結果
便の持参と写真による状態共有
正確な診断のためには、便の実物や写真の持参が非常に有効です。
便の持参方法
・新鮮な便(採取後2時間以内)をビニール袋に入れて持参
・冷蔵保存(冷凍は避ける)
・量は小指の先程度で十分
写真撮影のポイント
・自然光の下で撮影
・便の全体像がわかるように
・色調が正確に写るように設定
・複数の角度から撮影
実施される検査の種類
糞便検査(便検査)
糞便検査は下痢の原因を特定する最も基本的で重要な検査です。
直接塗抹検査
・顕微鏡で便を直接観察
・細菌、寄生虫、真菌の検出
・白血球や赤血球の有無
・脂肪球や未消化物の確認
浮遊法検査
・寄生虫の卵や嚢子を検出
・回虫、鞭虫、コクシジウムなど
・より正確な寄生虫診断が可能
培養検査
・特定の細菌の検出と同定
・薬剤感受性試験
・治療薬の選択に有用
・結果判明まで数日を要する
血液検査
全身状態の把握と内臓疾患の除外診断のために実施されます。
一般血液検査(CBC)
・白血球数:感染症や炎症の指標
・赤血球数・ヘマトクリット値:貧血の有無
・血小板数:出血傾向の評価
血液生化学検査
・肝機能(ALT、AST、ALP)
・腎機能(BUN、クレアチニン)
・電解質(Na、K、Cl)
・血糖値
・総蛋白、アルブミン
特殊検査
・膵炎の診断(リパーゼ、cPLI)
・炎症マーカー(CRP)
・アレルギー検査(IgE)
画像診断
内臓の状態や異物の有無を確認するために実施されます。
レントゲン検査
・腸管の拡張や閉塞の有無
・異物の存在確認
・腫瘤の検出
・腹水の有無
超音波検査
・腸壁の厚さや構造の評価
・腸管内容物の動き
・腹腔内臓器の詳細観察
・血流の評価
CT・MRI検査
・より詳細な内臓構造の評価
・腫瘍の広がりや転移の確認
・複雑な症例での精密診断
原因に応じた治療法
検査結果に基づいて、個々の原因に応じた治療が選択されます。
投薬治療
対症療法として、整腸剤(プロバイオティクス)や胃腸保護薬が用いられることがあります。原因治療薬としては、細菌感染の場合は抗生物質、寄生虫感染の場合は抗寄生虫薬、炎症性疾患の場合は抗炎症薬、自己免疫性疾患の場合は免疫抑制薬が選択されます。
輸液治療
脱水症状が認められる場合や、嘔吐により経口摂取が困難な場合には、点滴による輸液治療が実施されます。電解質バランスの補正や栄養補給により、体調の回復を促進します。重度の脱水では入院での継続的な輸液管理が必要となることもあります。
食事療法
消化器疾患の治療において、食事療法は非常に重要な役割を果たします。消化しやすい療法食への変更、アレルギー対応の除去食、高繊維食による腸内環境の改善などが、症状に応じて選択されます。食事の回数や量の調整も同時に行われ、胃腸への負担を最小限に抑えます。
外科治療
腸重積、異物の除去、腫瘍の摘出など、内科的治療では対応できない場合には外科手術が必要となります。これらは緊急性の高い処置であることが多く、迅速な判断と対応が求められます。
予防と再発防止のために
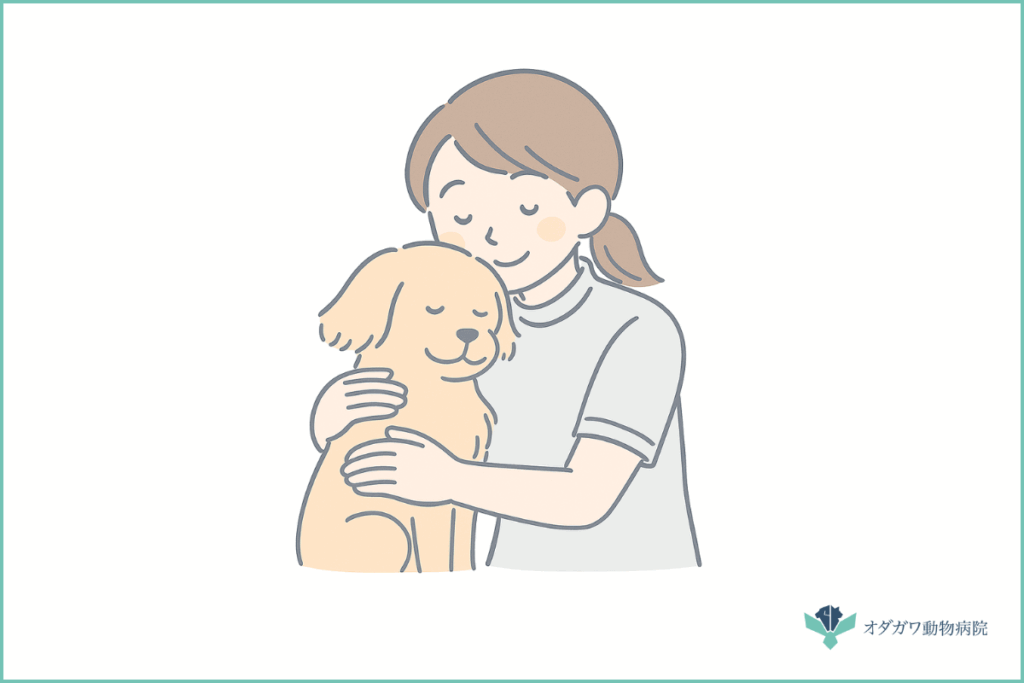
下痢の予防は、日頃の適切な管理と注意により大幅にリスクを減らすことができます。
フードの適切な管理
段階的なフード変更の重要性
新しいフードへの切り替えは、犬の消化器官に与える影響を最小限に抑えるため、必ず段階的に行うことが重要です。1週間から10日程度の期間をかけて、現在のフードに少しずつ新しいフードを混ぜながら比率を変えていきます。この方法により、腸内細菌叢が新しい食材に徐々に適応し、消化不良による下痢を防ぐことができます。
給餌量と回数の管理
適切な給餌量は犬の年齢、体重、活動量に応じて決定されます。一度に大量の食事を与えると消化器官に負担をかけるため、1日の食事量を2〜3回に分けて与えることが推奨されます。特に大型犬では胃捻転のリスクもあるため、食後の激しい運動は避け、落ち着いた環境で食事をさせることが大切です。
人間の食べ物を与えないルールの徹底
人間の食べ物、特に脂肪分の多い食品や調味料を使った料理は、犬の消化器官には適さず、下痢の原因となります。家族全員でルールを徹底し、テーブルからの食べ物やおやつの与えすぎにも注意が必要です。犬専用のおやつであっても、カロリーオーバーにならないよう適量を守ることが重要です。
獣医師おすすめのフードはこちら↓

定期的な予防医療
ワクチン接種の重要性
パルボウイルス、ジステンパー、アデノウイルスなど、重篤な下痢を引き起こすウイルス感染症は、獣医師の指示に従ったワクチン接種で予防可能です。
犬コロナウイルスは軽症例が多く、現在はコアワクチンには含まれない場合が多いため、接種の必要性は獣医師と相談してください。
定期的な駆虫の実施
寄生虫感染は外見からは判断が困難で、慢性的な下痢の原因となります。年に2〜4回の定期的な便検査と駆虫により、寄生虫感染を早期に発見・治療することができます。特に多頭飼いの環境や、野外での活動が多い犬では、より頻繁な検査が推奨されます。
環境整備と誤飲防止
生活環境の安全確保
犬の手の届く場所に、誤飲の可能性がある小さな物や有害な物質を置かないことが基本です。ゴミ箱にはふたをし、薬類は犬の手の届かない場所に保管します。散歩中も、道に落ちているゴミや食べ物を拾い食いしないよう、常に注意を払うことが重要です。
おもちゃ用品の安全点検
犬用のおもちゃ用品も定期的に点検し、破損や劣化による部品の脱落がないかを確認します。特にロープ状のおもちゃやぬいぐるみは、糸くずや詰め物が腸に詰まる可能性があるため、使用後は必ず片付け、損傷が見つかった場合は速やかに処分します。
ストレス管理と環境調整
規則正しい生活リズムの維持
犬は規則正しい生活を好む動物です。食事、散歩、睡眠の時間を一定に保つことで、ストレスを軽減し、消化器官の健康を維持できます。突然の環境変化が避けられない場合は、事前に少しずつ慣らしていく工夫が大切です。
適度な運動と精神的刺激
適切な運動量は犬の身体的健康だけでなく、精神的な安定にも重要な役割を果たします。犬種や年齢に応じた運動量を確保し、知育玩具やトレーニングなどを通じて精神的な刺激も与えることで、ストレス性の胃腸症状を予防できます。
定期健康診断の重要性
年齢に応じた健診頻度
7歳未満の健康な犬では年1回、7歳以上の高齢犬では年2回の定期健康診断が推奨されます。血液検査、便検査、身体検査により、病気の早期発見と予防が可能になります。特に中高齢犬では、癌や内分泌疾患などの重篤な病気が下痢の原因となることもあるため、定期的なチェックが重要です。
日頃の健康観察
飼い主による日常の健康観察も、早期発見には欠かせません。食欲、元気、排便の状態、体重の変化など、普段の様子をよく観察し、わずかな変化にも気づけるよう心がけましょう。変化を記録しておくことで、獣医師への相談時により正確な情報を提供できます。
まとめ
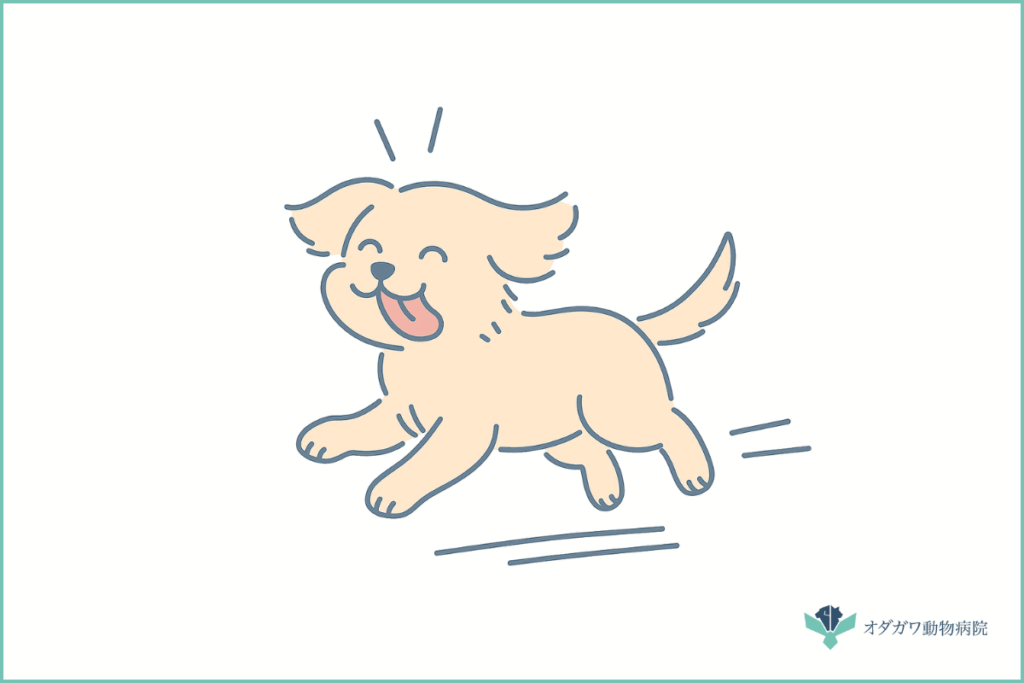
犬の下痢は、軽度の一過性のものから生命に関わる重篤な疾患まで、実に様々な原因により引き起こされる症状です。食事の変更や軽度のストレスによる軽微な下痢であれば、適切な自宅ケアにより改善することも多くあります。しかし、血便、激しい嘔吐、脱水症状、ぐったりした様子など、重篤なサインが見られる場合は「迷ったらすぐ受診」を最優先に考える必要があります。
特に子犬や高齢犬、持病のある犬では、症状の進行が早く、重篤化するリスクが高いため、軽度の症状であっても早めの受診を検討することが大切です。また、軽度の軟便であっても3日以上続く場合や、短期間で再発を繰り返す場合は、何らかの基礎疾患が隠れている可能性があるため、専門的な検査を受けることをお勧めします。
予防の観点では、適切な食事管理、獣医師の指示に基づいたワクチン接種と定期的な駆虫、生活環境の安全確保、ストレス管理、そして年齢に応じた健康診断が重要です。これらの取り組みにより、多くの下痢は予防することができ、万が一発症した場合でも早期発見・早期治療により重篤化を防ぐことができます。
愛犬の健康を守るためには、飼い主の正しい知識と日頃の観察が何よりも重要です。普段の様子をよく観察し、少しでも異常を感じたら獣医師に相談することで、愛犬の健康で幸せな生活を支えることができるでしょう。犬の下痢について正しい理解を持ち、適切な対応ができるよう、このガイドを参考にしていただければ幸いです。