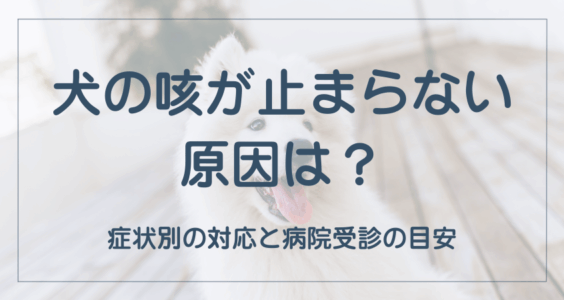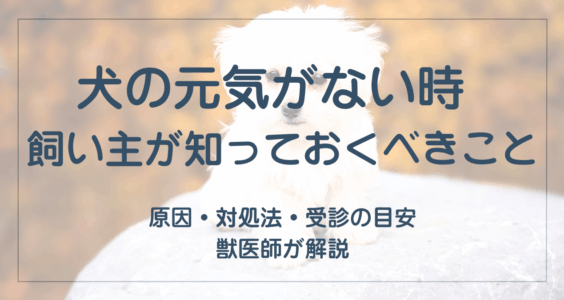愛犬が突然くしゃみをしたり、鼻水を垂らしている姿を見ると、飼い主としては「風邪をひいたのかな?」と心配になりますよね。人間と同じように、犬も体調を崩すことがあります。しかし、犬の「風邪」は人間が想像するものとは少し違う面があることをご存知でしょうか。
この記事では、犬の風邪について、症状の見分け方、原因、適切な対処法、そして予防策まで詳しく解説していきます。大切な家族の健康を守るために、正しい知識を身につけておきましょう。
犬の「風邪」とは?

犬に「風邪」という正式病名はない
実は、獣医学の世界では「犬の風邪」という正式な病名は存在しません。これは人間の医学でも同じで、私たちが日常的に使う「風邪」という言葉は、実は複数の症状をまとめて呼ぶ通称なのです。飼い主さんが「うちの子が風邪をひいた」と表現するとき、それは鼻水、くしゃみ、咳といった上気道の症状が出ている状態を指しています。
獣医師が診察で「風邪のような症状ですね」と説明するのは、飼い主さんに分かりやすく伝えるための配慮であり、正確には別の医学用語を使って診断を行っています。
医学的には上部気道炎・ケンネルコフ・ウイルス感染のこと
犬が風邪に似た症状を示すとき、獣医師は「上部気道炎」という診断名を使うことが多いです。これは鼻から喉、気管の上部にかけての炎症を指します。また、複数の犬が集まる環境で感染が広がる「ケンネルコフ」という病気も、風邪症状を引き起こす代表的な疾患です。
ケンネルコフは、パラインフルエンザウイルスやアデノウイルス2型、ボルデテラ・ブロンキセプティカという細菌などが単独または複合的に感染することで発症します。ペットホテルやドッグラン、動物病院の待合室など、多くの犬が集まる場所で感染リスクが高まるため、このような名前で呼ばれています。
その他にも、犬ジステンパーウイルスや犬アデノウイルス1型など、より深刻な感染症の初期症状として風邪に似た症状が現れることもあります。これらは適切なワクチン接種によって予防可能な疾患ですが、未接種の犬や免疫力が低下している犬では注意が必要です。
人の風邪は基本うつらない(逆も同じ)
多くの飼い主さんが心配されるのが、「自分の風邪が犬にうつるのでは?」あるいは「犬の風邪が家族にうつらないか?」という点です。基本的に、人間の風邪ウイルスと犬の呼吸器感染症を引き起こす病原体は種特異性が高く、種を超えて感染することはほとんどありません。
人間の風邪の主な原因であるライノウイルスやコロナウイルス(一般的な風邪のコロナウイルスであり、COVID-19とは別のものです)は、犬には感染しません。同様に、犬のパラインフルエンザウイルスやボルデテラ菌は、通常人間には感染しないとされています。
ただし、非常に稀なケースとして、インフルエンザウイルスの一部の型が種を超えて感染する可能性が研究されています。しかし、これは例外的な事例であり、日常生活で過度に心配する必要はありません。それでも、体調不良のときは念のため、ペットとの過度な密接接触は控え、手洗いなどの基本的な衛生管理を心がけると良いでしょう。
犬の風邪が悪化して肺炎になるケースもある
軽い風邪症状だと思って様子を見ているうちに、症状が悪化して肺炎に進行してしまうケースは決して珍しくありません。特に子犬や高齢犬、基礎疾患のある犬、短頭種では、上気道の炎症が下気道へと広がりやすい傾向があります。
最初は軽い咳や鼻水程度だったものが、数日のうちに呼吸が荒くなり、食欲不振や発熱を伴うようになると、肺炎を疑う必要があります。肺炎は命に関わる重篤な状態に発展する可能性があるため、早期発見と適切な治療が不可欠です。
「ただの風邪だから」と軽く考えず、症状の変化を注意深く観察し、悪化の兆候が見られたらすぐに動物病院を受診することが、愛犬の健康を守る上で非常に重要です。
なお、風邪のときに多い「食欲が落ちる」「元気がない」については、
こちらの食欲不振のコラムでも詳しく解説しています。
耳を掻く・頭を振るなどの症状がある場合は 外耳炎の可能性 もあります。
犬の風邪によくある症状チェック

愛犬の体調変化にいち早く気づくためには、風邪の典型的な症状を知っておくことが大切です。以下の症状が一つでも見られたら、注意深く観察を続けましょう。
咳(乾性/湿性)
咳は犬の風邪症状として最も多く見られるサインの一つです。咳には大きく分けて二つのタイプがあります。乾性咳嗽と呼ばれる「コンコン」「ケホケホ」という乾いた咳と、湿性咳嗽と呼ばれる「ゴホゴホ」という痰が絡んだような湿った咳です。
乾性の咳は、気道の炎症や刺激によって引き起こされることが多く、ケンネルコフの初期症状として典型的です。まるで何かが喉に引っかかっているような、「カッカッ」という独特な咳をすることもあります。これは逆くしゃみと間違えられることもありますが、頻度や前後の症状で区別できます。
一方、湿性の咳は、気道内に分泌物が溜まっている状態を示唆します。細菌感染が加わっていたり、炎症が進行して膿性の分泌物が増えている可能性があります。咳の後に何かを吐き出すような仕草をしたり、実際に粘液状のものを吐き出すこともあります。
咳が夜間や早朝に悪化する場合、あるいは興奮したときや首輪を引っ張ったときに咳き込む場合は、気管の炎症が強いことを示しています。また、横になると咳が出やすくなるのは、呼吸器疾患が進行しているサインかもしれません。
鼻水(透明→黄色は要注意)
鼻水の性状は、病気の進行度を知る重要な手がかりになります。風邪の初期段階では、透明でサラサラとした鼻水が出ることが多いです。これはウイルス感染による炎症反応で、鼻粘膜が刺激されて分泌物が増えている状態です。
しかし、透明だった鼻水が白濁したり、黄色や緑色に変化してきたら注意が必要です。これは細菌の二次感染が起きているサインで、単純なウイルス性の風邪から細菌性の上気道炎へと進行している可能性があります。黄色や緑色の鼻水は膿を含んでおり、より積極的な治療が必要な状態です。
鼻水の量にも注目しましょう。少量がときどき出る程度なら経過観察で良いかもしれませんが、常に鼻が濡れていて拭いても拭いても出続ける状態や、鼻水で鼻が詰まって口呼吸をしている場合は、早めの受診をお勧めします。
また、片側だけから鼻水が出る場合は、風邪ではなく鼻腔内の異物や腫瘍、歯の病気が原因である可能性も考えられます。このような場合は、症状が軽くても一度診察を受けることが大切です。
くしゃみが続く
くしゃみも犬の風邪症状として一般的です。1日に数回程度のくしゃみなら、ホコリや花粉などの一時的な刺激によるものかもしれません。しかし、連続して何度もくしゃみをしたり、毎日継続的にくしゃみが出る場合は、上気道の炎症を疑います。
犬のくしゃみは短い音から豪快なものまで、個体によってさまざまです。くしゃみの際に鼻水や鼻血が飛び散る場合は、鼻粘膜の炎症が強いことを示しています。
興味深いことに、犬は遊びや興奮状態のときにもくしゃみをすることがあります。これは「プレイスニーズ」と呼ばれ、攻撃的な意図がないことを示すカーミングシグナルの一種です。病的なくしゃみとの違いは、頻度と前後の状況で判断できます。
くしゃみに加えて鼻をこする仕草が増えたり、前足で顔を何度も拭う動作が見られる場合は、鼻や目に強い不快感があることを示しています。このような行動の変化も、体調不良のサインとして見逃さないようにしましょう。
発熱(体温の測り方)
犬の正常体温は37.5度から39.2度程度で、人間よりも高めです。個体差や測定時の状況によっても変動しますが、39.5度以上になると発熱と判断されます。風邪症状とともに発熱がある場合は、感染症が進行していることを示唆します。
家庭で犬の体温を測る場合、最も正確なのは直腸温です。動物用の体温計を使い、先端にワセリンなどの潤滑剤を塗って、肛門から2〜3センチほど挿入して測定します。ただし、犬が嫌がって暴れると危険なので、無理に測ろうとせず、動物病院での測定をお願いするのも良いでしょう。
最近では、耳で測るタイプの非接触体温計もありますが、犬の耳道の構造や被毛の影響で、直腸温に比べると精度が劣ることがあります。あくまで目安として使用し、正確な体温が知りたい場合は動物病院で測定してもらいましょう。
発熱に気づくサインとして、耳や腹部を触ったときにいつもより熱く感じることがあります。また、元気がなくぐったりしている、震えている、呼吸が荒いといった症状を伴うことも多いです。体温が40度を超える高熱の場合は、緊急性が高いため、すぐに動物病院に連絡してください。
呼吸が早い・苦しそう(※危険サイン)
安静時の犬の呼吸数は、1分間に15〜30回程度が正常範囲です。しかし、風邪による呼吸器の炎症や発熱によって、呼吸数が増加することがあります。特に、何もしていないのに口を開けてハァハァと速い呼吸をしている場合は注意が必要です。
呼吸の異常を見分けるポイントはいくつかあります。胸やお腹の動きがいつもより大きく、努力して呼吸している様子が見られる場合、これは呼吸困難のサインです。また、首を伸ばして呼吸しようとしたり、前足を突っ張って立った姿勢を保とうとする場合も、呼吸が苦しいことを示しています。
特に注意すべきは、舌や歯茎の色が紫がかったり青白くなる「チアノーゼ」という状態です。これは体内に酸素が十分に行き渡っていないことを示す緊急事態で、すぐに動物病院に連絡し、可能な限り早く受診する必要があります。
短頭種のフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリア、ペキニーズなどは、もともと呼吸器の構造上、呼吸効率が良くありません。そのため、風邪症状による気道の炎症が加わると、急速に呼吸状態が悪化する危険性があります。これらの犬種を飼っている方は、風邪症状に対して特に警戒が必要です。
食欲がない・元気がない
食欲不振は、多くの病気に共通する非特異的な症状ですが、風邪の場合も例外ではありません。鼻が詰まって嗅覚が低下すると、犬は食べ物のにおいを感じにくくなり、食欲が落ちます。また、喉の痛みや全身の倦怠感も食欲低下の原因となります。
いつもなら喜んで食べるごはんに興味を示さない、においを嗅ぐだけで食べない、少し口にしてもすぐにやめてしまう、といった様子が見られたら、体調不良のサインです。特に、24時間以上まったく食べない状態が続く場合は、脱水や低血糖のリスクもあるため、受診を検討しましょう。
元気がないという症状も重要な観察ポイントです。普段は散歩や遊びが大好きなのに興味を示さない、いつもより寝ている時間が長い、呼びかけへの反応が鈍い、動きがゆっくりしているといった変化は、体調不良を示しています。
ただし、犬は本能的に弱っている姿を隠そうとすることがあります。特に多頭飼いの環境では、群れの中での立場を守ろうとして、体調不良を表に出さないこともあります。日頃から愛犬の様子をよく観察し、わずかな変化にも気づけるようにしておくことが大切です。
目やに・涙
目やにや涙の増加も、風邪症状の一つとして現れることがあります。上気道の炎症が鼻涙管を通じて目にも影響を及ぼしたり、ウイルスや細菌が目の粘膜にも感染することで、結膜炎を併発するケースがあります。
少量の透明な目やにや涙は正常範囲内ですが、量が増えたり、色が黄色や緑色に変化したりした場合は注意が必要です。朝起きたときに目が開きにくいほど目やにが固まっている、目の周りの毛が涙で常に濡れている、目を気にして前足でこすろうとするといった様子が見られたら、感染が進行している可能性があります。
目やにの色と性状は、感染の種類を推測する手がかりになります。透明でサラサラしたものはウイルス性の炎症が多く、白や黄色の粘液状のものは細菌感染を示唆します。また、片目だけに症状が出る場合は、風邪ではなく目に異物が入っていたり、角膜に傷がついている可能性も考えられます。
犬種によっては、涙やけができやすい体質のものもいます。トイプードル、マルチーズ、シーズーなどの小型犬は、もともと涙の排出がうまくいかず涙やけになりやすい傾向がありますが、急に症状が悪化した場合は、風邪などの感染症を疑う必要があります。
悪化を疑う”危険な症状”:すぐに受診が必要

風邪症状の中には、様子を見ているうちに自然に改善するものもありますが、以下のような症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診すべき緊急性の高い状態です。
咳が止まらない/夜に悪化
咳が頻繁に続き、ほとんど止まらない状態になると、犬自身も疲弊してしまいます。特に夜間に咳が悪化して眠れない、咳き込んで吐いてしまう、咳のために食事や水を飲むのが困難になっているといった状況は、気道の炎症がかなり進行していることを示しています。
夜間や早朝に咳が悪化するのは、横になることで気道内の分泌物が移動したり、副交感神経の働きで気管支が収縮しやすくなったりするためです。このパターンが見られる場合は、気管支炎や肺炎への進行を疑い、早急な治療が必要です。
また、咳をした後にチアノーゼ(舌や歯茎が紫色になる)が見られる場合や、咳き込んで失神しそうになる場合は、呼吸機能が著しく低下している危険な状態です。このような症状が見られたら、夜間でも緊急動物病院を受診してください。
黄色〜緑の鼻水(細菌感染)
前述したように、鼻水の色が黄色や緑色に変化するのは、細菌の二次感染が起きているサインです。このような膿性の鼻汁が続く場合、抗生物質による治療が必要になります。適切な治療を受けないと、感染が副鼻腔炎へと進行したり、気管支や肺にまで広がって肺炎を引き起こすリスクが高まります。
膿性鼻汁に加えて悪臭がある場合は、感染がかなり進行している可能性があります。また、鼻血が混じる場合は、粘膜の炎症が重度であるか、あるいは風邪以外の病気(鼻腔内腫瘍や凝固異常など)が隠れている可能性も考えられます。
鼻水の量が多く、常に鼻が詰まって口呼吸をしている状態も、犬にとって大きなストレスとなります。特に短頭種では、もともと狭い気道がさらに狭くなり、呼吸困難に陥る危険性があります。
呼吸促迫・チアノーゼ
呼吸促迫とは、速くて浅い呼吸が続く状態のことです。安静時でも1分間に40回以上の呼吸をしていたり、呼吸のたびに腹部が大きく上下したり、肋骨の間が引っ込んで見える(努力性呼吸)場合は、呼吸困難の状態にあります。
チアノーゼは、体内の酸素不足を示す最も重要な危険信号です。通常はピンク色をしている舌や歯茎が、紫がかったり青白く見える場合、血液中の酸素濃度が著しく低下しています。このような状態は生命に関わる緊急事態であり、一刻も早く酸素吸入や集中治療が必要です。
呼吸の異常に加えて、横になることができず座ったままの姿勢を保とうとする、前足を突っ張って立っている、首を伸ばして呼吸しようとするといった様子が見られる場合も、重度の呼吸困難を示しています。このような症状は、肺炎や胸水、心不全などの深刻な状態を示唆するため、緊急の受診が必要です。
食欲がない/ぐったり
完全に食欲がなくなり、水も飲まない状態が24時間以上続く場合は、脱水や低血糖、電解質異常などのリスクが高まります。特に子犬や小型犬では、短時間で低血糖に陥りやすいため、より早い段階での受診が必要です。
ぐったりして動かない、呼びかけに反応しない、意識がもうろうとしているといった症状は、全身状態が悪化している危険なサインです。風邪だと思っていたものが、実は犬ジステンパーや犬パルボウイルス感染症などの重篤な感染症である可能性も否定できません。
また、発熱が続いて体温が40度を超える場合や、逆に体温が36度以下に低下している場合も、緊急性の高い状態です。特に低体温は、ショック状態に陥っている可能性があり、非常に危険です。
1〜2日で症状が悪化する場合
風邪症状が出始めてから1〜2日で急速に悪化する場合は、通常の風邪よりも重篤な感染症や、肺炎への進行を疑う必要があります。初日は軽い咳だけだったのに、翌日には呼吸が荒くなり食欲もなくなったという経過をたどる場合、病原体の毒性が強かったり、犬の免疫力が著しく低下している可能性があります。
特に注意すべきは、子犬の場合です。まだ免疫系が未熟な子犬では、感染症が急速に全身に広がり、数時間で重篤な状態になることもあります。また、ワクチン接種が完了していない子犬は、致死的な感染症にかかるリスクが高いため、わずかな症状でも早めに受診することが重要です。
症状の悪化速度が速い場合は、週末や夜間を待たずに、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。「明日まで様子を見よう」と判断している間に、取り返しのつかない状態になってしまうこともあります。
子犬・老犬・短頭種は特に危険
子犬は免疫システムがまだ発達途中であり、感染症に対する抵抗力が弱いため、風邪症状が出た場合は特に注意が必要です。生後6ヶ月未満の子犬で、ワクチン接種が完了していない場合は、軽い症状であってもできるだけ早く獣医師の診察を受けることをお勧めします。
高齢犬も同様にリスクが高いグループです。年齢とともに免疫力が低下し、また心臓病や腎臓病などの基礎疾患を持っていることも多いため、風邪症状が他の臓器にも悪影響を及ぼす可能性があります。普段は元気に見える老犬でも、感染症をきっかけに急速に状態が悪化することがあります。
短頭種については、その独特な頭蓋骨と顔面の構造により、生まれつき気道が狭く、呼吸効率が良くありません。フレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリア、ブルドッグ、シーズー、ペキニーズなどがこれに該当します。これらの犬種では、わずかな気道の炎症や腫れでも、呼吸困難に陥りやすいのです。
短頭種は暑さにも弱く、風邪による発熱が加わると体温調節がうまくできず、熱中症のような状態になることもあります。また、興奮や運動によって呼吸状態がさらに悪化しやすいため、風邪症状が見られる間は特に安静を保つことが重要です。
これらのハイリスクグループに該当する犬を飼っている場合は、軽い症状であっても早めに動物病院を受診し、獣医師の判断を仰ぐことが、愛犬の命を守ることにつながります。
犬が風邪をひく原因:本当に多い”環境要因”

犬の風邪症状を引き起こす原因は、単一のものではなく、複数の要因が複合的に関与していることが多いです。ここでは、主な原因について詳しく見ていきましょう。
ウイルス(パラインフルエンザ、アデノウイルス)
犬の呼吸器感染症を引き起こす主なウイルスには、犬パラインフルエンザウイルスと犬アデノウイルス2型があります。これらは、いわゆるケンネルコフの原因ウイルスとして知られています。
犬パラインフルエンザウイルスは、感染力が非常に強く、咳やくしゃみによる飛沫感染や、感染犬が触れた物を介した接触感染で広がります。潜伏期間は2〜5日程度で、感染すると乾性の咳を主症状とする上気道炎を引き起こします。多くの場合は軽症で済みますが、他の病原体との混合感染により重症化することがあります。
犬アデノウイルス2型も同様に、上気道感染症を引き起こします。このウイルスは、気管や気管支の粘膜に感染し、咳や鼻水などの症状を引き起こします。また、犬アデノウイルス1型は肝炎を引き起こす別の型ですが、初期症状として呼吸器症状が見られることもあります。
その他にも、犬ヘルペスウイルスや犬レオウイルスなど、さまざまなウイルスが呼吸器症状を引き起こす可能性があります。また、犬ジステンパーウイルスは非常に深刻な全身性感染症を引き起こしますが、初期症状として風邪に似た呼吸器症状が現れることがあります。
これらのウイルス感染症の多くは、適切なワクチン接種によって予防可能です。定期的なワクチン接種は、愛犬を感染症から守る最も効果的な方法です。
細菌(ボルデテラ)
ボルデテラ・ブロンキセプティカは、犬の呼吸器感染症を引き起こす代表的な細菌です。この細菌は単独でも病気を引き起こしますが、多くの場合はウイルス感染に続いて二次感染として関与します。
ボルデテラは、気管や気管支の線毛上皮細胞に付着し、粘膜の防御機能を低下させます。その結果、激しい咳が続き、場合によっては気管支炎や肺炎へと進行することがあります。ボルデテラ感染による咳は、「ガチョウが鳴くような」と表現されることもある、特徴的な乾性咳嗽です。
この細菌は、ペットホテルやトリミングサロン、ドッグラン、動物病院など、多くの犬が集まる環境で感染が広がりやすいため、このような施設を利用する前にボルデテラワクチンの接種を求められることがあります。ボルデテラワクチンは鼻腔内投与型のものもあり、より速やかな免疫応答が期待できます。
細菌感染が疑われる場合は、抗生物質による治療が必要になります。ただし、抗生物質は細菌には効果がありますが、ウイルスには効きません。そのため、症状や検査結果に基づいて、適切な治療法を選択することが重要です。
突然の寒暖差(冬/梅雨時期の検索対策)
犬も人間と同じように、急激な気温変化によって体調を崩すことがあります。特に冬場の寒い時期や、梅雨の時期の気温差が大きい日は注意が必要です。
冬場は、暖かい室内から寒い屋外への移動、あるいはその逆の移動によって、呼吸器粘膜が急激な温度変化にさらされます。これにより粘膜の血流が変化し、一時的に防御機能が低下することで、病原体の侵入を許しやすくなります。
また、冬場は空気が乾燥しやすく、気道粘膜も乾燥して傷つきやすくなります。粘膜が健康な状態では、粘液や線毛の働きによって病原体を排除できますが、乾燥によってこの機能が低下すると、感染症にかかりやすくなります。
梅雨の時期も要注意です。湿度が高く、日によって気温が大きく変動するこの時期は、犬の体温調節機能にも負担がかかります。また、梅雨時期は室内の換気が不十分になりがちで、空気がこもって病原体が増殖しやすい環境になることもあります。
季節の変わり目や気温差の大きい時期は、室温管理に注意し、散歩の時間帯を工夫するなどして、愛犬の体調管理に気を配りましょう。特に高齢犬や病気がちな犬では、体温調節機能が低下しているため、より注意深いケアが必要です。
免疫低下(シニア・持病)
免疫力が低下している犬は、感染症にかかりやすく、また重症化しやすい傾向があります。免疫力が低下する要因はいくつかあります。
高齢犬では、加齢に伴って免疫システムの機能が徐々に低下します。若い頃は問題なく防げていた病原体に対しても、抵抗力が弱くなり、感染しやすくなります。また、感染した場合の回復も遅く、合併症を起こしやすくなります。
慢性疾患を持っている犬も、免疫力が低下していることが多いです。糖尿病、クッシング症候群、甲状腺機能低下症などの内分泌疾患、慢性腎臓病、肝臓病などは、全身の健康状態に影響を及ぼし、感染症への抵抗力を弱めます。
ストレスも免疫力を低下させる大きな要因です。環境の変化、引っ越し、新しいペットの加入、飼い主の生活パターンの変化など、犬にとってストレスとなる出来事があると、免疫機能が一時的に低下することがあります。
栄養不良や肥満も免疫力に影響します。適切な栄養バランスが保たれていない食事を続けている犬や、逆に肥満によって代謝に問題がある犬も、感染症にかかりやすくなります。
また、ステロイドや免疫抑制剤などの薬を長期使用している犬も、医原性に免疫力が低下している状態です。これらの薬を使用している場合は、感染症のリスクについて獣医師とよく相談し、予防策を講じることが重要です。
ペットホテル・ドッグランなど接触感染
多くの犬が集まる場所は、呼吸器感染症が広がりやすい環境です。ペットホテル、トリミングサロン、ドッグラン、ドッグカフェ、動物病院の待合室など、さまざまな犬が接触する場所では、感染犬から健康な犬へと病原体が伝播するリスクがあります。
ケンネルコフという名前自体が、ケンネル(犬舎)で感染が広がることから名付けられたものです。狭い空間に多くの犬が集まり、ストレスも加わることで、感染が拡大しやすくなります。
感染経路は主に二つあります。一つは飛沫感染で、感染犬の咳やくしゃみによって飛散した病原体を、他の犬が吸い込むことで感染します。もう一つは接触感染で、感染犬が触れた食器、おもちゃ、ケージ、人の手などを介して病原体が広がります。
特にパピークラスやしつけ教室など、まだワクチン接種が完了していない子犬が集まる場では、感染のリスクが高まります。子犬を社会化トレーニングに参加させることは重要ですが、ワクチンプログラムが完了するまでは、参加する施設の衛生管理や参加条件をよく確認し、リスクとベネフィットを考慮して判断することが大切です。
これらの施設を利用する際は、事前に必要なワクチン接種を済ませておくこと、利用後は愛犬の健康状態をよく観察すること、少しでも体調不良の兆候があれば他の犬との接触を避けることなどが、感染拡大を防ぐために重要です。
自宅でできる対処法
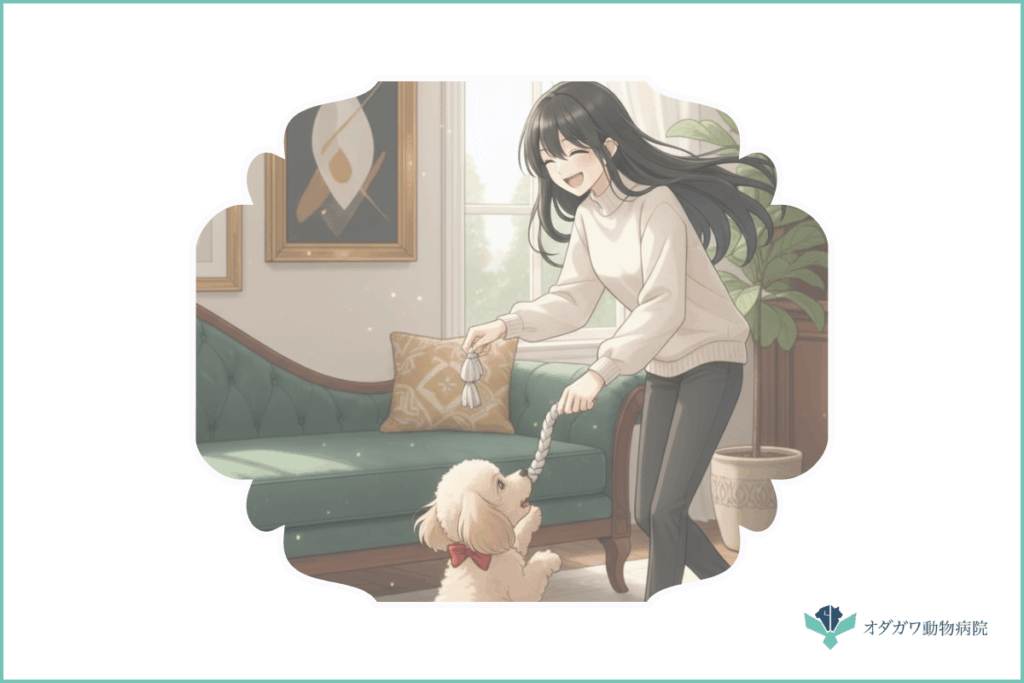
愛犬に風邪症状が見られた場合、動物病院を受診するのが最善ですが、軽症の場合や、すぐに受診できない状況では、自宅でできる適切なケアによって症状を和らげ、回復を助けることができます。ただし、症状が悪化する場合は必ず受診してください。
室温20〜25℃・湿度50〜60%に保つ
呼吸器の健康を保つために、適切な室内環境を整えることは非常に重要です。犬にとって快適な室温は、一般的に20〜25度程度とされています。寒すぎると体力を消耗し、暑すぎると呼吸が荒くなって呼吸器に負担をかけます。
特に風邪をひいている犬は、体温調節機能が低下していることがあるため、室温を一定に保つことが大切です。エアコンや暖房器具を使用する際は、直接風が当たらないように配慮し、温度が急激に変化しないように注意しましょう。
湿度管理も同様に重要です。適度な湿度(50〜60%)を保つことで、気道粘膜の乾燥を防ぎ、線毛運動を正常に保つことができます。乾燥した空気は、粘膜を傷つけ、病原体の侵入を容易にするだけでなく、咳を悪化させる要因にもなります。
加湿と空気の乾燥対策
加湿器を使用することで、室内の湿度を適切に保つことができます。特に冬場の暖房使用時や、夏場のエアコン使用時は、室内が乾燥しやすいため、加湿器の使用が効果的です。
加湿器がない場合でも、濡れたタオルを室内に干したり、洗濯物を部屋干しすることでも、ある程度の加湿効果が得られます。また、犬が過ごす部屋に水を入れた容器を置いておくことも、簡単な加湿方法の一つです。
ただし、過度な加湿はカビやダニの発生を促進するため、湿度計を使って適切な湿度を維持することが大切です。また、加湿器を使用する場合は、定期的な清掃を怠らず、雑菌の繁殖を防ぎましょう。
蒸気を利用した方法として、浴室で温かいシャワーを出して蒸気を充満させ、その中に犬を数分間入れる「スチーム療法」も効果的です。蒸気が気道を温め湿らせることで、粘液の排出を促し、咳を和らげる効果が期待できます。ただし、高温になりすぎないように注意し、犬が嫌がる場合は無理強いしないでください。
水分を摂らせる(少量ずつ)
風邪をひいている犬は、発熱や食欲不振によって脱水になりやすい状態です。適切な水分補給は、体内の老廃物を排出し、粘膜を湿らせ、回復を促進するために不可欠です。
ただし、一度に大量の水を飲ませると、吐いてしまうこともあるため、少量ずつ頻繁に与えることがポイントです。いつもの水飲み容器に加えて、手から直接少量ずつ飲ませたり、スプーンやシリンジ(注射器の針を外したもの)を使って与える方法もあります。
水をあまり飲みたがらない場合は、鶏肉や野菜を茹でた無塩のスープを作って与えるのも良い方法です。温かいスープは、水分補給だけでなく、栄養補給にもなり、食欲を刺激する効果もあります。ただし、玉ねぎやニラなど、犬に有害な食材は絶対に使用しないでください。
また、ウェットフードには水分が多く含まれているため、ドライフードからウェットフードに一時的に切り替えることも、水分摂取量を増やす効果的な方法です。
散歩は短めに
風邪症状がある間は、激しい運動は避け、散歩も短時間で済ませるようにしましょう。運動によって呼吸が激しくなると、炎症を起こしている気道に さらに負担をかけてしまいます。
ただし、排泄のための外出は必要です。いつもの半分程度の時間で、ゆっくりとしたペースで歩く程度にとどめましょう。寒い季節や雨の日は、特に短時間で済ませ、濡れた場合はすぐにタオルで拭いて体を冷やさないようにしてください。
犬用の服を着せることも、体温を保つのに役立ちます。特に小型犬や短毛種、高齢犬は体温が奪われやすいため、散歩時には服を着せて体を冷やさないようにすることが効果的です。
症状が重い場合や、呼吸が苦しそうな場合は、無理に散歩に連れ出さず、室内でのトイレに切り替えることも検討してください。ペットシーツやトイレトレーを使った室内排泄に慣れていない犬でも、体調不良時には受け入れることがあります。
安静第一(無理に遊ばせない)
風邪から回復するためには、十分な休息が最も重要です。犬が寝ている時間が長くなっても、それは体が回復しようとしている自然な反応なので、無理に起こしたり遊びに誘ったりしないようにしましょう。
静かで落ち着いた環境を用意してあげることも大切です。騒がしい場所や、家族の往来が多い場所ではなく、静かで温度が安定している場所に寝床を準備してください。ただし、完全に隔離すると犬が不安を感じることもあるので、飼い主の存在を感じられる距離感を保つことが理想的です。
多頭飼いの場合は、病気の犬を他の犬から一時的に離すことも検討してください。感染拡大を防ぐとともに、病気の犬がゆっくり休める環境を作ることができます。
子供がいる家庭では、犬が体調不良であることを子供にも理解させ、そっとしておくように伝えましょう。愛犬を心配する気持ちは大切ですが、頻繁に触ったり声をかけたりすることが、犬にとってはストレスになることもあります。
人の風邪薬は絶対にNG
これは非常に重要な注意点です。人間用の風邪薬や解熱鎮痛剤を犬に与えることは、絶対にしてはいけません。人間にとっては安全な薬でも、犬には重篤な副作用を引き起こし、最悪の場合は死に至ることもあります。
特に危険なのは、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛剤です。これらの薬は、犬では代謝がうまくできず、肝障害や腎障害、胃腸障害、血液凝固異常などを引き起こします。ごく少量でも中毒症状が現れることがあります。
市販の風邪薬には複数の成分が含まれていることが多く、その中には犬にとって有害なものが含まれている可能性があります。「少量なら大丈夫だろう」「以前に使ったことがある」という自己判断は危険です。
薬を使用する場合は、必ず動物病院で処方されたものを、指示通りの用法用量で使用してください。獣医師が処方する薬は、犬の体重や状態に合わせて選択され、適切な量が決定されています。
自然治癒を期待するのは危険な場合がある
軽い風邪症状であれば、適切な環境管理と栄養補給によって自然に回復することもあります。しかし、前述したような危険な症状が見られる場合や、症状が数日続いても改善しない場合、あるいは悪化している場合は、自然治癒を期待して様子を見続けることは危険です。
「様子を見ていたら悪化してしまった」というケースは非常に多く、早期に治療を始めていれば軽症で済んだものが、重症化してしまうこともあります。特に、細菌感染が加わっている場合や、肺炎に進行している場合は、抗生物質などの適切な治療が必要であり、自然治癒は期待できません。
また、犬は本能的に体調不良を隠す傾向があるため、飼い主が「まだ大丈夫そう」と思っていても、実際には相当悪化していることもあります。少しでも不安がある場合は、早めに動物病院に相談することが、愛犬の命を守ることにつながります。
電話での相談だけでも、受診の緊急度を判断してもらえることがあります。「こんなことで電話してもいいのだろうか」と遠慮せず、気になることがあれば獣医師に相談してみましょう。
動物病院で行う検査と治療

動物病院では、症状や身体検査の結果に基づいて、必要な検査と適切な治療が行われます。ここでは、風邪症状で受診した際に行われる可能性のある検査と治療について説明します。
視診・聴診
最も基本的な診察は、視診と聴診です。獣医師は、犬の全身状態、呼吸の様子、咳の性状、鼻水や目やにの有無と性状などを注意深く観察します。
聴診器を使って、肺の音や心臓の音を聴くことも重要な診察です。正常な呼吸音は、気管や大きな気管支を通る空気の音がかすかに聞こえる程度ですが、炎症があると、さまざまな異常音が聴取されます。
乾性ラ音と呼ばれる「ヒューヒュー」「ピーピー」という高い音は、気管支が狭くなっている状態を示します。湿性ラ音と呼ばれる「ゴロゴロ」「ブツブツ」という音は、気道内に分泌物が溜まっている状態を示唆します。肺炎では、肺胞に液体が貯留することで、「パチパチ」という捻髪音が聴かれることもあります。
視診では、呼吸の回数と深さ、呼吸の仕方(腹式呼吸になっていないか、努力性呼吸でないか)、チアノーゼの有無などを確認します。また、全身の栄養状態や、脱水の程度なども評価されます。
PCR検査(ウイルス)
特定のウイルス感染を確認するために、PCR検査が行われることがあります。鼻腔や咽頭から綿棒でサンプルを採取し、特定のウイルスの遺伝子を検出する検査です。
この検査により、犬パラインフルエンザウイルス、犬アデノウイルス、犬ジステンパーウイルスなどの感染の有無を確認できます。ただし、PCR検査は結果が出るまでに数日かかることが多いため、重症例を除いては、検査結果を待たずに治療を開始することもあります。
また、多頭飼いの場合や、ペットホテルなどの集団飼育施設で感染が疑われる場合は、感染源の特定と感染拡大防止のために、PCR検査が実施されることがあります。
レントゲン(肺炎の有無)
胸部レントゲン検査は、肺炎の有無や程度を評価するために非常に重要な検査です。聴診だけでは判断できない肺の異常も、レントゲンで可視化できます。
正常な肺は、レントゲン画像では黒く写ります。これは、肺が空気で満たされているためです。しかし、肺炎や肺水腫があると、炎症や液体貯留によって肺の一部が白く写ります。この白い陰影のパターンや分布によって、病気の種類や重症度を判断することができます。
気管支炎では、気管支周囲の肥厚が見られることがあります。また、心臓の大きさや形も同時に評価でき、心疾患が隠れていないかを確認することもできます。
レントゲン検査は非侵襲的で、多くの場合は無麻酔で実施できますが、呼吸困難が重度の犬では、検査のために保定すること自体がストレスとなり、状態を悪化させる可能性もあります。そのため、獣医師は犬の状態を見ながら、検査の必要性とリスクを判断します。
抗生物質(細菌性)
細菌感染が疑われる場合、あるいは二次的な細菌感染を予防するために、抗生物質が処方されます。膿性の鼻水や痰が出ている場合、発熱が続いている場合、白血球数が増加している場合などは、細菌感染の可能性が高いと判断されます。
使用される抗生物質は、ペニシリン系、セフェム系、ニューキノロン系、マクロライド系など、症状や感染部位、細菌の種類に応じて選択されます。投与期間は通常1〜2週間程度ですが、症状の改善具合によって調整されます。
抗生物質を使用する際の重要な注意点は、処方された期間を守って最後まで飲ませることです。症状が改善したからといって途中でやめてしまうと、細菌が完全に死滅せず、再発したり、抗生物質に耐性を持った細菌が増える原因になります。
また、抗生物質の副作用として、下痢や嘔吐などの消化器症状が現れることがあります。軽度であれば様子を見ても構いませんが、激しい下痢や嘔吐が続く場合は、獣医師に相談してください。
咳止め・抗炎症薬
激しい咳が続いて犬が疲弊している場合や、咳によって睡眠が妨げられている場合は、咳止め(鎮咳薬)が処方されることがあります。ただし、咳は体が病原体や分泌物を排出しようとする防御反応でもあるため、むやみに抑えることが良いとは限りません。
咳止めには中枢性のものと末梢性のものがあります。中枢性鎮咳薬は、脳の咳中枢に働きかけて咳反射を抑制します。末梢性鎮咳薬は、気道の知覚神経を鈍らせたり、気管支を拡張させることで咳を和らげます。
気道の炎症を抑えるために、抗炎症薬が使用されることもあります。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、炎症と痛みを和らげ、発熱を下げる効果があります。重度の炎症がある場合は、ステロイド薬が短期間使用されることもありますが、ステロイドは免疫を抑制する作用もあるため、感染症に対しては慎重に使用されます。
気管支拡張薬は、気管支が収縮して呼吸が苦しい場合に使用されます。特に喘息様の症状がある犬や、慢性気管支炎を持っている犬では、気管支拡張薬が症状の改善に有効です。
点滴・入院が必要な場合
脱水が進んでいる場合、食事が摂れていない場合、あるいは重度の肺炎などで集中的な治療が必要な場合は、点滴治療や入院が検討されます。
点滴によって、水分と電解質を補給し、体液バランスを整えることができます。また、抗生物質や抗炎症薬などを点滴に混ぜて投与することで、より確実に薬を体内に届けることができます。
入院が必要と判断される主な状況は、重度の呼吸困難がある場合、酸素吸入が必要な場合、継続的なモニタリングが必要な場合、在宅での治療が困難な場合などです。
入院中は、酸素室での管理、持続点滴、定期的なネブライザー治療、栄養補給などが行われます。状態が安定してきたら、徐々に酸素濃度を下げたり、点滴を減量したりして、退院に向けた準備が進められます。
入院のストレスが逆効果になる犬もいるため、在宅で十分なケアができる状況であれば、通院治療が選択されることもあります。獣医師と相談しながら、個々の犬にとって最適な治療プランを決めていくことが大切です。
風邪を予防する方法

風邪を完全に防ぐことは難しいですが、適切な予防策を講じることで、感染のリスクを大幅に減らすことができます。
混合ワクチン(何が予防できるか)
ワクチン接種は、感染症を予防する最も効果的な方法です。犬の混合ワクチンには、さまざまな病原体に対する抗原が含まれており、定期的な接種によって免疫を維持することができます。
一般的な混合ワクチンに含まれる抗原には、犬ジステンパーウイルス、犬アデノウイルス2型(犬伝染性肝炎とケンネルコフの原因)、犬パラインフルエンザウイルス、犬パルボウイルスなどがあります。これらは、5種混合、6種混合、7種混合などとして提供されています。
特にケンネルコフの予防に特化したワクチンとして、ボルデテラワクチンがあります。これは鼻腔内に投与するタイプで、より速やかな免疫応答が期待できます。ペットホテルやトリミングサロン、ドッグランなどを利用する予定がある場合は、施設によってはこのワクチンの接種を求められることがあります。
子犬の場合は、母犬からもらった移行抗体が減少する時期に合わせて、複数回のワクチン接種が必要です。一般的には、生後6〜8週齢で初回接種を行い、その後3〜4週間隔で2〜3回接種します。最終接種は生後16週齢以降に行うことが推奨されています。
成犬では、年1回の追加接種を続けることが一般的ですが、近年では3年ごとの接種で十分という考え方もあります。愛犬のライフスタイルや健康状態、地域の感染症の流行状況などを考慮して、獣医師と相談しながら接種スケジュールを決めましょう。
寒さ・乾燥の管理
前述したように、寒暖差や乾燥は風邪の大きな原因となります。特に冬場は、室内環境の管理が重要です。
暖房を使用する際は、温度だけでなく湿度にも注意を払いましょう。エアコンやファンヒーターは空気を乾燥させやすいため、加湿器を併用することをお勧めします。ただし、加湿しすぎもカビの原因となるため、湿度計でチェックしながら適切な湿度を維持してください。
散歩の時間帯も工夫しましょう。冬場は、日中の比較的暖かい時間帯に散歩に出かけることで、寒暖差によるストレスを減らすことができます。逆に夏場は、早朝や夕方以降の涼しい時間帯を選ぶことで、熱中症のリスクを避けられます。
小型犬や短毛種、高齢犬、病気がちな犬は、特に寒さに弱い傾向があります。冬の散歩では犬用の服を着せることも効果的です。ただし、服の素材によっては静電気が起きやすかったり、動きにくかったりすることもあるので、犬に合ったものを選びましょう。
寝床の場所も見直してみてください。窓際や玄関近くなど、外気の影響を受けやすい場所は避け、温度が安定している場所に寝床を設置しましょう。ペット用のヒーターやホットカーペットを使用する場合は、低温やけどに注意し、必ず温度調節ができるものを選んでください。
外での犬同士の接触
不特定多数の犬との接触は、感染症のリスクを高めます。特に、ワクチン接種が完了していない子犬や、免疫力が低下している犬では注意が必要です。
ドッグランを利用する際は、施設の衛生管理がしっかりしているか、利用条件としてワクチン接種が義務付けられているかを確認しましょう。また、明らかに体調不良と思われる犬がいる場合は、接触を避けるか、その日の利用を見合わせることも検討してください。
散歩中に他の犬と挨拶させる際も、相手の犬の健康状態に注意を払いましょう。咳をしている、鼻水が出ている、元気がないなどの症状が見られる犬とは、距離を保つことが賢明です。
ペットホテルやトリミングサロンを利用する際は、事前に施設の感染症対策について確認することをお勧めします。利用後は、愛犬の健康状態をよく観察し、1週間程度は他の犬との接触を控えめにすることで、万が一感染していた場合の拡大を防ぐことができます。
シニア犬・持病のある犬は注意
高齢犬や慢性疾患を持っている犬は、若く健康な犬に比べて感染症にかかりやすく、また重症化しやすい傾向があります。これらの犬では、より慎重な健康管理が必要です。
定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見と早期治療が可能になります。シニア犬では、少なくとも年に2回程度の健康診断が推奨されます。血液検査、尿検査、レントゲン検査などを定期的に行うことで、隠れた病気を見つけることができます。
栄養管理も重要です。年齢や健康状態に合わせた適切なフードを選び、肥満や栄養不足を防ぎましょう。特にシニア犬用のフードには、免疫をサポートする成分や、関節の健康を維持する成分などが配合されていることが多いです。
ストレス管理も忘れてはいけません。高齢犬は環境の変化に敏感になることがあります。できるだけ生活リズムを一定に保ち、安心できる環境を提供することが、免疫力の維持につながります。
持病のある犬では、その病気の管理をしっかり行うことが、感染症予防の基本です。定期的な通院と投薬を怠らず、主治医の指示に従って健康管理を続けましょう。
犬の風邪でよくある質問(FAQ)

最後に、飼い主さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
犬の風邪は自然に治る?治らない?
軽度のウイルス性上気道炎であれば、適切な環境管理と栄養補給によって、1〜2週間程度で自然に回復することもあります。人間の風邪と同様に、ウイルス感染に対する特効薬はなく、体の免疫力によってウイルスを排除することになります。
しかし、すべての風邪症状が自然治癒するわけではありません。細菌感染が加わっている場合、肺炎に進行している場合、あるいは犬ジステンパーなどの重篤な感染症である場合は、適切な治療なしでは回復しません。
また、自然治癒を待っている間に症状が悪化し、より重篤な状態になってしまうリスクもあります。特に子犬や高齢犬、基礎疾患のある犬では、様子を見すぎることが命取りになることもあります。
症状が軽く、食欲もあり元気であれば、数日間様子を見ても構いませんが、症状が改善しない場合や悪化する兆候が見られたら、すぐに動物病院を受診しましょう。「自然に治るかもしれない」という期待よりも、「悪化する前に診てもらおう」という判断が、愛犬の健康を守ります。
犬の風邪は散歩してもいい?
軽い風邪症状で、食欲もあり元気であれば、短時間の散歩は問題ありません。ただし、いつもの半分程度の時間で、ゆっくりとしたペースで歩く程度にとどめましょう。
散歩を完全に止めてしまうと、排泄の問題だけでなく、ストレスが溜まったり、筋力が低下したりする可能性もあります。犬にとって散歩は、排泄だけでなく、気分転換やストレス発散の大切な時間です。
ただし、以下のような症状がある場合は、散歩は控えた方が良いでしょう。激しい咳が続いている、呼吸が苦しそう、発熱がある、食欲がなくぐったりしている、雨や雪などの悪天候、気温が極端に低いまたは高い、といった状況では、無理に散歩に出かけず、室内でのトイレに切り替えることを検討してください。
散歩に出かける場合は、他の犬との接触は避けましょう。感染を広げないためにも、風邪症状がある間は、ドッグランや犬が集まる場所への立ち寄りは控えるべきです。
風邪薬を飲ませてもいい?
人間用の風邪薬を犬に飲ませることは、絶対にしてはいけません。これは何度強調してもしすぎることはないほど重要な注意点です。
人間用の風邪薬には、犬にとって有害な成分が含まれていることが多く、たとえ少量でも重篤な副作用を引き起こす可能性があります。特にアセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛剤は、犬には極めて危険です。
「以前に大丈夫だった」「少量なら問題ないだろう」という自己判断は、非常に危険です。過去に問題がなかったのは、たまたま運が良かっただけで、次回も安全である保証はありません。
薬が必要な場合は、必ず動物病院を受診し、獣医師が犬の状態を診察した上で処方した薬を使用してください。動物病院で処方される薬は、犬用に開発されたものか、人間用でも犬に安全に使用できることが確認されたものです。
何日続いたら病院に行くべき?
これは症状の重さによって異なります。軽い咳やくしゃみ程度であれば、2〜3日様子を見ても構いません。しかし、以下のような場合は、すぐに受診すべきです。
呼吸困難やチアノーゼが見られる場合は、緊急事態なので即座に受診してください。激しい咳が止まらない、膿性の鼻水が出る、発熱が続く、食欲がなくぐったりしているといった症状がある場合も、様子を見ずに早めに受診しましょう。
軽い症状でも、3〜4日経っても改善しない、あるいは徐々に悪化している場合は、受診のタイミングです。また、一度改善したように見えたのに再び悪化した場合も、二次感染などの可能性があるため、診察を受けることをお勧めします。
子犬、高齢犬、基礎疾患のある犬、短頭種では、より早い段階での受診が推奨されます。これらのハイリスクグループでは、「少し様子を見よう」という判断が命取りになることもあるため、症状が出たら早めに相談しましょう。
迷ったときは、動物病院に電話で相談することもできます。症状を説明することで、緊急性の判断や受診のタイミングについてアドバイスをもらえることがあります。
犬の風邪と肺炎の違いは?
風邪(上気道炎)と肺炎は、炎症が起きている場所が異なります。風邪は主に鼻、喉、気管の上部など、上気道に炎症が限局している状態です。一方、肺炎は肺そのものに炎症が及んでいる状態で、より重篤です。
症状の違いとしては、風邪では比較的軽い咳、くしゃみ、鼻水などが主で、食欲や元気はある程度保たれることが多いです。しかし肺炎では、激しい咳、呼吸困難、高熱、著しい食欲不振と元気消失が見られます。
呼吸の様子にも違いがあります。風邪では呼吸数が少し増える程度ですが、肺炎では明らかな呼吸促迫が見られ、横になることもできずに座った姿勢を保とうとすることがあります。
診断には、聴診とレントゲン検査が重要です。肺炎では、聴診で異常な肺音が聴取され、レントゲンで肺に白い陰影が確認されます。血液検査では、炎症マーカーの上昇や白血球数の変化が見られることもあります。
風邪が肺炎に進行することは珍しくありません。上気道の炎症が下方に広がったり、細菌の二次感染が加わったりすることで、肺炎を発症します。そのため、風邪症状だからと軽視せず、悪化の兆候に注意を払うことが大切です。